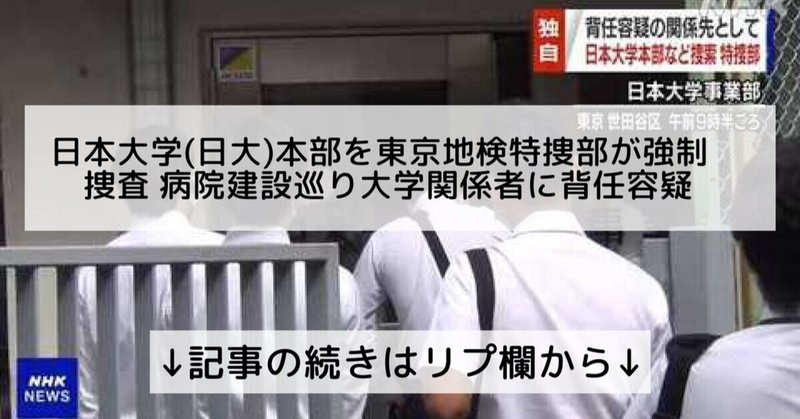
【行列ゼロ!じんたろ法律事務所】日大事件はガバナンス改革で防げるのか? その2
その1では「じんたろホカホカ壁新聞」がホットなニュースをまとめた。
その2ではじんたろ法律事務所が、日大事件から学校法人のガバナンスをちょっとだけ法律的に考える。
日本大学関係者から、ガバナンスが機能するのは現場の願いという嘆きが聞こえる。
それに答えるように政府と文部科学省はガバナンス改革に乗り出している。
これは元厚労相の塩崎恭久氏が仕掛け人なんだとか。
塩崎さんは常々、『ガバナンスなき学校法人には課税すべき』と話しているほどで、自民党の行政改革推進本部長だった頃にも提言を繰り返して、学校法人改革に取り組んできました。もともとコーポレートガバナンスに詳しく、上場企業への社外取締役設置などに大きな力を発揮して、社団法人や財団法人、社会福祉法人などのガバナンス改革を実現したこともある。まさに『ガバナンスの鬼』とも言える存在です。塩崎さんは次の総選挙には出ず、引退することを表明していますから、さしずめ“最後の戦い”といったところでしょう
塩崎氏は行革推進本部長や大臣も経験して、大学の現状に我慢がならないようだ。
「日本の大学は研究力や教育環境、国際性などで世界の大学と比較すれば、ランキングが低いとされていますが、ともかく、それらを下支えする経営力に乏しい。ですから塩崎さんは、理事会にもっと力を持たせ、経営を欧米の一流大学並みにして、研究・教育に投じる資金を確保させるべきだ、と考えています。今のように理事長独裁がはびこり、やりたい放題されていては、国際的な競争には勝てない。自民党にも文教族と言われる議員がいますが、彼らの関心は義務教育で、大学経営に関心を持っている人はほとんどいません。塩崎さんは『高等教育に関心を持っているのは自分だけ』と自負し、ひとり気を吐いています」
この『デイリー新潮』の記事には、文科省事務局と会議座長の増田宏一氏(元日本公認会計士協会会長)のバトルや、私立大学を天下り先にしている文科省は私立学校改革に腰が重いとか書かれている。
その真偽はわからないが、この会議が政府の骨太方針という肝いりから始まり、会議メンバーには久保利英明弁護士、野村修也教授(中央大学法科大学院)などガバナンス改革の著名な専門家がそろっている。
ゲストには冨山和彦氏を呼ぶなどスゴいラインナップだ。
1. ほとんどの人が知らない政府・文科省が進める「学校法人ガバナンス改革」って何?
そういうすごい人たちがシビアに議論している「学校法人ガバナンス改革会議」というのが今年の夏から開催されているのだが、たぶんほとんどの国民は知らないだろう
衆議院選挙の争点のかけらにもなっていない。
『デイリー新潮』が書いているように、今回のガバナンス改革では、ほとんど文科省の事務局側が事務仕事をしかさせてもらっていないようだ。
Youtubeで過去の会議が録画されているのでそれが垣間見える。
委員は以下の人。
安西 祐一郎 独立行政法人日本学術振興会顧問、学術情報分析センター所長
石井 尚子 桜通り法律事務所弁護士
岡田 譲治 公益社団法人日本監査役協会前会長・最高顧問
久保利 英明 日比谷パーク法律事務所代表弁護士
酒井 邦彦 TMI総合法律事務所顧問弁護士
戸張 実 日本公認会計士協会常務理事、戸張会計事務所所長
西村 万里子 明治学院大学法学部教授
野村 修也 中央大学法科大学院教授
八田 進二 大原大学院大学教授
増田 宏一 日本公認会計士協会相談役
松本 美奈 ジャーナリスト、一般社団法人Qラボ代表理事
本山 和夫 学校法人東京理科大学会長
いやあ、ガバナンス改革オールスターって感じ。
このメンバーに私学行政課長補佐の相原って人が事務局で加わっている。
でも、論点整理は、松本美奈っていう元読売新聞の記者と八田信二という公認会計士が行っている。
ふつうは文科省の事務局がやっていると思う。相原って官僚はとても頭のいい人みたいで受け答えが的確だけど、議論には一切入れてもらえない。音声の修正や発言の順番の交通整理だけ。たまに法文の解説をするのだけど、野村修也っていうロースクールでガバナンスを教えている教授がいるので、その人のほうが詳しい。文科省のエリートが付け焼刃の知識で歯が立つ相手ではない。
大学関係者では、本山和夫という現役の私大のトップと安西祐一郎という慶応大学の元塾長がいる。けれど、慶応はすでにガバナンス改革が目指している評議員会が最高議決機関になっているので、分が悪いのは東京理科大の本山氏。発言すると、なんか抵抗勢力に見えてしまう。
骨太方針からの発案
この時期に日大事件がたまたまあったからか、誰かが今記事にするようにリークしたのかもしれない。しかし、この学校法人ガバナンス改革は以前から用意されていたものだ。
第1回会議では、その解説をしている。
もともと、2020年4月 改正私学法施行の前に、2019年12月に新たな検討に向けて「学校法人のガバナンスに関する有識者会議」という会議体が設置されていた。
そこで延々、11回の会議を重ねて、2021年3月にとりまとめが発表された。そこでは、「今後、大学設置・学校法人審議会学校法人分科会の下に新たな会議体を設けて詳細を詰める」ことが示されていた。
その会議体が「学校法人ガバナンス改革会議」ということ。
「学校法人のガバナンスに関する有識者会議」で、だいたい今回の方向性は示されていた。というより、その会議から横滑りしたのが、野村修也氏、岡田譲治氏、酒井邦彦氏、八田進二氏。井原徹理事長(白梅学園)と長谷山彰塾長(慶應義塾)という私大経営者や両角亜希子東大准教授など高等教育の関係者や専門家は外れた。ガバナンス改革の専門家で固めた布陣で結論はだいたい見えている。文科省がねじ込んだと言われている私学関係者の本山氏はなんか貧乏くじを引いたみたいな格好になった。文科省としては当事者を入れてバランスを取ろうとしたのだと思うが、それがひとりじゃどうしようもない。
冨山和彦氏のスタンフォードのイメージ
第3回会議には冨山和彦氏が登場して、30分の講演と質疑の会となった。
ガバナンスボードというのは,実質的にはしっかりとインナーで,仮に人数が見かけ多くても実質やっているのはせいぜい5人や,6人です。だから逆に人数を絞ってしまってもいいのですけれども,そんなに人数は必要ないので。本当にやる気のある人の少人数で組んだほうが,ガバナンスボードが私は機能すると思います。だから人数はそんなに必要ないです。
結局,日本の理事会は理事長が一番偉くて,ほかの理事は何か業務執行理事みたいな理事長の部下みたいになってしまっているから,あれはやはりまずくて,アメリカのボードでいったらボードはあくまでもガバナンスボードなので,そこが学長を選ぶという形式ですから。最近学長に対してCEOという名前までつけてしまって,CEOを選ぶという仕組みなので,その関係性はしっかりと整理しなければいけないのと,ですからもし評議員会をボードと位置づけ,理事会というのは経営執行会議と位置づけるのであれば,それは評議員会をもっとスモールサイズにして,そこに本当に人材を得ることが必要になると思っています。
実際,どういう人で構成されているかというのは,ほとんどがその大学を卒業した著名な経営者,弁護士などそういう士業の人,それから一部学者です。そういう構成で,学者もどちらかというと大学経営をやっていた人が多いです。
冨山氏は自らが留学していたスタンフォードのイメージを理想のモデルとしているようだが、アメリカの著名な大学のケースからボード、理事会、CEOというモデルで話している。
とても面白い話で、冨山氏がかつて日本の大学を「G型」「L型」に分けるべきだという主張をしていたときと同じ発想で、理想形を語って、そこに進むイメージだろう。G型、L型では、地方の大学でシェイクスピアを教える教えないとか些末な話で、本道から外れる展開になってしまったが。
今回の会議では、毎回、論点整理がされている。
担当している八田氏と松本氏はたいへんだろうと思う。
だいたい論点は見えてきている。
一番は、評議員会。
理事会を議決機関とし、評議員会は諮問機関というこれまでの位置づけを変える。
評議員会が最終権限を持つべき。
しかし、すべてを議決するわけではなく、学校法人の運営に関する重要事項の承認を行うが、何を重要事項にするかということ。
評議員の義務・責任についても善管注意義務で損害賠償責任も負うが、訴訟などの形をどう考えるか。
評議員の適格基準はどうか。
現職の教職員について排除するべきか否か。今は排除でまとまっているが。
評議員の選任方式について、例えば独立の評議員選定委員会の設置の義務付けはどうか。
誰が評議員を監督するのか。相互監視というのが到達点。
任期は「理事と同等以上とする」でどうか。
人数をどうするか。
一般社団,財団法人では3人以上としているが、評議員会の実態把握や公益法人,社会福祉法人の実態を考えてどうするか。
あとは、理事会と理事長。
学校長を理事とするかどうか。理事の中から学校長を選ぶべきとか議論あり。
理事長の選任プロセスを透明化すべきでないか。
監事は常勤にするかどうか。
直近の会議の配布資料で、現在の議論の到達点はわかる。
2. 会社も国立大学もガバナンス改革ってやっているよね、それって何?
企業のガバナンス改革は2015年にコーポレート・ガバナンスコードや監査委員会設置会社などが導入された。
国立大学法人なんかも2020年に協会としてガバナンス・コードを発表している。
でもまあ、そのときに協会長はこんなことを言っている。
本ガバナンス・コードの各基本原則、原則、補充原則について、各国立大学法人の特性に鑑み実施していない場合には、「実施していない理由」を十分に説明することが求められます。そのため、一部の事項について「実施していない理由」を説明していることをもって、ガバナンスの体制が構築されていないと機械的に判断されるべきものではありません。
国立大学をまとめるのは、なかなか難しい仕事なのだろう。
公益法人も2019年にガバナンス・コードを協会として発表した。
こちらも有識者会議が報告書を出している。
3. なんで私立学校が反対するのか?
まあ、ガバナンス改革は世の流れで、経営者を監督する「機関」を機能させるという方向に動いている。それが会社では「株主総会」であり、学校法人では「評議員会」なのだ。
しかし、どうして私立学校の経営者はその改革に反対するのか?
一言でいえば、「理事会の自由が減る」ってことなんだろう。
「仲間うちでやっている評議員会に監督なんてできない」
「かといって、法的責任を負わせたりすると成り手なんていない。だいたいがボランティアなんだから」
「これまでの改革の流れと違う。2年前の改正のモニタリングもない」
「幼稚園法人と大学法人を同じにするつもりかっ! 人も金もない!」
ってのも、言い分はよくわかる。
教職員組合の見解がビミョーだ。
学問の自由、大学の自治という憲法に書き込まれたことから派生する教授会自治。
教授会が必要ってのは、私立学校法にはないけど、学校教育法にはあるのでややこしい。
私大経営者は、教学と経営は分離できないという反論している。
「仲間うち」という表現はよくないが、教授会参加者が経営の監督をする場所に参加すべきというのは、教職員組合も同じようだ。
日本私大教連が声明を出している。評議員会が独立組織で理事を排除し、理事会を監督するのはいいが、教職員を評議員に入れよと言っている。
「学内関係者」のうち、理事を評議員から除外することについては賛成です。教職員については、評議員となる教職員が理事長・理事会の意向から独立しているためには、理事長が実質指名するなど理事長・理事会が関与して選ばれた教職員ではなく、教学機関を代表する教員(職員もありえます)、民主的な手続きを経て選任された職員であることなど、透明性のある民主的な選任方法が重要です。
また、評議員会が社会に開かれた機関であることは、不祥事対応だけではなく、在学生とその保護者、卒業生、寄附者、地域住民、国民・市民といった幅広い「ステークホルダー」によって支えられている私立大学の公共性を担保するために必須です。ぜひとも、私立大学の教育・研究及び私立学校の運営・経営に見識のある人々の参加を求めたいと思います。
https://jfpu.org/wp-content/uploads/2021/09/20210921_yoseisho_mextgovernance.pdf
大学法人の一番の懸念は新たな権力抗争
大学法人の経営者の一番の心配は、評議員会に理事の選任、解任の権限を与えることは、学内抗争が激しくなるのではないかということだろう。
ヒアリングの後、私大連盟の田中会長は、改めて「意見と提案」を文科省の義本事務次官に渡している。
学校法人には経営と教学の間の緊張関係があり、学部等の組織によっても異なる利害関係が生じ、経営判断に学内の対立を伴うことも多い。特に不適切なリーダーを解任するというガバナンスの発揮は、あくまで業務に対する牽制・監督を目的になされる必要があるが、それを超えて学内の対立構造が持ち込まれると、評議員会が主導権争いを誘発する紛争の場となるおそれがある。
<提案>理事の解任手続きは、監事と評議員会の連携により、法令違反等の事由や職務執行状況に関する監事の意見に基づいて、評議員会と異なる第三者などの委員会を活用する仕組みを講じることが適切であり、ガバナンスの正当性が高まると考える。
「不適切なリーダーを解任するというガバナンスの発揮は、あくまで業務に対する牽制・監督を目的になされる必要があるが、それを超えて学内の対立構造が持ち込まれると、評議員会が主導権争いを誘発する紛争の場となるおそれがある。」
学長選挙で激しい抗争を経験している大学ほど、そういう危機感が強くなるのだろう。
評議員が減ることに反対する者はいないと思う。
しかし、誰が評議員になるのか、どうやってそれを選ぶのか、評議員を誰が辞めさせることができるのか。そういうことが今度は学長選挙以上に大事になる。
ガバナンス改革会議メンバーとの認識の乖離
ガバナンス改革会議の多くのメンバーは、コーポレート・ガバナンス改革とのアナロジーで考えるのだと思う。今回の場合、経営体とステークホルダーのうち、「経営者」「取締役会」「株主総会」「従業員」の関係でとらえるのだろう。
企業の形態でも「監査役設置会社型」「指名委員会等設置会社型」「監査等委員会設置会社」という形が選ぶことができる。指名委員会設置会社を選ぶ会社は少なく、外国人投資家に人気のない監査等委員会設置会社を選ぶケースが一番多い。日本はグローバル基準から考えれば遅れているのだ。
それはともかく、「経営者」「取締役会」の課題は、「監督」と「執行」の区分。「株主総会」の「監督」権限を強める方向に動いているのがコーポレート・ガバナンスの実際だ。
これを大学法人とのアナロジーで考えると、「理事」「理事会」「評議員会」「教職員」の関係で、「執行」と「監督」の区分はどうなっているだろうか。
執行役員を置く大学法人もあるが、「理事」の執行・監督の権限もあいまいなところが多い。「評議員」と「理事」が兼務するなんて、コーポレート・ガバナンスの構図から言えばあり得ないだろう。
ましてや「教職員」が「評議員会」の構成メンバーになることは、「従業員」が「株主総会」で権利を行使するようなものになる。最近、従業員持株会の効用についての研究もあるが、持ち株率は上場企業の市場で1%程度だ。あくまで従業員のインセンティブって位置づけだ。それに従業員が株主総会で権利行使することはあり得ないだろう。業務執行すべき従業員が、上から理事会を監督しているのである。
https://www.jpx.co.jp/markets/statistics-equities/examination/tvdivq0000001xhe-att/employee_2018.pdf
しかし、大学法人の評議員会の実際は、今も従業員が株主総会の半分以上を占めるところもあるという構図なのだ。
これは、伝統的に大学の学長を選挙で選んでいたという伝統と組織風土がそうさせているのだろう。学長は自動的に理事の一人になるのだが、それを理事会が拒否することは極めて困難になっている。
ガバナンス改革会議の多くのメンバーには、ガバナンスと呼べないこの状況こそ変えるべき対象に映るのだろう。
幼稚園法人と大学法人がいっしょのガバナンスでいいのか?
第5回の会議は面白かった。
反対の訴えを各団体がやっていたが、とくに小学校や幼稚園の協会の声は痛切に聞こえた。
反対する意見があると、いつもモンテスキューの法の精神を引き合いに出して、三権分立を否定するのかと言う委員もいる。企業のガバナンス改革や公益法人とのアナロジー、海外大学との競争でのランキングダウンとか出してくる委員もいて、私学側にとっては手ごわい。
それはそれで勉強になるのだが、幼稚園協会の代表が「幼稚園は保育所ほど補助金もない。もともと田畑を提供して近隣のためにやっていた園長も多い。バスの運転をしている園長もいる。大学法人と同じように考えないでほしい」という趣旨の発言には考えさせられた。
しかし、委員側は幼稚園連合会の不正を引き合いに出して反論していた。
そんな事件知らなかった。論点ずらしだが、ああいうのは論争では有効だと思った。
まあ、日大事件を引き合いに出すのも、同じ手法ともいえる。不祥事が目立ってしまって、ガバナンスとは何か? それは何のためにあるのかを考えるのが吹っ飛んでしまうように思える。
しかし、私学側は、結局、経営体で監督する機関を機能させることは大事でしょ、というところへの決定的な反論はできなかったと思う。
まあ、世の流れだものね。これ、まともに反論できる人、いるのかね?
4. ガバナンス改革が先行している社会福祉法人では不祥事はなくなったのか?
会議の第6回には、都道府県知事会の代表へのヒアリングがあった。
といっても、東京都の私学担当者がとりまとめて意見書を出しただけ。
でも、この伊予課長という人、なかなかの切れ者。
先行している社会福祉法人や公益法人レベルにすると言っているが、社会福祉法人のガバナンス改革で不祥事は減ったのか? そういうエビデンスがあってこの改革を進めているのかという指摘をした。
それには、またモンテスキューをすぐに引き合いに出す委員が、モンテスキューの三権分立で反論する。けれど、伊予課長が「モンテスキューはわかりますが、今は現にある日本の大学とか小学校とかの私立学校の話をしているんです」と切り返し、モンテスキューは空振りの感あり。
野村修也教授に至っては、エビデンスは関係ない!とまで言い出す。それはいくらガバナンスの有名教授でも無茶でしょ。
伊予課長は「文科省事務局は調べたのですか?」と、文科省に矛先を向けた。
おっと、これには、文科省の相原課長補佐、「文科省管轄の学校法人の不祥事はわかるが、社会福祉法人はその管轄に問い合わせないとわからない」との回答。
ここで、官僚を外して進めたこの会議のボロがでたみたいに感じた。いや、伊予課長と相原課長補佐は以心伝心だったのか?
ああ、この種のエビデンスなしでこの改革議論を始めたんだ、と誰もがわかった瞬間だった。
5. 社会福祉法人の不祥事の増減(じんたろ法律事務所しらべ)
そこで、じんたろ法律事務所がググった。
ちょっとググっただけ。
それでわかったことがある。
2017年まで、社会福祉法人では不祥事が多かった。読売新聞の調査では、寄付金が1億二千万円使途不明になっているところもあったり、カラ給与、理事長が2億円以上の私的流用をしたり、ひどいところが多かった。
2009~13年度に、役員が運営費を私的流用したり、理事会の承認を得ずに高額報酬を受け取ったりするなどの「公私混同」が65法人で確認された。うち13年度末までに、29法人は同法に基づく改善命令を受けた。寄付金約1億7000万円が使途不明になり、理事長が一部を私的に流用していた埼玉県内の社福は、改善命令に応じず、12年7月に解散命令を受けている。
65法人のうち約7割が、「理事長が年間2000万円の報酬を理事会の承認を得ずに受け取っていた」(浜松市)など、金銭に絡む不正だった。横浜市の社福の元理事長は06~08年頃、最大で月225万円を受け取り、勤務実態のない妻や長男にも月20万~100万円の給料が支払われていた。元理事長の流用総額は約2億2500万円。同市は社福への通知文書で、「理事会が機能しておらず、不適切な支出を抑止できなかった」と指摘した。」
それで、ガバナンス改革が進められ、2017年から評議員会を必置にして理事を解任できるようにするなど、法律を改正した。
従来の評議員会の位置づけは理事会の諮問機関で、地域の住民や福祉関係者の声を法人の運営に反映させる役割を担ってきました。これが社会福祉法の改正により、諮問機関ではなく議決機関となりました。
すべての社会福祉法人に評議員会が設置されることになったのです。
それで、実際に不祥事はなくなったのか?
いや、そんなことはない。
ないどころか、これまでになかったことも起きている。
社会福祉法人の理事などに意中の人物を選任してもらう見返りに、選任権を持つ評議員に現金を渡したとして、山梨県警と大阪府警の合同捜査本部は25日、社会福祉法違反(贈賄)容疑で、社会福祉法人「大寿会」(甲府市)の理事長高橋克己容疑者(49)=山梨県甲斐市=ら3人を逮捕した。同法違反(収賄)容疑で評議員の5人も逮捕した。
あれれ?
新たな犯罪が起きてるよ。
評議員会を必置にして、理事の選任・解任に権限を持たせたら、評議員を買収した。
山梨県の法人なのに奈良県のブローカーが暗躍した。
これって、2019年の事件。
でも、なんで民間事業所なのに贈収賄って、公務員対象の法律が適用されるのか?
2016年の社会福祉法改正(16年改正)で役員に贈収賄罪を課すようになったのは、社会保障費の増大とともに、一部法人の放漫経営や会計処理の透明性などが次々に露呈し、組織運営のガバナンスや会計監査の必要性が迫られたためだ。
ほかにも、栃木県の瑞宝会の不正受給とかもあった。
障害者支援サービスを手掛ける社会福祉法人「瑞宝会」(宇都宮市)が、介護給付費など計約4500万円を不正に受給したとして、14日から来年6月13日まで、運営する施設3カ所で新規利用者の受け入れを禁止する行政処分を出した。
ほかにもある。東京都の武蔵野会は、障害者の虐待から、次々に過去の事故が明るみになった。問題は報告義務を怠っていたこと。
都内を中心に25カ所で福祉施設を運営する社会福祉法人「武蔵野会」(東京都)が運営。大島恵の園では、入所者間の暴行や骨折事故などを都に報告していなかったことが2018~19年に明らかになり、都から改善指導を受けていた。
ガバナンス改革で不祥事がなくなるわけではない。
まあ、当たり前だが。
減ったかどうかはわからないが、贈収賄という新たな犯罪類型ができたのも事実。
オレオレ詐欺のような特殊詐欺でも、預貯金詐欺、それからキャッシュカード詐欺盗、架空金請求詐欺、コロナになったら給付金詐欺とか次々起きる。
防ぐしくみを作っても、もともと人間の善悪の量が増えたり、減ったりするわけではない。
6. 日大横領事件は防げるの?
で、本題にもどって、今回のガバナンス改革の肝の部分で日本大学事件は防げるのか?
おそらくあの手の横領事件を防ぐことはできないでしょう。
日大横領事件は、たぶん内部告発でわかったこと。ああいう事件は、会計監査人だと知らないし、わからない。ふつうの監事も同じ。最初の複数業者の見積もりまで調べられれば、予算より相場が低いことがわかるけど、それができるのは相当な人。その先のペーパーカンパニーとなると特捜以外に捜査はできないだろう。あの手の事件は内部の人間か、落とされた業者が告発する。それは、京大の霊長類研究所事件も同じだった。同志社のごみ処理無免許問題も同じ。おそらく、内部者が競合業者以外には知りえない事実。
こんな事件は防げないけど、「学校法人ガバナンス改革」で盛り込まれている評議員会の権限強化を実行すると、井ノ口理事だけでなく、田中理事長もすぐに辞めさせられる。
だって、株式会社日大事業部に委託した契約主はおそらく田中理事長だもんね。
日大は理事会で井ノ口理事の辞任勧告決議を上げただけ。
この人が辞任したから騒ぎは終わりってことではない。
7.非営利組織のガバナンスをどう捉えるべきか?
『非営利組織のガバナンス』という本がある。非営利組織に詳しいアメリカの研究者が書いている。
非営利組織に共通する「トラスティシップ」という概念を用いて、非営利組織を運営するリーダーシップとしてのガバナンスについて、3つのモードが必要だということを説明している。
トラスティシップとは、理事や受託者としての職務のあり方。trasteeは受託者、評議員、理事の意。
非営利組織のリーダーシップとしてのガバナンスのモードには3つある。
タイプⅠ:受託モード
タイプⅡ:戦略モード
タイプⅢ:創発モード
簡単にいうと、「受託モード」というのは、ステークホルダーの信託を受けているという自覚で、責任を官僚組織を使ってゴリゴリ行うこと。これは、エージェント理論から考えても同じ。監督されているという意識。それは当たり前のこと。
「戦略モード」は、マイケル・ポーターのような発想で戦略を描き、それを実行すること。そのときには必ずしも上意下達ばかりで動かすのがいいとはいえない。ミンツバーグの言うように創発的、またはプロジェクトや委員会方式でイシューで動かすのがいいときもある。
「創発モード」は、非営利組織は役員と従事者で構成される。多くの場合、事務局と言ってもよい。それらとのコミュニケーション、役員は境界にいたり、現場に立ったりして仕事をすることが必要。
非営利法人のガバナンスでは、その3つのモード切替、または複数を同時に使うことが大事。
ガバナンスというのは、使う人によって定義が違うが、組織の骨格やきまりごとを作り、それを使って運営すること、って感じかな。
骨格のなかの肉や内臓にあたるのを動かすのが、マネジメントってことだと思う。不祥事や不正は肉体の病気みたいなもの。マネジメント(運営)の過程で起きる。
ガバナンス問題が、ハードローの法律改正から、コーポレートガバナンス・コードというソフトローに移っていくのは、本当はどうマネジメントするかってことろが大事だから。
今回の学校法人ガバナンス改革は、ステークホルダーから「委託」されている非営利組織が、「受託」されているという骨格を作る提案なんだろう。
それ自身はまっとうな提案だが、長年、大学はCEOを従業員が選んでいたという「受託」よりも自己利益の追求を「大学の自治=学問の自由」だと信じてきた伝統がある。憲法に書き込まれたのは、大学が国家の戦争に加担した反省のためだった。その国家から「学問の自由=真理の探究」を守るってことだったはずのに、なんか明後日の方向に大学の歴史は動いた。私立大学では、真理の探究はどっかに行って、自分たちの自由の追求だけが残ったって感じ。
このおかしなガバナンスがここで修正されるかどうか、それは実はこの「大学の自治」=学長選挙を無くせるかどうかが問題の核心なのかもしれない。
組織のガバナンスの視点では、骨格を作り、局面に応じてモードを切り替える。これはアメリカの非営利法人の研究者なら当たり前。日本じゃ、違う理屈が成り立つのかもしれないけどね。
いずれにせよ、法改正でどんな骨格になろうとも、ガバナンス視点でモードを切り替え、肉体を動かす。それが組織の基本。そうしているうちにうまくいけば、不正としての不祥事は減るでしょう。
確かなエビデンスはないけど、原理的にはそういうことだと思う。
善悪の「悪」を発揮する人もその組織のなかで減ってくるんじゃないかな?
たぶん、ステークホルダーから委託された自分たちの組織だという自覚が芽生えてくるから、組織の健康に気を付ける。
そうやっていくのが「ガバナンスの骨格」をつくることじゃないかと思う。
日大ではその道のりはまだ遠いような気がする。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
