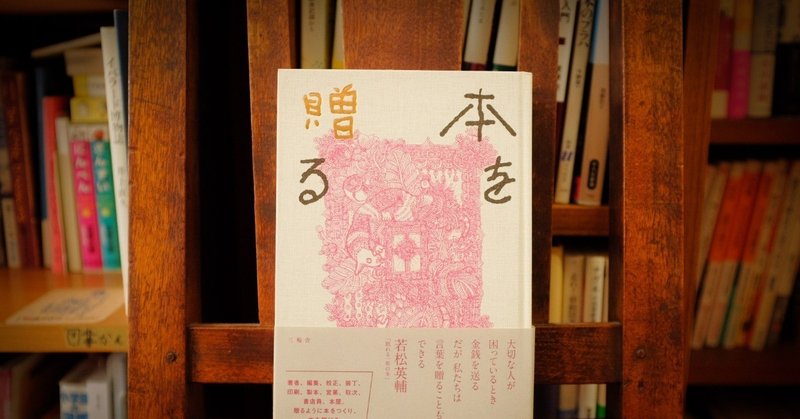
贈り、贈られて
この秋、とても素敵な本を手に入れました。
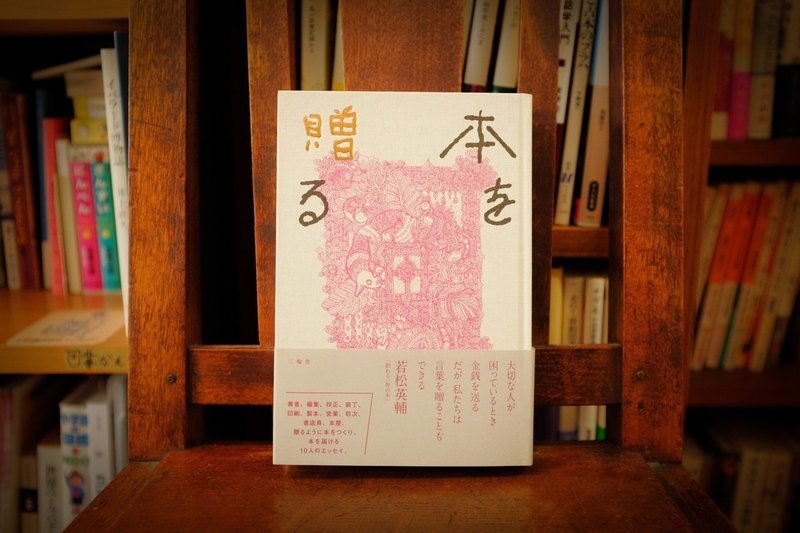
『本を贈る』
「出版業界はもう厳しい」と言われる一方で(いや、そうだからこそなお、でしょうか)、出版に携わるさまざまな、そして多くの人たちが、創意工夫を凝らし、人と人との間をつなぎ、そして情熱を込めて、本を作り、本を売るための営みを続けています。そんな状況を反映するように、今、書店に行くと、実に多様な「本の本」に出合います。いずれも魅力的な本ばかりなのですが、それらのなかでも、この『本を贈る』の魅力は際立っている、と感じています(あくまでも私見です)。
「本を贈る」という共通するテーマについて、本をつくり、本を届けることに携わる、編集者>装丁家>校正者>印刷>製本>取次>出版営業>書店・本屋>文筆家……が、それぞれに思い考えたことを綴ったエッセイ集です。
読み進むほどに、手に持っているその本がどういう道のりを、人の手を経てやってきたのかに思いが及び、ますます愛おしくなっていきました。このような感じを覚える本は、滅多にないと思います。そして、それぞれの人にとっての「贈る」で想定されていることが、意外やそれぞれに別の方向を向いていて、それがまた印象的でもあります。
プロがそれぞれの専門性を遺憾なく発揮し、本を読者へ届ける。そのためのリレーが私はすきだ。組織や会社や、利害関係、あるいはしがらみのなかで本をつくり、そして売ることは、大変なこともあるけれど、未来へ言葉をつないでいく。
(p.165:本は特別なものじゃない・笠井瑠美子・製本)
そう、本が一人の読者の手に届くまでの、思いの込もったリレーを、ぜひ味わっていただければと思います。
……と、ついつい前のめりで『本を贈る』についての話をしてしまいましたが、今回の記事のテーマは、その書名からいただいて「本を贈る」ということについて。
本をプレゼントとして贈ることは、結構難しい、としばしば耳にします。
ぼくにとって本は重たい贈り物だった。もらった側からすれば、もらっても読まない、読んだけど合わない、ということもあるはず。感想を求めて、面白くなかったと言われたらどうしよう。そもそも、感想がないということは読んでもいないんじゃないか。そんな風にぼくは勝手にもやもやして、「本を贈る」ことからどんどん遠ざかっていった。
(p.41:女神はあなたを見ている・矢萩多聞・装丁家)
まさにこの多聞さんの言葉のように、贈る側にとっても、贈られる側にとっても。人の本の好みというものは、なかなかわからないものなのではないか。もらっても困るんじゃないか、気を遣わせるんじゃないか、という気持ちが募る……ようです。私自身も、以前には同じように感じていました。
でも、本は手元を離れてしまえば、そこからはもう相手のもの。それは、著者にとっても、出版社にとっても、書店にとってもそうであるのと同様に、「贈り主」にとっても。そのように考えて、「贈る」という営み自体を、自分が心より楽しみながら行うのであれば、受け取る人が嫌な気持ちになる、ということはそうそう起こらないのではないでしょうか。
いつ、何がきっかけだったのかはまったく覚えていないのですが、今、自分にとって誰かに本を贈るという営みは、ごく自然で、また心が弾むことになっています。主には家族やごく親しい友人という信頼関係があるからこそ、だとは思いますが。また、「本“だけ”を贈る」ではなく、何かの機会に合わせて「本“も”贈る」ようにすると、心のハードルも下がるのではないかと思います。
ということで、まずは私が、誰かに「贈った本」について。
齋藤亮一『佳き日』は、たぶん私がもっとも多く、人に贈ってきた本(写真集)です。いちばん身近なところでは母に、そして2011年の東日本大震災以降、何かを贈りたいと思ったときには、まず一番にこの本を、届けてきました。一人一人が、それぞれにつらく厳しい日々を送るなかで、何気ない日常のなかにある“佳き日”の有り様を思い起こさせてくれる。自分自身、とてもとても強い勇気をもらった本で、今もなお、多くの人に見てほしい1冊です。
それほど遠くではないものの、年に数回しか会うことのない母には、考えてみると学生時代の一人旅のときから、折々にちょっとしたものを贈る習慣がありました。年を重ね、「もうあまりモノはいらないよ」と言われたこともあって、最近ではCDや本を贈るということが増えてきました(どちらもモノ、ではありますが、でも贈っているのはモノではないのですよね)。
前述の『佳き日』もその1冊。そしてほかに印象的だったものとしては、長田弘『ことばの果実』。誕生日だったか何かの記念日に、本を贈ろうと書店の棚をぶらりぶらり。著者名とそのタイトルがふと目に止まり、棚から取り出して見ると、まるで爽やかな香りが立ち上ってきそうな鮮やかなオレンジの絵の表紙。フィルムがかけらていたので中を読むことはできませんでしたが、この造本だけでも十分に「これを贈ろう」と感じられる1冊でした。
ふだん身近にいる妻にも、何かの折に本を贈り物にしてきています(若干、ほかのものを考えなくてよい、という思考停止の面もあるのですが……)。同じく長田弘『深呼吸の必要』を贈ったのは、仕事上の問題でいろいろ行き詰まっていて、日々しんどそうだなあ、と感じられていたとき。また飯島都陽子『魔女の12ヵ月』を贈ったときは、こちらはたまたまですが、やはり仕事で(日本の)薬草など昔の生活の知恵の文化について調べていたタイミングでした。このように偶然にぴったりと重なる、引き寄せるような感じは、あくまで自らが目の前の事象をそのように“読む”から、なのでしょうけれど、それでも何だか楽しくなる瞬間です。
詩と朗読をこよなく愛する友人には、岩崎航『点滴ポール 生き抜くという旗印』を。厳しい状況のなかから生まれた、意思のこもった凛とした五行詩の数々。静謐な写真と装丁も素敵なこの詩集は、きっとこれからも誰かへの贈り物にしていきたいなと思っています。そして結婚をして新しい生活に入ったばかりの友人夫婦には、吉野弘『二人が睦まじくいるためには』を。共にいる二人にとってはもちろん、いろいろな人生の立場において、多くの人の心に沁みる詩集ですね。今、自分の手元にはないので、いずれ手に入れて長く長く大事にしたい本です。こうしてみると、詩の本というのは、きちんと思いを込めつつも、比較的気軽に贈りやすい本なのかもしれません。
ときどき、何人かの親しい友人たちと、一つのテーマについて本(+食べ物やら余興やら)を持ち寄り、思い思いに話し合う小さな読書会を開いています。2年前の年末に開催したときのテーマが、まさに「贈り物」。そこでお互いが持ち寄ったさまざまな「贈り物」についての本も非常に興味深かったのですが、それに加えて、クリスマスの時期ということもあって企画した「本のプレゼント交換」が、これまたとても素晴らしかったのです。お互いに1冊ずつ、プレゼント本を持ち寄り、輪になって回していって贈り合う。それぞれの手元にやってきた包みを開くと、そこでまた一つずつ、印象的な話が披露されるのです。

(※2年前の読書会の際の、「贈り物」に関する私の選書です)
これはおそらく、私たちの読書会の恒例行事になりそうです。昨年末にも行い、その際に私が選んだのは、坂本千明『退屈をあげる』。かわいらしく、そして切ない物語。今、この慌ただしい世界にあって、退屈をくれる存在。この本は現在、青土社から刊行されていますが、もともとは作家さん自身の自主制作本からスタートしています。たまたま原画である版画の展示を見に行ったことがあり、そのときからとても魅了されている作品です。
さて、続いては、私が人から「贈られた本」について。
私の両親は、本を買うことについてはかなり寛容だったので、ふだんからさまざまな本を買ってもらっているほうだったと思います。それでも誕生日のような機会には、やはりプレゼント、というかたちで本を贈ってもらいました。なかでも特に印象的なのは、12歳の誕生日に贈られた吉川英治『三国志』(六興出版の全10巻本、白地に黄色の切り替えパターン)。これだけのボリュームのものを一気に、という今思えば相当贅沢なプレゼントで、当時は横山光輝の三国志がちょうどアニメ化された時期でしたが、それを脇目に、この本を熱中して読んだのはよい思い出です。
仕事でよく訪れる大きめの書店で、歴史まんがシリーズのセットなど、ちょっと特別な感じのある本を購入している家族を見かけることがときどきあります。きっと、クリスマスや誕生日などのタイミングなのでしょう。自分の子供の頃のことを思い出しつつ、会計をする親の隣で、子供たちがワクワクしたとてもよい顔をしていて、見ているこちらも嬉しくなる光景です。
私から贈るのと同様に、妻からもさまざまな本を贈ってもらっています。そのなかでも特に気に入っているのは、初めの頃にもらった「APIED vol.11|尾崎翠『第七官界彷徨』ほか」でしょうか。さわやかなミントグリーンに繊細な植物画の描かれた装丁。尾崎翠の作品の世界観を包むかたちとしてとてもふさわしいものだと思います。
友人から贈られた本にも印象深いものがあります。トーベ・ヤンソン『旅のスケッチ』は、ヤンソンの静かな毒(褒め言葉です)がじわじわと味わえる、初期短編集。ヤンソン自身が手掛けた挿画も、またシンプルで美しい装丁も魅力的で、手元に置いておきたい1冊です。またこの本は、友人と小さなチェコ料理屋さんに行き、美味しいチェコ料理とビールをいただきながら、本やアートのことなどをたっぷり話し合ったときにもらったもので、そんな具体的な記憶と結びつくのも、贈り物としての本のよいところだと思います。
結婚のお祝いとしていただいた本もありました。ピーター・トレメイン『アイルランド幻想』です。私たち夫婦が、新婚旅行でアイルランドに行ったので、そこから連想して、元々は妻の知己であった友人からいただいたものです。美しいタイトルとは裏腹に、伝承・幻想物語の宝庫でアイルランドを舞台に、怪奇的なエピソードが繰り広げられる短編集。超自然の存在は畏怖すべきものですが、でもいちばん恐ろしいのは人間の心理のほうなのかもしれない、と感じさせられます。夫婦の間に生じる狂気の物語などもあり、結婚祝いの本としては相手を選ぶ選書だと思いますが(笑)、私たちにとってはお気に入りの本で、友人のセンスに脱帽です。
贈られた本として最後に紹介するのは、ヨースタイン・ゴルデル『ソフィーの世界』。中学3年生のとき、私は体育祭で脚の骨を折り、しばらく入院することになりました。そのとき、部活動の顧問の先生がお見舞いとして持ってきてくれたのがこの本でした。600ページを超える分厚い本ですが、ミステリーをベースとした巧みな構成、共感しやすい登場人物の設定、凝った美しい装丁と、惹きつけられる要素に溢れていました。けがのために手持ち無沙汰だった、という状況はもちろん、ちょうど世界に対して“なぜ”を感じてくる年頃だったことも相まって、一気に読み通しました。
「哲学」というものに初めて触れるきっかけとなって、その後の高校、大学での学問との向き合い方の一つの軸となり、またとにかく立ち止まり考えることを辞めない、という今に至るまでの生き方に深く影響を及ぼしており、まさに私の人生において欠かすことのできない本となりました。そして今、奇しくも、この本を刊行した出版社で本作りに携わっているわけですから、これは運命的な出合いと言ってもよいですね。(M先生、心より感謝しております)
私の「贈った本」「贈られた本」についてのお話は、ここまでです。が、最後にちょっと余談を。
我が家に訪れるサンタクロースは、子供の希望するプレゼントに加えて、毎年1冊、本も贈ってくれるのです。そして、これがまた不思議なことに、私が子供の頃もそうだったのですが、世代を超えて、現在、私の子供のところにもまた、そうして届けてくれるのです。
サンタから私の子供への、クリスマスの本の贈り物は、1歳のときのシシリー・メアリー・パーカー『フラワー・フェアリーズ(花の妖精たち)のお話』から始まりました。
2歳:ディック・ブルーナ『クリスマスって なあに』
3歳:レオ・レオーニ『いろいろ1ねん』
4歳:モーリス・センダック『そんなとき なんていう?』
5歳:ローラ・インガルス・ワイルダー(安野光雅 絵・訳)『森のプレゼント』
6歳:レイモンド・ブリッグズ『さむがりやのサンタ』
7歳:マーガレット・ワイズ・ブラウン『ちいさなもみのき』

クリスマスのお話を中心としつつ、子供の成長に合わせて、なんとも素敵な選書をして届けてくれるのです。たまたま祖父母の家に移動して過ごしたクリスマス・イブの夜にも、ちゃんと届けてくれたという経験もあったからでしょうか。ここ数年は、自分の希望するおもちゃが大本命なのは言うまでもありませんが、「サンタさん、ことしはなんのほんをくれるのかな?」と、いつもワクワクして待っています。
クリスマスまで、あと2ヶ月を切ったところ。今年はどんな本を持ってきてくれるのでしょうか。そして、願わくば、一年でも長く、サンタが我が家に本の贈り物を届け続けてくれますように。
贈るのも、贈られるのも、はじめはちょっと恥ずかしかったり、戸惑うことがあるかもしれません。でも、なじんでしまえば、こんなに素敵な贈り物もそうそうないのではないでしょうか。贈られてすぐに読んで楽しむのもよし、長く時間をおいてまた読むのもよし。その度に、本の向こうにいる人の顔と、贈られたときの物語が浮かんできて、何度も何度も豊かな気持ちを味わうことができると思います。
本の贈り物の楽しさ、ぜひ味わってみてください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
