
本のいのちをつなげる“人”

すっかり更新が滞ってしまっていて申し訳ありません。秋頃から「まとまった文章が全く書けない」状態に陥っておりました(本の仕事に関わる者としては由々しき事態ですが……)
さて、突然ですが、編集を担当した島薗進『いのちを“つくって”もいいですか?』についての読書会を開催することになりました。発売からちょうど1年後にあたる2017年1月29日(日)に行います。詳細はこちらをご覧ください。
本ブログ、4章まで書いたところで尻切れトンボのようになっておりましたが、読書会を開くことが決まったこともあり、書き残していたことをまとめて、きちんと環を閉じておきたいと思います。
ただ、本の内容に関わることは前回記事「ドコニモナイ、ドコニモナイクニ」までに留めたいと思います。5章「『いのちは授かりもの』の意味」はマイケル・J・サンデル『完全な人間を目指さなくてもよい理由』を、6章「小さないのちの捉え方」、7章「つながりのなかに生きるいのち」は日本人の宗教儀礼や文化慣習についての先行研究を議論の端緒に、また折々に参考にしながら、著者の考える試論が徐々にかたちとなっていきます。西欧的なキリスト教文化に根差すものとはまた異なる、日本やアジア諸国の文化・宗教的な要素を土台に据えた新たな倫理を打ち出せる可能性があるのではないか——そのように著者のメッセージが根底にあり、またそのために数々の著作が上げられるパートでもあるので、ここについてはぜひ本書のテキストそのものとじっくり向き合っていただければ幸いです。私自身、この部分について深めたいテーマは多々あるのですが、まだ混沌とした状態でもあるので、引き続き考え続けていきたいと思います。
本書にまつわる一連の文章を締めくくるにあたって記しておきたいのは、この本が出来上がるのを支えてくれた方々にまつわる、本の話です。
目次の次のページを開くと、そこには4名の方のお名前(皆、4字!)が記されています。
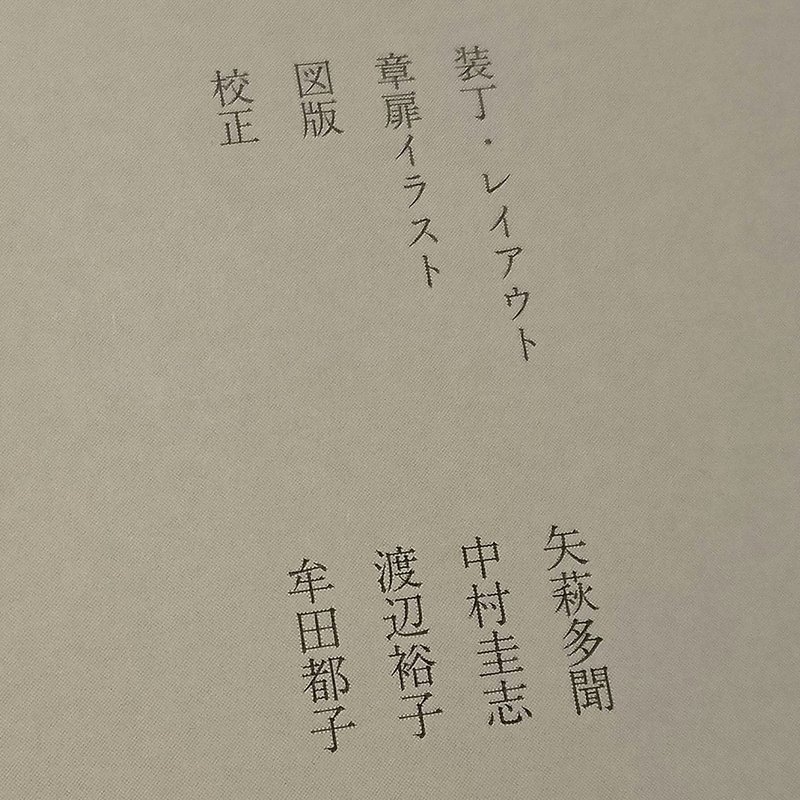
当然ながら、著者・島薗進さんの手に成る本書ではありますが、“本”としていのちを吹き込んでくれたのは、特にこの4名の方の支えによるものです。
iPS細胞の仕組みなど、科学的な説明に添える図版を描いてくれた渡辺裕子さんは、ふだんから月刊誌でもよくお世話になっているイラストレーター。説明的な要素は的確に、かつ人物やイメージカットはやわらかく親しみやすい雰囲気に仕上げてくれます。
ユニーク(でちょっぴり風刺の利いた)マンガも多く手掛けられていて、こちらは仕事とは別に、個人的に楽しませていただいております。
順番が前後しましたが、本書の装丁・レイアウトを手掛けてくれたのは装丁家の矢萩多聞さん。
私が初めて多聞さんの本を手にしたのは、確か大竹昭子編『ことばのポトラック』だったと思います。「おもしろい本だな」と外見から手に取り、クレジットで多聞さんの名前を見つけました。どこかで聞いたことがあるような気もしつつ、印象に残る名前。
実は既に読んでいた中島岳志『中村屋のボース』、『インドの時代』や佐野衛『書店の棚、本の気配』、森まゆみ・津田篤太郎『未来の漢方』など、素敵な装丁だな、と思って本を開くとしばしば多聞さんの名前に出会うことに。さらに、シリーズの装丁をされている〈就職しないで生きるには21〉のご自身の著書『偶然の装丁家』を読み、ガツーンと大きなショックを受けました。同じ年月を生きてきて(多聞さんは同い年)、同じ分野の仕事に携わっているけれど、こんなにも違った、密度の濃い生き方をしている人がいるなんて、と。ぜひ一度仕事を頼んでみたい、という思いが募る一方、自分の凡庸さや熱意の足りなさが恥ずかしくもなりました。
そんなことを感じていた2014年12月、多聞さんのツイートで、バングラデシュのレンガ職人たちを撮った写真展が開かれていることを知りました。独特の力強さのあるモノクロームの写真に、多聞さんがデザインした手製本の写真集があるとか。以前、ある縁があって旅をしたバングラデシュはとても思い入れのある土地でもあったので、展示最終日にコニカミノルタプラザに駆け込んだのです。
その写真を撮っていたのが吉田亮人さん。やはり同い年だった吉田さんとその場で意気投合し、いずれ京都で多聞さんも交えて再会しようということになりました。その後、一度は機会を逃してしたものの、2015年夏に東京で行われた上記の写真集『Brick Yard』にまつわる吉田さんと多聞さんの対談イベントにて、ようやくお話できました。やはり多聞さんが装丁を手掛けていた『アントニオ・タブッキ 反復の詩学』の著者であるイタリア文学者・花本知子さんと私が一緒にお仕事をしていたことなどもあり、短い時間ながら本にまつわるさまざまな話をして、また近いうちにかくかくしかじかの本の装丁をお願いするかもしれません、ということを伝えました。ただその装丁が好きだったことに留まらず、著書『偶然の装丁家』を読んで多聞さんは自分なりの死生観、いのちの捉え方を持っているのだなと感じ、きっと『いのちを〜』の主題をしっかりと汲んでくれるはず、という確信があったからです。
ようやく本の全体構成が見えてきた秋、正式に多聞さんに装丁・組版を依頼しました。多聞さんとの仕事のハイライトは、『偶然の装丁家』にも描かれていて、編集者など装丁を依頼する人には有名な「紙芝居プレゼン」。用意したラフ(およびその生成過程)を、相手の反応も見ながらタイミングよく提示していく、ライブ感たっぷりのまさに紙芝居。目の前で繰り広げられるストーリーは実におもしろく、そして最終的に辿り着いたデザインは文句なく素晴らしいものでした。自然光の入るカフェで目にしたあのプレゼンの感動は忘れられません。
その後も多聞さんは、ミシマ社の『ちゃぶ台』、吉田亮人さんの『Tannery』、川内有緒『晴れたら空に骨まいて』など、ひとつひとつ素敵な装丁をたくさん手掛け続けていて、また『たもんのインドだもん』の執筆や、絵の個展などにも大活躍。取材のことを少しだけうかがったことのある『紙の旅』も、そろそろ具体的にかたちが見られそうで、今から大変楽しみです。
続いては、各章トビラの絶妙な犬キャラクターのイラストを描いてくれた中村圭志さんのことを。
中村さんを形容するのはなかなか難しく……確かにイラストを描いてもらいましたが、専業のイラストレーターではありません。第一に優れた宗教学者であり、著述家・翻訳家。またイラストだけでなく、独特の世界観のある絵画を描いているアーティストでもあります。
中村さんには、『いのちを〜』の元となった連載「いのちとモノ」からイラストをお願いしていました。著者の島薗さんと打合せをして連載のテーマと原稿の進め方などを一通り決めたところで、イラストをどうするか、という話に。内容にゆるやかに関わりつつ、死をも扱うややデリケートな内容を緩和できるようなイラスト——ただ絵の雰囲気がよいだけではなく、内容を深く理解したうえで表現できる人に依頼する必要があります。そこで島薗さんから名前が挙がったのが中村さんでした。
名前を聞いてすぐに、『信じない人のための〈宗教〉講義』と『宗教のレトリック』を思い出しました。前者は、一定の距離を取りながら、その機能や意義を深く読み解く優れた論。後者はレトリック・修辞技法という切り口で宗教の存在やその機能を分析したもの。いずれも他にはない大胆な方法で本質に迫る論を展開していて、非常にインパクトを受けたことを覚えています。特に後者を読んでから中村さんのホームページなどにも目を通していて、宗教学研究室の先輩であること、絵を描く人であることも既に知っていました。
こうして、実は著者・イラストレーター・編集者がみな同じ宗教学研究室出身者、というチームでの連載がスタートしたのです。医療・健康情報の雑誌上において、「死、いのちの有限性を認識したうえで考える生、健康の意味」ということを隠しテーマとしたエッセイだったので、やわらかい文章を心がけたものの、それでもなかなかデリケートな要素を扱うことも多々。もし文章だけを読むのであれば、雑誌の連載としてはちょっと取り付きにくい面があったかもしれません。しかし中村さんに原稿を送ると、根底にある問題意識は完璧に汲みつつ、ユーモア溢れるアレンジを施してイラストに仕上げてくれたのです。著者の原稿をいちばん最初に読むのは編集者の特権ですが、中村さんから返ってくるイラストも全く同じ存在感を持っていて、連載中、私は毎月毎月それをワクワクしながら待っていました。『いのちを〜』には描き下ろしのカットもあり、連載分から採られたのはそのごく一部。24点のほとんどは、今皆さんにご覧いただくことはできない状態で、個人的に非常に残念なことだと感じています。
そうして2年間、中村さんには全ての原稿にも目を通してもらっていたので、書籍化の作業のなかでも、進捗を報告したり実際にイラストを発注する折に、いつも簡潔に的を射たアドバイスをいただき、『いのちを〜』が生まれるまでの過程を、始めから完成までずっとサポートしていただいたと感じています。
2014年に刊行された『教養としての宗教入門』が好評を博し、中村さんは世界各地のさまざまな宗教をフラットな目線で、かつ学術的な知を背景に語れる著者として、専門的な世界を超えて一躍注目を集めるようになりました。『教養として読む世界の教典』『世界5大宗教全史』など宗教学の本丸をわかりやすく説く本から、『徹底分析! ハリー・ポッター』『SEKAI NO OWARIの世界―カリスマバンドの神話空間を探る』のように宗教学的な視点でサブカルチャーをユニークに読み解く本まで、多彩な、そして一つ一つが本当によく練られた本を、次々と送り出しています。
イラストレーターとしての中村さんの魅力も大いに実感しつつ、『信じない人のための〈宗教〉講義』以来の惚れ込んでいる者として、中村さんと本を作りたい、と強く願っています。真打ちとなるある題材のほか、いくつかのテーマを考え、お話を伺っているところ。私にとって、今もっとも大切に磨きたい課題です。
最後は、校正を担当してくれた牟田都子さん。
今、今年でこそ、ドラマ「地味にスゴイ! 校閲ガール・河野悦子」によって校正・校閲という職業が世間一般に認知されるに至りましたが(といってよいのでしょうか?)、出版業に関わる人でなければ、その存在はほぼ知られていなかったと言ってよいのではないでしょうか。人・社によっては、出版業界の人でもその意義をちゃんと理解していないことさえあるかもしれません。
編集という仕事を10年以上も続けていると、校正・校閲者がいなければとんでもない事態になっていた、ということはもう数えきれないほど。個人的にその意義を感じていることに加えて、「誰もが発信者になれる」web時代において、はじめの騒ぎがすぎてそれが日常に近づいてくるに従って、校正・校閲というものが求められるようになっていくのではないか、ということを漠とではありますが考えていました。
牟田さんと初めて会ったのはちょうどそんなことを考えていた時期で、ある編集関係のイベントに参加し、アフタートークで意気投合。「編集ナイトがあるならば、次は校正ナイトをやりたいですね」という話をしたことを覚えています。それからちょうど一年後、なんと牟田さんは本当に「校正ナイト」を実現させてしまいました。当日参加できなかったのは残念でしたが、こちらの記事からもその熱量が伝わってきます。
出版社の校閲部に務める傍ら、ひとり校正者「栞社校正室」として活躍の場を広げている牟田さん。書籍編集の経験がほぼなく、特にこの人に、という頼るべき校正者を持っていない状態で、上の記事に見られるようなゲラに向き合う姿勢や、石橋毅史『口笛を吹きながら本を売る』のようなノンフィクションの校正を手掛けられていたことなどから、『いのちを〜』の校正を依頼することにしました。決して強い指示や表現はないものの、きめ細かく行き届いたチェックが本全体にわたってなされていて、著者の島薗さんもその丁寧が仕事ぶりにとても感嘆していました。
その後も栞社校正室は引く手あまたのようで、いつもお忙しくされているようです。鹿子裕史『へろへろ: 雑誌『ヨレヨレ』と「宅老所よりあい」の人々』、マリー・ムツキ・モケット『死者が立ち止まる場所』、若松英輔『悲しみの秘義』等々、粒ぞろいの素晴らしい本に校正者として携わっています。そして、これらの本の著者や編集者が牟田さんの校正を非常によく信頼していることが、あとがきやSNSでのやりとりから伺えます。本来、黒子的な存在である校正者が、第一にはその仕事の質が高いことが要因であるにせよ、名のある個人として評価さら、信頼されているということは、とても興味深いことだと思います。
どれだけ自分の手掛けることに誠意を込めて向き合えるのか。すべてはここに帰結するのではないでしょうか。そのようにして取り組む姿勢、およびその結果は、同じように物事に取り組んでいる人たちにとって、自ずと共感・共鳴できるものなのでしょう。すぐれた本には、それをつくる優れたスタッフ、チームが存在する。
その意味で、『いのちを〜』にはそれぞれの面で最高のスタッフが集い、支えられたことで、あのような1冊に仕上がったのだと確信しています。本をつくっているのは、すべて“人”なのだ——そんなことにも思いを馳せながら、多くの方にこれからも本書を長く読んでいっていただけることを、心から願っております。
(『いのちを“つくって”もいいですか?』に関する記事、これにて了)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
