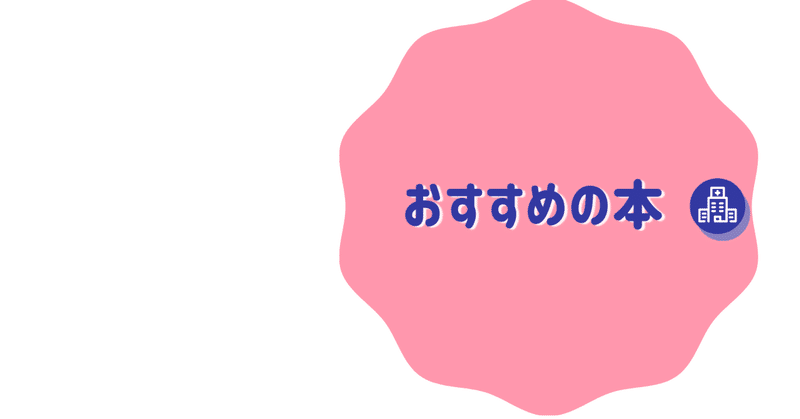
おすすめの本~診断エラー学のすすめ~
みなさん、「診断エラー」に関してご存知でしょうか?真剣に日々の診療にあたるなかでも「診断エラー」はある一定の確率で生じてしまいます。
しかし、そのエラーを防ぐ努力は臨床医である限り必要不可欠であり、責務であるといえるでしょう。
昨今、診断エラーは「患者の健康上の問題について、正確かつタイミングよく解釈できなかったり、その解釈が患者に説明されなかったりすること」と定義されており、医学的にも社会的にもインパクトのある問題と認識されるようになりました。
2001年に全米医学アカデミーから「To Err is Human」というレポートが出版され、米国では年間に4万4000人〜9万8000人が医療過誤で亡くなっているという事実が報告されました。
その後、診断エラーの領域において外来セッティングでは少なくとも成人患者の20人に1人は1年に1回誤診されるというデータもあります。特に我々が日々診療にあたる現場であるプライマリ・ケアの領域は特に隣り合わせの領域です。
したがって、今回は「診断エラー」を学ぶのにうってつけの本をご紹介いたします!診断エラー初心者の私を成長させてくれた2冊を前編と後編に分けてお伝えします。
1冊目は「診断エラー学のすすめ」です。

この本は日本病院総合診療医学会の若手部会診断エラーチームによる日経メディカル連載を基に作成されたものです。
ポイントは以下の3点です。
① 診断学の基本、診断プロセスに関しても学ぶことができる。
② 診断エラーとは何か、そして診断エラーをどのように分析するかを学ぶことができる。
③ 豊富なエラー症例における多角的な視点での考察がある。
①「診断学の基本、診断プロセスに関しても学ぶことができる。」
臨床推論で用いられる直感的思考と分析的思考からなるDual process theoryやSemantic qualifierの解説や鑑別診断の挙げ方などが丁寧に解説されています。診断学初学者でもスッと入っていけるような構成になっており、診断学ってよくわからないといった学生、初期研修医でも読みやすいです。さらに上級医にとっても不確実性への向き合い方や陰性感情への向き合い方など、自分の普段のプラクティスを見返すきっかけになる内容が記載されています。
②「診断エラーとは何か、そして診断エラーをどのように分析するかを学ぶことができる。」
個人的には診断エラーの総論を扱っている第2章が診断エラーの理解が進み、とても勉強になりました。診断エラーを定義することは難しく、その歴史的背景から解説いただいています。そして、昨今診断エラー研究が必要とされ、major journalでも取り上げられる機会が多いのですが、有用な診断エラーの測定方法が必要であるといわれています。現時点での診断エラーの測定方法に着目し、Revised Safer Dx instrumentやRoot cause analysisなどがわかりやすく説明されています。ぜひ一読いただきたい部分になっております。
③「豊富なエラー症例における多角的な視点での考察がある。」
実際著者らが経験したエラー症例が20症例以上記載されており、どの症例も明日の診療に活かせるものばかりになっています。いずれもbiomedicalな視点、さらにはnon-biomedicalな視点からも考察されています。診断エラーは知識不足などのbiomedicalな問題のみではなくnon-biomedicalな問題で生じることが多いです。忙しさや人手不足などのシステムに関連する要因、陰性感情を持ってしまう患者のキャラクターなどの患者要因、アンカリング(診断プロセスの早期に特定の特徴に固執する傾向)をはじめとした認知バイアスなども合わさることにより診断エラーは生じます。それらを具体的な症例で学ぶことが可能です。症例を通し学ぶことで、類似症例を診療する際に自分の思考をメタ認知することも可能になると考えます。
今週はここまでです。
向き合うことにエネルギーを要するテーマですが、臨床の現場では切っても切れないテーマでもあります。
次回、オススメのもう1冊をご紹介しますので、ぜひご覧ください。
(文責:會田 哲朗 福島県立医科大学 総合内科)
※当記事の内容は、所属する学会や組織としての意見ではなく投稿者個人の意見です。
LINE公式アカウントに友だち登録していただくと、最新note記事や、当チームの主催するセミナー・勉強会のご案内が届きます。
当チームに加わりたい・興味がある、という方は、LINE公式アカウントに友だち登録のうえ、【参加】とメッセージを送信してください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
