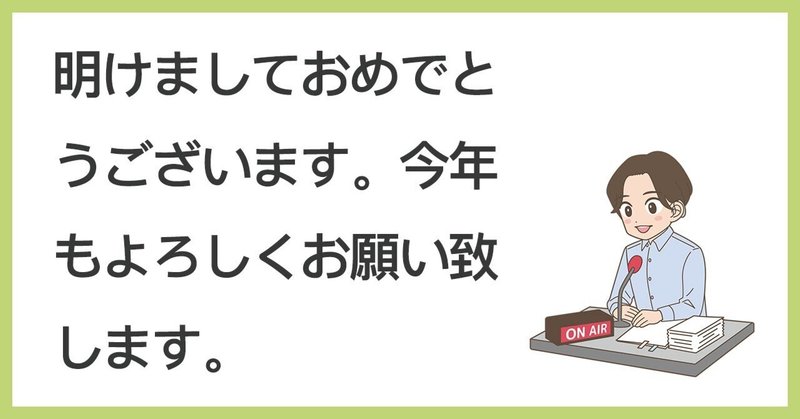
明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願い致します。
新年、明けまして、おめでとうございます。今年もよろしくお願い致します。
さて、今年一年はどのような一年にしていくのか。と考えたことをずらずらと書くのが通例かと思いますが、正直、私自身としては、今年もやることは変わりません。
私の目的は、難聴の方をより良く生活できるようにすることであり、そのための手段が変わることはあっても目的が変わることは(今の所)ないからです。
その目的は、新年になろうが、来年になろうが変わりません。時代の変化や取れる手段の変化によって変わる部分はあるのですが、本質の部分は変わらない、ということですね。
とはいえ、ここで終わるのもなんだか寂しいので、今回は、今後の補聴器のことでもお話ししていこうと思います。
AIが発達した世界における役割
さて、口調を元に戻そう。去年は、AIやらチャットGPTやらそういったAI元年の年だったように思う。
こういった話に付随して、AIが仕事を奪うとか、生き残るためにチャットGPTを使いこなせ、だのでてくるのは、新しい技術が出てくるたびに起こる一種のパターンなのだろう。恐らく、イギリスの産業革命の時も同じように機械が労働を奪う。と今のように声高々にして言っていたに違いない。
では、AIが発達した世界における補聴器、あるいは、補聴器に携わる人は、どのようになってくるのだろうか。
私は、AIやチャットGPTやら機械の方が優れてくることにより、教えるから、寄り添う。へのシフトにあると考えている。
今までは、販売する側、あるいは、提供する側に知識やらスキル、技術やらがあった。しかし、インターネットが発達し、さらにAIやチャットGPTやらが出てくると、その格差、情報の非対称性は徐々に少なくなってきた。(情報の非対称性とは、買い手と売り手の情報格差により、買い手側が不利な立場になること)
本質の部分はまだまだだが、調べればわかること、調べることで情報を得ることができるようになると、どんどん教えるという部分は、なくなってくる。調べればわかるようになってきたからだ。
では、そうなると補聴器はどのようになるのか。恐らく、教える。ではなくて、寄り添う。になってくるのではないか。と私は考えている。情報を教えるのではなく、お客様にとって大事な情報、重要になる情報をお互いに共有し、そして、共に良くしていく。協創スタイルといえばわかりやすいだろうか。
補聴器は知識があれば改善できるのか。というとそんなことはない。補聴器をどう調整するのか。という点は、相談しないといけないし、そもそもそこに正解はない。
一人一人難聴の程度から、音を感じる感覚。さらにどのような補聴器が良いかの好み。そういったものも入るので、正解なんて存在しない。
その事から私は、補聴器とは正解を作り上げていくもの。と考えていた。一人一人の状況が異なるのであれば、そもそも正解なんてない。だから、一人一人に合う正解という改善を作り上げていく必要がある。ということだ。
さらに今現在は、まだ補聴器を作るというところまでは行っていないので、補聴器をどのように作るか。周辺機器の部分から、ものによっては、考えていく必要も出てくるだろう。
ただ、一つ言えるのは、AIやチャットGPT、機械などの進歩が進めば進むほど、教える、から、寄り添うへ大きくシフトしていくのではないか、と考えている。
変わる価値観
今まで、このような業態については、知識やスキル、技術といったものが大切にされてきた。
ここに関しては、今後も残っていくだろうが、そこにプラスして、そこのお店に相談したいか、そこの人に相談したいか。がより入ってくるように感じる。
技術や知識、スキルが高ければ、より自分の状況をよくしてくれそうだし、聞こえの改善に貢献してくれるのであれば、これらがあることは良いように思える。
しかし、AIやらチャットGPTやらが発達してくることは、均一化が進むと同意だ。
それらを使いこなすのにものすごく特殊な技能が必要だとか、特殊なものが必要だとかがない場合、全体のレベルが上がると言うことを意味する。
すると少しのスキル、技術、知識の差は、ほとんどなくなる。今まで、そこが強みだった人、あるいは、会社は、その強みを無くすことになる。
では、そのような世界になったときに残るのはなんだろうか。それは、人ではないかと思う。
今までは、愛想が悪くても態度が悪くても知識や技術、スキルがあれば良かった人もいるだろう。しかし、機械の方が優れてくるようになれば、その先は、人として、どうか。が見られる世界になってくるということだ。
機械の進歩は、本質しか残さない
ところで話は変わるが、私の中のテーマの一つは、難聴の方は、どのようにしたら幸せになれるのか。がある。
これに関する答えは、良い人間関係を作ること。ここにあるのではないかと考えている。
この内容は、ハーバード大学の成人発達研究というものがベースになっており、TEDトークでも人気の内容だ。発表しているロバート・ウォールディンガー氏は、
75年にわたる研究からはっきりとわかったことは、私達を健康かつ幸福にするのは、富でも名声でも無我夢中に働くことでもなく、良い人間関係に尽きるということです。
とはっきり述べている。
そして、この傾向は仕事にも現れる。仕事といえば、自分がしたいこと、あるいは、興味があることをするのが良いという考えが多いだろう。
好きなことで生きていく。Youtubeのキャッチコピーは、この時代に大きく刺さった。その事から、今では"好きなことを仕事に"。という声が大きくなった。
ただ、私の感覚からすると、好きなことを仕事にすることが必ずしも幸せにつながらないのではないかと感じている。それよりも誰と働くかだ。
自分がいて心地が良いと感じる人、自分がこの人といると安心する、相性がいいなと感じる。今までの経験から言えるのは、そのような人と仕事している時は充足感を感じていた。どのような仕事でもだ。
これは先ほどの教えるから寄り添う。へのシフトにも関係する。
つまり、最終的に誰と共によくしていくのか。そこが大事になるということだ。その感覚は、お客様を対応していると良くわかる。
自分が話していて伝わると感じる感覚、この人に相談すれば安心するという感覚。機械が発達した世界というのは、このような人間の本質しか残らない。
最終的には、どのようなものもコミュニティ運営のようなものに近づいていくのだろう。そして、その際に大事になってくるのは、技術や知識以上に良い人間関係になってくるということだ。
考えれば考えるほど、機械の進歩は、本質しか残さない。ということを教えてくれる。
結局人は、誰と過ごしたか。それで人生は大きく決まる。パートナーだって、仕事だって、そうだ。
機械が進歩すればするほど、そのような本質しか残らないのではないか。と私自身は思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
