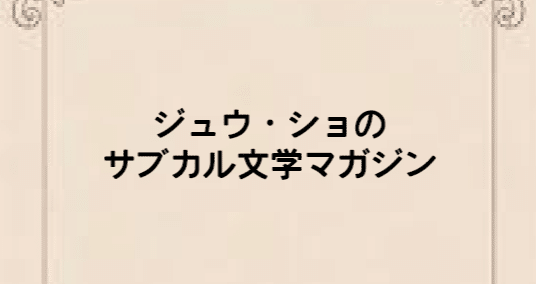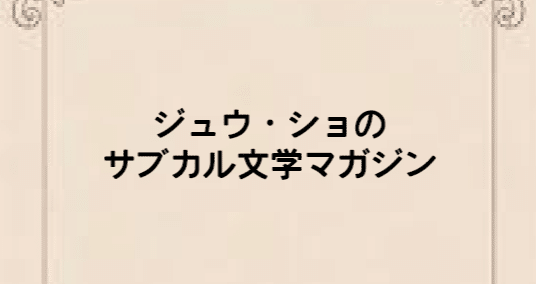太宰治の「人間失格」で笑えなくなった人は、いったん寝るべきだ
太宰治といえば、非常にネガティヴかつ陰鬱な作品ばっかりで、読んでいて暗くなると思われがちだろう。はい。その通りです。一見、死ぬほど暗い。ずーっと、うじうじしている。
しかし人によっては、笑いながら読める人も多い。渋谷のクラブでコロナビールの瓶にレモン沈めてる兄ちゃんが読んだら「いや、こいつ自分好きすぎるっしょ。ウケんだけどやばくね」と笑いながら読むに決まっている。
なかでも「人間失格」という名作はヤバい。とにかくずーっと自分語りで、自意識過剰が止まらない。「他人に気を遣い