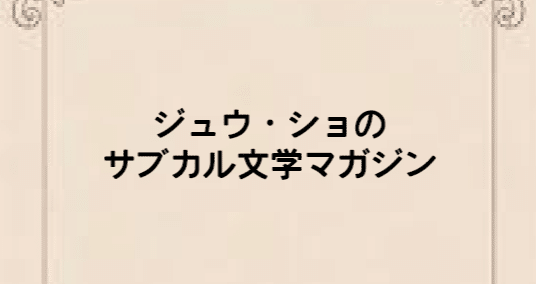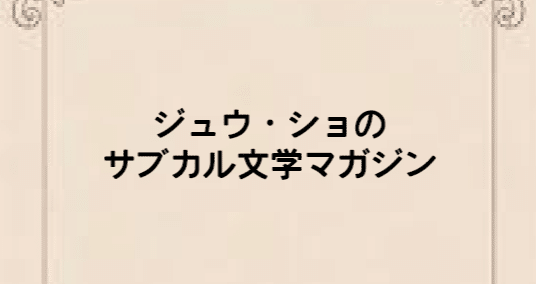芥川龍之介とは|人間のエゴを描き「答えのない難題」を書いた作家
芥川龍之介の作品は、たぶん日本国民の80%くらいが読んだはずだ。「羅生門」は高校の教科書の常連ですよね。福田雄一監督の作品における佐藤二朗くらい毎年出てくる。
男が死人の髪を売ろうとする婆さんを見つけ、服を剥ぎ取り逃げていくシーンに衝撃を受けた人も多かろう。「イカれた婆さんだ。服をパクられても仕方ないだろ」と感じた方もいると思う。しかし一方で「ちょ、婆さんかわいそうじゃね? お腹減ってんだから仕方ないよ」と思った人も多かろう。
芥川龍之介(特に初期)という人は、こうした「