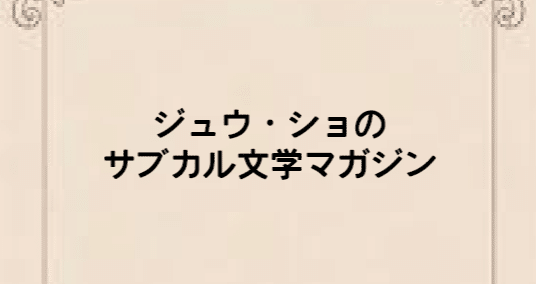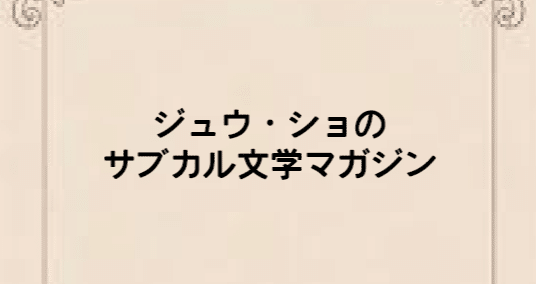「フランダースの犬」でルーベンスのキリスト画が描かれた理由とは
『フランダースの犬』と『火垂るの墓』は、ちょっとマジで発禁にしてほしい。いや子どものころは「なにこれ、かわいそう……」って、そんだけだった。しかし大人になってから観ると、救いがなすぎてバウンスビートくらい動悸がしてオロオロ泣く。18才以上禁止とかにしてほしい。O-18。オーバー18歳だこんな作品は、やめろ。観せるなもう(泣)。
そんなフランダースの犬といえば、やっぱり最終回。主人公のネロと愛犬のパトラッシュが寄り添ってルーベンスの「キリスト昇架」と「キリスト降架」を観て「な