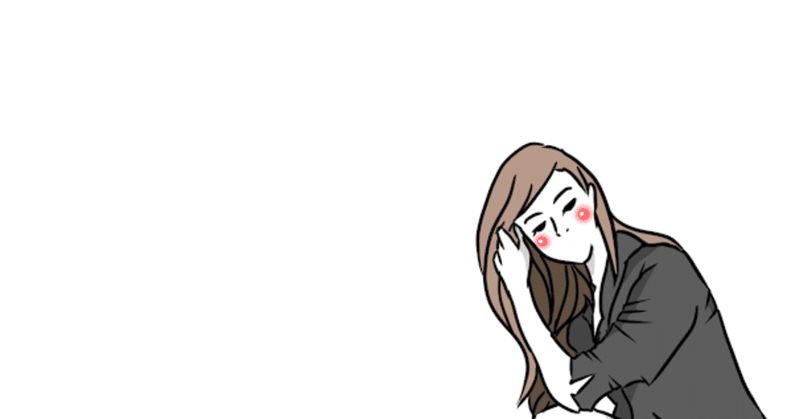
エリートフェミは死んだんだ、いくら敵視しても帰っては来ないんだ
もうあの時代は終わって、君も「草の根のフェミニズム」、「内なるフェミニズム」と向き合う時なんだ
まず語っておきたいのが、Prof.Nemuro氏という人物について。
彼はTwitterをやっていないにもかかわらず、かなりの数のフォロワーがおり、その中にはTwitterやnoteにおいて反フェミニズムのアルファアカウントになっている人物も多数含まれています。つまり、彼らのオピニオンリーダー、ネットにおける反フェミニズム勢力の首領と考えられる人物だったのです。
この記事は彼の主張を簡潔に解説したものとして、長らく彼のページの固定記事になっていました。
女は結婚相手の男(用心棒兼食料調達係)に経済力を求めるので、賃下げ・非正規雇用化のネオリベ改革は「適当な相手にめぐり会わない」「資金が足りない」理由による非婚化を促進する。結婚してもカネの制約のために子沢山は難しくなる。
結局のところ、エリート女とグローバル投資家(株主)の利益のために、経済活動と人口再生産を両立させる安定構造(男社会)を破壊したことが、非婚化・少子化の根本原因ということになる。男女共同参画≒ネオリベ改革と「希望出生率1.8」の実現は両立できない。
注目すべきは、改革を主導したフェミニストの多くがchildlessだったことである。子がいないことは「自分の死後のことは知ったことではない/後は野となれ山となれ」という環境破壊者的な考えにつながりやすい。ある意味では「無敵の人」のルサンチマンによって社会が破壊されたわけである。
以前私は、00年代末期ごろまでのフェミニズム批判が、家族観の解体を進める、あるいは非婚化・少子化を加速させるという方向からしか批判されていなかったと述べましたが、彼のフェミニズム批判も、それを過去形の文に書き直したものに過ぎませんでした。その上で、エリートの罪ばかり追及していたのです。インセルやKKOの勢いが強かったこともあってこのようなフェミニズム批判は大きな支持を得ていたと思われますが、私は前々から、この理論は昨今のツイフェミのような、エリートでなく草の根の勢力に切り込む力を持っていないと思っていました。
一方最近の彼は、この記事を一番上に掲げるようになりました。
あらゆることを裁定者に委ねることは非現実的なので、些細なことは寛容の精神で受け流す「器の大きさ」が美徳になる。この態度はhonorカルチャーでは「弱腰」と否定的に評価されるものの、dignityはhonorから進化したものなので、どちらも「筋を通す」ことを重視する点は変わっていない。
一方、主婦が内面化しているのが、honor/dignityとは全く異質のvictimhoodカルチャーである。victimhoodでは自分が被害者であることを第三者にアピールしてリンチをけしかける。筋を通すことよりも嘘をついてでも被害者を装って味方を増やした方が勝ちにつながる。主婦が自分が被害者であることを強調する漫画を描いてネットに載せた行動にもこの心理が働いている。
「女の社会進出」を単純に良いことと考えて推進した男たちは、女も男と同じく道理や公正を重んじるdignityカルチャーを内面化していると考えていたのだろうが、現実は息を吐くように嘘をつく想定外のvictimhoodカルチャーだった。現代社会の基本ルールとは相容れないカルチャーによるシステムのハッキングが先進国の混迷の一因となっている。
この記事には、もはやエリート女のエの字も出てきません。victimhoodカルチャーを内面化しているのが主婦の階層であることは重要です。これはすなわち、彼もエリートフェミニズムの力が衰え、主婦(及びそれになりたがる女たち)によるフェミニズムが日に日に強まっていることを認めたように思えます。
彼は以前の記事で、フェミニズムの構造をジョージ・オーウェルの『動物農場』に準え、エリートフェミニズムを🐷(作中で革命家を示す、漢字ではなく絵文字なのは彼がそう表現しているため)、草の根フェミニズムを🐕(作中で側近や秘密警察を示す)に例えていましたが、こんな状況で🐷が🐕を管理できる能力があるとは思えません。🐕は🐷の示すような革命をあえて拒否し、独自のやり方で革命を起こそうとしています。そこに🐷が追従しているのが、今日のフェミニズムの在り方なのです。
そこで今回は、「エリートのフェミニズム」がどのように没落していったのかを追ってみたいと思います。
前史:WomenAgainstFeminismとその社会学的研究
この記事でも少し触れましたが、ここでキーワードになるのが、「ポストフェミニズム」という用語です。これは大まかにいうと、フェミニズムはもうやるべきことをやった、社会運動としての役割を果たしたという考え方のことです(フェミニズム思想の一流派やそのような名前の運動を指すものではありません)。
参政権や雇用機会の獲得によって、フェミニズムは大きな曲がり角を迎えました。女性の権利獲得はもう果たした、ではなぜアカデミア(エリートのフェミニズムは概ねここから発信されていました、余談ですが久米泰介氏がアカデミアでの人材確保に躍起になっていたのもこのため)に進出してまで続けようとするのか、というスタンスが生まれるのも容易だったわけです。アメリカのフェミニズムでは、このポストフェミニズムは「一部フェミニストの立場」あるいは「運動」にまで一時期広がりましたが、日本では一部学生たちの「フェミニズム教育・ジェンダー研究」に対する疑念についてそのように呼ばれることがあります。いずれにせよ、アカデミアのフェミニストは、反フェミニズム言説や男社会の構造のほかに、こうしたスタンスとも戦う必要が出てきていたのです。
上記事の高橋氏などが行っている研究は、この「ポストフェミニズム」の実態をつかむことが目的になっています。
ここで高橋氏が注目したのが、英語圏においてインターネットを介した女性たちによる反フェミニズム運動「WomenAgainstFeminism」でした。
高橋氏とは別のポストフェミニズム研究者が言うには、(これとほぼ同じ時期にあった)若い女の専業主婦願望などが彼女らの関心の対象になっており、これは高橋氏が「WomenAgainstFeminism」を分類したところの「性別役割重視」派に相当します。
MeTooは、フェミニズムの何を変えたか
先の高橋氏の記事では、この勢力とMeTooとのつながりを示唆する記述があります。ちなみに記事のもとになった論文ではWomenAgainstFeminism自体ちょうどMeTooのあった2017年で活動が止まったことにも触れられており、その動きに合流していることがここからも窺えます。
以上のようにポストフェミニストたちの主張を整理することで見えてくるのは、「女らしさ」の享受と「女であることによって社会的に不利な扱いを受けないこと」を当然視するポストフェミニストの主張は、根本的には、現在フェミニズムが目指しているものと齟齬するところがないのではないか、ということだ。
例えば、フェミニズム原理に近いハッシュタグ運動#MeTooは、「女性的魅力」の発揮(例えば、女優という職業)と、セクシャルハラスメントにあわずに職業生活を全うできるような社会的環境の両方を要求したものといえる。
MeTooというのは、高橋氏が述べているようなものに矮小化できないことは、皆さんもお分かりのことでしょう。そもそもハリウッドの芸能界は発端となった場所に過ぎず(第一次世界大戦におけるサラエボ、第二次世界大戦におけるトチェフのようなもの)、芸能界の枠を超え、草の根フェミニズムの人口に膾炙したわけです。
その意味で、アカデミアなどのエリートから、芸能界含めた草の根への「パワーシフト」がフェミニズムの内部で起きたのが#MeTooの本質だったと言えます。
これとほぼ同時期に日本の草の根フェミニズムの間で流行したのが、かの悪名高き『旦那デスノート』でした。
この現象は、日本の場合、フェミニズムの発信場所が大学や企業からではなく、家庭の台所からになってしまっていることを示していると思われます。それはつまり、日本における今後のフェミニズムの主張は大まかにいうと「地位向上や社会進出は諦めるから、代わりに家庭内であたしたちの思うように暮らさせろ!」という方向に舵を切っていく、ということになるのが容易に予想できるのです。
そうなればおそらく、エリートフェミニズムの入り込む余地は全くなくなるでしょう。
上野千鶴子の敗北宣言
ここまでの話を踏まえたうえで、2019年東大入学式の上野千鶴子氏のスピーチを見てみましょう。
あなたたちのがんばりを、どうぞ自分が勝ち抜くためだけに使わないでください。恵まれた環境と恵まれた能力とを、恵まれないひとびとを貶めるためにではなく、そういうひとびとを助けるために使ってください。そして強がらず、自分の弱さを認め、支え合って生きてください。女性学を生んだのはフェミニズムという女性運動ですが、フェミニズムはけっして女も男のようにふるまいたいとか、弱者が強者になりたいという思想ではありません。フェミニズムは弱者が弱者のままで尊重されることを求める思想です。
私にはこのスピーチがエリートフェミニズムの敗北宣言であるように読めました。あえて太字部分のように言っていることから、草の根フェミニズムが地位向上をあきらめたのを暗に認めたことに他ならないでしょう。その意味で言うと、この時点で既にエリートフェミニズムが草の根フェミニズムをきちんと指導できている、あるいは管理下に置いているとはとても言えない状況だったのです。
さらに2020年に入ると、上野氏は次のような対談記事を寄稿しました。この記事は某匿名掲示板でも「上野の敗北宣言」「自分が間違っていたと認めるのは大きい」「共働き嫌がってる女多いからな」などと評されており、(特に若い世代の)草の根女性との乖離がさらに浮き彫りになったものと言えます。
それにもかかわらず、上野氏はこんな発言で記事を締めているのですから、実態はむしろ逆と考えたほうがいいのかもしれません。エリートフェミニズムは、草の根女性たちの軍門に下ったと。
日本史上において自己利益最優先の女が今ほど大量に生まれたことっておそらくないんですよ。歴史上快挙ですよ。
まずはこうしたパワーシフトを理解しておくこと、それだけでもフェミニズムへの見方は変わってくるでしょう。もう既に「エリートフェミが女の地位向上や社会進出を進めてくれたおかげで俺たちは恋愛や結婚ができなくなった、だからこそエリートフェミを駆逐しなければ」などと言えるような段階にはないのです。
そもそもなぜこういうことを言わなければならないか
これまで私が述べてきた主張は、どちらかというと「比較的若い世代の男性」に向けて、かつてのフェミニズム批判(エリートの罪ばかり追及するProf.Nemuro氏なども含む)に安易に迎合するな、という論点が中心でした。今でこそそのような若い世代はかなり少なくなったので、次はかつてのフェミニズム批判の「罪」を追及する段階にきていると思います。
昨年の末、第5次男女共同参画基本計画が閣議決定されました。反フェミニズム寄りであるとされる政治家たちは「選択的夫婦別姓」には抵抗したとされますが、それ以外の政策ではどの報道にも指摘がないことから原案のまま通したと思われます。まだまだ家族の解体に関わらないイシューへの彼らの関心は薄いわけです。いやむしろ、フェミニズム以前の性意識のほうが、女にとって安全かつ幸福に生きられると彼らが考えていたからこそ、彼らは一部のフェミニズム政策にのみ反対していたわけです。その意味で言えば、彼らこそこれから「フェミニスト」に転向してしまう可能性が高いといえます。
結局、彼らのフェミニズム批判は本当に完全なものではなかった。そここそがかつてのフェミニズム批判の最大の「罪」と言えましょう。
