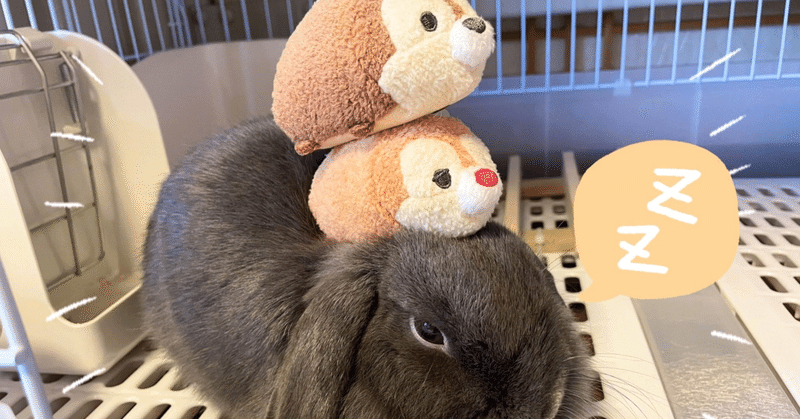
ミック&マティックⅡ
先日のシステムの話の続きです。
世の中で起きているたくさんの問題。システマティック(systematic)な問題だったら解決方法に簡単に辿り着けるが、システミック(systemic)な問題の場合、どうやって手を打ったらいいのか、まるで検討がつかず途方に暮れてしまう。
サイエンスやテクノロジーの世界ではよく、原因をつきとめるために大きな物事を要素に分けて分解し、一個一個を観察してダメなところをそれぞれに改善し、それらをもう一度組みあげるというやり方で問題を解決しようとする。そういう還元主義は、わかりやすくてパワフルな方法なので、多くの人が社会問題のような複雑な難題もこの方法で解決を図ろうとする。しかし、実際にはこのようなやり方はまるで役に立たない。それどころか、分解してみてもなんだかよくわからないとか、そもそも分解できないとか、実際にやってみるといろいろ困難に突き当たり、結局お手上げになってしまう。実は、論理的に解決できるようなシンプルな問題はすでにかなり解決している。逆に言えば、今残っているのは還元主義のような方法論では解決できない、複雑で大きな問題ばかり。しかも、どんなに学問や技術が進歩しても、問題が解決するどころかむしろ増えているのが現状。その解決の糸口はどこにあるのか。
孫泰蔵さんは『冒険の書』の中で「確信を突く良い問いを立てること」が必要ではないか?と提案されています。
「そもそも、なぜその問題があるんだろう?」といった根本的な問いを立て、その問いをどんどん深めていく。調べたり手を動かすことで、初めて見えてくることがあり、これまでの問いがより深いものになる。そしてまた次の行動を起こす。そこから更に新しい問いが生まれる。こうしたプロセスを繰り返していく。
辿ってきた道をふと振り返ってみると、「ああ、結構いろんなことがわかってきたな」という事実に気がつく。これは「探究(explore)」といい、イノベーションもこうしたプロセスから生まれるのではないか?、と主張されています。
イノベーションは後世の人間が評価する結果論に過ぎない。イノベーションを起こすぞ!・・ではなく、探究の結果として、イノベーションが生まれている。システミックな問題も、こうして解決するという訳。
さて、これをどうやって実装するか。簡単じゃないから、高い山を目指したくなる性分です。
参考書籍:
[2023.03.25投稿]
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
