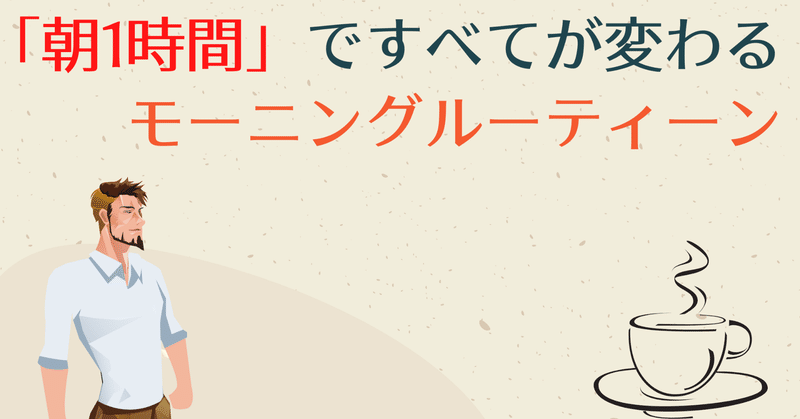
読書レポート:「朝1時間」ですべてが変わるモーニングルーティーン
■書籍紹介
著書:「朝1時間」ですべてが変わるモーニングルーティーン
著者:池田 千恵
出版社:日本実業出版社
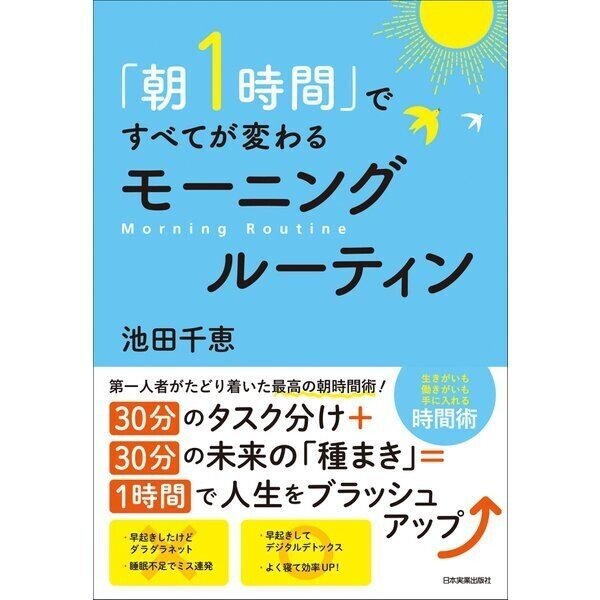
■はじめに
自分の現在地として、役職がない一般メンバーです。しかし、目の前にあることとしては2021年で役職を得ることです。
役職者とそうなれていない自分で比較すると、労働時間でいうと約半数ほどの役職者には負けていないと考えています。
今、役職がないということは時間の使い方がうまくない、ただがむしゃらにタスクを処理しているだけになっている可能性があると考えます。
そこで、勤務時間の生産性を上げ、さらにプライベートの学習時間も作れるような生活リズムを作りべく、この本を手に取りました。
■早起きのコツ
まず、朝の1時間を生み出すためには今よりも早起きができなくてはなりません。
今までは、起きた時間に合わせて出社していたので、5:00出社のように早起きができる日もあれば、9:00ギリギリに出社する日があったりとバラバラでした。
早く出社できるかは、その日のタスクの多さに合わせて調整していることもあり、朝6:00に起床しても、結局8:30出社になったりと早起きしても出社する目的がありませんでした。
私は会社から徒歩10分前後のところに住んでいるため、朝8:00に出社すれば、朝の1時間が確保できます。
(朝ワークの時間を考えると、厳密には7:30出社になります)
朝の1時間でやることはその日のタスクではなく、「優先順位を明確にすること」と本書では取り上げられています。
つまり、その日のタスクを洗い出し、優先順位を決めるための1時間なのです。
■なぜ「朝1時間」なのか
ここまででそもそも自分がなぜ安定して早起きができないのか振り返り、「目的」を持つことによって早起きができるようになるとインプットしました。
次は、早起きと言っても何時に起きなければいけないのか、何時から取り掛かったらいいのかを見ていきます。
この本では早起きの「時間」は関係ないと言います。
そもそも目的として「人生をブラッシュアップすること」なので、無理やり早起きして昼間の集中力を下げることは目的に反することになります。
そのため、すぐにできることとして「1時間早く活動を始める」ところから始めることになります。普段の生活習慣を少し変えるだけなので取り掛かりやすいです。
また、1時間早く起きるなら明日からでも取り組めます。
実行に移すまでのタイムラグが少ないことも「1時間」の理由になります。
さらに、これは自分の体験とも重なる部分ですが、朝は集中を妨げるものが少ないため、集中できる時間が確保できるため、非常に有意義な時間を過ごすことができます。
■朝「優先順位決め」を行うメリット
この本では7つのメリットが紹介されていますが、そこ中で私の生活で得られると考えた4つについてまとめます。
①「決めグセ」がつき、行動が早くなる
②「念のため思考」を排除できる
③仕事を抱え込まなくなる
④日中の集中力が増す
①「決めグセ」がつき、行動が早くなる
そのタスクは本当に「今」しなけらばならないのか、本当に「私」がしなければならないことなのか。心の中で思っても言えない場面が多々あります。
それは「決めグセ」ができていないからと著者は言います。
「もっと効率的にできるかもしれないけど、とりあえずやろう。」
「他人に依頼する文章を作るのが面倒だから自分でやっちゃおう。」
正直とても多くあります。
上長に相談すると「(他のメンバーに)下ろしていいよ。」と言われますが、「下ろす作業って、結局自分でやらなきゃなんですよね?」と思い、今のところ半分くらいの割合で下ろせてないです。
これを朝のうちに「下ろしてしまう」か「自分でやるか」を決めてしまうと、朝のスケジューリングの中に下ろすための時間の確保が出来るということです。
②「念のため思考」を排除できる
朝1時間の優先順位決めの時にタスクとして洗い出すかどうかの判断軸として「念のため思考」を排除することができます。
私はよくやってしまうのですが、「念のため "cc" つけてメンションしようだったり、資料の作成中に「念のため途中までできた資料を上げておこう」とやってしまいます。
しかし、上司も暇ではないため、"cc" をつけられたものはしっかり見ない可能性がありますし、途中まで出来上がっている中途半端な資料はそもそも何を確認したらいいのか上司も分からないでしょう。
これはこの本に書かれていて、私はやってしまっている時があると反省しています。
上司からするとあいまいなタスクに対して「これはなんだろう?」と考える時間に繋がりますし、私からしてもメンションつけたり、タスク上げしたりの時間が無駄になるわけです。
そこで、朝の優先順位決めの時に「必要」な報告を途中で入れる場合は「進捗報告」をタスク化し、その時の気分で連絡を増やさないことが大事になります。
しっかり「朝1時間」で整理する時間を活用します。
③仕事を抱え込まなくなる
自分が仕事をできる人間だとは胸を張って言えないところがありますが、やはり社内では中堅層まで来ていると自負しています。仕事を任されやすいポジションになってきました。
あまり断れない性格もあったりなかったりではあるのですが、やはり頼られたらそれに応えたくなってしまう気持ちがあり、タスクがどんどん増えていきます。すると「1人ブラック企業」となってしまうのです。
そこで、朝の時間では大きなタスクをもらった時に、そのタスクの構成を分解し、どこか部分的にでも他人に依頼ができるところはないかを考え、依頼する時間にすることで脱1人ブラック企業ができると考えます。
④日中の集中力が増す
「朝1時間」のタスク管理が習慣化すると、朝が自分の「ピークマネジメント」の時間になると著者は言います。
「ピークマネジメント」とは、うまくいくためのルーティーンのことで、自分で分かりやすいと感じたのが、野球の打席に入るときの例えです。
私は小学校6年生から中学の3年間、野球をやっていました。
そこで打席に入る時、次のようなルーティーンを作っていました。
1. 審判に「お願いします!」という
2. バッターボックスの土を均す→踏み込みに合わせて削る
3. バットを2回まわす
4. 大きく体を反らす
5. 投球を待つ
これは少年野球の公式戦で、初めてセンター前ヒットを打った時にやっていたモーションでした。
「これをやってうまくいったから、次もやろう」そうして中学でも続けていました。
これを今の生活に合わせると「業務時間前に1時間のタスク整理を行ったから業務が捗った」となるわけです。
社会人になってからは忘れてしまっていたルーティーン作りが今ここで思い出され、実践することで毎日のリズムづくりができると考えています。
■おわりに
今回は毎日行うことで日々の生産性を上げる方法をインプットしました。
先日、「毎日の学び」をやっているときに、人間は大きな変化を一度に行うと、その反動でできなくなる期間がある心理学があると知りました。
一度にたくさんのことや大きなことをやってしまうと「今日はまぁいいか。」「昨日頑張ったから今日は無理」と思考も心理的にもなってしまうようです。
それを知ったときに「毎日少しずつだけど続けること」が重要で、大きな目標を達成させるカギは「毎日」にあると気づきました。
『千里の道も一歩から』
慣用句はうまいように作られているなと感じた次第です。
■今後取り組むこと
・朝7:30に出社し、タスク整理 / 優先順位付けを行う
2月から一段と案件も増え、タスク管理ができないと1人ブラック企業になってしまうため、2週間スパンで見直しを図ります。
■前回の進捗
①1日5つのタスクに対し、「〇〇したい」に置き換えてみる
これについては、火曜日に5つの目標に対し2つまでしかできなかったことから、断念してしまいました。
緊急タスクが入ったときに、どうしても「〇〇したい」と思うことができなかったためです。
下方修正にはなりますが、
『毎日コツコツと「1日1つのタスクに対し、「〇〇したい」に置き換えてみる。』
に変更をし、今週も実施いたします。
②自分の伸ばすことを来週までに考える
「今日の学び」をやっていて気付いたことですが、あまり広告運用の部分でDSPや他媒体に詳しい人が社内だと限られていると気づきました。
そこで、「毎日の学び」を活用しつつ、社内の媒体攻略メディアという形でこのnoteを活用できたらと考えております。
一足先に、Twitter広告の構築についてnoteにまとめております。
(平日に作成し、かなり時間を取られてしまったため、土日などの時間に余裕があるときに作成しますが、情報収集は平日でもできるため、取り組みの一環とします)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
