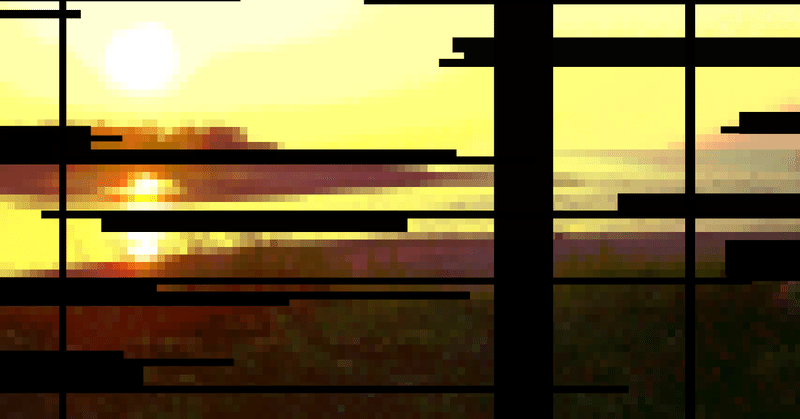
#9 サニー 2
2
べランダから見える空には少し雲が流れているようだった。
まるで美しく澄んだ水たまりのようであった。
僕が住んでいるアパートは、細い路地裏にある。そしてその隣に、新築のピカピカの一軒家が、立ち塞がるように建っていた。
ベランダ側でしかも三階建てだから、僕の部屋には光がおよそ四時間しか差し込まない。ただでさえ駅から遠く狭いのに日当たりが悪くなったせいで家賃は事故物件かというくらいまで落ちに落ち切っていた。僕としては、家賃が安ければそれはそれで助かるのだが。
その家が建ったのは今から五年前だったが、今現在その家には家庭が出来上がっていた。
三十代後半の夫婦に兄妹二人が、今、住んでいる。太陽が沈むと彼らの家庭生活の営みというものが、毎日音として聞こえてくる。食器と食器が触れ合うガチャガチャという音、団らんの笑い声、母と息子の喧嘩、娘の走るばたばたという音、テレビの音、風呂場の音。一般家庭に起こりうる全ての演奏が……。
――僕はそれが聞こえるたび、何故か耐えられないほどの痛みが胸の中で沸き起こった。寂寥というものが喉の奥から湧き上がって吐きたくなった。何故か理由が分からないが、悲しくてもやもやして、泣きたくなってしょうがなくなるのだ。
それは僕が、家族というものに対して特殊な感情を抱いているからだろうか。
現在。
気だるい昼下がり、ベランダから見えるレンガ柄の直方体からは、変声期頃の男子の声と甲高い女児のわいわいと遊ぶ声が、小さく届いていた。今日は土曜日だから小学校は休みなのだろう。
僕は椅子に腰かけ、煙草を吸い一息ついた。そして、サボテンのサニーに話しかける。
「サニー、おれは上手くやれているよ」
「…………」
彼女は依然として寡黙だった。サニーに語りかけた言葉が返ってくる事は今まで一度も無かった――当たり前である、彼女は植物で、しかも声帯器官を持っていないのだから。 それでも僕は、ずっと前から、出会ったときから彼女に話しかけている。
「大変な仕事はようやく終わった。後は少々の買い出しと、それから最後の大切な仕事を終わらせれば、今日やるべき事は全て終いだ」
ただ一つ言える事があるとすれば、僕はサニーの事を家族だと思っているという事だ。彼女は、ただ一人の僕の理解者である。
サボテンは鋭い針を持ち、生きているのだか鉱物の類なのか分からないほど遅い成長速度ではあるが、それでも僕自身の話を真面目に聞いてくれるという点で、彼女は今まで会ったどの人間よりも人間らしかった。
サニーは元々僕が所有する植物ではなかった。元は数年前の恋人のものだった。だが彼女は五年前にどこか遠くの国へ行ってしまった。サニーは、その際に置いて行った、僕にプレゼントした数少ない物の一つだった。
最初僕はサニーを憎みさえしていたが、次第に親しみ、というか愛情まで覚えるようになった。次々と失っていった僕の人生の中で、彼女だけが僕の傍に居続けてくれたからだ。
僕の元恋人がこの植物についてどう思っていたか分からない(それどころか僕自体をどう思っていたかさえ今となっても分からない)。ただ一つ言える事は、サニーは今僕の傍にいて、僕の元恋人はガラスのような砂の上で満点の星空を眺めているという事だけだ。それ以上、語るべき事はない。
僕は灰皿に煙草をもみ消して、チェックリストの後半の項に手をつける事にした。「休憩は終わりだ。サニー。これからとても苦しい仕事をしなければならない」
これから僕がするべき事は、大家と家族に対してそれぞれ遺書を書くことだった。
大家への手紙はごく単純な事務事項であった。――押入れに入った、廃棄と書かれた段ボールやごみ袋を、指定の通りに廃棄してほしい。冷蔵庫や食器などの日用品は、後の住人に使ってもらって構わないが、死人の使っていた道具なんて、と思うのならお手数だがこれも廃棄してほしい。別の段ボールに入った本は、古書店にでも売って適当な金にしてほしい。机の中にある程度の金額が入った封筒があるから、それを手間賃としてほしい。来月の家賃も同様にそこに入っている。金は余ったら好きなように使ってほしい。それから、最期のお願いなのだが、机の中には僕の親への遺書が入っているから出来れば届けてほしい。僕の実家の住所は――
このような内容の文章を手書きで書き、最後に印鑑と僕の署名を入れた。封筒に入れて大家の住所を書き、切手を貼って忘れないように机の上に置いた。
さて、と僕は次に親に対する手紙を書き始めた。
親に対しての遺書は、中々筆が進まなかった。
進むわけが無かった。僕は父と母にもう、五年程会ってない。上京して大学に通っていた頃は、一年に一回程度は帰郷していたが、就職してからは何だかんだと理由をつけて帰らなかった。
電話をしたのは一年前だが、元気にしているなどの月並みの会話しかしなかった。親には、仕事を辞めた事などについては話していなかった。だから、彼らは能天気に『早く孫の姿を見せてくれ』と言っていた。とんでもない事である、僕は自分の人生すらまともに運転できないのに。
試行錯誤しては紙を破り捨て、次第に太陽は西へと傾いていく。遺書の為だけに買った便箋を何十枚もゴミ箱に捨て、しかし僕は僕の家族だった人達に対し、一体何を書けばいいのかまるで分からなかった。育ててくれてありがとう? 家族の中で唯一不能者だった僕を育ててくれてありがとう? 実際それは真実であったのだが、そんな言葉を書く気には一切なれなかった。
ベランダから見える空がオレンジ色から、紫色となり、僕はなんとか歯を食いしばって、今まで書いてきた文章の一部をちぐはぐに繋ぎ合わせて、何とか遺書を完成させた。父、母、兄、姉の四人にメッセージを書き、ようやく苦心して書いた一枚の手紙は、ありふれていた陳腐な文章のように見えた。
僕はもうこの遺書がこれ以上目の前にある事が耐えきれなかった。僕は封筒に入れ糊付けをし、机の中にしまい込んだ。切手を貼らなかった――これを実家に郵送するのは不可能な仕事であった。
――僕は田舎で、農家の末っ子として産まれた。上には年の離れた兄と、三歳年上の姉がいた。
僕の兄と姉は、父母に似た大変優秀な社会人へと成長した。
兄は農大へ進んだあと帰郷して、父らの農業を継いだ。
姉は経済の大学に進んだ後、農業のシステム化を行うIT企業を起業した。現在は兄と協力して会社を育てている。
僕は、何とかという東京の理系大学に進んで、農業とは関係の無い仕事に就いた。その五年後、何もかもが嫌になって仕事を辞めた。
父は努力家であった。
代々先祖から受け継いできた農地を、さらに育てようと東京の大学に身一つで進み、農業、そして機械化や最先端の技術について、他の学部の生徒と交流をする事で造詣を深めた。田舎に戻った後はその人脈から重工の人間やIT企業の人間と共同で仕事をし、その間も最先端の農学や他分野の勉学を怠らなかった。効率的に作物を生産する術を開拓し、先代の百倍の収益を得るようになった。先見の明があり、チャレンジ精神の凄まじい男であった。
母は日本人には珍しい楽天家であった。
冷夏で不作になり収入が落ちた時も、台風で作物が滅茶苦茶に父が一度胃ガンで入院した時も、『なんとかなる』と笑って子ども達を励ました。父を徹底的に支え、時に膝を折りそうになる父を励ました。我々を育てる傍ら、父の代わりに経理を担当し、アルバイトの管理や面倒も見ていた。体力と根気があり、まさに太陽のような女であった。
兄は母のタフネスが、姉は父の知性が遺伝したように思える。しかし、僕には何も無かったように思える。僕以外家族は全員笑いの絶えないうるさい家だったが、僕だけが物静かで抑鬱の面を持っていた。母の父がそのような性格であったから、僕にはそういうのが隔世遺伝したのかもしれない。
皆々、とても優秀な人間だった。彼らは一体何を得続け、そして何を失い続けているのだろう。僕には想像もつかないけれど、その二つを天秤にかけたらきっと前者が下に傾くという事だけは分かる。
僕は……彼らと自分を比較しないわけにはいかなかった。彼らと比べ、僕はきっと失ったものの方が多いと思う。二十二の時に些細な喧嘩で多くの友人を失い、二十三の時に夢と自信を失い、二十五の時に恋人を失った。働いていくたびに未来に希望を見出せなくなった。
やがて、自分は一生幸福にはなれない事を理解した。幸福というものを享受する器官が私の脳には存在しないのである。
それがどういうものか分かっていなければ、幸せとは一生手に入る事の出来ない悪魔な果実だ。そしてある年齢を境に、幸福というものを知る事が出来なくなる。それまでに幸福を得られなかった人間は、一生幸福になりえないのだ。そうして多忙な時期が続いていくうち、最終的に僕は僕自身を保つのが酷く難しくなってきたようだ。それは、両手で水を零れないように保つようなものだ。指の隙間からどんどんと水が漏れ出て、ついには何もかもを失う。
それならば、空っぽの器になる前に……。
……全ての仕事を終えて、僕は自分が酷く疲れ切っている事に気付いた。天井を見上げ、吐きそうな気分を誤魔化すように煙草に火を付けた。
真上を見上げながら煙を吐き出し、それは切り離された蜘蛛の糸のように四方へと霧散していって、やがて天井へと吸収された。
「サニー、これで全ての仕事は終わったよ」
僕は机の前にいるサボテンに話しかけた。
「全て、終わったんだ。下らない僕自身の記録も、忌々しい学術書も、それから、あの能天気な馬鹿どもへの手紙も。全部書き終わったよ」
サボテンは相も変わらず黙っていた。
「おれはずっと孤独だったよ。サニー、君以外は誰もおれの孤独を理解してくれちゃくれなかったんだ。おれの家族も、父も、母も、血が繋がってるはずなのに、異星人みたいに距離が遠かったんだ」
サニーは何も言わず、じっと聞いていた。
外から食器の鳴り合う音が聞こえてきた。隣の家族が休日の団らんを取っているのだ。
僕はふとこう思った。彼ら四人の家族は本当に血が繋がっているのだろうか。あるいは血が繋がっていないのに家族のふりをしているのだろうか? あるいは。彼らの中には血の繋がった異星人は? いや……いないのだろう。彼らは本物の家族として、現在人生を楽しんでいるみたいだった。少なくとも彼ら全員の遺伝子はまともだったみたいだった。
そう思うと外壁のレンガが血液で――遺伝子を含んだ本物の血液で――塗れているようにみえた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
