
vol.42 ジュール・ルナール「にんじん」を読んで(高野優 訳)
125年前のフランス文学。あとがきに「母親による精神的虐待の物語」とある。
名作とされるこの小説、いらだちながら読んだ。少年「にんじん」に対するあまりにもひどい母親の仕打ちは許せない。長女や長男を溺愛する一方、次男「にんじん」に対する言動は、愛情のかけらも感じない。親が子に示す意地悪な戯れのレベルではない。相手を追い詰めて人格を破壊するようなひどい仕打ち。具体的な内容を記すのも躊躇する。今なら、少なくとも社会通念上の道義的責任を問われる事象だ。僕なら、間違いなく児相に通報する。

<あらすじ>
フランソワ・ルピックは、赤い髪とそばかすのある顔のために、家族から「にんじん」というあだ名で呼ばれている。家族から不当な扱いを受けている。押し付けられる雑用、理不尽とも思える母親の怒り。兄も姉も父親も「にんじん」には冷淡で、遠ざかっている。そんな中「にんじん」は皮肉とも言える視点で冷静に観測しながら成長していく。(ウィキペディア参照)
この物語を読んで、「かわいそう」という感情が湧いてしまった。僕は、「かわいそう」という気持ちは、どこか自分の価値を基準にして、相手を評価し、上から見下ろしているような気がして、あまり好きではない。しかしこの「にんじん」の家庭は、あまりにも罪だ。そして、「かわいそう」だと思ってしまう。このままだと「にんじん」は精神的に追い込まれ、こころの病に罹ってしまう。いよいよ深刻で、自殺を考えていたことを父親に打ち明けている。

しかしこの小説、そんなことでは終わらない。なんといっても名作なのだ。「にんじん」は、おそらく生まれてずっと、母親から理不尽な仕打ちを受けてきた。それでも、心を病むこともなく、腐らずに頑張っている。成長過程での残酷さはあるにせよ、少年らしい視点を維持しながら、将来に高い可能性を感じさせる頭の良さがある。「自分の意見」の項では、堂々と自分の思いを伝える。そして、徐々に、兄や姉、父親からも、理解を得る。最後の最後で、「にんじん」の賢さ、たくましさに救われた。
さらにほっとするのが「最後の言葉」の項。「僕はお母さんが、生まれてからずっと嫌いだ」と、その思いを父親に伝える。赤い髪とそばかすだらけの幼い少年から、健全な精神や知恵を蓄えた少年に成長していることに、ほっとした。大人になる過程で、大切なことがしっかり育まれていると思った。「母親から精神的虐待を受けた物語」から「虐待を受けた少年が生き抜く物語」に変わった。
この小説を読んで、やはり、親による子への虐待のニュースを思い浮かべる。社会の監視をかわしながら、しつけを言い訳に、子を虐待する親。なすすべを持たない子は「どうか打たないで」とお願いするばかり。親は子を支配し、子の考えを操る。子どもの人権なんて考えない。そんな概念もない身勝手な親。プライバシーが声高々に邪魔をし、深く踏み込めない社会がある。深刻なジレンマを感じる。
この作品、作者ルナールの、少年の頃の体験をもとに書いたものらしい。ルナールの心に、深い傷を残した親による虐待が、この作品を生んだのかもしれない。しかし、血縁のつながりは、閉鎖的な環境をつくり、理不尽な行為を隠してしまう。その中で、子どもの将来が奪われることは、いかにも悲しい。
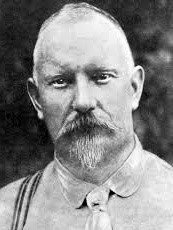
平成最後の読者感想文、こんな感じになりました。(^ ^)
(おわり)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
