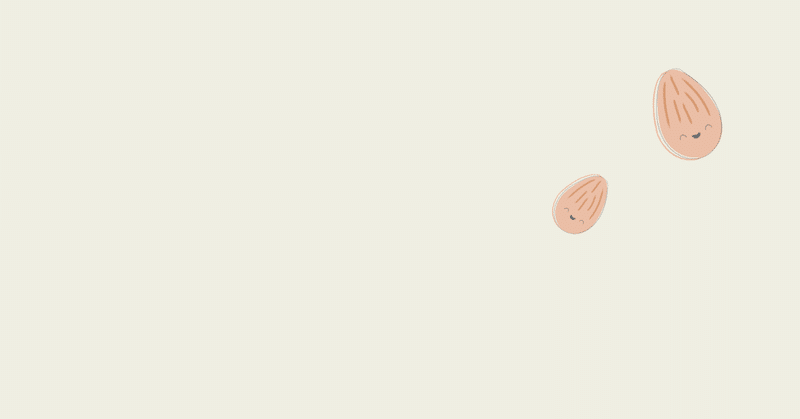
【小説】いつか扉が閉まる時 3年生・夏休み(4)
久保に「途中まで送る」と言われたが、出かけたついでにスーパーに寄るからと断る。
すると「買出し?今日のお礼に付きあうよー」と言い出した。
「いいよ別に。それより英語の勉強をしなよ」と建設的な提案をする私に、まあまあと言いながら久保はスーパーまで勝手に付いてきて自転車を止めた。
私はカゴを手にとって、ジャガイモやニンジンや卵を入れていく。
すると私の進行方向に久保が回り込んで、私の手からカゴを奪い取ろうとした。
「何するの」
「持ってみたいんすよ、カゴ」
「そこにあるから持てば?」と私は大量に積まれているカゴを指差した。
「俺、何も買わないもん…こういうのは任せてよー俺、力持ちだよー」
「自分で持てる範囲じゃないと、重くて持ち帰れないから」
「ちゃんと紗枝さんの家まで持ってくよ、近いし」
「それはいい」
「遠慮しないで」
「します。もう、ついて来ないで、おうちに帰って?」
久保はしゅんとした顔になって「わかった。じゃあさよなら」とスーパーを出て行った。
悪かったかな、親切で言ってくれたのに。でもそこまでしてもらう理由はないのだから。
私は家にある食材を思い出し、足りないものをカゴに入れていった。
…うっかり買いすぎてしまった。
持ってきた2枚の袋に食材がぱんぱんに入り、しかも5キロの米が予想以上に重い。
自分の力量を過信したのは夏の暑さによる判断力の低下だろうか。
左腕に抱えている米がずれ落ちそうになる。
脇に力を入れたが、落ちそうだ!
と思ったら、左腕が急に軽くなった。
「無茶するなあ」と久保が私の米を持ってそこにいた。
どこから現れた?
「帰ったんじゃなかったの?」
「帰ろうとしたら、無茶なことしてる人を発見して急いで戻ってきたの」
「ありがとう…でも、大丈夫だから」
「全然大丈夫そうじゃなかったけど?」とへらっと笑う、いつもの久保だ。
私は2つの袋を片手に提げ直し、空いた手で久保の手から米を取り返そうとすると、久保は米を自分の頭より高く上げた。
「5キロなんて軽いんで」
「返してよ」
「持ってくよ」と久保は米を片手で頭上に上げながら、さらに袋を1つ奪い取ろうとする。
「紗枝さんの家の前で帰るからさ…嫌がらないでよ。傷つくよ俺」
へらっと笑ったその顔が一瞬だけ寂しそうに見えた。
もう、仕方ないな。
お願いするより他に道は無さそうだ。
久保は自転車をスーパーに置いたまま、米と袋を軽々と運んでいる。
「今日は紗枝さんが夕飯作るの?」
「うん。母、来月何かの説明会があるから、最近帰りが遅いの」
「そう…何作るの?」
「まだ決めてない。冷蔵庫見て考える」
「料理上手なんだね」
「そんなことない。大事なのは栄養を取ることだから味付けは適当で」
「俺も食べてみたいなあ」
「すごく薄味だからお奨めしないよ。市販のものは濃すぎて苦手なの」
うちのマンションが見えてくる。結局、久保は徒歩で学校近くまで戻ってきたので、自転車を学校に置いていけばよかったくらいだ。この後、またスーパーまで自転車を取りに行かないといけない。
「じゃあ、ここで。本当にありがとう」
「いえ、どういたしまして」
私がまず袋を両手にかけ、お米を受け取ろうとすると、突然「紗枝?」と母の声がして私は驚いた。
「あら、もしかしてお米を運んでくれたの?」と母は久保に話しかける。
「通り道だったんで。こんにちは」久保はうちの米を持ったまま頭を下げる。
「ありがとう。あら?あなた」
母は一歩近づいて久保をまじまじと見た。
「もしかして手島圭一君って知ってる?」
「兄です」
母はやっぱり!と手を叩いた。
「そっくりね。もちろんあなたの方が若いけど」
「垂れ目が似てるってよく言われます」
「圭一君は教え子だったの、私は担任ではなかったけれど。お礼にお茶出すから上がって行かない?手島君」
そうか。
お兄さんと久保は姓が違うのか。そして、母はそのことを知らない。お兄さんが手島なら、弟も手島と思ってる。
そのことを伝えるべきか、迷って久保を見た。
久保は私に小さく「てしまでいいから」と言ってから「じゃあ、お米上まで運びますね」と母に付いて行く。
(続く)
