
東京で「見上げる」こと。「まっすぐ見る」こと。/『PERFECT DAYS』
我々が「小津安二郎的なもの」として連想するのが、静止した身体とすれ違う眼差しであるならばヴィム・ヴェンダースの『PERFECT DAYS』(2023)で──笠智衆が『東京物語』(1953)で演じた役と同じ苗字を持つ──役所広司の身体とは「反小津安二郎的なもの」として、動き続け対象をまじまじと見る身体であるといえる。
「動く」身体と「見る」身体
役所広司の身体は夢という「見る」ことを強いられた睡眠から目覚めるとすぐに布団を畳み、身支度を整え、外の自販機でコーヒーを買い、車に乗り込む。この日々繰り返される反復運動の中で同じく反復される静止する瞬間を見落としてはならない。玄関を開けた役所は一度「立ち止まる」。それは運動の否定であるが、動き続ける彼の身体が否定された時、彼の身体は「見る」身体へと変貌する。
彼の身体とは「動く」身体であると共に相補的に「見る」身体である。利用者の出現はトイレ清掃(「動く」こと)の中断であるが、すると彼の身体は見上げ始める。見上げた先にあるのはエンドロール最後に提示される「木漏れ日」であるが、その木漏れ日とは影による運動であり運動する影に他ならない。常に運動を探し見上げる役所広司の身体は映画鑑賞的とも言い得る。
「見上げる」ことと『ベルリン・天使の詩』
これに対し同監督作『ベルリン・天使の詩』(1987)の天使(ブルーノ・ガンツ)が天界より人間を眼差すその仕方は「見下ろす」ことであったことを忘れてはならない。分断された当時のベルリンで眼差しを投げかけることしかできない天使を主人公とする本作は、人間の非情を同情的に「見下ろす」前半と、下界に降り、人間として生きることを彼が選ぶ後半とで構成される。筆者が個人的に乗れないのは非情に嘆く主人公の天使が後半、ベルリンの政治的危機を見逃し、映画史が創り上げて来た「恋愛」へと向かうその非政治的な脚本にある。全体を「見下ろす」ことで見ることのできた政治的な問題は、その全体性に与することにより見えなくなってしまう。そうした批判にヴェンダースが自覚的だったのかはわからないが、そうした政治と全体性の対比から成る二項対立は35年後の東京でも同様の法則として生きている。

批判されているように、資本主義に搾取された労働者を美化するような『PERFECT DAYS』の語りには見苦しさがあるが、その見苦しさを体現する役所広司の「動くこと」は、全体性に組み入れられることからの反撥のようにも見受けられる。「見る」身体が映画鑑賞者を象徴しているのであれば、「動く」ことは映画監督的な表現であるが、映画というものも一つの労働の上に成り立つというゴダール的なテーゼが見受けられはしないだろうか。しかし彼は幸せそうに見える。その心境は、反小津安二郎的なものへと接近していく2023年の東京において企業の資本で映画を撮らざるを得ないヴェンダースの心境と似たものではないだろうか。
資本主義を批判するために資本主義に則って映画を撮る人のように、『ベルリン・天使の詩』はメロドラマを描かなければならなかったのではないだろうか。天使だって全体を「見下ろす」映画監督であるが、映画を撮るためにはカメラを持ってそこで動く被写体に近づくため、下界へと降りていかなければならないのだ。果たしてブルーノ・ガンツは天使への回帰願望があったのだろうか。その願望は役所広司に引き継がれているように思える。『PERFECT DAYS』は『ベルリン・天使の詩』の続編として、堕天使である役所広司は天を「見上げる」。
「まっすぐ見る」こと『パリ、テキサス』
干渉を望んで下界へ降りた天使が天へ回帰することを望むのであれば、そこに干渉への願望はもはやない。役所広司にとって他者とは色恋に悩む男女であり、反復運動を中止するトイレ利用者であり、自分が何者かを示す家族である。笑み絶えない役所広司の顔から開かれた歓待性を誤解してはならない。まさに彼の顔が硬直する時、それは「動く」ことを止め、更に「見る」ことすらやめた時であるが、それは誰に対しても向けられる。
姪(中野有紗)の存在はほかの他者とは異なり彼に変化を与える。「見上げる」だけだったその眼差しを「まっすぐ見る」ことに変えた彼女は、マジックミラー越しに佇む『パリ、テキサス』(1984)のナスターシャ・キンスキーの分身である。愛の不信に病み、不気味な身体を纏うハリー・ディーン・スタントンも堕天使の1人である。自分が見ていることを相手に見られない状態で「見る」という行為を通して加害性を捨て、歓待性は開かれる。また見られていることの確信を持たずに声で対話を試みることもひとつの歓待性の開かれだろう。スタントンとキンスキーの眼差しの不一致の絡み合いによって、歓待性が生じ得るのであれば、小津安二郎の眼差しの不一致とはまさしく歓待性の問題である。役所広司も、最後にその眼差しを遮断するサングラスをかけた三浦大知との対話において、自らを木漏れ日として晒すことによって他者を受け入れるのだ。
そして、彼にそれを教えたのは姪である。彼女が役所広司と同じ運動を行い、同じ方を見たこと。同じ対象を見る彼女を後ろからカメラに収めること。それらこそが他者を受け入れながら自らを存在させる仕方なのだ。濱口竜介の『寝ても覚めても』(2018)のラストショットはまさに小津安二郎の「見る」ことへのパロディとして成立していたように、「まっすぐ見る」ことを通して反小津安二郎的な身体を主人公としたこの物語が小津安二郎的なものを超えて小津安二郎そのものと出会うのだ。
小津にあって、生きているものたちは、言葉をかわし合うことよりも、さらには正面から見つめあうことよりも、二人並んで同じ方向に視線を向け、同じ一つの対象を瞳でまさぐることが、より直接的な交感の瞬間をかたちづくるのである。
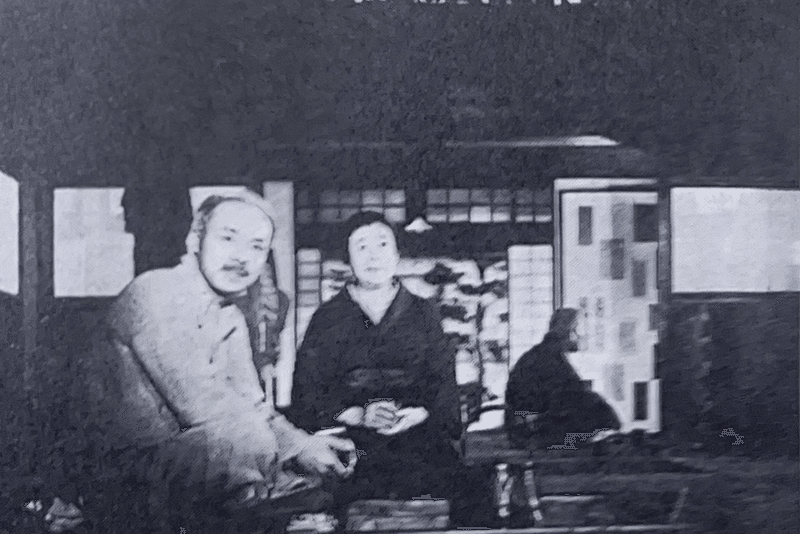
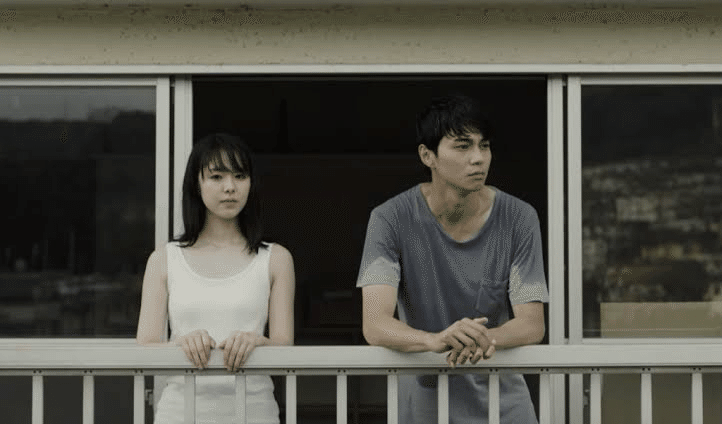
文:毎日が月曜日
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
