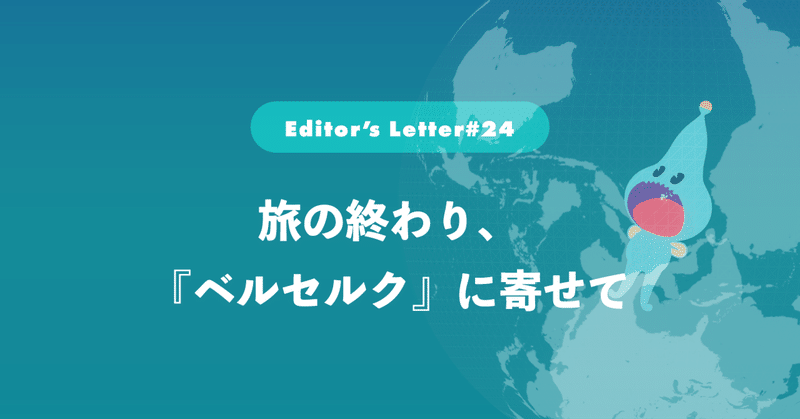
旅の終わり、『ベルセルク』に寄せて
※2021年10月1日に配信したメールマガジンに掲載したテキストです
感傷に浸る以外にないのでもうこの話はしないつもりだったんだけど、三浦建太郎がペン入れした最後のベルセルク364話を読み、『ヤングアニマル』のベルセルクメモリアル号のクリエイターの追悼を読み、「大ベルセルク展」にいってきたのでこれを書いてる。ネタバレを大いに含みます。
三浦建太郎の死について、ほかの多くの読者同様、わたしも、どう心の整理をつければいいのか今もわからない。
いやそれも正確じゃなくて、誤解を恐れずに言えば、一番心を乱されているのは、三浦建太郎の死ではなくて、ガッツの旅が断たれてしまった事実にだ。
人が死ぬことそれ自体は悲しいことだと思うけど、わたし個人としては、必ずしも不幸だとは思わない。一人残らずいつかは死ぬんだから、突き詰めればいずれ訪れる終わりが早いか遅いか、という尺度で捉えることも可能だからだ。
しかし、終わることができなかった物語はあまりに不幸だ。物語は必ず、何らかの形で終わるために存在するので、宙ぶらりんになってしまった物語は不遇と言うほかない。生き物は問答無用で死ぬ時が終わる時だけど、物語には死というものが存在しないから終わるためには誰かがちゃんと作為をもって終わらせないといけない。
現在刊行されている40巻、そして誌面に掲載された前述の364話を、よしんば物語の区切りに相応しかったと好意的に解釈したとしても、どう考えてもガッツの旅は終わっていない。
※現在は、ヤングアニマル掲載済みの話数を収録した41巻が刊行されている
キャスカはかつてのようにはガッツを見れない。ようやく記憶を取り戻したとは言え、惨殺された仲間たちの無念と、自身が被った心身の傷が、致命的にその関係性を歪めてしまった。当然、グリフィスとの因縁にも決着がついてない。それぞれの選択と覚悟がどういう未来を運ぶのか、まだ描かれていない。
どんなレトリックで言い繕っても、作者の死によって絶筆となってしまった『ベルセルク』において、ガッツやキャスカたちは──もちろんグリフィスも──進むことも戻ることもできず、あの暗い旅の途中で佇んでいるしかない。わたしたち読者は、進まない時間の中で永遠に取り残された彼らの姿を傍観することしかできない。これが、『ベルセルク』を巡る現時点でのつまらない事実だ。
現実から飛躍する想像力こそがフィクションの醍醐味であるのに、作者の死というただの現実だけがどうしても動かしがたい。当たり前すぎることだけど、つまらない事実に歪められてフィクションが屈してしまう、それがどうにもいたたまれない。
あんなにも苛烈な漫画を描く三浦建太郎は、嘘みたいに朗らかで優しく快活な人柄で、編集者や漫画家にとても好かれていたそうだ。メモリアル号や「大ベルセルク展」からもそのことがよく伝わってきた。
展示の最終エリアでは、三浦建太郎のインタビュー動画が流されていた。この先の展開について、2つほど生前の本人の口から語られたこともあったが、この旅がどう終わるのかについての言及ではなかった。
大勢でモニターを囲む形で眺めていたインタビューの最後、三浦建太郎が少しカメラ目線になって、「これからも『ベルセルク』を頑張りますのでよろしくお願いします」と口にした瞬間、思わず顔を伏せたのはわたしだけではなかった。
唯一、『ベルセルク』の結末を知っている人物がいる。高校時代からの無二の親友で、同じく漫画家として『ホーリーランド』などを描いてきた森恒二だ。
親しい漫画家に「ハッピーエンドになる」と話した。書いてあるがその親しい漫画家とは誰なんだろう。
— 森恒二『創世のタイガ』最新9巻は12月23日発売です! (@taigaofgenesis) September 22, 2021
自分は聞いてない。三浦は最終回については自分にしか話していないはず。憶測で書いているのだろうか。。。困惑した。(森)#ベルセルク https://t.co/3kNpiJWYbZ
彼はかつて三浦建太郎の実家に居候していたこともあり、漫画家としては互いの作品にアイデアを提供し合う仲でもあった。あまり例のないことだけど、三浦建太郎と森恒二の漫画は、原作付きを除いたすべてが、お互い相談し合いながら制作されているのだという。
あり得たかもしれない未来を知っている人物がいる。続きを読むのは諦めるから、せめて彼らの旅の終わりだけでも明かされてほしい、と思ってしまう。けど、森恒二がまさかそんなことを明かすわけがないので、結局読者がその結末を知れる術が今のところ皆無であることに変わりない。
スタジオ我画が引き継ぐんだろうか。スタジオ我画というのは、三浦建太郎自身が設立し、彼のアシスタントたちが所属するベルセルクの制作会社のことだ。
三浦建太郎はベルセルクの大部分を自分で描いている。穏やかな人柄とは裏腹に、漫画に対してはどこまでもストイックで妥協をしない。ベルセルク展で展示されていた原画は、その一コマ一コマが完全に絵画だった。
その書き込みは原画で見ればなおのこと尋常ではなく、人間の業とはとても思えない筆致が迫ってくる。その全てから、三浦建太郎の狂おしい魂の息遣いが聴こえてきた。
現在連載されている部分では、アシスタントに任せるのは建造物やモブくらいで、「本当に人に任せられる部分が少ない」とハッキリ口にした三浦建太郎が、本人不在の中、アシスタントたちだけで連載を描き継ぐことを良しとするだろうか。わたしには全くわからない。
しかし、そもそもそんなこと、わたしのような部外者に言われるまでもない。メモリアル号の最後、編集部のコメントにはこうある。
「作品の今後につきましては申し訳ございませんが今は未定とさせて頂きます。
一つだけ言えること、それは共に『ベルセルク』を作ってきたヤングアニマルとして、何より「三浦先生だったらどう思うか」という事を第一に考えていければと思っております。」
これまで『ベルセルク』をつくってきてくれた方々に深く感謝をしているし、この先編集部およびスタジオ我画がどんな決断をしたとしても、考え抜かれた末に違いないので、応援したいと思っている。その上で、わたし個人は非常に勝手で独善的だと思うけど、一つのことを願わずにはいられない。
現実には大団円などは存在しない。始まりもなければ終わりもない。物語的なお約束もない。現実はただ、現実としてそこにある。現実の方はそれでいい。物語は、その現実に代わって、わたしたちと世界の間を約束で結ぶことができる。
それは現実の代替ということでもなければ、模倣ということでもなく、逃避とも違う。物語はただ、物語でしか描けない真実を映す、現実ではないがしかし必ず現実と対になった、この世界の器官のようなものだ(とわたしは解釈する)。この器官が機能しなければ、世界は正しく呼吸することができない。
生前、三浦建太郎は『ベルセルク』の近年の展開について、「ファンタジーのお約束を全部踏んでいく」ところから考えたと語っていた。
「ガッツたちが妖精島に着くまで、仲間ができて一緒に目的地を目指すRPG風の流れですが、このシリーズは「ファンタジーのお約束を全部踏んでいこう」から考えました。海に出たら海賊船・クラーケン・人魚……そういった有名なファンタジー要素を全部出して骨格を作り、それをランドマークにするんです」
ファンタジーの一番大事なお約束こそは、異界に足を踏み入れた一行が、旅から帰ってくることだろう。それは必ずしもハッピーエンドを意味しないが、しかし何らかの形で「旅」から帰還する行きて帰りし物語、それこそはファンタジーの王道中の王道だ。わたしは『ベルセルク』読者なので、三浦建太郎を見くびったりなど絶対にしない。三浦建太郎ほどの人間が、そのお約束を考えていないわけがない。
だから願わくば、どうかガッツたちに、何らかの旅の終わりが示されてほしい。作者である三浦建太郎は死んでしまったが、ガッツたちを旅から解放してほしい。読者にその姿を思い描かせてほしい。それが、誰かが描き継ぐという形をとって表れるものなのかはわからないが、わたしはただそれだけを願っている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
