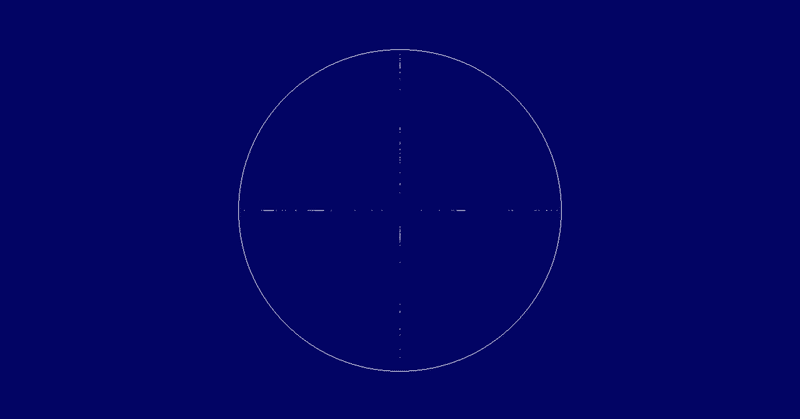
ファイア・イズ・アウト、リメイニング・ヒート 7
「うおおッ……」キャタリナとミゼリコルティアのカラテ衝突により空気が歪み、クレーンアームが揺れる。アングバンドは両手のチャカ・ガンをそのままに、両手の小指を薬指で祈るように掴まる……クレーンアームの先端より滑車を介し垂れさがるワイヤーの先、フックの鈎にだ。
「……サイオーホースッてか……アイツが加速してくンなきゃヤバかったかもな」
『キャタリナの正面突撃にカウンターを合わせる』、それ以外に勝つ方法はないという同意の元、アングバンドはキャタリナが左右から攻めるルートを銃弾で塞ぐ役目を請け負った。鉄骨から飛び降り、フックに手が届くまでのほんの僅かとも言える役割。
だが早く保身に走りフックに手を伸ばせば、寸前でキャタリナが軌道を変えるかもしれない。そうなればミゼリコルティアが破れ、各個撃破に次ぐ各個撃破、待つのは全滅だ。ニンジャアドレナリンによって引き延ばされた時間……短くも怖ろしい時間だった。……だった? 否、戦闘はまだ終わっていない。
軋む背筋に鞭打って背を反らし、上を見る。「フー……ッ」キアイを入れ直し、右腕を離し、左腕小指と薬指で全体重を支え、右チャカ・ガンを仕舞い、再びフックを掴む。両利きに矯正したものの、元は左利きだ。左の方が力が出る。
「フーッ……」キアイを入れ直し、左腕を離し、右腕で力強く全体重を支え、左チャカ・ガンを仕舞い、フック……その上部のワイヤーを力強く掴む!「フーッ……」
交互に全身を持ち上げていく。やがて滑車部に行き当たった。掴める部位がない。アーム上に復帰するにはこれまでより倍以上自分の身体を引き上げる必要がある。
「フー……ッ」腕の上下位置を入れ替え、左腕を上に……身体を振って勢いをつけ……右腕を離し、上へ……「クソッ!」ナムサン! 熱気と緊張による手汗が、体を保持する左腕を滑らせた!
伸ばした右手が何かに当たる。強靭に握られ、腹がぞわりと冷えるような感覚と共に引っ張り上げられた。ミゼリコルティア。「……おい、寝てんのか? 自分で支えろ」アングバンドは慌てて遊ぶ左腕をアーム上にひっかけ、勢いつけて全身を持ち上げた。「フーッ……サンキュ」「ん」
「……もしかして終わったンか?」大きく息をつきながら、アングバンドは問うた。ミゼリコルティアは答える代わりに煙草を取り出し、それで眼下を指した。
コックハートがキャタリナをキャッチしたその時、炎上する重機に囲まれるノーボーダーの顔色は限界に達していた。「コーホー……コーホー……」「もう無理です、火を消しますよ」「でも……」「……もしイクサが続くなら、酸素はあるに越したことはありません」「……そうね」
アンバーンドが指揮者めいて肘から先を頭上でひと回しすると、重機を焼いていた炎は終息していく。(((ニンジャ)))アンバーンドは考える。
(((できると思った事ができる。……ジツを使えば使うほど、ニンジャのイクサに身を浸せば浸すほど、できると思える事が増えていく)))アンバーンドは己のメンポに触れた。重金属のザラついた表面。
ノーボーダーは苦み走った顔で懐から無線を取り出し、制御室に通信する。「スネークフット=サン。換気システムを再開して。コーホー……そう。付箋が貼ってあるでしょディスプレイに。コーホー……それそれ。焦らなくてもいいわ。でも急いでね」
ゴゥ……どこかで機械の動作音がして空気が動き、残熱を吹き払っていく。「アー……ゲホッゲホッ……」ノーボーダーが口覆いを引き剥がす。白い養生テープの下から、口に当てていた円筒形のマテリアルを引き剥がした。アンバーンドもまた、生成可能となったメンポを外し、同じものを取り出す。
そして見守る。カラテの交錯と、コックハートの決死の行いを。
やがてクレーン車から、アングバンドがコックハートの肩を、ミゼリコルティアがキャタリナの頭を軽く叩いて(「……何!? なんなの!?」)降りた。所在なさげに佇むアンバーンドの傍らに立つノーボーダーがそちらに投げキッスを放ち、アングバンドはそれを大げさに避けた。
「なんだお前。ジツ持ちだったンかよ」「残念ながら違うのよねこれが」ノーボーダーは肩を竦めた。「説明いる?」「別にいい」「そうよねー!まずね、アンタは知らないかもしれないけど、モータルもニンジャも酸素って言うのがないと生きらんないの」「ッブン殴るぞ」「地下空間って事は、絶えず空気を入れ替えているワケよね」ノーボーダーは飄々と続けた。
「カトンの火は必ずしも燃焼に酸素を必要としない……でも物が燃えてれば別。だから制御室で換気システムを切って、私達はこれ」ノーボーダーは円筒形マテリアルを提示する。「地下でガスが出た時の対策かと思うケド……小型の酸素ボンベがあったからこれで頑張ったワケ」
「要するに」ミゼリコルティアが煙草を吹かした。「キャタリナ=サンにダメージを与えたのは酸素不足やら一酸化炭素中毒ってワケね……逆によく動けたもんだ」「ね。そこは予想外だったわ」ノーボーダーは背後からヨロシ紋のついたAEDを取り出しながら語る。「気絶したら酸素ボンベ吸入させて蘇生させる手筈だったし」
「アンバーンド=サンには『燃やしまくって足留めして!』ってロクに説明もなくムチャ振りしたの。ごめんなさいね、アンバーンド=サン」「イエ……」「それにしてもこう……ゾワッとするような邪悪ニンジャムーブだったわね! ホントよ? もしかしてアンバーンド=サンって演劇経験があったりする?」「イエ……」
焦げた重機から立ち昇る煙が、外周部の床付近のスリットに吸い込まれていく。無色透明の空気が動いているのはそれと知って集中して見なければ分からないが、色がつけばその働きは明白だ。広域空調特有の、薄くて大きい圧力を肌に感じる。
(((最初キャタリナ=サンに感じたプレッシャーの何割かはこれだったのかもしれないな)))とミゼリコルティアはひとりごち、煙を吐く。向こうではキャタリナが「……ベンダーミミックって何!?」と叫んでいる。
「スネークフット=サンも回収しないとね」「……そうだな」「そうなんですけど……」一同が大扉の前に立つと、触れるまでもなく、鉄製のそれはぐねぐねと歪んで見える。未だ容易に肉を焼き焦がすに十分な熱量が蓄えられ、陽炎じみた現象を起こしているのだ。電子制御回路が焼き切れたのか、ノーボーダーの遠隔操作も上手く行っていない。
アンバーンドは熱量を“見積も”った。それは実際奇妙な感覚であった。サーモグラフィーのように、元からある感覚に分かるよう翻訳するものではない、もっと直観的かつ……確信に満ちたものであった。「……でき、る」アンバーンドは自然と手を伸ばし、触れる。熱が物理法則に従い、低温部目掛けて、つまり焼ける鉄塊に無防備に触れる愚者の腕へと殺到する──それを感じる。
「エン・ジツ……」触れた箇所から小石を投げ込んだように波紋が──見えざる熱の波紋が広がり、扉から壁面へ、壁面から円周上に広がり、上方へ散逸させる
「フーン、器用なもんだ」ミゼリコルティアは一言コメントすると、鉄扉の取手をチョンチョンと触り、熱くも冷たくもないのを確認すると、そのカラテで巨大な鉄扉を無造作に三十センチほど開けた。
しかしミゼリコルティアはすぐには中に入らず、そして少し考える仕草を見せた。「どうしたのよ?」「……ああ、悪い。ノーボーダー=サン。スネークフット=サンを迎えに行ってくれ」
「別にいいけど……私だけで行くの?『お姉さま』が迎えに行ってあげた方がスネークフット=サン。嬉しがるんじゃなーい?」「なんでアタシがアイツを嬉しがらせなきゃならないんだ?」「アッ ハイ」純粋に疑問だ、という表情を見て、ノーボーダーは反射的に答えた。「それにな」ミゼリコルティアは頭を掻く。
「ちょっと気になる事があんだわ。キャタリナ=サンに確認しねぇと……」「そ? そんじゃ行ってくるわ~」ノーボーダーが鉄扉をスルリと抜けていく。「じゃアングバンド=サン、警戒ヨロシクしていいか」「ッアン?」ミゼリコルティアは苦笑する。
「アァー……」アングバンドは半ば呆然と、意味のないコトダマを吐いた。「マジだ。気ィ抜けてら。いや……いや、まァいいか。任しとけよ」「ヨロシクネ」ミゼリコルティアが歩き出しかけ、アンバーンドもそれに続いた。
「あの……私も少し彼らに用が……」「好きにしろよ」ミゼリコルティアはにべもなく言った。「つってもアングバンド=サンと一緒に警戒に回ってくれるとありがたいんだが」
「アッ ハイ……イエ、すみませんが…」アンバーンドは拳を握った。そしてメンポをポケットに押し込む。「話さなければ。私は彼女の……そして彼の、仲間を……殺したという話ですから」ミゼリコルティアは一瞬だけ、アンバーンドの横顔を視線で撫でた。「気にしてたら身が持たねぇぞ」「…………」「フ、好きにしろよ」
コックハートとキャタリナはクレーン車のルーフに腰掛け、未だ会話はどこかぎこちなく、しかし触れ合うような距離感で話しながら、睦まじくスシを食べていた。キャタリナなどは無邪気に足をパタつかせている。無作法であるが"あえて"犯しているわけではない。ただそれが無作法だと知らないのだ。
親のいた事がない彼らの、外見よりずっと幼稚で、かつ自然になされるムーブ。そしてアトモスフィアは、モータル時代に学校を出、小さな捻じれがあった以外ごく普通のネオサイタマ的人生を送っている──送っていた、とそう自認するアンバーンドにとって、自分とは違うリアリティを生きた人間の様に感じられた。
(((だが人間だ)))アンバーンドは独りごちた。……そして池に石が落ち波紋が出来るが如く、別のコトダマが脳裏に響くのを感じてもいた。(((そしてニンジャだ)))
「ドーモ、お二人さん」ミゼリコルティアが手を挙げ、気軽な様子でコックハートと、そしてキャタリナに声をかけた。キャタリナはスシを食べながら、一瞬だけ所在なげにした後、後ろから歩み出たアンバーンドを見て目を細めた。「…………」「…………」
「悪ィけど後にしてくれっかな」ミゼリコルティアはにべもなく張りつめたアトモスフィアを断ち切った。「アタシらの安全に実際関わるんだ。キャタリナ=サン。……アー、単刀直入に訊くが、アタシにブン殴られる前と後で何か変わった気はしねーか?」
「……そんな聞き方する? 普通?」「何が? 今何かアタシが遠慮する要素あったか?」心底わからない、といったミゼリコルティアの表情を見て、キャタリナは息を吐いた。「ナイデス」「そうだろ」「そういう感じな人なワケね」
「と言っても……そうね、何か頭の中がクリアになった気は、する……かも」「フーン」「キリエに何かあるのか? ミゼリコルティア=サン?」コックハートが尋ねた。ミゼリコルティアはすぐに答える代わりに、しばし空中に視線を彷徨わせた。
「どっから説明したもんかな。まずジツってのがあるだろ」「アンバーンド=サンの使うカエン・ニンポのような?」コックハートがあっさりと地雷原に踏み込み、キャタリナとアンバーンドの間の緊張度が上昇したが……二人は気付かないのか気付いた上で無視しているのか、そのまま話を続ける。
「そ。で、ジツってのも絶対無敵の一方通行パワーじゃない。種類にもよるが、高まったカラテで対抗……相殺したり弾いたりする事が、まぁ出来なくもない」「フーム」コックハートは腰を降ろしたままスローな正拳突きモーションを繰り出した。
「そんでだな。上でキャタリナ=サンとカチ合った時──そういう気配があった。『肉体と重なり合った形のないモノ』を殴った感触だ。経験上……エンハンスメントとかそういうのかな」「それは……!」コックハートが身を乗り出した。
「それは……キャタリナが操られていた……と?」「そういうんじゃないんだろ?」ミゼリコルティアはポリポリと頭を掻きながら……位置的にはキャタリナの下であるにも関わらず、睥睨するかのような視線でキャタリナを射た。「わ、私は……!」
キャタリナは反射的に口を開きかけ、閉じた。顔色が青くなっていく。ミゼリコルティアは一歩、二歩、三歩……進み出て、スシを取り、咀嚼した。「繰り返すが、アタシらの安全が懸かってる。分からない、という答えも、まァ事実である限りアリだが」
ミゼリコルティアは自らの視線をキャタリナが追っているのを確認した上で、コックハートに視線を遣り、頭を傾けた。「ウソ。だけは、ナシで。頼むわ」
キャタリナは眼球を左右に動かし、しばし言葉を探していた風であったが、やがて観念したように真っ直ぐ正面やや下を見て、膝上に握り拳を置いて話し始めた。「私達……"縦糸"とか"横糸"って分けられてたのは知ってるんだっけ」
「ああ」「"縦糸"は特に走り回って、ニンジャをキャッチする役割……具体的には"転送"する役割。鳶28区内なら、サタナキア=サンに貰った装身具で……」キャタリナは思い出したかのように自らの右脚を左脚の膝の上に置くと、ストレッチパンツの足首部分をめくり、嵌まった銀のミサンガを「イヤーッ!」
ミゼリコルティアは跳び上がり、ミサンガを両断! キィーン……遮る物のない空間でカタナが折れたような、物悲しい音が鳴り、断面から朱色の光が二重螺旋状に噴出した。それには赤と緑と青の破片も混じり、一瞬のハナビ・スペクタクルめいて一瞬で消え去った。ムッジョ……。
「ああ……」キャタリナは細く息を吐いた。シャリ、と音を立てて、切断されたミサンガが地面に落ちた。「…………」「サタナキア=サンのは……いや、まぁいいや」ミゼリコルティアは落ちた銀の鎖をポケットに流し入れる。
「……どういう事だ?」コックハートが沈黙の中へと切り込んだ。ミゼリコルティアは……頭を振り、僅かに口の端を曲げた。「ジツによる洗脳とかは受けていなかった。アタシが危惧したのは転送の方だし、これでアタシが口出す領分は終わりだ」
キャタリナは顔を伏せた。隣のコックハートにキャタリナの隠した表情を窺う事は出来なかったが、位置的に下から覗き込む形になるアンバーンドにはそれが見えた。羞恥。後悔。自己嫌悪。アンバーンドは──弾かれたように視線を外した。
「んじゃ、ノーボーダー=サン遅いし、見てくるわ」ミゼリコルティアは何らかの緊張感を増すアトモスフィアを背後に、ごくアッサリと、三人を、それも複雑な因縁を持つ三人を放置して踵を返した。鮮やかな退場であった。
場を離れるミゼリコルティアは、内心で己の懸念──根拠は勘だが──についての思考を進める。(((スネークフット=サンみたいな洗脳担当がこの狩場に投げ出されてたのが疑問だったが……サタナキア=サンのマインドコントロールは、ジツ由来とかじゃねぇ。総合的な技術、あるいは……)))
ミゼリコルティアは思い出す。カフェで対峙した大和撫子めいた姿。顎で、歯で、その舌で、目で──相手に喜んで破滅をも選び取らせる化生めいた気配。モータル時代、同じ種類の"本物"から見取り稽古めいたスキルラーニングを試みた経験がある故に堪え切れた──(((魔性か)))
キャタリナは何か話そうとしたコックハートの口にすかさずスシを押し込み黙らせると(「ムグーッ」)クレーン車のルーフから体を滑らせ、ストンと土に足を付け、アンバーンドと相対した。
「アノ」キャタリナは早速言葉に詰まったが、アンバーンドは「ハイ」と相槌ひとつ打つと、そのまま待った。主文を読み上げられる被告人のように厳粛に。
キャタリナはプラチナブロンドに染めた──褪色して地毛が出てきている──ガシガシと頭を掻くと、一際大きく息を吐き、それからまた息を止め……訥々と話し出した。「アンバーンド=サンがルカさんを殺した。憶えてないんだよね?」「……ハイ」「……だからか」
キャタリナは泣き笑いのような表情を作った。「私達が……夜……ただ歩いていた……アンバーンド=サンを襲った」「…………」アンバーンドは思わず勢い込んで顔を上げ、それからそれを恥じるかのように拳を強く握り締めた。
「ニンジャを追って、キャッチしろって話だったけど……ノルマをこなした後は、好きにやれた。だから……あの日、仲間と……ノルマをこなしたサタナキア=サンの下の仲間と、偶然鉢合わせして、それで……」「エット」「ゴメン、まず聞いて」アンバーンドが遮りかけたが、キャタリナは続けた。
「それで……歩いていたモータルを……アンバーンド=サンを……追って、囲んで、また逃がして、追って……。そうやって、"遊んで"た。落ちてた空き缶でサッカーやるみたいに」
アンバーンドは……頭痛を堪えるように目を伏せ、頭を伏せた。脳裏に去来する最初のインパクト。──三つ並んだヤクザの顔。銃弾。スリケン。銃弾。スリケン。ヤクザスーツのニンジャは、倒れる真ん中のクローンヤクザの両眼球を戯れに撃ち抜いた──ニンジャの無邪気なまでの残虐性。
「それで……その時にアンバーンド=サンがニンジャソウルを宿して……返り討ちにあった。……だから、私がアンバーンド=サンを一方的に責める筋合い、ないんだ」「それは」「キャーッ!」ナムサン、それはこの場の誰かが発した声ではない。細く絹を裂くような少女の──スネークフットの悲鳴だ。
「オイオイ」少し遠くで立哨をしていたアングバンドが、チャカ・ガンの一丁を四番搬入路の方へと向けた。徒歩で向かっていたミゼリコルティアが片手を挙げてフレンドリーファイアを予防しながら駆け込み……鉄扉の前で静止した。
「お二人はここに居て下さい!」アンバーンドは一言残すと弾かれたように飛び出し、鉄扉前でミゼリコルティアと、同じく立ち往生するアングバンドに合流した。「これは……」
扉の向こうの空間は、床は朱色の光で12の長方形に区切られ、こちらから見える三面の壁にはライオン、バタフライ、ゲイシャがそれぞれ荒々しい筆致で描かれていた。キャタリナとの戦闘以前には余白も多く、あからさまに未完成な壁画であった。だが……。
「イクサの最中にもそりゃ進行してるわな……」アングバンドがおもむろに銃弾を朱色の線に打ち込んだ。何の反応もない。銃弾が溶け落ちたり、光が強まったり乱れたり……そういった反応は何もない。アングバンドは……率先して踏み込む!
蛮勇にも思えたが、しかし何事もなく制御室の方へと走っていく。アンバーンドとミゼリコルティアもまた、一瞬で視線を交わすと、踏み込んでゆく。
ミゼリコルティアは走りながら素早く背後を、今しがた潜った鉄扉の側を見る。イカの壁画が浮かんでいた。「ライオン、バタフライ、ゲイシャ……そしてイカ……12面の左右対称パターン」「知っているんですか?」ミゼリコルティアは頷いた。「シュギ・ジキ。こいつは神秘的な……」
先行するアングバンドは『第四 制御室』のフスマを蹴り開けヤクザシャウト!「スッゾコラーッ!」室内にはスネークフット、そして彼女を庇う様に立つノーボーダー、それらに対する存在は……背負う金属製シリンダーに、外から入る朱色の光を反射させつつ上半身をゆっくり捻り、振り返って見た。
痩せた体躯。気味の悪いガスマスクめいたフルフェイスメンポ。ニンジャだ! 「邪魔立てするか、ソウカイヤの」「ア……!?」アングバンドは唸った。「テメェ、アッコラーッ! ドコナテッパナラーッ!」
「フム」新たなニンジャは上半身を捻った状態から全身を波打たせ、嘲るような口調でアイサツした。「ドーモ、はじめまして。モスキートです。フィヒ……少女欠乏な……ショ・ウ・ジョ……少女!!」
たとえどのような変態アトモスフィアを漂わせていようと、アイサツは大事だ。古事記にもそう書かれている。アングバンドは忌避感を奥歯で嚙み潰した。
「ッドーモ、はじめまして、モスキート=サン……アングバンドです!」アイサツ終了ゼロコンマ3秒、銃撃を加えんとしたアングバンドとモスキートの間に、ノーボーダーが割り込んだ!「待って!」
「どけコラーッ! シャッスゾコラーッ! どう見てもパブリックエネミー重点!」「確かにパブリックエネミーだけどモスキート=サンは私の仲間……知り合い……同僚……他部署の同僚なのよ! スネークフット=サンの悲鳴はちょっとその、インパクトが強すぎて……」「少女」ノーボーダーは何か喋ろうとしたモスキートのフルフェイスメンポをアイアンクローめいて掌で覆った。
「やめよノーボーダー=サン。指紋がつく」「……ッテメーの仲間ってんならよ」アングバンドはモスキートを務めて視界から外しながら言った。「ザイバツだろ」「……そうよ」ノーボーダーは……腰に手を当て、強いて胸を張った。「じゃあ、どうする。ザイバツと事を構えるの? それは今? それはここで?」「…………」
「アングバンド=サンが銃を収めるってんなら」一瞬の沈黙に、ミゼリコルティアが踏み込んだ。「アタシらの方に否はねぇよ。元々サタナキア=サンの策謀に巻き込まれた寄合い所帯だしな。ドーモ、はじめましてモスキート=サン、ミゼリコルティアです」「ホゥ……? ホゥこれは……ドーモ」「ドーモ、アンバーンドです」「ドーモ」
「ッオイ、俺はまだ……」アングバンドは言いかけて止め、舌打ち。それからモスキートを威圧的にひと睨みすると、舌打ち。チャカ・ガンのトリガーから指を離し、ぞんざいなホールドアップ姿勢を取った後、袖に収めた。舌打ち。
「フー……」ノーボーダーは誰にともなく小さくオジギをした。スネークフットはひとまず誰も動かないのを確認した後、パタパタとミゼリコルティアの背後へと回り込み、隠れた。
だがモスキートはフルフェイスメンポをノーボーダーに掴まれたまま、ギギギギと音が鳴りそうな動きで上半身を更に捻り、スネークフットを視線で追った。「少女よ……俺はアイサツしたぞ。君はどうだ? 出来るかな? ア・イ……サ・ツ……」
「…………」スネークフットは目尻に涙を浮かべながらミゼリコルティアを見上げたが、彼女は首を横に振った。アイサツされれば返さねばならない。それはニンジャの神聖なる掟なのだ。「ド、ドーモ、モスキート=サン、スネークフットです」「フィヒ」
「フィヒーッ! 少女ニンジャと激しく相互情報循環交換行為! 高まる!震えるオモチめいて……」「なるほど?」ミゼリコルティアはフラットな視線をノーボーダーに向けた。「ペドフィリア?」「一言では言えないわ」ノーボーダーはどこか悲壮感に似たアトモスフィアを滲ませながら答えた。
「っていうか!」ノーボーダーは掴んだモスキートの頭部を捩じ切らんばかりに力を籠めた。だが実際には力が弱くほとんど動かない。「 こんな!所に!送り込まれたのは! モスキート=サンが少女の気配がするとか言って単独行動したからでしょ! パラゴン=サンあたりに言いつけるわよ!」
「それは怖い」モスキートはゆっくりと上半身の捻りを戻し、ホールドを解くと、他四人に向き合った。「では真面目に……紳士的に……情報循環と行こうか」
「俺は他のニンジャと同じ部屋に飛ばされたが、早々に離脱し、ニンジャ野伏力を駆使してステルスしつつ探索していた」アングバンドが胡乱げにノーボーダーを見る。ノーボーダーは頷いた。「これでも斥候ニンジャとして優秀なのよ。これでも」
「そして探索の末、出口らしき場所……ここを見つけたが、その時には奥でイクサ音が聞こえていたゆえ、潜んでおった。まさかノーボーダー=サンらが戦っていたとはな。そして戦闘音が止んだゆえ、満を持して少女の気配重点したのだ」「………………なるほど?」誰も反応を返さない為、仕方なくミゼリコルティアが相槌を打った。
「まぁ……もう出口もそこだしな。アタシらも無駄に消耗したくない。やり合うなら……何をやり合うにしても、外でやってくれ」「フム」モスキートはねっとりとした視線をミゼリコルティアに注ぎながら首を九十度じみて傾けた。
「それは」「キャーッ!」ナムサン、それはこの場の誰かが発した声ではない。細く絹を裂くようなハイティーンの──キャタリナの悲鳴だ。「オイオイ!」アングバンドがガリガリと頭を掻きながら叫んだ。「ッ先客万来かよ!」
「フーゥム、このトーン、フレーバー、テクスチュア……ズバリ女子高生! フィヒーッ!」叫び走り出そうとしたモスキートの両肩を押し留めながらノーボーダーが警告をする。「モスキート=サン、次は庇えないからね。物理的に無理。ミゼリコルティア=サンのカラテ半端ないんだから!」「俺とて獣ではない。紳士……任せておくがいい」「不安だワァ……」「ッいつまでやってンだ、いいから行くぞ!」
長くて短い搬入路を色付きの風となって駆け抜ける五人のニンジャは鉄扉を潜り、キャタリナと争う新たなニンジャエントリー者を見た。ガンメタル色の異国風ニンジャ装束。キャタリナの蹴り足が霞むほどのハイキックに対し、開脚動作で的を下げ躱す! ワザマエ!「パンキ!」
「ッアー……」アングバンドは呻いた。
「私スカジ―チェ、バジャールスタしたのみ。シトー? スマー・サショール?」「何言ってるか分かんねーんだよ!」キャタリナがハイキックから回転動作に繋げ繰り出したローキックを、開脚状態から素早く地面を転がる動作、ワーム・ムーブメントで回避!
エントリーニンジャの戦闘経験が優れているのは疑いようもない、しかしキャタリナが攻め切れない最大の要因は、彼女にとって経験のない独特なムーブ! ガンメタル色の異国風ニンジャは腰に手を当てながら立ち上がり、弾かれたように伸び上がる右脚が……割って入ったアングバンドの股間直下で停止!
「……バリショーイヤ、アングバンド=サン。半分諦める事をしていましたが、元気であるかもしれないのはよりよい良い事ですね?」「アー……ドーモ、サボター=サン」アングバンドは冷や汗を流しながらタフを纏う。
「もっと日本語勉強した方がいんじゃねェか? トラブルの元だ」「元を断てば問題ないかもしれませんね?」サボターは腰に手を当てたまま、蹴り足を元に戻した。「私記憶間違いなければアナタが言うをしていたではないですか?」「…………」
アングバンドはキャタリナに背を向けたままヒラヒラと手を振って、チャカ・ガンを取り出していない事をアピールした。意を汲んだかは定かではないが、キャタリナは刺々しい殺気を収め、一歩下がった。
「否定はしないぜ。まァ……こっちは色々あったんだよ。あの後ここに……まぁワープさせられてな。ここにいるメンバーでここまで来たってェワケよ……サボター=サンは? アレ? 地下にいたワケじゃねェのかよ」「シトー? 転送?……あぁ、アナタが呑まれる事をしたエールカーカーアー旗色の光なら私避けていた」
背後からキャタリナが補足した。「そいつ……サボター=サン? エレベーターで来たんだよ。上から」「そりゃスゲェや」アングバンドは目を見開いた。サボターは目を細めると「クエスト進捗はどうですか」と切り込んだ。
「エート……なんだっけ。イヤ待てよ忘れてねェよ? 思い出すのに時間がかかるだけだ……アー……ソロモンの指輪ね。そうそう。コイツらの主人が持ってるってよ」アングバンドは親指で背後のキャタリナを指した。「ッなんかそういう話だったよな?」
「パニャートナ、つまりインタビュー出来たという事ですね?」「ッアー……」サボターはサーベルめいて更に目を細めた。「はっきりしない事私嫌いですね?そうであるならば横に居て下さい。私が直接インタビューします重点」
「ウアー……」「インタビューかね?」ヌッと、ガスマスクのメンポがアングバンドの肩越しに突き出された。アングバンドが反射的に繰り出した裏拳を側転動作で回避すると、そのニンジャはブルブルと身体を震わせながらアイサツした。「ドーモ、はじめましてサボター=サン、ザイバツのモスキートです」
「オイオイ……」アングバンドが頭を抱えた。キッとノーボーダーの方を睨むと、そちらも頭を抱えている。「ザイバツ」サボターが鸚鵡返しにした。「オーチン・プリヤートナ、モスキート=サン。ソウカイシックスゲイツのサボターです」
「ソウカイシックスゲイツ」モスキートが鸚鵡返しにした。そしてグルリと180度じみて首を巡らせた。「さぁ、俺はモスキート……さぁ、さぁ焦らさずに君の名前を私に注ぎ込んでおくれ。ハイティーン……おお、もしや君はフィヒ、女子高生の……ニンジャなのか……?」
「…………」視線を受けたキャタリナは露骨に困惑と嫌悪を顔に出し、アングバンドに説明とフォローを求めるように視線を送ったが、彼は首を横に振った。アイサツされれば返さねばならない。それはニンジャの神聖なる掟なのだ。「ウェー……ドーモ、モスキート=サン、キャタリナです。あと学校には行ってない」「フィヒ」
「フィーヒヒーッ! ローティーンニンジャに引き続きハイティーンニンジャと激しく! 相互情報循環交換行為! ハイアンドロー! アーッ! 俺はどれほどの高みに至るというのか!」「シトーエータ?」サボターはフラットな視線をアングバンドに向けた。
アングバンドは一切の感情を欠落させた声で「知らねぇ」と吐き捨てた。キャタリナは自身のジャージのファスナーを無言で上まで上げた。
「ドーモ、サボター=サン、アンバーンドです」状況が混沌とし、膠着した機を狙い、アンバーンドがアイサツをした。「無所属です」他のニンジャも続く。「ドーモ、ミゼリコルティアです。フリーランス」「ドーモ、ノーボーダーです」「ドーモ、コックハートです。イタマエ見習いだ」「ドーモ、スネークフットです……」
「フバーチット」サボターが鼻を鳴らした。「一枚の岩ではない状況という事ですね? ならいたずらにカラテはやめにしましょう。目的を目指す事を果たせばそれでいい。私は指輪を追って来ましたが、それは手に入りそうですか?」
アングバンドはガリガリと頭を掻いた。「少なくともここじゃねェよ。ここは指輪の持ち主の狩場だ。ニンジャをブチ込んでブチ殺す鉄火場ッてな……」サボターは少し考える素振りを見せた。「大切な人物が狩場を現れる事はないと言いたいことを主張しますか?」アングバンドは少し考える素振りを見せたが、すぐ頭を振った。「まァうん、そういうの」
サボターはぐるりと周囲を見渡した。「確かさ……長くここに居る事をすべきではない」つられてアングバンドも見渡す。「な……」六方向の鉄扉から、朱色の光が溢れ出し、漏れ出して来ている。
それは単に「光が差し込む」といった具合ではなく、質量めいて細い隙間から高圧水が浸透するように噴き出し、拡散している。全員の……否、一人のニンジャを除く全員が異様なる光景に目を奪われたその時!
「……そしてそれはザイバツのニンジャを殺す事をしないでここを出る理由になるないですね?」サボターが視線をぐるりと向ける。「シトー?」そして目を細めた。「グヂェー?」
「フィヒーッ!」全員の目線が奪われたその瞬間、跳躍していたのはモスキート! 右手首の仕込み針機構から硬質の針を突き出し、引っ込め、また突き出す!「直! 結! フィーヒーッ!」「ンアーッ!」
ガードするスネークフットの腕に針が深々と突き刺さり、血液を吸入する! モスキートは更に針からシリンダー内の汚染血液を注入事で相手をカロウシさせる恐るべきドク・ジツの使い手なのだ! アブナイ! 「「スネークフット=サン!」」キャタリナとコックハートが泡を食う! だが!「フィ……ヒ……?」
「イヤーッ!」「グワーッ!」ミゼリコルティアのカラテ掌打が直撃! モスキートは身体をくの字に折り曲げて吹っ飛び、ウケミを取る事すらなく地面に叩きつけられる!「オイ、もういいだろ。イエローカード二枚だ。三枚か?」視線を戻したアングバンドは舌打ちしてチャカ・ガンを取り出した。「殺すぜ」
ノーボーダーが何か言おうとしたその時、モスキートはバネ仕掛けのジョルリめいて直立した! だが……そのアトモスフィアはどこか先と異なっていた。フルフェイスメンポの奥の目は虚ろであるにも関わらず、動作がイヤにキビキビとしている。強固に制御されたジョルリめいて……。アングバンドは振り返った。吸血攻撃を受けたスネークフットに。
少女ニンジャは急激に血を失いフラつきながら、その目を爛々と光らせている。「ミワク・ジツ……私の血を媒介に、オーダーを書き込めるようにする……」「…………」ミゼリコルティアはスネークフットの膝裏を軽く蹴り、身を横たえさせ、自身は膝立ちとなった。
「お前が洗脳の基点だったんだな?」「そうです」ミゼリコルティアが尋ねると、朦朧としているにも関わらず、ほとんど間を置かずスネークフットは答えた。「私がやりました」「フ、」ミゼリコルティアは鼻で軽く笑い飛ばした。「嘘はよくないな?」「お姉さま、違います、私が……」
「ハイハイ……」ミゼリコルティアは口元に指を当て、スゥと目を細めた。「マジの魔性ってワケか。サタナキア=サンは」スネークフットは答えない。そうしてゆっくりと……意識を失うかと思われた瞬間、目を見開き、宣言した!「『モスキート=サン』」
「ハイ」モスキートは直立して聞き入れる。オーダーを! ミゼリコルティアは無言で手刀を形作る。「お姉さまの……『ミゼリコルティア=サンの言う事を聞きなさい』」「ヨロコンデー」
「モスキート=サンは血を体内に取り込んだから……あと最短でも一日は……保つ……ゴメンナサイ……」「……何へのフォローなんだよ」ミゼリコルティアは不機嫌に鼻を鳴らした。
横合いからコックハートがタッパーを差し出した。「……まだスシが少し残っている。回復の足しにしてくれ」「……いいの?」残っているのは四ピース。いかにも心許ないが、貴重な栄養でもある。
「ああ。本当はフレデリカに会えた時の事を考えて取っておきたかったが……命には代えられんさ。四つとも食べるといい」「……二つで十分ですよ」「いや、四つ喰食べろ」「二つで十分ですよ、わかってくださいよ……」曖昧に押し問答をしながら、スネークフットはスシピースをひとつずつ、計二つ咀嚼すると、ほぅ、と息を吐き、やがて穏やかな寝息を立て始めた。
「…………」ミゼリコルティアは躊躇なくスネークフットの胸元に手を入れると、ネックレスのチェーンを引き出した。チェーンだけだ。ストーンなどはない。「一応おさらいしとくと、コイツはサタナキア=サン……の関係者かもしれねーが、便宜上な。サタナキア=サンが力を籠めたアイテムだ」
ミゼリコルティアはチェーンを土の上に放ると、膝立ちのままにじり寄り、カワラ割りの形を取った。「リアルニンジャか、マジックアイテム持ちか、あるいはその両方。……イヤーッ!」チェーンに拳を打ち下ろす!
噴出する朱色の二重螺旋、そして赤、緑、青の断片、一瞬の、しかし半ばこの世ならざるスペクタクルに、初見のニンジャは息を呑んだ。「ファンタースチカ」サボターが呟いた。「マジックアイテム……期待できそうですね?」
光が消え去ると、その光景を直視した一同が目をしばたく中……ミゼリコルティアは直立するモスキートの方を冷酷に見遣った。「じゃ、ジツのテストするか」「ハイ」「テメェの顔を殴れ」「何故?」「チェックに必要だからだ」「ハイ。グワーッ!」モスキートが己の顔を殴打!
「テメェの腹を殴れ」「ハイ。グワーッ!」モスキートが己の腹を殴打!「財布出せ」「ハイ」モスキートが装束の奥からヘソクリと思しき小型の素子入りガマグチを取り出した。
「食え」「ハイ」モスキートはガスマスクメンポを押し上げ、隙間からオハギめいて差し入れたガマグチを咀嚼!「ムグーッ!」「もう一度自分の顔を殴れ」「ハイ。ムグワーッ!」ナムサン!ギャング私刑じみたムーブ!
「ヨシ、もういいぞ。財布もしまってスネークフット=サンを運べ。あと、針を刺したくなったらテメェの太腿に刺せ」「ハイ」モスキートは涎でべとつく財布をしまうと、スネークフットを身体の前方で片手で抱え上げ、そしてもう片方の手で己の太腿に針を突き刺した。「グワーッ!」
ミゼリコルティアは無関心そうにそれらの光景に背を向け、一同に声をかけた。「どうした? コントロール出来てるのはわかっただろ。さっさと上、上がるぞ」「アッ ハイ」「オ、オウ……」同じ勢力のノーボーダーは色を失い、最もモスキートに対し敵対的であったアングバンドでさえ腰が引けている。容赦のない傭兵流制裁が、一時的に場のイニシアチブを取ったのだ。インガオホー、あるいはサイオー・ホースめいて……。
ノーボーダーはドアガールめいてエレベーターのボタンを押し、カーボンフスマを開放させた。「オムカエドスエ」と合成マイコ音声が流れる。「ええと、六、七と……九人」アンバーンドが人数を数えた。
内部は存外に広く、詰めずとも十人は乗れそうだ。六方の鉄扉から溢れ出す朱色の光は、デッドエンドのマグマめいて迫ってきている。一度で全員乗り切れるのは僥倖だ。一同はそれ以上話す事もなく、エレベーターのカゴに乗り込んだ。
エレベーターパネルのボタンは二つ。「B49」と「44」その二つの不吉な数字しか、パネル上にはない。皆がその不吉さに瞬時戸惑うと、サボターが鼻を鳴らし、「44」のボタンを押下した。
「サボター=サン、よく押せるな」アングバンドが感心した様子で言った。日本では「4」がつく数字は“死”に繋がり実際不吉とされ、ビルヂングにおいてそれらの数字のついた階層や部屋は存在しない事になっている。サボターは侮蔑的に鼻を鳴らした。彼はこうした日本的なセンチメンタリズムを本質的に軽蔑しているのだ。
「ウエへマイリマスドスエ」カーボンフスマが閉まり、ノイズ混じりの合成マイコ音声が響いた。浮遊感。そして必ずしも統一的アトモスフィアを持たない多人数で狭所に乗り込んだ際の、気まずい沈黙。
……その中で、アンバーンドは、先のやり取りを思い返していた。ニンジャは邪悪。モスキート=サンの変態性欲でさえ、ニンジャ邪悪さの延長線上にあるものだ。そしてそれに呼応するように、彼自身の欲求──形のない、欲求への欲望とでも言うべき衝動が湧き上がってくるのを感じていた。
モータルとしての自身の経験に照らすなら……「不満がない、仕方がない」と己に言い聞かせていても、いつの間にか握っている拳。胃腸が弱っているのに、味と油と刺激の強い物を食べたいという想念。見出さず、闇に沈め、形を与えられない衝動は、必ずどこかで噴き上がってくる。そしてそれを満たしてやっても、根本の欲望が消え去ることは無い。
(((だがそれらの欲求の根源を癒す方法があるとしたら……?)))アンバーンドの脳裏に泡のように浮かぶ想定。この閉所。イマジネーション。炎。黒い塊。バッファロー。邪悪さ。力。ニンジャの力。そして黒髪の大和撫子めいた……。浮かび上がる泡を潰すようにそれらを否定していく。見出さず、名を与えず、形を崩して……これまでも……これからもずっと?
ガコン、ガコン……エレベーターのカゴが少し揺れた。「うわッ」キャタリナがよろめき、コックハートに支えられた。「ンだよ、安普請だな」ブチブチと文句を言うキャタリナに、コックハートがフ、と息を吐いた。
「キリエが蹴ったからじゃないのか?」「んな……そりゃ……蹴ったくらいで歪む方が悪いだろ……」口を尖らせるキャタリナに、狭いカゴの中を、不謹慎と知りつつ笑うのにも似た苦笑めいたアトモスフィアが生じた。
「あの」そのアトモスフィアに気が緩んだか、アンバーンド自身は独り言のつもりであったが、気が付くとそれなりの声を出してしまっていた。皆が胡乱げな目を向け、更にはノーボーダーが「どうしたの?」と相槌を入れた為下がるに下がれず、アンバーンドは急いで質問をでっちあげた。
「イエ……あの……ふと思いまして。皆さんお若いですよね」「……なァに、それ!」ノーボーダーはコロコロと笑った。「ニンジャは老化が止まるのよん。少なくとも外見はね。アー……スローハンド=サンは……まぁいいわ。だから外見から年齢はアテにならない……って話したわよね? してなかったっけ?」「あぁ……」アンバーンドは頷いた「してましたね」
「そうそう。だから理論上は五十年でも百年でもこのまま……」「え、ちょっと待ってください、そんなに……?」ノーボーダーは僅かに顔をしかめた。「私がそんな年齢だっていうワケじゃないわよ?」「アッ ハイ」
「ニンジャの肉体は頑健よ。健康寿命だけで百年はあるんじゃない?」「イクサやら病気やら薬物依存で割と死ぬけどな」アングバンドが混ぜ返した。ノーボーダーもしかし、その点に否やは無い。「考え方によっては辛いかもね。子供もなく百年……」
「ま、待ってください」アンバーンドは泡を食った。「子供がない……もしかして出来ないんですか?」「ン……」キャタリナが居心地悪げに身を捩った。「ン? アー……」ノーボーダーは額に手を当てた。「そーね、人によっては辛い話だったわコレ。やだわモータルの感覚だいぶ忘れてる」「スカジ―チェ、パジャールスタ」
腕を組み、壁に身を持たせ掛けていたサボターが不意に口を開いた。「その人は何ですか? ニンジャでは?」アングバンドがアンバーンドの特殊な状況について説明した。「ッアァ……アンバーンド=サンはよ、昨日だか今日だかくらいにニンジャに成ったんだってよ」
だがアンバーンドはそれ所ではなく、次々と湧いてくる泡のような疑問をコトダマにするのに必死であった。「エット……それじゃあ……ニンジャの皆さんは、あの、エット、大体ですよ。大体何を生きがいにしてるんです?」
ゼンモンドーめいた質問……だが気後れなく即答したのはコックハート。「師匠は……子供を成す事が出来ないからこそ、ワザを伝えていくのだと言っていたが」
「フン」サボターが侮蔑的に鼻を鳴らした。「生きがい。やりがい。日本的センチメンタリズムですね?私はスカウトの仕事をする人をしませんが、アナタも遠くなくソウカイヤの軍門に下るか、さもなくば死を選ぶ事になるでしょう。弱者強者に支配されるそれとても自然な事ですね?」
ノーボーダーはどこか取り成すように言葉を引き継ぐ。「ま、何かでっかい事をやる組織に身を捧げるってのも実際悪くはないわよ。折角ニンジャになったんだもの。夢はでっかく、カチグミ以上のカチグミ、格差社会! ってね」
「……ノーボーダー=サンと言いますか? アナタソウカイヤの所属ではない?」「ヤッベ」先のゴタゴタで、サボターはザイバツ所属はモスキートだけだと誤解しているのだ!
「まぁ、そういうのは吞んでる時にでも考えたらいいんじゃねぇの」ミゼリコルティアがアクビをした。
「酔って生きて、夢見ながらドブで溺れてくたばる。人間そんなモンだろ」「ヘッ、違いねェや」アングバンドがタフめかして笑った。「そうですか……」アンバーンドは曖昧に笑った。「そうですか」
アンバーンドは俯く。実際の所、アンバーンドにはそれほどの失望があったわけではない。現代のネオサイタマ派遣登録者は過酷だ。新しい事業がアブクめいて起こっては破綻する。労働者は給与が支払われている内に、揺れるカゴからカゴへ移り渡る。逃げ遅れれば給料はおろか、責任を負わされ、借金、ケジメ……逃亡犯罪者の群れめいたサツバツとした界隈だ。
朝にはバリキドリンクで覚醒し、夜にはザゼンドリンクで鎮静させられる。身体に蓄積していく軋み。次の場所に移るまでと言い聞かせて……次の場所。その次の場所。そして……ふと枕元に立つ輪郭のない模糊とした“いつかの終わり”のイメージはイーヴィルスピリットめいて、バリキでもザゼンでもどうにもならない。
(((そうじゃなくなる為には)))アンバーンドは沈思する。(((力を振りかざして好き勝手暴れ回る? ……それもいいのかも。けれど……)))先のイクサを思い起こす。キャタリナ。ミゼリコルティア。アングバンド。ノーボーダー。
(((力なら、上には上がいる。そしてそれは、数と経験と知略とカラテでひっくり返す事も出来る。……自分はその中であくまで勝ち通せると? それとも組織に腹を見せて、誰かのオーダーに従ってまた"仕事"をするか……)))
(((ニンジャ)))カゴの中のニンジャ──人間達がグニャグニャと──世界が揺れている。否、揺れているのは自分の頭部だけだ。いや、エレベーターシャフトが歪んでいるのだっけ──。
多少活気付き、皆が思い思いの事を話し出す中、ノーボーダーはノーボーダーに近づいて来た。「なんか随分と沈ませちゃったみたいね」「イエ……」「でもそうねー、ニンジャに成ると、人間関係リセット、家族と縁が切れちゃう場合が多いから……アンバーンド=サン、家族は?」
「……いません」アンバーンドは暗い、微笑にも似た表情を浮かべた。「母は早くに亡くなって……父は私のジュニアハイスクールの修学旅行のお金を出す為に内臓を売って……ハイスクールを卒業する年には、亡くなりました」
「アラー……」ノーボーダーは自身の顎下に腕をやって掌で支えた。そしてニヤリと、冗談めかして言った。「何もかもネオサイタマが悪いわ」「ハハ……」「内閣総辞職して政権交代だ!」「……ソウダー」
「ハハ……」
浮遊感が強くなり、腹を抑えつけられるような感覚が加速度的に増していく。エレベーターが目的のフロアが近付いて減速しているのだろう。
(((何も変わらないのか? ニンジャ……衝動を隠し、黒々としたものを抑えつけて、一体、何を目指し、何の為に、この生を耐えなければならないのだろう──)))
「トウチャクドスエ」合成マイコ音声が流れ、カーボンフスマが開いた。ニンジャは扇じみて八つの軌道に分かれて飛び出し、辺りを警戒する。
天井には豆電球じみた最低限の光源と、建物を支える円柱が等間隔で並んでいる。その他にはマテリアルは何もなく、容易に四方を見渡す事が出来る。床はコンクリートの平面。そして壁面には──。
「なんだありゃ、ユーレイ?」アングバンドが怪訝そうにチャカ・ガンを向けた。「イージオット。そのようであることありません」サボターが侮蔑的に言った。
「熱が少なすぎる……プロジェクションマッピングめいたムービー……?」アンバーンドが呟いた。四方のガラス窓には、一般的な“カチグミ企業の深夜オフィス”が縦三列……三フロア分投影されていた。つまり、昼と変わらぬ様を。
「なるほど?」アングバンドがチャカ・ガンのカメラ・アイをズーム操作した。よく出来ているが、外から普通に見せかける為、内から……ここから見ると文字が反転して見える。音もなく働き続けるモータル達の向こうでは、上弦の月が刻を迎え、自らを隠そうとしていた。
ノーボーダーがふと背後のエレベーターを見ると、巧妙に他の柱と区別がつかない様偽装された部分のハッチを開けた奥に操作パネルがあった。(((サボター=サンはこれを見つけたワケね……ソウカイシックスゲイツ。侮れないわねぇ)))
「……三階ぶち抜きか」「バレないのだろうか?」キャタリナがどこか呆れたように言い、コックハートもまた疑問を口にした。「バレないでしょうね」アンバーンドが苦笑しながら応対した。「私はカチグミ企業とほとんど縁がありませんが、誰も他人の事など……同じ社員であっても、気にしたりしませんから」
モスキートは虚ろな目で、抱えたスネークフットを抱え直したり、針を己の太腿に刺そうとする寸前で逡巡していた。「ま、いーだろ」ミゼリコルティアが伸びをした。「で、どうやってこっから出て行きゃいいんだ? サボター=サン……いや待て」ゴォーン…………。
ミゼリコルティアのニンジャ聴覚はどこからか、マグロツェッペリンが静穏走行しているような小さな、太く遠い音を聴いた。窓の外……から?
ォォォォ…………。
「ミゼリ……?」誰ともなく声をかけようとした時……多少の差はあれど全員が何らかのニンジャ感覚で捉えた。「違う!こっちだ!」
オオオオ…………。
「ドアが閉まりますドスエ」
「イヤーッ!」KRACK!
エレベーターのカーボンフスマがねじれて吹き飛び、天井に激突し、床を跳ね、天井をバウンド、床をバウンド! ジグザグに飛びながら正面の窓ガラスに叩きつけられ、巨大なクモの巣めいた亀裂を生じて止まった。
だがフスマの行く末などに目線を遣るものは誰もいない。エレベーターのカゴ、その床とフスマとをカラテ破壊した蹴り足でふわりと着地する。その右手には、男ニンジャの、首。その左手には、女ニンジャの、首。
放射状に広がった髪が、漆黒の羽衣めいて遅れてまとまる。「ドーモ、皆さん」大和撫子めいたアトモスフィア。それは細い三日月のような笑みを浮かべ、新月のような目で睥睨した。「サタナキアです」
◆◆◆◆◆◆◆
3.クロス・ファイア
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
