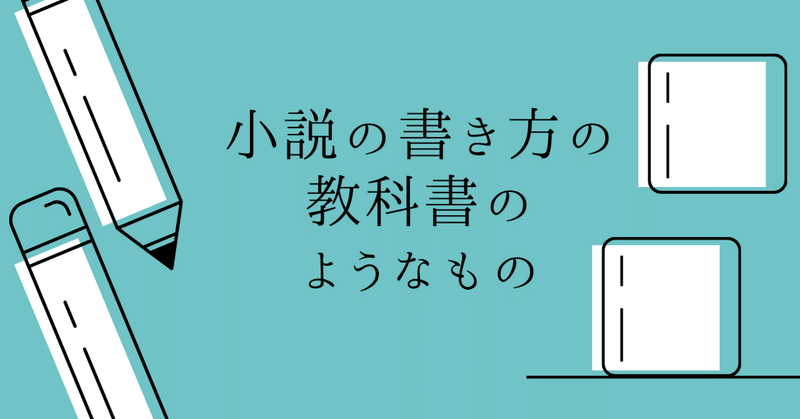
構成力をつけるトレーニング方法
最後に、構成力をつけるトレーニング方法について紹介します。
前の記事で述べたように、物語にとって最も良い構成を見つけるためには、大きな手術が必要になる場合があります。ですが、最初のうちはなかなかそこに踏み切れません。せっかく書いたものを捨てたくないし、どのエピソードも設定も愛着があって一部を切ったり入れ替えたりしたくないからです。
それはわたしも同じです。せっかくまとめあげたものを、できれば直したくないのです。
しかし、たまたま最初に思いついたその構成が物語にとってベストである確率は、初心者の間は低いでしょう。手術をせずに放置して完成品としてしまえば、十分にポテンシャルを発揮しなかったもったいない作品になりますし、小説を書く力も身につきません。
そこで、構成力を身につけるトレーニング方法を紹介します。これはわたしが偶然見出したもので、あとから振り返ったら、あのおかげで今があるなと思えたので、みなさんに紹介したいのです。
方法はシンプルです。
用意するのは、自分で書いた完成した小説作品。それは推敲に推敲を重ねて仕上げたものが望ましいです。これ以上直すところはないとあなたが考えた作品のほうが効果的です。
その作品を、作品のメッセージや味わいを残しながら、三分の一の長さの作品に書き換えてください。これがトレーニング方法です。
国語の要約問題のように無味乾燥な説明文だけを並べては小説にはなりません。また、伝えたかったことの一部だけをピックアップするのもダメです。文章に小説としての味わいを残し、伝えたいことを伝え、物語の魂は変えずにやるのです。
これをやると強制的にどこかを削らざるを得なくなります。削りたくなくて自分で自分をごまかしていたときとは違う無慈悲な目で原稿を見ることになります。どこかを削ろうとすると、あなたの心は全力で抵抗するでしょう。ここだけは削らないでくれと懇願するかもしれません。でも、その懇願を聞いて見逃していたら文字数に収まりませんから、泣く泣く何かの要素を削るのです。
そうすると、どうなるか。三分の一も削ったらきっと物語は台無しにぐちゃぐちゃになってしまうはずです。ところがあら不思議。なぜか、元の作品よりも面白く味わい深い作品になってしまうのです。
つまり、元の文章の内容は、小説に必要な濃度の三分の一の薄しかなかったのです。
三分の一に削るというのはわたしの経験則です。なんとかしてデビューしたくて、でも新たに書き下ろす根性もなく(書こうよ!)、昔書いたものをリメイクして公募の賞に送るということをしていた時期がありました。
あるとき、1000文字の掌編小説の募集がありました。新たに書き下ろす時間はない(いやいや、書こうって)。じゃあストックから出そうと思ったものの、一番短い作品は3400字だったのです。それでも出したかったので3000字越えの作品を1000字に収めるよう試行錯誤しました。そうしたら、最初に書いたものよりも面白い作品になってしまったのです。それは衝撃的な体験でした。
その衝撃を一緒に味わってもらうために、2種類の小説を読んでもらいます。
以下に載せたのは、わたしがある仕事でウェブ連載していたときに、エピローグとして添えた短い小説です。読んでみてください。手紙の終わりまでが作品で、1596字の短編です。
去年、父が亡くなった。九十歳の大往生だった。初めて書いた小説は、父親についての話だった。そのせいか、いまだに読者や編集者から、すてきなお父様を持って幸せですね、と言われる。そんなことを言う彼らは、小説家の仕事が何かを忘れているのだろう。小説家の仕事は嘘をつくことだ。理想の父親を書いたのだから、すてきなのは当たり前だ。あれは私の切実な嘘だった。こうあって欲しいという願いだった。この父さえいなくなればと何度も思いながら私は育ってきた。威張りちらして、人の話を聞かず、自分勝手で、絶対に間違いを認めない。母に手をあげ、しつけと称して子供をなぐる。楽しい思い出なんてひとつもない。父と分かり合うことは不可能だった。父は、私が堅実な仕事に就くことを望んでいた。だから、小説家になると宣言したときは激怒した。でも、それが私の望みであり復讐だった。父の理想の息子像から外れ、完全に失望され、私は自由になった。それからしばらくは、音信不通状態だった。息子の武尊が生まれると、父との関係は少し変わった。目尻を下げてでれでれしている父は、ただの孫に弱い老人だった。頭をなでられている武尊を見て、うらやましいと思っている自分に気づいた。私は父のことが好きだったのだと、そのとき初めて自覚した。小説に書いたように、自分に笑いかけてほしかった。でもそれはもう、かなわぬ望みだった。
遺品を整理するために、私は初めて父の書斎に足を踏み入れ、そこで、言葉を失った。本棚に私のすべての作品が並んでいた。ずっと昔に書いたものも、小さな出版社から出たものも全部初版でそろっていた。その中に、デビュー作もあった。他の本よりもよれよれになっていて、明らかに何度も読んだ形跡があった。私は血の気が引いた。どうせ父は読まないからと、好きなことを書いた本だ。本当の父とは似ても似つかない、理想の父親像。当の本人は、どんな思いで読んだだろうか。残酷なことをしたと後悔しても、もう遅かった。父はもうこの世にいないのだ。もっと早く、この本について父と話すべきだった。フィクションだからと言い訳することも、今は恨んでいないと伝えることもできない。
そのとき、本に挟んであった何かが床に落ちた。封筒だった。「小説家になった我が息子へ」と表に書いてある。いったい何が書いてあるのだろう。懺悔だろうか。私は心を痛めながら、便箋を開いた。恐る恐る読み始めた私は、途中で思わず吹きだした。それは予想外の内容だった。おかしくておかしくて笑いが止まらなくなった。さすが父だ。最後まで、自分勝手な勘違いをして逝ってしまった。これでいい。私たちは、理想の親子だ。私は涙が出るまで、ずっと笑いつづけた。
小説家になった我が息子へ
この手紙を読む頃には、お父さんはこの世にいないでしょう。生きているうちに口で言えなかったから、手紙を書きます。この本に挟んでおけば、きっと見つけてくれるだろうと思っています。お父さんは、この本を読むまで、ずっと後悔していました。お前に厳しくしすぎたかもしれない、と。お前の顔を見ると、どうしても心配が先に立って、がみがみ言ってしまう。きっと恨まれて嫌われているだろうと思っていました。でも、そうじゃなかった。親の愛情がちゃんと伝わっていたことが、この本を読んで分かって、嬉しかった。こんなふうにお父さんのことを理解してくれていたなんて、最初読んだときは、感動で涙が止まりませんでした。嬉しくて嬉しくて、何度も読みました。小説家というのは不思議な職業だ。口に出して言えないことを文字にしてくれる。目に見えないものを書いて、人の心を溶かしてくれる。お父さんを書いてくれてありがとう。お前はお父さんの、理想の息子です。これからももっと、いろいろな人の気持ちを代わりに書いてあげてください。
父より
いかがでしたか。さて、この小説を400字の小説のコンクールに出すことになりました。かなり無理がありますけど、新しく書き下ろすよりは楽だろうと思ったのです。みなさんはこんな手抜きをせず、ぜひともどんどん書き下ろしましょう。ともあれ、あれやこれや試行錯誤して、以下のようになりました。
デビュー作は、父の話を書いた。そのせいか読者や編集者から、素敵なお父様ですねと言われる。だが、あれは俺の父を書いたものではない。こんな父であってほしかったという切実な願いを書いたものだった。
人の話を聞かず、自分勝手な父。小説家になると宣言したときも激怒された。いつか分かりあえたらと思っていたが、もうそれはかなわぬ夢となった。父は死んでしまったからだ。
遺品を整理しているときだった。本棚に、俺のデビュー作を見つけて青ざめた。どうせ読まないからと、好きなことを書いたのに。
本には封筒が挟まれていた。「小説家になった我が息子へ」と表に書いてある。中を開いて思わず吹きだした。そこには『この本を読んで親の愛情がちゃんと伝わっていたことがわかって、嬉しかった』と書いてあったのだ。さすが父だ。最後まで、自分勝手な勘違いをして逝ってしまった。
俺は涙が出るまで、ずっと笑い続けた。
これを講座で披露して、どちらの小説の方が好きですか? って聞いたら40人のうち38人が後者と答えたのでした。ショック。大ショック。
でも確かに400字のほうがいいのです。悔しいけれども。400字に削る過程は大変でした。気に入っているエピソード(孫の話)や言葉(小説家の仕事は嘘をつくことだ)や設定(息子の初版本を買いそろえていた父)など、削りたくない要素がたくさんあって、心で泣きながら削っていったのです。それなのに、削ったあとのほうがいいなんて、削られたエピソードが報われないですよね。
しかし、これが結果なのです。この例からわかるように、作者は親ですから自分が生み出したすべてに愛着があります。でも小説を書くときに大事なのは作者の愛着ではなく、読者が楽しめるかどうかです。自分の愛着コレクションを家に呼びつけた友人に披露するのは構いませんが、お金を払って泊まりにくる旅館のお客様にあれも見てこれも見てと強要したら、どちらが客かわかりません。
このトレーニングによって、小説にとって必要なものと、自分が書きたいだけで小説にとって必要ではないものを見分ける目が養えます。
絶対に削りたくないけれど、削らざるを得ない状況に追い込むのが、文字数三分の一作戦なのです。こんなふうにぎゅっと濃縮して初めて面白い小説になるのです。三分の一に凝縮して、空いた三分の二にはもっとふさわしい別のエピソードや要素を書けばいいのです。
ということは、文字数を水増しするためにだらだらとエピソードを引き延ばしたり、間を埋めるためだけのつなぎのシーンを入れたりした小説が面白いわけはありません。小説の文にはすべて意味があり、文の並び方もすべて計算し尽くされているのです。
このトレーニングをして、初稿の無駄な要素を無慈悲に切り落とすことができるようになったら、作品のパワーが段違いにアップします。だまされたと思って、ぜひ一度やってみてください。
以上で、小説の書き方の教科書のようなものの連載をひとまず終わります(また気が向いたら増えていくかもしれません)。あとは実践あるのみ。書いて、読んでもらって、伝わらなかったら反省して試行錯誤する。そのくり返しで小説を書く力は鍛えられます。一つだけ、注意点があります。小説は完成させないと、次のステップに進めません。途中で止まってしまったものを何作書いても、小説の力は身につかないのです。あきらめず、一作ずつ仕上げていきましょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
