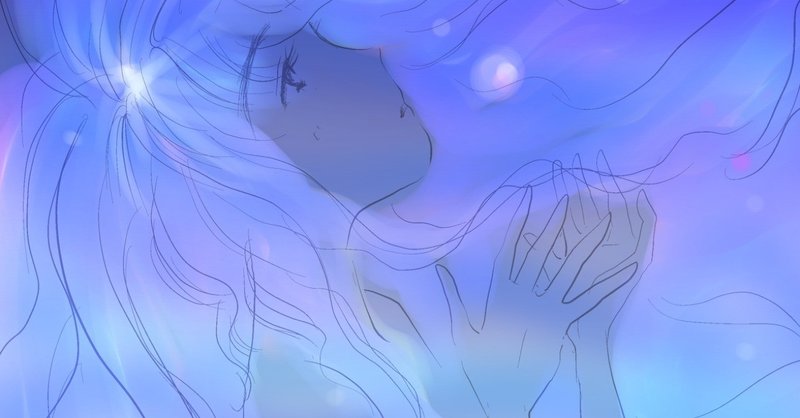
CALLING
僕が彼女のことを知ったのは、ネットの動画投稿サイトで偶然その歌声を聴いたのがきっかけだった。どんよりとした梅雨空が続いていた。動画の方も曇天模様のいつかの休日の昼下がり......夕暮れ前といった感じか。どこかの公園にある円形劇場のような所で彼女は歌っていた。投稿者はその会場の観客の一人だったようだ。遠目だったので、彼女の容姿についてははっきりとは分からないが、静かな佇まいで、その歌声は美しく澄んで、どこか寂しげながらも人を惹きつけずにはおられぬ何かがあった。それ以来、気づくと僕は日に何度もその動画を再生していた。しかし今日また見てみたら、それは削除されていた。
会ってみたい。生でその歌声を聴いてみたい。
そんな想いに突き動かされ、僕は彼女を捜し始めた。まずはその投稿者を突き止めて会う約束を取りつけ、なんとか話を聞くことができた。しかし有力な情報を得ることはできなかった。投稿者の男性は彼女の名前も年齢も何も知らなかった。歌っていた場所は都内のとある公園の円形劇場で、撮影された動画は一年近く前のものだった。分かったのはそれだけだ。しかし削除の理由は聞くことができた。ある日突然、動画投稿サイトの運営から削除依頼が来たというのだ。
「何故ですか?」
「さあ、私にも分かりませんよ。ただあれをみて気分の悪くなる人が出たそうですよ。そう言われたら......仕方ないじゃないですか」
何か判然としない理由ではあったが、僕のあずかり知らぬ大人の都合があったのかも知れない。このまま手がかりなしで捜索終了か……そう思った矢先だった。 あちらこちらのネットの掲示板で彼女のことを知っている人はいないか訊いて回っていた中に、返事をくれた者がいたのだ。
「彼女の名前はMANA。出身はN県の海沿いの町らしい。年齢は不詳。地元で歌っている所を誰かが撮影して動画投稿サイトに上げた所、東京のどこだかの音楽事務所にスカウトされて、一度だけ東京に出てきたらしいが、以降消息不明。件の円形劇場の動画もどうやら東京に出てきたその時に撮影されたものらしい」
ガセかも知れないが、何故だか捨てておけない何かを感じた僕は、金曜日を待って仕事を定時で終わらせ(言っていなかったが僕は公務員だ)、二泊三日分の荷物をま とめ、気づいたらN県行きの新幹線に飛び乗っていた。手がかりも殆ど残ってないというのに(例の動画は投稿者の彼にこっそりコピーさせて貰った)。
実質、正味二日もないのに彼女を......MANAを見つけることなど到底無理だろう。それでも僕が捜しに行かなければ誰も彼女を見つけることなどないのではないか、彼女は僕に捜し当てられることを待っているのではないか、次第にそんな妄執にとらわれるようにまで なっていたのだ(我ながら頭おかしいとも思う。今となってみれば、だが)。
あの歌声だけで捜し当てるのはやはり無謀だった。
まずは新幹線の主要な駅で降りて、駅や近くの飲食店、カラオケ屋の店員さんなどにあの動画を見せながら、訊いて回ったのだが、全く収穫はなかった。初対面の人達に話しかけるのはかなり骨の折れることだった。相手にされなかったり、むっとされたり......。かなりぐったりしてしまい、帰りの新幹線はずっと寝ていた。
それから一ヶ月程経ったある日、MANAについての新情報が入った(まだネットでこそこそ情報を集めていた。便利な世の中で良かった)。
どうやら彼女は数年前までN県J市の路上で歌っていたらしいというのだ(僕が先月捜していた場所よりだいぶ南の方だった)。
ちょうど来週からお盆休みに入る。僕は夏休み前の子どものように、そわそわしながら休みに入るのを待った。
J市に降り立つと早速聞き込み調査をした。彼女の特徴は殆ど知らない。ただあの動画一つをひっさげてひたすら聞き込みをした。駅前のストリートミュージシャンがいそうな場所や、近くの店など朝から日が暮れるまで回った。やはり簡単なことではなかったが、一日足を棒にして訊いて回ったおかげで、やっと手がかりらしきものをつかむことができた。
「あっ、この子なら私知ってるよ! U浜という海水浴場の近くにいるんじゃないかな? 今もいるかは知らないけど、天気がいいと海の向こうにS島が見えるって。そこでよく歌ってたって聞いた」
「ありがとう! 今から行ってみます」
町を離れるにつれ、次第に潮のにおいが強まってきた。海が近づいてきたのだ。
バスを降りるともう日暮れ間近の時間帯で、海水浴場とはいえ人影もまばらになりつつあった。
ここでの聞き込みは今日はもう無理か。
僕は近くに宿を探しその日はその浜の近くで休むことにした。お盆だというのに素泊まりでも空いている宿があって助かった。その旅館は鄙びた、と言っていい程度には古びていた。それでも一応温泉付きだったし、中庭も木々が手入れされ、なかなかどうして悪くはなかった。思えば一人でこんな風に思い立って旅に出ることも初めてで、どうしてこんなことになったのか自分でも不思議に思った。僕は決して感情に 流されて思いつきで行動するタイプではない。むしろ臆病で慎重で何に対しても腰が重い方だ。粘着気質ではあるとは思うが。
暇つぶしに旅館のお土産売り場をウロウロしていて、ふとあるものが目に留まっ た。蝋燭だ。キャンドルではなく、いわゆる和蝋燭と言われるものだ。僕がそれを手に取りためつすがめつ見ていると、
「何かお探しですか?」
と売り場の店員兼旅館の 従業員とおぼしき年配の男性が僕に声をかけてきた。
「あ、いや......別に」
そう答えると、聞きもしないのに、
「これは和蝋燭です。この近くに昔から続いている蝋燭屋があって、そこのものですよ。お客さん興味がおありですか?」
と話しかけてきた。
「あ、いえ、そんなには......ははは」
「そうですか。残念です。その蝋燭にまつわるこの海岸に伝わる男女の悲恋物語もあるんですがね......」
その老人が本当に残念そうな表情を浮かべながらそう言うので、思わず口が滑った。
「あ、少し! えっと、少しだけ......聞きたいです」
「そうですか。じゃあ少しだけ......」
老人の話はこうだった。
昔、日本海の向こう側のS島からこちらの浜に住む若者に逢うために海を渡ってくる不思議な女がいたのだが、実は若者には許嫁があって、それでも若者はその女に逢うために夜な夜な抜け出していたのだそうな。それを許嫁の母親が知って、若者を咎めた。その女が海を渡ってくる時に目印にしている神社の常夜灯があったのだが、咎められたその晩、若者はその神社の献灯をひと夜休んでしまったのだそうだ。そのために女は遭難して溺れ、そこの崖下に打ち上げられたそうな。若者はたいそう悲しんでその女の後を追ったという話だ。
「それが後に人魚伝説となって今に伝えられている。すぐそこのG浜という所に碑も立っているから、興味があったら見に行ってみるといい」
僕は正直そんな話はどうでも良かったが、とりあえずそこは「はぁ」とだけ言って話を合わせておいた。結局、その売り場の蝋燭とその話がどういう関係があるのか、よく分からないままだった。蝋燭は買わずに部屋に戻った。
そんなことよりMANAだ。明日夜が明けたらさっさと支度してまた捜そう。時間は限られているんだ。僕はイヤフォンを耳に挿しMANAの曲をリピートした。
翌朝、早めに目が覚めたので支度をしてすぐに宿を出た。関東では連日連夜猛暑だと天気予報は言っていたが、ここは海沿いなのもあってか、朝の空気はひんやりとして潮の香りも今日は心地よく感じた。こんな朝早くでは海水浴客もまだ出ていない。
しかし、人もまばらな海岸線を歩いているのは僕と犬の散歩をしている地元住民ぐらいしかいなかった。
U浜海水浴場から海岸線に沿って北上していくと、G浜という所に辿り着いた。
(あれ......確かここって......) 何かを思い出しかけていたその時、脳に衝撃が走った。
〜♪
ほんのわずかの音だが、潮騒に混じって鼻歌のようなものが聞こえてきたのだ。しかしそれはすぐに風と波の音にかき消されてしまった。僕は目を凝らし耳を澄ませてあたりをきょろきょろした。
(間違いない! 今の声......) MANAだ!
もう一度あたりを見回すが姿を確認することはできない。声も消えてしまった。もう一度歌ってくれたら......そう思っていたら、また鼻歌が聞こえてきた。今度は割とはっきりと聞こえる。
「!」
振り返ると、僕からおよそ距離にして70〜80メートル程離れた所にラブラドールを連れた女性が浜辺を散歩しながら鼻歌を歌っている。
僕ははやる気持ちを抑えながら近づいていった。僕の接近に緊張したように犬が反応した。その緊張が伝わり、彼女も鼻歌を止めた。
「あ、あの......お、おはよう......ございます」 僕が精一杯の勇気を振り絞って挨拶をすると、彼女はこちらを向いた。そしてその目は僕を見てはいなかった。
「おはようございます。気持ちのいい朝ですね」
「は、はい......」
僕は驚いてしまって、咄嗟に声が出なかった。
彼女は目が見えない人だったのだ。
小柄でほっそりとした身体、色白で丸みを帯びた顔つきはまるで少女のようだっ た。つば広の帽子をかぶり、髪は肩を過ぎる程の長さで斜めに一本の三つ編みに結っていた。細かい青い花柄のコットン生地のロングのシャツワンピースに白い薄手のカーディガンを羽織っているその姿は、動画のMANAとも雰囲気が違ったが、やはり年齢不詳な感じがした。 僕があまり長いこと声を発さずにじろじろと見ているのを不審に思ったのか、彼女 は訝しそうに眉間にしわを寄せて、
「あの、なにか?」
と今度は毅然とした口調になって言った。
「あ、あの、えと......MANA......さんですか?」
しどろもどろになりながら、やっとそれだけ言うと僕はまた不躾な視線をちらちらと相手に向けた。
「はい。そうですけど。東京の方?」
ため息で一呼吸置いてから
「東京へは行きませんけど。もう」 と今度は明らかに怒ったような口調で言い放った。
「あ、違いますよ。僕は、その......あなたのファンで」
「ファンがわざわざこんな所に来る? どうやって場所を調べたのか知らないけど、 迷惑です。帰って下さい」
「あっ、えっとごめんなさい!!あの!でも僕は......別に怪しいものではなくて、 あなたの歌に救われたっていうか......」
「何それ、キモッ!!行くよレン!」
「ワンッ!」
ああ......。やっちまったか。
ここまできてどーする俺!
僕はこっそりとMANAのあとをついて行った。決してストーカーとかそういうので はなくただもう少し話をしてみたかった。 彼女の家は海の近くにあった。平屋の一軒家で、犬一匹と一人で暮らしているようだった。しばらくすると、彼女は花を持って部屋から出てきた。そして波打ち際まで 降りてきて今度は鼻歌なんかじゃなく、大きな声で歌を歌いながら花を海へ向かってばらまき始めた。
ひとり去りゆくあなたのために
この花束を捧げましょう
本当は私もあなたと一緒に
海の向こうにいきたかった
波がさらったあなたの身体
海の底は暗かろう
海の水は冷たかろう
めしいた私のこの目にも
あなたの姿が見えるよう
私の声が聞こえますか
私の声が聞こえますか
私の声が聞こえますか
私の声は 届かない
動画以外のMANAの歌を聴くのは初めてで、僕は圧倒されていた。動画の時よりももっと力強く心を揺さぶる歌声。大仰なようだが、今にも大波が起こりそうな程だ。
僕がはらはらと涙を流して見ていることに気づいたMANAが近づいてきた。
「あなた、さっきの人?」
「あ、は、はい。すみません。あの、決して後をつけたり......ああいや、してました。 ごめんなさい。あ、キモイですよね。......すみません、あの」
「……こっちこそキモイとか言ってごめんなさい。今の全部見てました?」
「あ、はい。生歌が聴けてとても感激したって言うか......」
「正直どん引きでしょ?」
「はぁ。あ、いえ!!」
僕は頭をぶんぶん振り回した。
「ここら辺りの人はみんな私の頭がおかしくなったって多分思ってる」
「……」
「わざわざ遠くから私を訪ねてきたんでしょ? 少しお話しましょうか?」
そう言って僕たちは砂浜に腰を下ろした。 初対面の僕に対して、MANAはぽつりぽつりと自分の生い立ちなどを話し始めた。
MANAは本名を清原真魚(きよはらまな)と言った。幼い頃に両親を海の事故で亡くしていた。そしてその後何度も海に「呼ばれた」という。
「もうホントそれはね、呼ばれたとしか言いようがない。気づくとフラフラと海に入って行ってしまうの。誰かが海の底で私のことを呼んでいるのよ。ホントよ。みんな私のこと気が触れたと思って同情した目で見てたわ。あ、私以前は目が見えたの」
中空を見つめながら静かな口調でそう話す真魚。
「でもそのたびにね、こちらに引き戻された。幼なじみの男の子がいたのよ。その子が私をこちらにいつも引き戻してくれて......。落ち込んでいる私に歌を勧めてくれたのも実は彼だったの。そうこうしているうちに元々弱視だった私の目は徐々に見えなくなりつつあったんだけれども、その後、事故で完全に見えなくなったわ」
「事故って?」
「その時は、いつになく高い波だったんだけど、また海に呼ばれたの。なんだろうね。人魚伝説の人魚の末裔だからか、亡くなった両親が海から呼んでいるのか。とにかくふとした時に海に引き寄せられてしまうの。それで、その時もいつものように彼は助けに来てくれた。そして......」
今さらっと変なこと言わなかったか? と僕は思わないでもなかったが、つい流して聞き入ってしまった。
「波は私ではなく彼をさらっていったのよ。いつだって波はそう、私ではなく私以外の者をさらっていく......私を連れて行けば良かったのに!」
そう言った後しばらく真魚は肩を上下させて嗚咽した。 僕はどうしていいか分からず、彼女の背中を優しくさするのが精一杯だった。
やっと落ち着いてきた真魚は静かな口調で続けた。
「ごめんなさい。その時は私も必死に彼を助けようとしたんだけど、波の力が強くて私にはどうすることもできなかった。私は気づいたら病院で、もう目は見えなくなっていたの」
彼女は絶望した。
光のない世界で天涯孤独の身となってしまったのだ。それから彼女は遺族年金と障害者年金によって細々と生活している。
「これで私の話はおしまい。聞いてくれて有り難う」
「いや......なんと言っていいのか、聞くことしかできなくて。真魚さんはその...... 強いんですね。僕も真魚さんの話を聞けて、歌声も聴けて、ありきたりな感想だけど ......すごく良かったです」
そう答えながら僕の気分はざわざわしていた。
なんだ?
何かが引っかかっていた。
「呼ばれた」ってなんだ? 人魚の末裔ってなんの話だ? 海は何故彼女を呼ぶのか......。
まともな話じゃないのは分かっていた。そもそも僕はなんでこんな所まで一人でのこのこやってきたのか? 彼女の話を聞くため? 彼女の歌声を聴くため? 削除された動画は何故削除されたのか?
僕もそろそろ帰らなくちゃいけなかった。お盆休みは明日で終わるのだ。考え込んでいる僕の背後から真魚の声がした。
「あなたが来てくれて本当に良かった。今日は海が騒ぐの......」
振り返って見た真魚の目は、僕をまっすぐ見ていた。

完
(初出「季刊マガジン『水銀灯』vol.2」所収)
ありがとうございますサポートくださると喜んで次の作品を頑張ります!多分。
