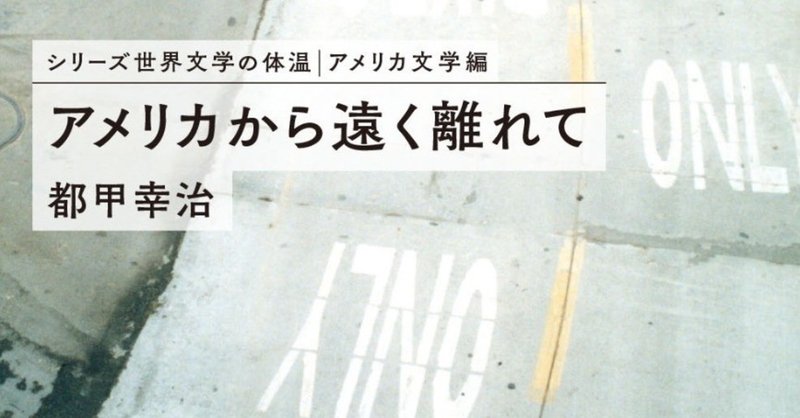
第2回 サリンジャーの臙脂色の表紙(都甲幸治)
高校に入った僕は、日本現代文学と出会った。それまでも日本文学は読んでいた。小学校五年生ぐらいのころかな。中学受験のために買った国語の参考書に、読んでおくべき日本近代文学リスト百冊、みたいなのがついていて、それを参考にしながら夏目漱石、森鷗外、志賀直哉なんてビッグネームの作品を少しずつ読み進めていた。
五百円単位で貯めたお金を握り締めて書店に行き、文庫本を買いそろえる。古臭い文章の中にも、共感できる部分はある。そうして作品はだいぶ読んでいた。すっかり影響を受けてしまって、小学校六年のとき、担任に言われて付けた日記の文章は漱石のパロディになっていたぐらいだ。
その他にも、中学時代から古典文学は読んでいた。江戸時代に書かれた杉田玄白の『蘭学事始』を、書店のカバーも付けない岩波文庫で読みながら電車の車内で立っていたら、急に目の前のおじさんに席を譲られたのを憶えている。僕としては、自分の興味で読んでいただけだったのだが、身長百五十センチもないような子供がやたらと古い本を読んでいるのは異様な光景だったのではないか。
高校でも古典はけっこう好きで、鴨長明『方丈記』や吉田兼好『徒然草』、紀貫之『土佐日記』、そして『伊勢物語』など、これも文庫本で読んだ。出家や恋に破れた古代人の気持ちなど、読んでいるととても心に染みてくる。というとやたらと渋好みの高校生、という感じだが、それだけではない。
きっかけは、筑摩書房から出た『高校生のための文章読本』だった。一九八六年刊だから、ちょうど出版されたばかりのものが、高校の副読本として採用されたのだ。これは画期的な本だった。高校の国語の先生が、様々な現代文学を集めてアンソロジーにしている。その選び方の見事なこと。
高橋源一郎『さようなら、ギャングたち』は擬音やルビを多用した、いわゆるポストモダン文学だったし、イサク・ディーネセンの『アフリカの日々』は、ケニアの高原で見るトカゲについての印象的な文章だった。今の日本にはこんな書き手がいるのか。そして、世界にはもっともっと瑞々しい文章があるのか。ページをめくりながら僕の心は震えた。
この本がいかに凄かったかは、いまだにちくま文庫版で買えることからもよくわかる。この本をきっかけに、『高校生のための批評入門』など、一連のシリーズが展開していったのも有名な話だ。
あまりの衝撃に、僕は書店をさまよい、『文章読本』の中の、心が動いた書き手の本を一冊ずつ買っていった。高橋源一郎だけではない。村上龍、村上春樹、山田詠美など、そのころ活動を始めたごく新しい、若い作家たちの作品をこうしていくつも読んだ。
彼らの作品には共通した特徴がある。まず、日本近代文学に比べて文章が軽い。当たり前だが、現代の、しかも主に都市の生活を描いている。読む上での難易度が低く、高校生の自分が苦労しなくてもどんどん入ってくる。要するにすごく新しい感じがした。
この高校時代の感覚は、けっこう正確なものだったと言える。七〇年代までの日本の作家たちと、それ以降とは断絶がある。それまではフランス、イギリス、ドイツ、ロシアといったヨーロッパの文学を読み、マルクス主義を代表とする思想とも取り組みながら作家たちは作品を書いていた。
だが八〇年代以降の書き手たちは、ヨーロッパ文学よりもむしろアメリカ文学を読み、あるいはアメリカの映画やテレビを観て作品を書くようになった。言うなれば、それまで大江健三郎がフランス文学への入口となっていたように、高橋源一郎や村上春樹はアメリカ文学への入口となっていたのだ。
こんな新しい文学の背後にある、現代アメリカ文学ってどういうものなんだろう。無知な僕の前にあった壁を破ってくれたのは、『百万人の英語』という英語教育雑誌に掲載されていた、作詞家の売野雅勇のインタビューだった。
そのなかで彼は言う。アメリカ文学だったら、とにかくサリンジャーが一番だね。自分は高校生のとき彼女に紹介されて英語で読んで、ずいぶんハマったもんだよ。当時、膨大な量のヒット曲を作詞して時の人だった売野さんが言うんだから間違いないんじゃないか。僕はうつのみやの洋書売り場に走った。
金沢の中心街にあるうつのみやの洋書売り場は、たいして大きくはなかった。それでも探してみると、臙脂色の表紙に黄色い字でそっけなく、J. D. Salinger Catcher in the Ryeと書いてあるペーパーバックを発見できた。
実はそのとき僕はちょっとがっかりした。本当はペンギン版の、クリーム色が美しく紙の質もいいバージョンを探していたのだ。でもアメリカ版はいかにも再生紙、という感じの安っぽい、色も暗めの紙を使っていて、表紙も粗雑だった。でもまあいいか。僕はお小遣いで買い求めて、どうにか読み始めた。
冒頭からいきなり驚いた。今まで読んでいたどんな英文とも違っていたのだ。それまでは教科書か、教科書に準じる名作の教材版ばかりで、わりと端正な英語で、巻末には語彙の説明があったりした。でも『キャッチャー』は違う。
高校生のホールデン・コールフィールドが自分の言葉で、直接読者に話しかけてくる。誇張の多い文章で、ちょっと気取ってみたり笑わせてみたりしながら語るのは、高校の先生の偽善や、友達との行き違い、高校を追い出された悲しみ、そして妹への想いなど、自分に身近なものばかりだった。
こういう文学があるのか。その感覚は本当に圧倒的だった。僕はそれまで、小説はどこかの偉い人が、たくさんの知識と見事な文章を駆使しながら、人間の奥に秘められた心情を巧みに綴る、みたいなものだと思いこんでいた。けれども『キャッチャー』は違う。そこらへんによくいる高校生が貧しい語彙で、でも自分にとっての切実な話を延々と語る。
苦労しながら最後まで読んで、僕は完全にノックアウトされてしまった。数字を大げさに言い立てる、というレトリックがかっこよくて、日常でもしばらく真似していた。もっとも、僕以外誰も『キャッチャー』なんて読んでいないから、ただ変な顔をされただけだけど。
思えばこのときに、僕にとってのアメリカ文学が定まったのかもしれない。外国語で書かれている。でも日本文学よりも、今の自分にとってはもっと身近で、言葉も体験も感情も、内側から全部わかる。まあ、言ってみれば、地球の裏側に突然、親友ができたようなものだ。
今僕が翻訳しているチャールズ・ブコウスキーもジュノ・ディアスも、ちょっと傾向は違うがドン・デリーロも、すべて僕にとっては、自分の感覚を解き放つことのできる大事な友人のようなものだ。彼らの文章を読んでいると、細かな身体感覚まで含めて、体の内側からしっかりと伝わってくる気がする。
こう考えてくると、今の僕を作っているものの原点にサリンジャーがいることがよくわかる。言ってみれば、彼との出会いの衝撃を繰り返そうとして、いまだに翻訳や研究を続けていると言っていい。
最後まで英語で読み終えたあと、日本語版ではどうなっているんだろうと思って、白水Uブックス版の『ライ麦畑でつかまえて』も読んでみた。野崎孝の訳文に感じたのは、微妙な、でも執拗に続く違和感である。もちろん野崎孝の訳は素晴らしい。だけど、言葉の感覚や間合い、場面の空気感が常に、僕が英語版を読んでいるときに感じたのと少しずつ違う。どうしてこうなるんだろう。翻訳ってなんなんだろう。
それまで僕は翻訳のことを、原作のまま日本語に移したものだと思いこんでいた。だからこそ、このズレの感覚は微妙でも重要だった。ひょっとしたら、原作と訳はまったく別の本なのかもしれない。
翻訳者になった今思えば、それは当然のことである。翻訳家は原作を読み、自分なりにイメージ化して、自分の能力いっぱいの日本語を使いながら作品を書き直す。もちろん意味はそのまま移しても、細かなニュアンスや音、リズムは移しきれない。だからこそ、そこに翻訳家独自のものが訳文に忍び込んでくる。そして自分をどんなに透明な存在として消し去ろうとしても、翻訳家の身体的感覚の痕跡は訳文に残る。
それは決して誤訳ではない。むしろ芸術家としての翻訳家の自由と関わる部分だろう。したがって、同じ作品の訳でも、野崎孝の『ライ麦畑でつかまえて』と村上春樹の『キャッチャー・イン・ザ・ライ』では全く違う。そしてまた、それぞれの人が原文で読んだCatcher in the Ryeとも違う。
僕にとってはこの、英文で読んだ原作の手触りが何より貴重だった。そしてそうした作品を読みながら、こういうものに関わる仕事がしたい、と強く願った。おそらく高校生のときのこうした想いが徐々に人生に作用して、今、アメリカ文学を読んだり訳したりする仕事へと僕を導いたのだろう。
というとその後、アメリカ文学一辺倒になったような感じがするが、そうではない。一九八五年にちくま文庫が創刊されて、初期に出た蓮實重彦『表層批評宣言』を何気なく読んで圧倒された。まったく一行も分からない。それなのに、うねるような文章はセクシーとしか言いようがなかった。だから分からぬまま必死に読んだ。
次いで同じ著者の『反日本語論』も読んでみた。野坂昭如の野坂は「のさか」か「のざか」か。日本語ではどうでもいい差が、フランス人には決定的な差になる話。フランス人の妻が漢字の表を見て、こんなに無秩序な文字の世界があっていいのか、と苦しむ話。ベルギーで息子が “J’ai vu.” 「ジェ・ビュ」(私は見た)という言葉を地元風に「シェ・フュ」と発音するようになる話。
すべてがかっこよくてお洒落で、なおかつ絶妙に難しくて、しかも文章が上手かった。批評ってこんなにかっこいいものなんだ、と深く感心した。そして、大学に行ったらこういう人に習えるんだろうか、と思った。
当時蓮實重彦と並んで目立っていた批評家が柄谷行人だった。人生で初めてお小遣いで買ったハードカバーの本が彼の『批評とポストモダン』(福武書店)だ。これはうつのみやではなく、109の地下のリブロで買った気がする。
こんなに難しい本が読めるのかな。少々ビビリながらカウンターで本を差し出すと、店員さんが「この人の本はどれも表紙が真っ白ですよね」と気さくに話しかけてくれた。でも高校生の僕はもちろん、こなれた答えなどできずに、「は、はい」と言うだけで精一杯だった。
柄谷行人の本も、当時の僕にとっては難しかった。彼が議論の前提としているマルクスもフーコーも何も読んでいなかったのだから、すんなりとわかるわけがない。歯を食いしばって読んでも、せいぜい一時間に五ページか、よくて一〇ページがせいぜいだった。でも何かものすごくためになるものを読んでいる感じがした。そしてこうした本を読んでいる自分に酔った。
蓮實重彦も柄谷行人も、大学に入っても読み続けた。僕が今でも批評が好きなのは、彼らのおかげだと思う。その後、大学では蓮實先生の授業を取り、今、朝日新聞の書評委員会では月一回、柄谷さんに会っている。というと、夢が叶った感じがするが、うーん、それもちょっと違うんだな。
地方の高校生だった僕が本で読んでいるときの彼らは、何というか、東京で光り輝く生きた神様というか、この世のものとも思われない存在だった。だけど実際に蓮實先生に習うようになると、夏休みは不思議なベルボトムのジーンズを履いてくるし、昼休みは生協食堂のハンバーガーの列に並んでいるしで、けっこう気さくで普通のおじさんだった。
柄谷さんだって、「僕は関西出身だからやっぱりウケたいよー」なんて言っているし、駄洒落もけっこう言うし、当然ながら妄想の柄谷行人とはまったく違うタイプの人だ。
というと二人をナメている感じになってしまうかもしれないが、それも違う。やっぱり本当に能力が高い、日本でもトップクラスのすごい人だと言うのは変わらない。でも僕が高校生のときに思い描いた神様のような彼らこそが、僕を鍛えてくれたんだと思う。
あんなふうになるのは難しいけど、でも自分なりに精一杯成長したい。彼らの著作が僕にそう思わせてくれたのは確かで、だからこそ高校時代の僕は、何としても東京の大学に行かなくてはならない、と決めつけてしまったのだった。
プロフィール

都甲幸治(とこう・こうじ)
1969年、福岡県に生まれる。現在、早稲田大学文学学術院教授、翻訳家。専攻はアメリカ文学・文化。主な著書に、『偽アメリカ文学の誕生』(水声社、2009年)、『21世紀の世界文学30冊を読む』(新潮社、2012年)、『狂喜の読み屋』(共和国、2014年)、『読んで、訳して、語り合う。――都甲幸治対談集』(立東舎、2015年)など、主な訳書に、ジュノ・ディアス『オスカー・ワオの短く凄まじい人生』(共訳、新潮社、2011年)、同『こうしてお前は彼女にフラれる』(共訳、新潮社、2013年)、ドン・デリーロ『天使エスメラルダ』(共訳、新潮社、2013年)、同『ポイント・オメガ』(水声社、2018年)などがある。
「アメリカから遠く離れて」過去の記事
第1回 聖書と論語
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
