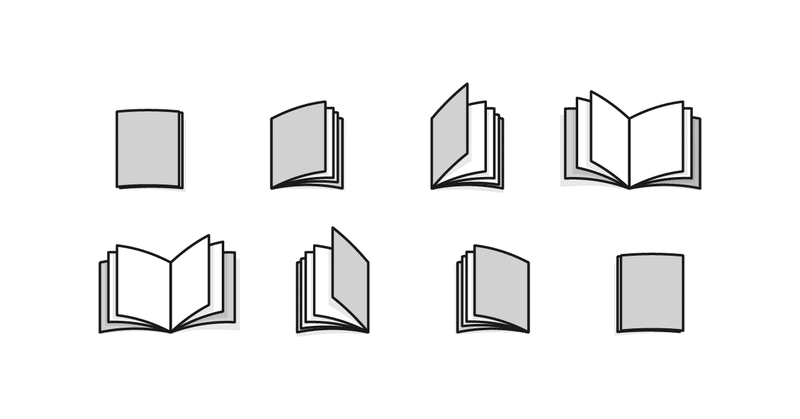
村上春樹「貧乏な叔母さんの話」
村上春樹といえば、誰もが知る日本の小説家である。『ノルウェイの森』(1987)、『海辺のカフカ』(2002)は、長年愛される名作となっており、映画化や舞台化もされている。
一方で、SNS上では「#村上春樹っぽいツイート」のようなハッシュタグが存在するように、「独特の言い回しで理解し難い小説を書く人」という揶揄もされているようである。確かに最近テレビドラマ化で話題になるような小説とは違って、どんでん返しの復讐劇的なストーリー展開が魅力的なわけではない。
わたしは自他ともに認めるハルキストである。家の本棚にはほとんどすべての村上春樹の長編小説と短編小説集があり、ハードカバーの新刊が発売されるたびに模範的なオタクよろしく本屋に買いに行く。
しかしそれだけ村上春樹の小説が好きなわたしでも、誰かに村上春樹の小説を勧めるのは難しい。世間話をしていて好きな小説家を聞かれたときに、数人の作家の中に村上春樹を忍びこませ、相手が食いついたらお互いが好きな作品の話をするけれども、多くの場合は「ムラカミハルキとか好きなんだ〜」と言われてわたしも「そうなんだよねえ〜」と濁してしまう。
村上春樹のファンとしてある程度の時間を生きてきたわたしが思うに、それくらいムラカミハルキという名前は世間一般に「名前は知っているし読んだこともあるが、セックスと音楽の話ばかりを婉曲な言い回しで永遠にしているよくわからん作家」と認識されているようだし、「村上春樹の小説が好きだと言ったら、この人はわたしのことをサブカルクソ女だと思うだろうか」と考えてしまうので、処世術的に村上春樹の話題を避けたりする。あとはシンプルに森見登美彦のウケがいいので森見の話で盛り上がってしまうことも多々ある。
そういえば『ノルウェイの森』と『海辺のカフカ』以外は世間的に認知されているのだろうか。わたしが高校生だったとき、『ノルウェイの森』と『海辺のカフカ』くらいは読んだ気がするが特に拒否反応も無ければハマることもなく、そんなことより伊坂幸太郎と東野圭吾と有川浩と恩田陸と海堂尊と乙一と湊かなえと森博嗣のエンタメ作品のほうがわたしにとっては魅力的だった(意外と作家名を覚えているものである、なつかしい)。
わたしは高校まで学校のお勉強以外してこなかったのに、大学に入学したとたんに映画や文学や音楽や美術やさまざまなものを目の当たりにして急激に人生の方向転換をすることになった。フランス文学の研究者の教授のゼミに入ったのでひな鳥の刷り込みに近いかたちで村上春樹を当たり前に好きになったし、方向転換が急すぎて反動としてそれまで崇拝していた伊坂幸太郎のこともいままでの読書経験のことも忘れてしまった。
「オーガニックなハルキスト」ではないのによくもまあここまで偉そうに書いていたものだが、逆にその方向転換さえあれば、それまでの読書経験をふいにできる程度には村上春樹との出会いが衝撃的だったのだ。
たしかに万人受けするような題材でも文体でもない。物語は平坦でやや暗く、 あっけなく人はいつの間にか死んでいるし、ドラマチックで胸がときめくような出会いも別れも無い。 登場人物は回りくどい言い回しで身のない話をし続ける。猫語を理解できる障害者みたいなへんてこな人物は出てくるし、登場人物の男は出会い頭の女とすぐにセックスをする。わたしに子供ができて、思春期の自分の子供に村上春樹を読めと言うかと言われたら、確かに強制はできないと思う。村上春樹よりわかりやすくて楽しくてエンタメ性のすば抜けた作品はこの世にごまんとある。
それでもわたしは『海辺のカフカ』が好きだし、『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』も好きだ。短編小説なら「かえるくん、東京を救う」は傑作に違いない。それでもここで取り上げる作品をひとつに絞れと言われたら、大学の授業で課題図書として指定された短編集『中国行きのスロウ・ボート』に収録された「貧乏な叔母さんの話」を挙げるだろう。
授業で先生がどういう解説をしてくれたのかはもう正直覚えていない。家にある文庫本に書き込まれているメモを見るにどうやらソシュールの話をしていたようだが、ここでわたしが半端な記憶力でもって説明することもできないしする必要も無い。初めてこの短編を読んでから5年か6年が経ってそれでも私の中に残っているのは、この作品には村上春樹の自分の作品に対する姿勢そのものが描かれているからである。
貧乏な叔母さんとは何か。主人公の背中にある日貼り付いた「貧乏な叔母さん」は、その人の母親だったり、食道がんで死んだ犬だったり、ずっと昔の小学校の女教師だったりと見る人によって姿を変える。
その人が思うに役に立たない、かわいそうで、しかし誰に迷惑をかけるわけでもなく、あたりまえに身近に存在する……
もしわたしが「貧乏な叔母さん」を見たとき、その姿は村上春樹に見えるかもしれない。ノーベル文学賞受賞を毎回勝手に日本人から期待され「また日本人受賞ならず」などと報道され、自分の作品を好きな人のことは一般的な小説を読むのが好きな人とは別の「クレイジーな信者」として「ハルキスト」とかいう造語でもって表現されてしまう。ジャンル「村上春樹」がすでに確立され、これから村上春樹の小説に出会う人たちのなかで何人が純粋に作品に偏見なく向き合えるだろうか。作中に「貧乏な叔母さん」について以下の記述がある。
---------
そう、完璧さがまるで氷河に閉じこめられた死体のように、叔母さんの存在の核の上に腰を下ろしている。ステンレス・スティールみたいな立派な氷河だ。おそらく一万年の太陽にしかその氷河を溶かすことはできないだろう。しかしもちろん貧乏な叔母さんが一万年も生きるわけはないから、彼女はその完璧さとともに生き、その完璧さとともに死に、その完璧さとともに葬られることになる。(村上春樹『中国行きのスロウ・ボート』p.80.中公文庫)
----------
わたしが貧乏な叔母さんを見たとき、その姿が村上春樹に見えたとして、彼が文句を言うことは無いと思う。作品の最後で主人公は「一万年後に貧乏な叔母さんの桂冠詩人になるのは悪くない」と言う。「一万年後には貧乏な叔母さんの街が形成されているだろうが、それまでにいくつもの冬を乗り越えなければならない」
村上春樹の作品はその普遍の完璧さで、エンタメ小説やビジネス新書や「これを読めば健康になれる」など有用さを謳う書籍が本屋の入り口に平積みされる現代においても、ほとんどの本屋の文庫本コーナーの「む」行に並べられている。彼が「貧乏な叔母さん」でなくなるのは一万年後かもしれないが、本人が「自分はこれからもその完璧さを保ち続けて構わないのだ」と「貧乏な叔母さんの話」を1980年に書いたのだとすると、もうわたしがガヤで騒ぎ立てるのも違うように思える。
最新作『一人称単数』(2020)は、6年ぶりの短編小説集である。「ぼく/俺/その他一人称」=登場人物の視点で語られる、読んでいると「わたし」がどこにいるのかわからなくなる素晴らしい研究結果の発表のような作品群だった。
わたしは村上春樹になれるとも思っていないしなろうとも思っていないので、村上春樹の作品を読んで「なるほど参考になるなあ、こう生きよう」などと思っているわけではない。一万年後に氷河が溶けるのを待たなくても、わたしが好きな『海辺のカフカ』や『世界の終わりとハードボイルドワンダーランド』が素晴らしいことには変わりない。琥珀の中に閉じ込められて姿を変えず現代まで残っている葉っぱや昆虫は美しい。村上春樹が死ぬまでその完璧さを失わずにいられることを、いちファンとして祈っている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
