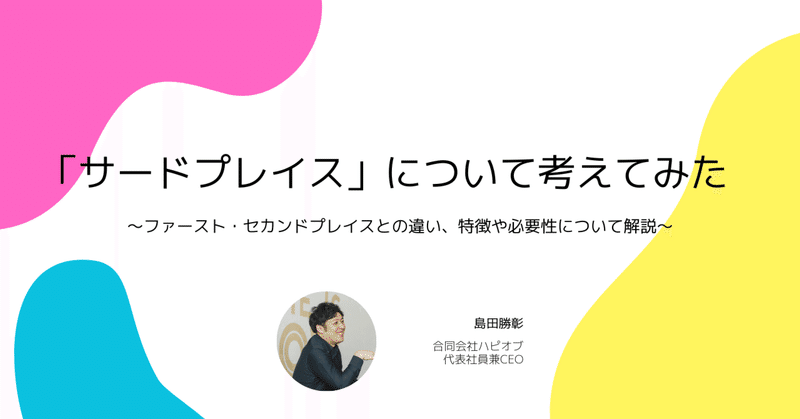
「サードプレイス」について考えてみた〜ファースト・セカンドプレイスとの違い、特徴や必要性について解説〜
皆さん、こんにちは。
カフェ・公園など、自宅や職場とは隔離された「新たな居場所(サードプレイス)」を求めている人が増えている。ブイキューブさんの調査によれば、コロナ流行後、約6割の人が「必要性が高まった」と回答しています。
カフェや公園以外にも、コワーキングスペースがサードプレイスとして認知されるようになってきました。最近では地方でも様々なスタイルのコワーキングスペースがオープンしています。(ちなみに私のオフィスも、金曜日だけコワーキングスペースになります)
今回の記事は、人生の幅を広げる・ストレスを和らげて心地よく生きるために必要と言われている「サードプレイス」についてまとめてみました。個人的な見解も含めつつ、テクノロジーの変化で多様化している部分についてもできる限り触れていきます。
「サードプレイス」とは
サードプレイス(第三の場所)とは、自宅、学校、職場とは別に存在する、居心地のいい居場所のこと。
この言葉は、アメリカの都市社会学者レイ・オルデンバーグがその著書の中で定義されたと言われています。当時は都市社会を主として「自宅・学校・職場からの役割を解放され、いち個人的にくつろげる場」の必要性を訴えました。
この定義からも分かる通り、サードプレイスはハード(物理的)な部分だけではなくソフト(精神的)な部分も含んだ言葉です。「居場所」というイメージが強いためハードな意識に偏りがちですが、本来はハードとソフトの両面が揃って「サードプレイス」です。特に、役割の解放についてはとても重要な視点だと個人的には考えています。
なぜ「サード」なのか
言葉の認知は広がっていますが、「サード」の意味まで認知されている人はそれほど多くないかもしれません。下記の資料のように、ファーストプレイス(家庭環境)、セカンドプレイス(職場環境)の次に位置付けられるのがサードプレイス(居心地よい場所)です。

レイ・オルデンバーグ(2013)みすず書房 より引用
これは私の個人的な見解になりますが、サードプレイスは確かに「居心地のよい場所」と定義されていますが、決してファーストプレイスとセカンドプレイスが居心地が悪いことを前提にしているわけではないと考えています。
近年はサードプレイスの重要性が高まるあまり、ファーストプレイスとセカンドプライスに対しての議論が少ないように感じますが、人生を多くの時間は自宅や職場で過ごします。私たちの会社は主に、セカンドプレイス(教育環境や職場環境)に対するアプローチが多いですが、自宅や学校・職場の充実についても大切であることがここでちゃんと伝えておきたいと思います。
「サードプレイス」の特徴
言葉の定義だけ見れば「居心地の良さ」がサードプレイスということになりますが、下記の資料のとおり、居心地の良さを実現するためのいくつかの視点についても著書の中では定義されています。

最近は特に「目立たない存在」という視点が薄れているように感じます。サードプレイスそのものの需要が高まるあまり、人気スポットとしての認知ができてしまったり、歴史や趣きについても軽視されがちです。
全てを満たしたサードプレイスは存在しないかもしれませんが、サードプレイスを提供する立場はこのような視点がなければいけません。つまり、ハードな側面だけでなく、ソフトな側面も満たすためには「誰がいるのか、誰が運営しているのか」という視点も重要となります。
中立性やニュートラルという視点も、サードプレイスの大きな特徴です。カフェや公園などは公共性も高く中立性を担保しやすいため、サードプレイスとしての認知がかなり広がっていると推測できます。
「サードプレイス」の必要性①
前述したとおり、コロナによってサードプレスの意義や重要性は一気に高まったと思いますが、その理由は何なのでしょうか?多くのメディアで語られているのは「リフレッシュ」の視点です。
これまでは自宅がリフレッシュの場所も兼任していたケースが多かったと思いますが、コロナによってリモートワークが急速に広まり、自宅におけるリフレッシュの立ち位置は薄れてしまいました。
また、これまで気軽にいけたカフェなどもコロナによって行きづらくなり、さらにリフレッシュできる環境が狭まりました。こうした強制的な居場所の制限が人々から「居心地」を奪っていったことも、コロナの大罪のひとつだと私は考えています。
コロナ流行がピークアウトし、日本でも5類への移行が決まりました。このような背景から今、サードプレイスはまさに「リフレッシュの場所」としての必要性のピークにあると感じます。
「サードプレイス」の必要性②
「多様な人々の交流・つながり」という視点も、サードプレイスの重要性を語る上では欠かせません。リカレントやリスキリングなど時代の変化に人々も対応するために、一人ひとりが職場環境以外のコミュニティに所属して新たな情報を得る必要性が高まっています。
「chatGPT」に代表されるように、テクノロジーの進化によって既存の仕事が消滅していくケースはますます増えていくでしょう。その中で、意図的に新たな交流を作ることは必要不可欠であり、サードプレイスはその点においても相性バツグンです。
ちなみに私は「計画的偶発性理論」にとても共感する部分が多く、サードプレイスはまさにうってつけです。(これが私のオフィスを金曜日だけコワーキングスペースにしている理由でもあります)
人生を豊かに生きる
たった一度の人生です。あくまで私の個人的な見解ですが、ストレスフルに生きるのはもったいないし、歳を重ねるごとに学びや人々とのつながりが広がり深まることは人生を豊かに生きる上で必要だと考えています。
最近のサードプレイスはハードの環境も変わりつつあります。メタバースなどの登場で、ネット上のサードプレイスにもリアリティが組み込まれつつあります。これからもサードプレイスの在り方はどんどん進化していくでしょう。
私にとってサードプレイスは、自分の役割がフラットになりいち個人として心地よく過ごせる場所であり、ファーストプレイスやセカンドプレイスの大切さも再確認できる場所です。いろんな角度から、人生においてプラスになる場所だと思っています。
多目的交流拠点「HUB」
私が代表を務めるハピオブのオフィスは、多目的交流拠点「HUB」という名前が付いており、レンタルスペースとしての機能や金曜日はコワーキングスペースとして利用することが可能です。
富山県富山市を拠点にしており、場所はまちなかの「総曲輪(そうがわ)通り沿い」なので、アクセスは充実しています。東京などの都市圏から富山にお越しいただく方や市外から中心部いらっしゃる方の「交流拠点」として役割も担っています。
私もこの場所では「カッツ」と呼ばれており、会社の代表という役割から解放され、自分らしくいられる場所(時間)という認識でいます。人との関わりは様々なシーンでありますが、状況に応じて仕事仲間であったり友人であったりする関係性は、私が目指す理想のひとつでもあります。
私たちもサードプレイスを運営する立場として、その意味や意義をさらに理解しつつ、自分達の人生もさらに豊かにしていければと思います。もし興味があれば、ぜひ金曜日に気軽にお越しください。
島田に会いたい!という方も大歓迎ですが、私がオフィスにいる時間が結構限られていますので、島田に御用のある方は事前にTwiiterにメッセージなどいただけると幸いです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
