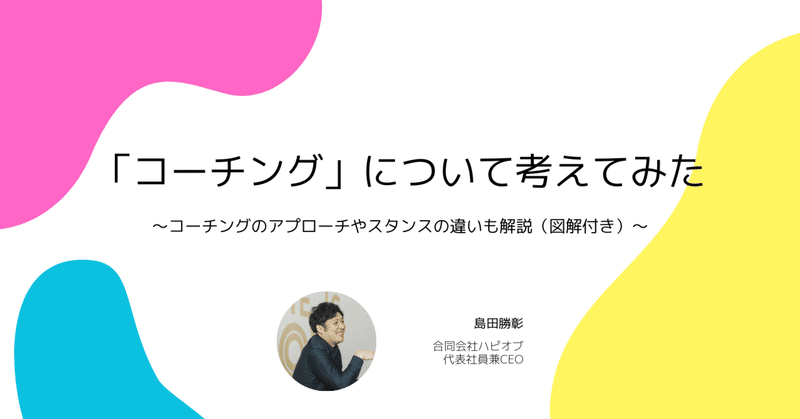
「コーチング」について考えてみた〜コーチングのアプローチやスタンスの違いも解説(図解付き)〜
皆さん、こんにちは。
私が「コーチング」を知ったのは、社会人になってスグでした。知り合いに紹介されて、右も左もわからぬままコーチングを体験しました。効果を全く感じられず、怪しいイメージだけが残りました。
そんな私も、数年前にコーチングスクールに通い、今ではコーチ(主に経営者やリーダー層向け)として働く一面があったり、スクール修了生として新たなにコーチングに興味を持った方々にお話する機会があったりします。
私なりの「コーチングとは」をまとめてみました。一部、資料や図解などで説明しています。ちなみに、本記事はコーチングのスキルについてまとめた記事ではありませんので、あらかじめご了承ください。
「コーチング」とは
コーチングとは、「答えを創り出す」ための技術(スキル)
この言葉の定義は、専門家やコーチングを提供する組織や団体によって異なります。私なりに共通項を抜粋して、上記のように定義してみました。実はコーチングを学ぶ際に、定義についてかなり調べました。
特に、コーチングの基幹である「コーチ」という言葉が、馬車(人を目的地まで連れていく手段)に由来しているという点は、コーチングを扱うすべての人が理解しておくべき「共通の起点」だと思っています。
「コーチ」と「コーチング」の違い

この違いは、「人か技術か」で区別すると分かりやすいと思ってます。この理解ができたことで、私が社会人になってスグに体験したのは「コーチング体験」ではなく、「ビジネス・コーチと話す体験」だったと整理することができました。
現代において「コーチ」を名乗る方々は、様々な領域に存在しています。最もイメージしやすいのはスポーツの業界かと思いますが、日本ではビジネスのシーンでも広がっています。ただ、資料にも書いた通り、すべてのコーチがコーチング(技術)を使用するまたは理解しているとは限りません。ここがちょっと難しいところですね。
「コーチング(技術)」の観点から考えてみると、こちらもコーチを名乗っていない方々が使用しているケースは急速に広がっています。士業の方々をはじめ、最近では、教師などの教育の業界や、カウンセリングなどの医療の業界でも注目されているようです。
「コーチング」のアプローチ

これはあくまで私の個人的な見解なのですが、コーチングには大きく2つのアプローチが存在していて、技術を使う人それぞれの「スタンス」に大きく影響していると考えています。それを示したのが上記です。
前述した通り、コーチングを「答えを創り出すためのスキル(技術)」と定義した場合、答えの位置付けを、①自分の内側に眠っている想い(願い)にする場合と、②すでに可視化されている目的(目標)にする場合に分けることができます。
コーチングを提供する人にも得意と不得意の領域があると思っていて、その違いがこの「スタンス」であると私は考えています。ちなみに、クライアント(コーチングを受けたいと思っている人)にも、この位置付けは適用可能です。どちらか一方ではなく、自分なりの割合があると考えると分かりやすいかもしれません。
「価値観型」と「ビジョン型」
少し話は逸れるかもしれませんが、「原点主義と目的主義」を「価値観型とビジョン型」という表現で置き換えている面白い考えがあるので、せっかくなので紹介させてください。ここでは詳細は割愛しますが、私もこの考えを知ってから自分のスタンスを明確にするきっかけをもらいました。
ちなみに私は、「価値観型」にかなり寄っている人間です。原点主義の傾向が強く、意義や背景を理解できた方が行動できるタイプです。自分を理解できると悩みに対する解決方法も整理できる。コーチングというスキルは自分自身にも活かせるスキルです。(これを「セルフ・コーチング」と言う)
「コーチング」のメリット
コーチングというスキルを通して得られる最大のメリットは「行動変容」であると私は考えています。行動変容とは、読んで字の如く「行動そのものが変わる」ということです。コーチングを受けることで、自分が求めていた答えに近付くことができ、それによって行動における量や質が変化します。
これについては、コーチングを提供している「提供者」としてもクライアントの変化から感じ取ることができますし、実際にコーチングを学んだ自分自身が、その学びの過程で行動(生き方)が大きく変容したことで実感している部分もあります。
私がコーチングを学ぼうと思ったのは、社内のメンバーに対する面談のアプローチのひとつとして検討したことがきっかけですが、想像以上にメリットがあったと今は感じています。人への向き合い方、自分への向き合い方も変化しました。
「コーチング」に触れたい人へ
きっとこの記事を読んでくださっている方は、すでにコーチングについて興味がある方が多いと思います。そんな方に、私がどうしても伝えておきたいことがあります。

どうしても「まずはコーチングを体験してみて」と言いたくなるところではあるのですが、まずは自分と向き合うことをお勧めします。
冒頭でも述べましたが、コーチングの言葉の由来は「馬車(人を目的地まで連れていく手段)」です。自分がどこへ行きたいかを伝えなければ、馬車は出発することができません。(少し専門的な話になってしまいますが、「どこでもいいから連れて行ってください」はカウンセリングの部類です)
自分がどんなスタンスで、どんな課題を持っているのか。それを自分なりでいいので一度考えてみましょう。そして、その仮説をコーチングを提供している人へ投げてみてください。その先に、コーチングを「体感」が待っています。
私はコーチングを「コーチングスクール」の中で体感しました。私が通ったコーチングスクールは受講期間中にペアコーチという課題があって、同期生がお互いにコーチングをしあう時間が設けられています。半強制的ではありましたが、あの経験があったからこそ「納得感」があります。
人生に「納得」する
私の座右の名は「選択を正解にする」ですが、この想いの裏には、自分なりの正解を信じることが「納得できる人生」に必要ではないか?という仮説があります。コーチングというスキルは、その仮説を立証に近づけるために必要な手段でもあります。
先日、主体性に関する記事も書かせてもらいましたが、その中でも自分自身と向き合う重要性について説かせてもらったつもりです。これからも、個人としても、組織としても、その意義を発信し続けていきたいと思います。
3/22 20:00〜
最後にお知らせです。私がコーチングを教わった「ZaPASSコーチ養成講座」が13期生を募集しています。ちなみに私は3期生です。今月はオンラインにて修了生による座談会が開かれていまして、私も登壇する予定です。
当日はスクールで学んだことを中心にお話をさせていただきますが、本記事のことにも少しだけ触れたいなと思っているので、もしも興味がある人がいらっしゃれば、オンラインでお会いしましょう。
尚、日頃の活動や感じたことは「Twitter」で呟いていますので、よかったら見ていただけると嬉しいです。フォローも大歓迎です!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
