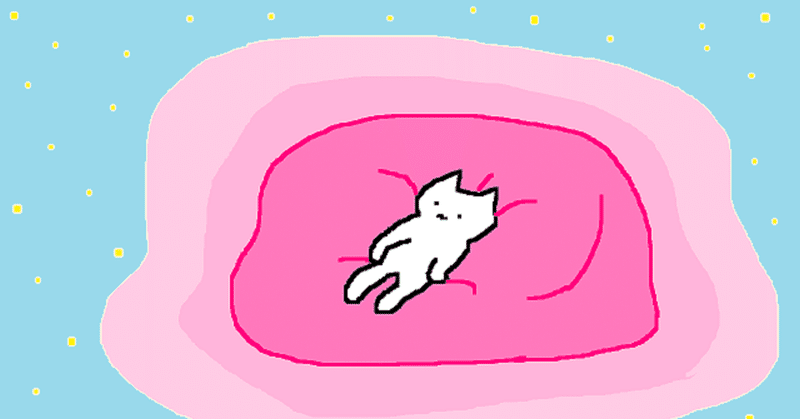
言語思考と視覚思考の媒体選択、アニメと漫画と小説
人類には、
視覚優位型と言語優位型がいる。
「なんか絵を描いて」と言われればサラサラ描けるけど
「なんか喋って」と言われても言葉に詰まる。
そんな人は視覚優位型だろう。
あるいは、
「なんか絵を描いて」と言わても困るが、
「なんか喋って」と言われればスラスラ喋れる。
そんな人は言語優位型だろう。
なぜこのような話をするかと言えば、普段聞いているポッドキャストでそんなテーマがあったからだ。
「ビジュアル・シンカーの脳」という本を題材に話しているのだが、本の著者であるテンプル・グランディン氏は、人々が思考する時に言語的に思考する人と視覚的に思考する人がいると主張している。もっというと、視覚的に思考する人の中にも図形描写として考える人と絵画描写として考える人に別れるようだがよく分からないので割愛する。
また、思考に限らず記憶に関しても同様の現象がみられる。
文章を記憶しやすい人と、映像を記憶しやすい人がいるのだ。ただし記憶に関しては更に体感や聴覚なども関わってくるので二分することは出来ない。
どうでもいい話だが私は映像の方が覚えやすい。都道府県は地図をガン見して覚えたものだ。
さて、話はそれたがタイトルに戻る。
アニメと漫画と小説についてだ。
あらゆる創作物において、実写を抜いて現代はこの3つが主な媒体となっている。特に今はアニメがかなり強い。アニメといえば、一昔前は子供が見るもので大人になっても見るのは一部のマニアックな人種だけだった。しかし今や、別にマニアじゃない普通の大人が気軽にアニメを見る時代なのだ。
これは、サブスクリプションの台頭により好きな時間に好きなアニメを見られるようになったことが大きいと考えられる。また、小説や漫画と違い圧倒的低コストで人気作品に触れられるのも一因だろう。
しかしここで制作側は考えなくてはならないことがある。
あらゆる創作物に置いて、
自分の作った物語をどの媒体で表現すべきか?
ということである。
今は
ラノベがコミック化し、
コミックがアニメ化、
あるいはその逆・・・
人気であれば実写であれ映像であれ文字であれ、自由に媒体の垣根を越えることが出来る。しかしその反面、それぞれの「善し悪し」を十分に理解しきれていないように思われる。
なぜなら、これらは作者の脳内をより精巧に現実世界に出力する為の手段だからだ。まさに、アニメ、漫画、小説は、視覚思考あるいは言語思考の産物なのである。
「言葉が分からん」人に小説を書かせるのも
「絵が分からん」人にアニメを作らせるのも
到底おかしな話なのは分かるだろう。
しかし、ここで一つ問題が出てくる。
絵でイメージしたものを言語で表現する、
あるいは
言語でイメージしたものを絵で表現する、
という翻訳作業を失敗している作品が多くある、という問題だ。
これは漫画のアニメ化など媒体を変えた時だけではない。作者が制作している段階ですでに失敗している作品も多いのだ。
もちろん、成功している作品も多くある。
鬼滅の刃や葬送のフリーレンなど近年のアニメ作品の多くが映像化に成功している。制作側がアニメ作品の本質を理解し、作品を咀嚼し、アニメとしてしっかり抽出しているからだ。
対して、あまり良くないのがコミック化である。
これは私の偏見だが、近年の「絵が描ける」という人間のうち一定数は「言語思考だが絵も描ける」という人種だと考えている。
なぜかというと、
日本での識字率がほぼ100%なのと同様に、絵も教育によってある程度は上手くなるからだ。現代はyoutubeなどで無料で絵の描き方を知ることが出来る。それも「言語的に」である。
つまり、
全く描けない状態から「言葉で学んで」描けるようになった人間はもうその時点でだいぶ「言語思考」寄りの人間なのである。
極言語思考の人間が絵に興味を持たないであろうことは分かるが、
やや言語思考の人間であれば、なんとなく絵の道に進んでしまうのもまぁあることだと思うしそれが悪い事だとは思わない。現に視覚優位の私も今このように文章を書いているのだから・・・。
しかし、言語思考の人間が描いた漫画というのはどうなるかというと、思考から出力までに言語情報を視覚情報にするという無駄な翻訳が間に入ってしまう。セリフはともかく絵に関して言えば、絵でイメージしたものをそのまま絵で出力している人間よりもパフォーマンスが大きく下がってしまうのも仕方がないだろう。
そしてこれは逆もしかり。
視覚思考者とて、誰でも絵が描けるわけではない。
そんな視覚思考者が物語を考えた時に真っ先に思い浮かべるのは小説である。しかしこれもまた、同じ問題に直面する。
視覚思考者が出力する言語は、どうしても言語思考者よりも薄い内容になってしまうのだ。
例えば、野原一面に咲いた花をイメージした時に
脳裏に、青空の下で色とりどりの花に囲まれた女性の映像が浮かんだのなら漫画やアニメを作るべきであり、
「夏の午後、青い空に広がる花野。そこには赤や青、黄色の花が風に揺れ、微かに甘い香りを漂わせていた。その美しさに圧倒されながら、彼女はそっと息を吐いた。」
とセリフが浮かんできたなら小説を書くべきなのだ。
空白埋めの挿絵みたいな漫画が面白そうには思えないだろうし、
月並みなセリフばかりな小説が面白そうにも思えないだろう。
しかしそれが「月並みである」と判断するにはどちらかの性質を持っていなくては難しい。
極言語思考者や、極視覚思考者にとってはこのような悩みとは無縁だ。なぜなら彼らにとって表現すべき媒体は既に決まり切っているから。しかし、どちらとも言える人間や、やや言語優勢者、やや視覚優勢者にとってこの問題はよく考えるべきことである。
とはいえ、漫画の場合はこの限りではない。というのも漫画には字がふくまれるのでセリフやナレーションが優れていれば絵の方は下手くそでも結構評価されるのである。逆に言うと文章がダメなら絵が良くないと厳しいが。
もちろん、純粋な画力と言うよりは読者を魅了する絵、という意味である。
言語思考なのに絵を頑張って、どっちも中途半端・・・みたいな作品は多い。どっちが得意なのかをハッキリさせて得意な方を伸ばした方が間違いなくいい作品になるだろう。
今回は、言語思考か視覚思考か?という観点でアニメ漫画小説について語ったが、それ以外にもそれらの特徴を比較して言いたいことは多々ある。
最近読んだ「とらすの子」「君が獣になる前に」という2つの作品について。
しかし長くなったのでこれで終わりにする。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
