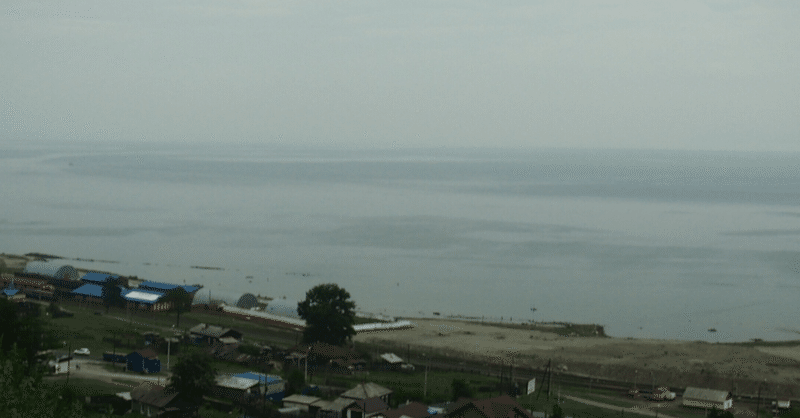
ごまめのごたく:ロシアのもろもろ(3)シベリア民族
おさらい
前々回「シベリアに独立を!」という本を読みながら、シベリア民族についての知識を深めていこうとしていたところでした。
著者「田中克彦」氏は、モンゴル語を専門とする言語学者で、ポーターニンというシベリアの探検家、地理学者、民俗学者の生い立ちと活動を中心に、話を進めています。
ポターニンの生い立ちと背景:復習
ロシアの探検家、地理学者、民俗学者のポターニンは1835年、シベリアの、旧ソ連の核実験場の近くにある、セミパラチンスク(今日はカザフスタン共和国領)の近く、父が所属するコサック軍が駐屯地として常任する村で生まれました。
コサックの軍人を父として生まれた男の児は、当時、かならずコサック軍の軍人にならなければならず、彼は11歳の時に、オムスクの陸軍幼年学校に入り、六年在学して、卒業とともに少尉に当たる位をもって軍務につきました。
コサックとテュルク
もともとコサックは15世紀後半にポーランド・リトアニア連合王国や南ロシアから、農奴制を拒否し、自由を求めて集まってきた集団で、18世紀半ばからはロシア政府の辺境軍備に仕えていました。
コサックを指すロシア語の「カザーク」は、キルギス語、カザフ語、タタール語などで「自由、独立の人」を意味します。そして、コサック軍団の最頭目をアタマンと言います。
コサックに属する人たちには自らの起源がテュルクに近いと考える人たちが多く、その人たちは、コサック独特の制度にかかわる用語をテュルク諸語(タタール、カザフ、キルギス語など)で説明したがる傾向があるそうです。
たとえば、ロシア軍の一等大尉にあたる「エサウール」は、ヤサウル(指揮者)に由来し、このヤサは、モンゴル語の「支配する」にさかのぼります。テュルク語の「ヤサ」は「ジャサ(統治する)」に対応していて、「ジャサック」あるいは「ザサック」は、「支配者」「政府」「権力」などを意味します。
16世紀後半にロシアのシベリア進出が始まり、ロシア軍はシベリアを征服して土着の人たちを支配すると、かれらに「ヤサック」という現物税を課して、高価な毛皮を大量に手に入れて富を築いたのですが、これもテュルク・モンゴル語起源です。
ヤサックとして手に入れた黒てんの毛皮の多くは、ドイツのライプツィヒの毛皮取引所に出されて大人気を博していました。
テュルク系民族について
ここでの広義のテュルク系民族はTurkic peoples またはTurks
狭義のトルコはTurkish
中国での呼称は突厥
現代の代表的なテュルク系諸民族の分布

Wikipedia「テュルク系民族」より
タタール人、アルタイ人、トゥヴァ人、ヤクート人(以上ロシア)
トルコ人、アゼルバイジャン人、ウズベク人(ウズベキスタン)、トルクメン人(トルクメニスタン)、キルギス人、カザフ人(カザフスタン)、ウィグル人(中国)、クリミア・タタール人(ウクライナ)
一部地域にチュルク系民族が居住する国
* リトアニア、ポーランド、ロシア、トルコ
ハザールを起源とする種族が居住
* ベラルーシ、リトアニア、ポーランド
タタール系種族が居住
* アフガニスタン
ウズベク人など多くのテュルク系民族が居住
* イラン
北西部にアゼルバイジャンと同ゾックのアゼリー人、
北東部にトルクメン人
* モンゴル
西部にカザフ人、北部に少数のトゥバ人
* パキスタン
北部に、少数のウィグル人、トルクメン人
テュルク系民族の移動

Wikipedia「テュルク系民族」より
この図の赤丸の地域(バイカル湖南部付近)から、テュルク系民族が拡散したそうで、初期のテュルク人発祥の地は赤丸の南東端あたりで、時代は紀元前2000年あたりだそうです。
チュリム族について
こういうことを下書きしていると、「note.com」がシベリアのチュリム族の若い女性中心のバンド「OTYKEN」の記事を押してきました。
アメリカ公演予定とかグラミー賞候補になったとか(ロシアのウクライナ侵攻後すべてキャンセルされ実現できなくなりました)すごい勢いのようで、一体どういう経緯で結成されて、金が掛かってるけどスポンサーはどこなんだろう、とか気になって調べますが、やはり「note.com」が推してきた ` jullias suzzy ' さんの記事が、よく調べて書かれてます。
すごいですねー
OTYKENメンバーのチュリム族というのは、チュルク語系の言語を使用するチュルク系民族(東シベリアからトルコに至る広く分布する)で、シベリア中南部トムスク付近を流れるオビ川の支流チュリム(チュルイム)川周辺に居住する少数民族。人口は数百人、チュリム語を話せる人は200人くらい、母語としている人は数十人程度とのこと。(Wikipediaから要約)

赤線の国境左下は、カザフスタン共和国
前回述べた核実験場は左下☆あたり
その右の都市セメイは昔のセミパラチンスク
ポターニン達が入れられた監獄のあったオムスクが左端に見えます
ポターニンの人脈とシベリア調査
「シベリアに独立を!」の要点をNoteします。
1865年にシベリアの陸軍幼年学校で、ロシアからの分離・独立を呼びかける宣言文が発見されたことに端を発して、帝政ロシア当局は宣言文所持者を多数逮捕し、流刑に処した。
ポターニン達59人が拘束されて、オムスク市の監獄に入れられ、その後、要塞司令官直属の軍営倉に移された。
ポターニンには、動植物の採取や岩石の調査など自然研究への野心があり、1871年に釈放され、1876年から77年に行われた西北モンゴルの旅で、多くの採取品を持ち帰った。
そのかたわら、彼はこの旅の期間中に驚くべき多くの口碑を集めた。
ポターニンはこれらの口頭伝承の中で、
キリスト教の宇宙観、とりわけ天地創造、天命を受けた息子の地上への降下、悪魔との闘いなど、多くのモチーフがキリスト教伝承と共通することに注目し、
キリスト教そのものの発生が南シベリアか北モンゴルにある、
とさえ主張している。それがバルカンを通ってヨーロッパに伝わったのだと考えるに至った。
そうした伝承の東から西への伝播は神話にとどまるものではなく、中世ヨーロッパの英雄叙事詩もまた、東の発祥地からヨーロッパに伝わったものだと考えるに至った。
チェルスキーとヤクート人
ポターニンが、オムスクの監獄の中で知り合った人物に、ポーランド人のチェルスキーがいた。
軍営倉に移された後、ポターニンは軍の特別許可を受けて、チェルスキーを連れてイルティシ河畔に出かけていき、地質学上の標本を集めて持ち帰った。
チェルスキーはその後病気のため軍務を解かれ、1871年にイルクーツクに移った。
彼は、1891年に、ヤクート(サハ)に入り、インディギルカ、コルィマ両河を踏査し、その調査中、92年に亡くなった。

中央から左下、バイカル湖の北にレナ川の源流があり
中央ヤクート平原を通って北海にそそぐ
その東に、チェルスキーの名前を冠した山脈がある
言語学的にみると、ヤクート人のサハ語はトルコ語と起源を同じくするアルタイ語だし、そこに多く住むエヴェンキのことばもツングース語群に属するアルタイ語であって、日本語にかなり近い構造の言語を話している。
私は、これらの言語を話す人たちのことを、アカの他人とはとても思えない。
もしかして、日向(ひなか)の高千穂の嶺に天降りましました天孫はヤクート人の血を濃厚に含んでいるかもしれないと思っているからである。
サハ共和国
サハ(共和国):
1922~1991年はヤクート自治共和国。91年現国名に改称。ロシア東部、北極海に面しており、レナ川、ヤナ川、インジギルカ川、コルイマ川流域を占める広大な国で、首都はヤクーツク。1月の平均気温-43.5℃、7月は19℃で、全域が永久凍土帯に入る。
チュルク語系の言語を持つヤクート人の国で、住民の約三分の一がヤクート人で、約半分がロシア人。秀産業はトナカイ、馬の飼育と狩猟
金、ダイヤモンド、岩塩、天然ガス、スズ、石炭など豊かな地下資源の開発が進められている。
ここで脇道:ステンカ・ラージン
ここまで書いて、世界史の常識(私は、あまり持ち合わせているとは言えない)を得るため、大まかなロシアの歴史をざっと目を通してみたのですが、ステンカ・ラージンという人物が目に留まりました。
すぐに「そうそう、子供のころ外国の民謡として「ステンカラージンの歌」というのを良く聴いたことがあるぞ。歌詞もほどほどに覚えている。この歌のタイトルの人?」と、疑問符が点灯しました。
Wikipediaの「スチェパン・ラージン」によると、
「スチェパン・チモフェエヴィチ・ラージン1630-1671 は、コサックのアタマンで、モスクワ・ロシア南部において貴族とツァーリの官僚機構に対する大掛かりな抵抗運動を指揮した。日本でもいわゆるロシア民謡である『ステンカ・ラージン』と共に名高い。しばしばステンカ・ラージンとも呼ばれる」
ということで、その人でした。
