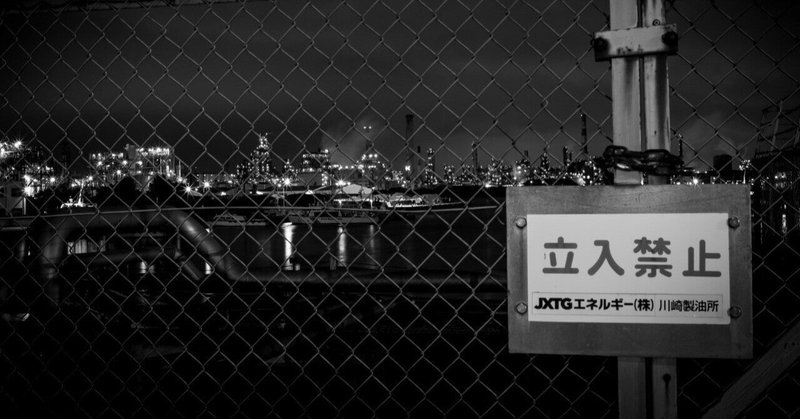
「マナーを守れ」という言葉ほど意味のない言葉はない
こんにちは、フリーランスフォトグラファーのまちゃるです。
今回は前回の記事「SNS映えの中でそのスポットの管理者や自治体は意識を高く持ってほしいという話」の続編的な内容になります。
出張撮影の際に撮影場所の管理者(主に自治体)に問い合わせると、明確な基準を持っているところもありますが、「他の利用者のご迷惑にならないようマナーを守って撮影してください」という注意のみのところも多数あります。
こういうどちらかというとゆるく、厳密な許可申請を必要としない場所は撮影を行うには一見楽なように見えます。
ただその一方で、利用者同士のいざこざや一般利用者(撮影者ではない方)からカメラマンに対するクレームが出ていることもよくあります。
昨今のSNS映え全盛の中で、一部のカメラマンのルール違反・マナーの欠如が問題になっていますし、そのマナーの問題はスマートフォンなどで撮影を行うライト層にも広がっているように感じます。
なぜこのようなマナーの欠如が起こっているのか、様々な記事で触れられていますが、僕はそもそも「マナーを守れという言葉ほど意味のないことはない」と考えています。
それは一言で言うと「人それぞれのマナーの基準が違うから」です。
この社会のルールと言えば、憲法に始まり、各法律や条例と言った明文化されたものがあり、法律の中でも比較的運用に幅があるものから、厳格に適用されるもの、罰則付きのものと多種多様に及びます。
社会の中での揉め事をスピーディーに解決し、当事者同士の異論を出さないようにするには厳格な法律が必要な一方で、世の中で起こる森羅万象にそれだけでは対応できないため、運用に幅を持たせた法律やさらに広い規範のような「マナー」と呼ばれるものがあります。
先ほど「マナーを守れという言葉ほど意味のないことはない」と書きましたが、僕もマナーには一定の有用性があると思っていますし、全否定するものではありません。
意味がないのは「本来マナーで済ませてはいけない解決手段にマナーを用いている」という点です。
以前、note内でも書きましたが金沢の人気観光地・兼六園でも三脚の使用や商業撮影について問題になっていました。
最近少し運用が見直され、少し事態は改善するかと思われたのですが、その一方で前撮り業者の場所占有や機材の持ち込みすぎなどのトラブルが起きているようです。
これは本来、「撮影時間は何時から何時まで、場所はこの区域に限る」「機材の持ち込み・占有はここまでとする」という明文化をしなければいけないにも関わらず、撮影業者のマナーに委ねた対応によるトラブルです。
確かに自分も出張撮影サービスを提供する立場からすれば、より撮影の正確性を上げるために照明を用意したり、広範囲で撮影を行いたいと考えます。
ただ、このカメラマン側の常識は一般利用者からすれば非常識・迷惑な行動であり、そこにマナーへの認識の不一致が発生します。
となれば管理者側は撮影業者と一般利用者間でのトラブルを減らすような明確なルール作りが必要になってきます。
マナーに任せた現状の方法は双方にとって、使いづらい状況とも言えます。
さらに近年では、価値観も多様化してマナーに対する考え方も合わせて多様化をしてきました。より多くの主張がぶつかり合ってトラブルが複雑化する可能性もあります。
繰り返しになりますが、決してマナーを守れということを全否定しているわけではありません。
時には利用者それぞれがマナーとは何かを考え、弾力的に運用されることも必要です。
その一方で「本来はマナーに任せる場面ではなく、ルール化するところはルール化すべき」だと僕は考えます。
一昔前は「マナーを守れ」で済んでいたことが、現在では済まなくなっている事例も多数出てきています。いろんな方向にいい顔をして利用者の努力だけで施設やスポットを管理できる時代は終わったと思います。
今こそスポットの管理者(特に自治体)は時代の流れに合ったルール作りを進める時ではないでしょうか。
サポートしていただいたものは情報収集や撮影に使わせていただき、役立つ情報としてみなさんに発信できればと思います☆
