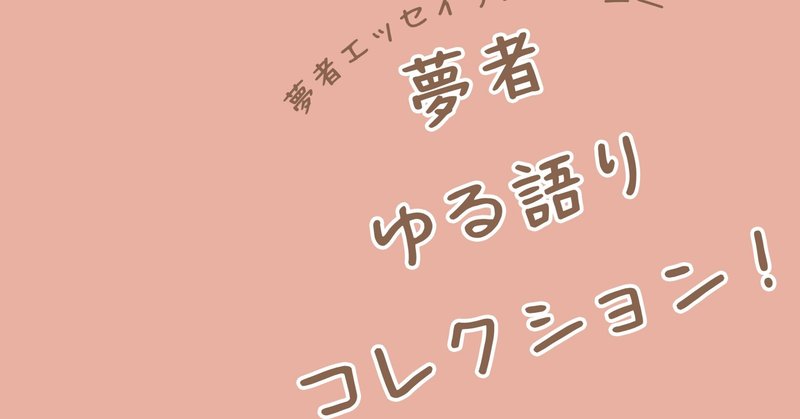
夢創作について語るエッセイアンソロジーを出した
※2022.07.13追記
BOOTHの頒布を再開したのでリンクを貼っておきました。
記事を書いたことを忘れかけていたのでちょっと遅くなったのは秘密です。
まあ出したの半年ほど前ですが。
そして今は一時的に頒布を止めているのでPixivのサンプルくらいしか紹介できるものがないのですが。
でもね、すごいんですよ、これ。
去年の秋、夢創作を愛する者=夢者たちが夢創作について語るエッセイアンソロジーを出しました。
主催であり頒布者でもある私の都合で今は一時的に頒布していない――というかBOOTH通販全体を閉めている――のですが、7月9日の夢箱大阪での頒布後にまた通販を再開する予定です。
なのでちょっとした宣伝を兼ねて、このなんだかすごいアンソロジーのお話をしようと思いました。
私は主催として色々やらせてもらったのですが、参加してくださった皆さんの熱量がとんでもなくて圧倒されるばかりでした。趣味として夢創作を嗜むひとたちによる、エッセイと論文の境目にあるようなテキストたち。いえ、一般的なカテゴライズにおいてはエッセイで良いのでしょうし私も宣伝の際などには「エッセイアンソロ」と読んでいますが。
このアンソロジーはTwitterの鍵アカウントでフォロワーさん方に寄稿を募った、いわば身内公募のような形で作ったものでした。最初は「びっくりするほど誰ものってこなかった」の画像みたいになるんじゃないかという不安もありましたが、できる限りのアピールをしたり執筆ハードルを下げたり(一問一答形式のみでの参加も可能にしました)した結果、予想を遥かに上回る8名の方に参加いただきました。ものすごくのってもらえてありがたい限りです。私が一度夢創作に関するエッセイ本を出していたことで、イメージしやすかった方もいるかもしれません。
そしていただいたテキストは、みんなそれぞれに夢創作を愛しているのだと実感できるものばかり。初めてアンソロジーの主催をするという緊張や苦労はたしかにあって、それでも原稿を受け取った瞬間に吹き飛んでしまうような、本当に嬉しく楽しい経験だったと覚えています。
一問一答の形式では、同じ質問でもみんな違ったり、逆に「やっぱりこういう道を通るんだ!」と頷けるところもあったりと読み比べる楽しさがあります。そしてテーマ(○○な話の書き方、などのテーマを主催側から個別に提供しています)や自由記述のエッセイでは、これでもかというほど愛を語っていただきました。10Pほど埋めた方もいて受け取った時の衝撃がすごかったですね。
そんな楽しくも自由なエッセイアンソロジーで、私が嬉しかったことはたくさんありました。その中でも二つ、後で思っても嬉しくて忘れられないことがあります。
一つ目。私が個人で出したエッセイ本は「こういう形式で夢創作への愛を語ってもいいと思うんだ! みんなもやろう!」の気持ちで作ったものでした。だけどその際は私の観測範囲では個人でエッセイ本を出すひとを見つけられず、それこそ「誰ものってこなかった」の気持ちになっていた時期もありました。ですがエッセイアンソロを出すときにエッセイ本の感想を送ってくださった方も参加してくださったりしました。それでようやく「あ、きっかけが無いだけで乗りたい人はいるじゃん!」という気持ちが芽生え、それと同時に「私が出した本は無意味じゃなかった」と思えたのです。
私が出した本も夢創作の考察本や同人誌に関するエッセイなどを出した先駆者たちがいたからこそ、書いていいと思えたものです。そちら側に回れたのだと思えたことが、とても嬉しく感じました。
そして、二つ目。これは最近気づいたのですが、参加してくださった方々が堂々と「夢書きです」と名乗って書いてくれたことです。夢オンリーのオンラインイベントで頒布したこともあり、ある程度夢が好きな人ばかりが読んでくれるだろうと想定した本なので、気負わずにそう書けたのだと思います。
「夢書き」であることは私や参加者の方々にとって、一番的確な自分のカテゴライズだと思います。だけどそう名乗ることって、まだまだ場によっては難しいときがあるのだとも思うのです。夢創作というジャンルは外から見れば、「多様すぎてよくわからないもの」=「昔読んでいた、書いていたという記憶から適当にラベリングしても良いもの」みたいに扱われることも多いと感じています。現役の書き手にとってそれは不本意であり、「じゃあわかってもらえないしオープンな場では夢書きって名乗らんとこ」といった考えになる方もいるのではないでしょうか。もちろん当エッセイアンソロジーがオープンな場かというと……まあ……夢創作をテーマにしたイベントなどでしか頒布予定がないので……という感じではありますが。
なんだか変に深掘りしようとしてしまったので閑話休題。
とにかく私が言いたかったことに戻ります。この本、すごいんです。愛がたくさん詰まっているんです。
だけど私の力不足もあり、夢創作を愛する人たちのところに届ききっていない感覚があるのです。結局のところ、筆を執った理由はそれだけでした。気づいていなければ、その人にとっては存在しないと思ったので。とりあえず、存在することを知ってほしかったのです。
それだけです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
