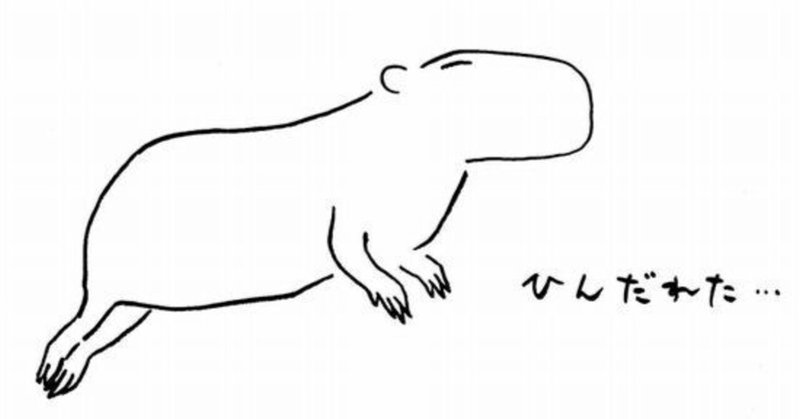
竹田現象学における「本質観取(本質直観)」とは実質的に何のことなのか(いったん完結)
竹田現象学における「本質観取(本質直観)」とは実質的に何のことなのか
http://miya.aki.gs/miya/miya_report37.pdf
できました! (※純粋経験論:レポート一覧のページからもダウンロードできます)
西氏、苫野氏の著作の分析も含めようと思ったのですが、さらに長くなってしまうので、ここでいったん完結させることにしました。PDFファイルで20ページです。過去のブログ記事の内容を訂正し、さらなる説明も加えています。
本ページでは、最後の7章・8章を掲載します。
「語りえない」ものとは? ~ 野矢茂樹著、ウィトゲンシュタイン『論理哲学論考』を読む、第1~3章の分析
http://miya.aki.gs/miya/miya_report35.pdf
と併せて読まれると(そういう人がいますように・・・)よりいっそう理解が深まると思います。
竹田現象学における「本質観取(本質直観)」とは実質的に何のことなのか
本稿では、竹田現象学における「本質観取」「本質直観」とは実質的に何を示しているのか、どういった意義を有するのかを明らかにするものである。その手法に一部には賛同者がいるようであるが、私自身は違和感も抱いている。
そもそも「理念」「本質」というものが実際に具体的経験として現れているのか、竹田氏の”経験観”に対しても疑念を抱いている。これらを竹田青嗣著『現象学入門』(NHKブックス、1989年)を分析しながら具体的に説明してみたい。
ただ、竹田氏による「本質観取(直観)」に関する見解は、真理、そして言葉の意味について以下二つの重要な論点を明らかにするという意義も有しているのではなかろうか。これらについて本文でより詳細に論じてみたい。
(1)真理はただ現れるもの、ただ与えられるもの、そしてパーソナルなものである。
(2)真理の普遍性・客観性を追求するプロセスにおいて(他者とのコミュニケーションにおいて)言葉の意味を言葉で伝えあうために、どうしても本来の(言葉の)意味としての知覚経験や心像ではなく、(他の様々な経験・知識との因果的関連付けにより導かれる)二次的な意味を用いるしかない、という事情がある。そしてそのプロセスの中で二次的な言葉の意味を「本質」と取り違えてしまう可能性がある。
<目次>
1.出発点は経験であり、経験から汲み上げられたものではない/経験は構成されたものではない
2.<主観>あるいは「純粋自我」の「はたらき」というものは現前する経験ではなく、因果的推論の産物にすぎない
3.「理念」「本質」という”何か”が新たに現れることはない(どこまでも言葉と個別的・具体的な経験だけしか現れない)
4.言葉=概念なのか?
5.「リンゴ」がどのように見えているかの問題ではない/<知>=概念とは実質的に何のことなのか
6.経験すべてが原的に与えられたものである/意識の自由・不自由が「不可疑性」の源泉ではない
7.真理とは与えられるもの・ただ現れるもの、そしてパーソナルなもの
8.言葉の意味を言葉で伝えあうとき(真理の普遍性を追求するとき)、本来の意味と二次的意味との転倒が生じうる
<引用文献>
7.真理とは与えられるもの・ただ現れるもの、そしてパーソナルなもの
真理を保証するものが経験の不可疑性(=竹田氏の言う明証性)ではないのならば、真理を保証するものはいったい何なのか、という話になってくるだろう。
竹田氏は次のように説明されている。
ひとはリンゴを見て、それをミカンだと確信したりできない。
現時点において、とにかく私はそれが「リンゴ」だと思ったのだ。ミカンやメロンだとは思えない。それが全てである。それが現時点における私にとっての真理なのである。
私が「正しい」と思っているのだから、それは(私にとって)「正しい」し、自らが疑わない限り再検証などはしない。それが全てである。真理というものは与えられるもの、ただ現れるものなのだ。まさにここが「本質観取(直観)」のキモであると言えるだろう。ただしそれは不可疑性を持つものではない。
また記憶に関しても、昨日の朝はパンにジャムをつけて食べたと思い出せても、ごはんにふりかけをかけて食べたと思うことはできないのである。当然記憶があやふやで確信できないという場合もあるが。記憶に関してもそうとしか思えないという、与えられた・ただ現れた事実があるのだ。
このように真理とはどこまでもパーソナルなものなのであるが、他者とコミュニケーションをとっているうちに、あるいは書籍やテレビや最近ではネット記事などで、他者の見解が自らのものと異なっていると知ることがある。その時、他者の見解が正しく自らの見解が間違い・勘違いであったと思い、自らの真理の見解を訂正する場合もある。一方、自分の方が正しいと思えば訂正はしないであろう。訂正しようがしまいが、真理かどうかの判断はあくまでパーソナルなものなのである。
自らの見解を訂正するケースはどういうものであろうか・・・? 単一の要因に還元することはできなさそうだが、考えられる事例として、よく見たら見間違いだったと気づくとか、自分の言葉遣いが間違っていたと気づくとか(その対象物は別の名前で呼ばれていたことを知るとか)、その他にもさまざまな状況がありえるだろう。
他者とのコミュニケーションや様々なメディアの情報から、私たちの真理観は訂正・更新されていく。こういった、認識の普遍性を獲得するプロセス、自分の認識が客観性・普遍性を持っていると思えるようになるプロセスにおいて、言葉の意味を、実物を指し示すだけではなく言葉で伝えあう必要が出てくるのである。
8.言葉の意味を言葉で伝えあうとき(真理の普遍性を追求するとき)、本来の意味と二次的意味との転倒が生じうる
竹田氏は、<知覚>と<苦痛>についての本質直観を試みている。
たとえば<知覚>という言葉を本質直観するとすれば、われわれは、自分のうちで<知覚>という言葉の意味(=本質)を、たとえば「記憶」や「想像」といった言葉とどういう点で区別しているのか、と問うことになる。このことが可能なのは、このときわれわれは<知覚>というものの存在のありようについて問うのではなく、ただ、この言葉による自分の中での意味の与えられ方だけを問うからだ。
さまざまな意識表象のうち、<意識>の自由にとって彼岸であるような像的表象、われわれはこれを<知覚>と呼ぶ。さまざまな<知覚>表象に伴う情動のうち、<意識>がこれを原則的に遠ざけようとする情動、これを<苦痛>とわれわれは呼ぶ。
・・・「<意識>の自由にとって彼岸であるような像的表象、われわれはこれを<知覚>と呼ぶ」というのが竹田氏の結論であるが、これが無効であることは既に説明した。
<知覚>とは、究極的には今、本や紙やコンピュータ、そしてそこに書かれている文字が現れているその視覚的経験、あるいは聞こえている車の音や犬の鳴き声、それら経験そのものなのである。
竹田氏は、その具体的経験に関係する因果的理解、つまり先ほど私が説明した二次的意味を「本質」と捉えようとしたと考えることもできる(失敗してはいるが)。言葉(言語表現)の一次的・本来的な意味は当然「言葉」ではなく、あくまで言葉で指し示されるもの(事象・経験)である。しかしそれを言葉で表現し他者に伝えようとするのであれば、関連する他の知識と関連づけながら説明するしかない。
リンゴという言葉が示すものは、リンゴの実物そのものであり(具体的には私たちの知覚経験としてしか現れないのだが)、それこそが究極的な(「リンゴ」という言葉の)意味なのである。「普遍的意味様式」(竹田、64ページ)でも「言葉それ自体が含む普遍的規定性」(竹田、59ページ)でもない。その一次的・究極的な意味を様々な知識を援用し別の言葉で説明することで他者に伝えられる、それら二次的意味が(時に)「普遍的意味様式」「普遍的規定性」と呼ばれるものなのである。
私たちは日常的に<知覚>や「記憶・想像」(あるいは「夢」)とを「普遍的意味様式」「普遍的規定性」を論拠にしながら区別しているわけではない。それらは明らかに体感的に違うものであるし、多くの場合、いちいち自分自身にその区別の根拠を説明する必要もない。「記憶」と「想像」とは区別がつけにくいかもしれない。しかし私たちは思い浮かべた心像をただ「記憶」と思うだけであるし、時に「想像」と思うだけである(もちろん事後的な根拠づけとして様々な要素を考えることはできる)。日常生活においてわざわざそんなものを準備する必要もあまりないかもしれない。しかし、それらの区別を他者と共有しようとする場合、他者に(言語で)説明しようとする場合、そこに様々な知識を援用して因果的に説明する必要が出てくるのである。
<苦痛>というものが、何らかの情動的な体感感覚を伴うことは合意できる。しかし、その体感感覚そのものが<苦痛>なのである。<苦痛>を遠ざける・<苦痛>から逃げたくなるというのは<苦痛そのもの>を味わったら人々はこういう行動をとりがちだ・そう思いがちだ、という具体的経験どうしの因果的関連づけである。しかも常にそうである保証もない。苦痛から逃げず耐えて克服したいという場合もある。
ここにおいても竹田氏の言われる「本質」とは、(私の言う)二次的意味、他の経験・知識(知識も経験の積み重ねである)との因果的関連づけにより導かれるものであると言える。しかも反例を考えることができるため成功しているとは言い難い(そういう場合もあるね、という感じか)。
前章において、真理がただ現れるもの、ただ与えられるものであるという側面が本質観取(直観)のキモの一つであると述べた。本章で明らかにしたもう一つのキモは、真理の普遍性・客観性を追求するプロセスにおいて(他者とのコミュニケーションにおいて)言葉の意味を伝えあうために、どうしても二次的意味として表現するしかない事情がある、ということである。そのプロセスにおいて二次的意味が「本質」と捉えられてしまう認識の転倒が起こっているのではなかろうか。
辞書における言葉の意味は、言葉として書かねばならない。図や写真も掲載されることがあるが、メインとなるのは言葉による説明である。繰り返しになってしまうが、究極的に言葉の意味とはその対象事物である。しかしその意味を言葉で示そうとすれば、他の知識との因果的関連づけ(あるいは同一性・類似性)によって説明するしか他に方法がない。それゆえ、二次的意味が「本質」として捉えられがちなのであると考えられる。辞書・辞典による意味の転倒とでも言おうか。
分析哲学では私的言語批判などというものがある。以下の見解も特定の人たちの間では正しいと認められているものであるのかもしれない。
語の意味を知るとはいわゆる「メンタルイメージ」(語に対応する私秘的なイメージ)をもつことではない。たとえば、「政府」や「征服」などの一般名辞の意味を知ってそれを適切に用いる行為者になることができるということは、その名辞の下に包摂され集められている諸観念を生き生きと想像出来るようになることではなく、むしろ、その名辞を他の名辞との関連上適切な仕方で用い、通時的な自分自身からも、会話の相手からも、承認されるようになるということである。
これも二次的な・・・というより言葉の使用法にまでかかわっているからむしろ三次的と言うべきか・・・意味、いや、むしろ言葉の意味の普遍性・客観性を追求するプロセスについての説明と言えるのではなかろうか。このプロセスの結果として、私自身が持つ言葉の意味、パーソナルな究極的意味(より正確には言葉と経験との関係)が普遍性を持っていると思えるようになる、ということなのである。言葉の意味と、その客観性獲得プロセスとを混同してしまっているのが上記のような見解なのだ。
<引用文献>
竹田青嗣著『現象学入門』NHKブックス、1989年
フッサール著『デカルト的省察』浜渦辰二訳、岩波文庫、2001年
デイヴィッド・ヒューム著『人間本性論』木曾好能訳、法政大学出版局、1995年
勢力尚雅著「第4章 ヒュームの懐疑論と寛容論」勢力尚雅・古田徹也著『経験論から言語哲学へ』放送大学教育振興会、2016年、72~92ページ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
