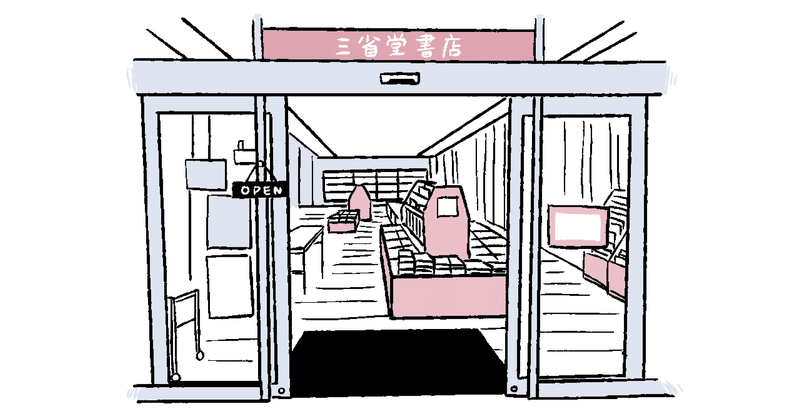
「はい、三省堂書店、ICU売店です。」
学生時代に2年間バイトをしていた書店が、今月で閉店することになった。
理由はご多分に漏れずコロナによる売上低迷なのだが、特にここで小売店の悲惨な実情や、政府の対応不足を嘆くつもりはない。ただこの書店は僕にとって非常に特別な場所だったので、twitterの140文字ではその想いを書き下すことができず、久しぶりにnoteの文書投稿ページを開くことにした。マンガ以外をアップするのは半年ぶりくらいになる。その間にnoteのテキストエディットページは新しいバージョンにグレードアップしていた。なるほど…それはどうも、おひさしぶりです。
* * * * *
三省堂書店ICU売店は、その名の通り、ICUという大学の構内にひっそりと店を構える小さな書店だった。おそらく利用者の98%はICU関係者で、残りの2%はふらっと花見にやってきた近隣住民である(ICUの桜並木はちょっとした観光スポットになるくらい美しい)。そして「書店」と銘打っていながら売上の大半はカップ麺や菓子パン、そして店頭で淹れるコーヒーが占めていた。

当時ICUの2年生だった僕は、この「大型書店の系列でありながら食品ばかりを売っている奇妙な売店」が好きで、何とかしてここで働く手立てが無いものか考えていた。高校時代、担任に「君には無理だ」と言われてあっさり美大進学を諦めた僕は、家から近いという理由だけでこの大学を選び、さして彩りの無い学生生活を送っていた。そんな自分にとって「大学構内の変わった書店でバイトが出来るかもしれない」というのはささやかな非日常への扉だったのだと思う。毎日食べたくもないスナック菓子を買いに行っては、レジの方に「今バイトって募集してないんでしたっけ?」と聞き続けたりもした。ただ、答えはいつも「ごめんね、ここの学生さんは雇えない決まりなの。」というものだったけど。
しかしそこから半年ほど経った頃、転機は突然訪れる。
「オモロいから、来月からうちで働いてみるか」
人事異動で新しくやってきた、京都訛りの店長がそう言ったのである。
毎日尋ね続けたのが功を奏したわけでもなんでもなく、僕の悲願は、店長交代による方針変更で、あっさりと叶えられた。

しかし、バイトと言えば引っ越しバイトくらいしか経験のない2年坊主である。お昼休みの壮絶なラッシュのレジ打ちも、複雑な本の発注も、全く覚えられなかった。一日で5000円分のレジ誤差を出したこともあった(通常は多くても1000円前後)が、優しいパートのおばさま方は誰も僕を責めなかった。
最終的に書店で僕に唯一任せられる仕事は、書籍や食品のPOPを書くことになった。POPと描いて「ポップ」と読む。平積みにした本の間からヒョッコリと生えている、あの小さな看板のようなヤツだ。
今でも覚えている。最初に描いた店頭POPは「工場萌え」という写真集のものだった。僕はハガキ大の厚紙に「毎度うっとりさせております」というキャッチコピーと、工事現場の立て看板を模したイラストを描いた。

「あのポップ、すごい評判いいよ。おかげで本もすぐ完売になっちゃった」と社員のキクチさんは言ってくれた。今思えばリップサービスだったのだろう。さらに思えば「工場萌え」は当時一大ブームを巻き起こした写真集なので、POPなぞ無くとも売れたはずの本である。しかし単純な僕は、おだてられて木に登る猿のように、次々と新作のPOPを描き漁り始めた。書籍のPOPだけでは飽き足らず、アイスやサンドイッチのPOPまで描き始めた。食品なんて年中同じ物を売っているのだから取り立ててセールスする要素もないはずである。しかし僕が1枚イラストを描き終えるとキクチさんやパートのおばさま方は「うまいうまい」と言って、すぐに次のお題を用意してくれた。
あまりにPOPの絵に凝りすぎて店長に「うえはらくんは、オタクなんか?」と聞かれたこともあった。自分でもどっちなのかわからなかったので「多分、違います」と答えたけど、今思えばこの回答はそこそこオタクっぽいね。
* * * * *
今思い返すと、不思議なことがある。
それまでの僕は、意識的に絵と距離を取っていた。
自分は美大を選ばなかった、「絵の道から降りた」人間だという負い目があったからだ。
当時の僕にとって絵を描くことは「未練」そのものであり、自分が選べなかった道を指を加えて見つめるような、切ない行為だった。
今思うとすごく馬鹿馬鹿しいんだけど、絵を忘れるために敢えて慣れないスポーツに手を出したり、使うアテのない簿記の勉強をしたりしたこともあった。結局社会人になってから美大に入り直し、そこもさして特別な場所でないということは後で分かるのだけど、二十歳の僕の狭い狭い世界は、そんなみっともないプライドでパンパンだったのだ。
そんな僕が、このバイト先のPOP作りでは、素直に絵を描くことができたのである。
「これは仕事の頼まれごとだから仕方ないんだ」という自分への言い訳が出来たからかもしれない。ともかく、あの書店のカウンターでマジックペンと色鉛筆を操っている時間だけは、未練も後悔もない、純粋な目的のためだけの絵を描くことができていた。そんなのはおそらく、中学時代に美術部でやったデッサン以来だと思う。その純粋な「表現のための表現」というものを、僕は大学構内の小さな書店の、こぢんまりとしたレジカウンターで知ったのだ。
それ以外にあそこで教わったことと言えば、あとは電話の取り方くらいのものである。この少し長めで、舌を噛みそうな書店の名前を、いつしか僕は一息で言えるようになっていた。
「はい、三省堂書店、ICU売店です。」

月日は、キクチさんがブックカバーを折るのと同じくらいテキパキと流れ、僕は大学卒業の時を迎え、同時にバイトも卒業することになった。店長はずっと「おれの目の黒いうちはお前に卒論を提出させん」と言っていたのに、提出日当日になると「出し忘れたらあかんから、早めに行っとき」と午前のシフトを抜けて提出させてくれた。いつの間にか僕の学生生活は、たくさんの心優しい人たちと大量のPOPに囲まれて、色鮮やかに輝いていた。
* * * * *
先日、その書店が閉店するということを知って、数年ぶりに店を訪れた。
もう「店長」はとっくに別店舗へ異動になっており、キクチさんも、パートのおばさま方もいなくなっていたが、昔働いていたことを現店長に伝えると、彼は標準語で「今までありがとうございました」と深々会釈をしてくださった。
当然、僕の描いたPOPは残っていない。
僕がそこで働いていたことを示す痕跡は何一つなかった。
挨拶も済んだのでそろそろ帰ろうか。
そう思った折、1つだけ、ある物を見つけて僕の心臓は高鳴った。



あの頃、「ラジオ英会話」とか「東洋経済」とか、そういう雑誌を開店前に荷解きして並べていた書棚である。そこに10年後、まさか自分の描いた漫画が置かれるなんて…!!
唐突に、あの無心でPOPを描き続けた時間が蘇った。
もしもあそこで絵を描いていなかったら、次に僕が本格的に絵を描き始めるのはそれから更に5年ほど後になっていた。いや、そもそもあの時間がなかったら、果たしてもう一度美大に入り直そうなんて発想に至っていたのだろうか。そして今、漫画を仕事にするような人生を送っていただろうか。
絵を描くことの純粋な楽しさをもう一度僕に教えてくれた場所。
閉店間際に訪れたその書店は「いいから描き続けろよ」と背中を押して、僕を送り出してくれたような気がした。
…とはいえ、こうも都合よく解釈して勝手に熱くなる僕を見たら
「店長」は言うかもしれませんね。
「やっぱりうえはらくんは、オタクやな」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
