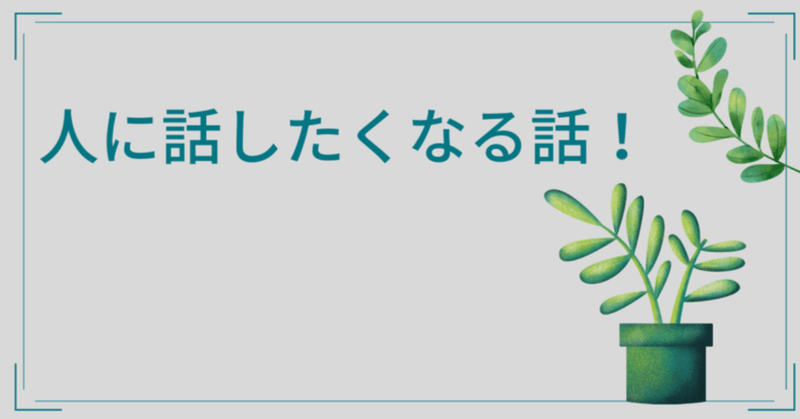
岩手の県名はどうやって決まったのか?
こんにちは、ハレルヤです。
今回は岩手のお話です。
東北地方にある岩手県、龍泉洞や中尊寺、大谷翔平などで有名な県ですが
岩手県はの地名の由来をご存知でしょうか?
岩手県の由来は『鬼が岩に手形をつけた』ところから岩手になったと
いわれています。
では、その手形がついた岩は何処にあるのでしょうか?
その岩は、盛岡市名須川町の三ツ石神社にあります。
三ツ石神社には高さ6メートルの岩が二つとやや小ぶりの岩が並んでいるのですが、その表面に苔の生えていない部分があります。
それが大きな手形の形をしていることから『鬼の手形石』と呼ばれています。


この手形にまつわる伝説によると、昔この地域に住んでいた鬼は、村人や旅人に対して悪行のかぎりを尽くしました。
困った村人は信仰の対象であった三ツ石に『助けてほしい』とお願いしました。
すると、三ツ石の神様が鬼を捕まえ三ツ石に縛り付けました。
観念した鬼は二度と悪行をしないと誓ったので約束の印として
三ツ石に手形をつけたので、三ツ石の神は鬼を逃してやりました。
それ以来、手形の痕には苔が生えなくなったという。
この伝説から岩手という地名が誕生したといわれています。
今回は以上です。
サポートいただいた活動費は全額 複勝転がしに使わさせていただきます。💕💕💕 皆さんの応援待ってます! (゚∀゚)ウキーー!!💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕
