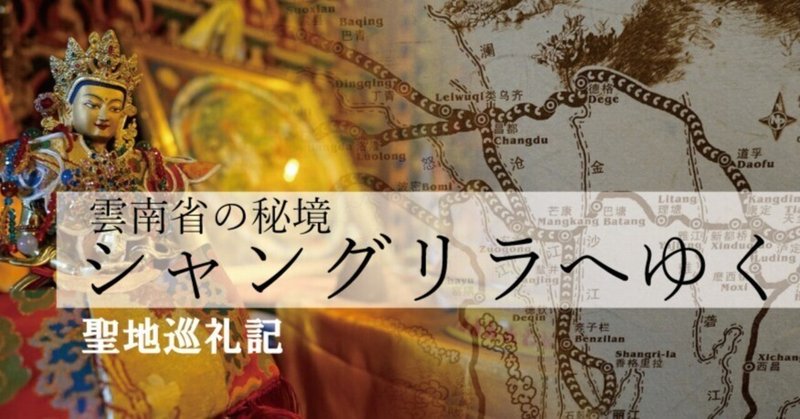
シャングリラへゆく⑭修行するチベット僧と完成前のお堂に潜入
理想郷のことを人はシャングリラと呼ぶ
雲南の香りに魅せられて僕は旅をした
冒険家が探し求めたシャングリラに想いをよせ
奥へ奥へ雲南省の秘境を旅した記録
①から読めばより深く楽しめます
シリーズ「チベットへゆく」の第二部
シャングリラへゆく物語
修行僧と完成前のお堂に潜入
今回、再び雲南省へ戻ってきたのは
転生僧に謁見が叶うという事になったからだ
8月に麗江で知り合った孫君の紹介で
四川省甘孜県に位置し理塘に近い山奥の寺にきた
あれほど待ち望んでいた転生僧の謁見は
僅か5分もなく終わった。
僕は聞いていみたい質問もあったが
質問する事は叶わず終わる
その後、若い僧は僕らに寺を案内してくれた
ここは元々はサキャ派系の寺
今でも古いお堂が残っている
サキャ派とは
チベット4大宗派の一つ
赤い帽子をかぶる事から赤帽派とも呼ばれる
ちなみにゲルク派は黄色い帽子
一時期サキャ派は政権を握っていた時期もあるが
カギュー派の分派のパクドゥモ派に実権を奪われ
その後、ゲルク派が実権を握る
サキャ派も
その後分派しゴル派、ツァル派に分かれる
この寺は、それをベースしつつ1995年から
明珠佛学院として設立され
チベット仏教を学ぶ僧を受け入れている
何個かあるチベット仏教学院の1つだった
資金を集めお堂建設を長年かけて
行っている途中で敷地はかなり広い
建設中のお堂の中に招待され製作途中の
部屋を見せてもらう

この神はマハーカーラといい
ヒンドゥー教のシヴァ神の化身の一つ
日本では大黒天として広まった神になる


後の青い棚には小さな仏が入る予定
2階に上がり写真を撮影した
別の建物に移り螺旋階段を最上階まで上がり
部屋に入ると、部屋の中央に大きな
立体曼荼羅が配置


立体曼荼羅はポタラ宮殿の白宮でも
芸術品の域を超えた繊細さで沢山飾ってあった
40人の僧が2年を費やし製作といっていた
部屋の四方の壁には仏がギッシリ整列され収納
柱、天井、壁の装飾は鮮やかで細かく
チベット模様
完成までには、まだ暫くかかりそうだが
完成した部屋を見てみたくなる
孫君は色んな場所に寄付の1元札を置いていた
僕らも、ここに来る前に立ち寄った店で
お札を両替し持参していたので
1元札を至る所に挟み寄付する
仏の腕に挟んだりして
飛ばないように何かに挟み置いていく
1つの部屋で何枚も挟む

建物の屋上に上がり法輪を見に行った
目の前で見るのは初めて
中央の法輪は 輪の中心は世界の中心
悟りに至る8つの過程を意味する
左右に配置された鹿は鹿野苑
これはインドのサルナートを指す
サルナートは釈迦が初めて説法を説いた地で
インドに行った際に行った場所でもあった
昔は、鹿が多く生息していた事が由来らしい
チベット寺に行けばこの法輪は必ず見かける

屋上から一望でき
目の前に黄金の屋根を持つ建物が見える
昔から あるお堂
元は、こんな小さな寺だった

外壁の中に入ると一時期、僧の住居として
使われていた様子
今は使われてなく外壁に沿って部屋が残っている

かなり古いお堂の中で、中央に寺の偉い僧が説法
その周りに熱心に聞く弟子達と地元民がいて
年配の老婆や信仰の熱い人達が参加し
僧の話を熱心に聞いていた
この空間はとても絵になり雰囲気が良く
とても自然体だった
熱心に説法をする僧と真剣に聞き入る弟子達
言葉が解かるなら聞いてみたと思うような時間
屋上から山側を見ると
四角く水色壁の建物が目に付く
ここが学院になり学院生の宿舎と教室がある


かなりの人数が暮らす事ができそうな学院で
思いのほか綺麗
学院宿舎を抜け奥に進むと赤いレンガで
作られた古そうだけど大きなお堂があった

黒い垂れ幕をくぐると門があり、中に入ると
沢山の修行僧がお経の暗記をしていた
それぞれにお経を唱え、大きなお堂は低い声で
真言を詠む声が部屋中に響く音色は
壮言な空気感
足音をたてるのも気を使う
僕らは気配を消しつつ壁に沿って奥へ歩く



お堂の中央奥には大きな仏像があり
他とは違う輝きをはなっていた
数多くの蝋燭と貢物、花やお金が至る所に
置かれてる
孫君は、ここでもお札を
色んな隙間に挟み置いていく
僕らも真似し残ってるお金を何枚も
置けそう場所に置いていく
蝋燭台の下や仏像の手や仏具の隙間などに
置いていく

中央に白い一際、価値の高そうな
変わった形の箱があり
案内してくれてる若い僧が
この中に特に偉い高僧の
仏舎利が入っているという

そのお堂を抜けると、まだ奥に大きな広場がる
ここは大祈祷会が年に2回開かれるらしく
他方からも多くの僧がここに集結するようだ


この地域の冬は厳しい
僕らが想像する以上に修行は厳しい

寺の外壁にはマニ車があり
大きなものから小さなものまで


最後僕らは、寺の外壁にそり
マニ車を回し寺を出る事になった
案内してくれた僧に
何度も お礼をいい車にのり寺を後にした
寺の門を出て
サイドミラーに映る黄金の屋根が
小さくなっていく
ここは小さな宇宙
修行僧の多くは小さい頃に預けられた
貧しい人が多い
中には大きくなり修行し
仏道に入る者もいるが年々時代の変化により
僧の数は減っているという
小さい頃から(物心つく前から)寺に入り
出家し、この小さな宇宙が
世界の全てとして生きていく
ここは隔離された宇宙
下界の人を簡単には近づけない
近くの村に住む人が出入りするだけの
人里離れた山奥
もし、僕が今の生活を知らず
この世界に生まれ育ったならば
彼らと同じく無心でお経を読み解き
解脱する精神世界と人々の救済へと
魂が肉体を抜け出る時まで
祈り続けるのだろうか?
ここの僧たちは
ダライ・ラマ十四世の事を
どこまで知っているのだろうか?
詳しく知らないのではと気になった
中国では十四世の崇拝は禁止されている
その名を口にすることすら危険なのだ
許可を得て学院として運営するこの学院で
十四世を教える事はないはずだ
ゲルク派でもなく、極める教典も違う
かつてチベットで
生ける神として崇められた
最高指導者のダライ・ラマ法王
この半世紀の歴史を無かったことにして
チベット仏教を語ることなど出来ない
僕は踏み込んだ質問を本当はしてみたかったが
それはタブーだとも知っている
そんな会話は簡単にできない
修行僧達の本音を聞いてみたと思いながら
サイドミラーから寺は見えなくなった
修行僧と完成前のお堂に潜入
僕らが寺を後にし向かったのは
チベット仏教史に度々登場してくる地
理塘
有名な転生僧が何人か生まれ堕ちている
ダライ・ラマ七世(ケルサン・ギャツォ)も
そのうちの一人
彼の転生劇の話が僕は好きだったから
理塘に行く事は
僕にとっても特別な聖地巡礼になる
陽が沈む前に理塘を目指した

⑮ 聖地理塘へゆく へ続く
↓↓聖地巡歴記 インド編(完全版) はこちらをどうぞ!
↓↓聖地巡歴記 西安編 はこちらをどうぞ
↓↓聖地巡歴記 ミャンマー編 はこちらをどうぞ
↓↓聖地巡歴記 南京編 はこちらをどうぞ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
