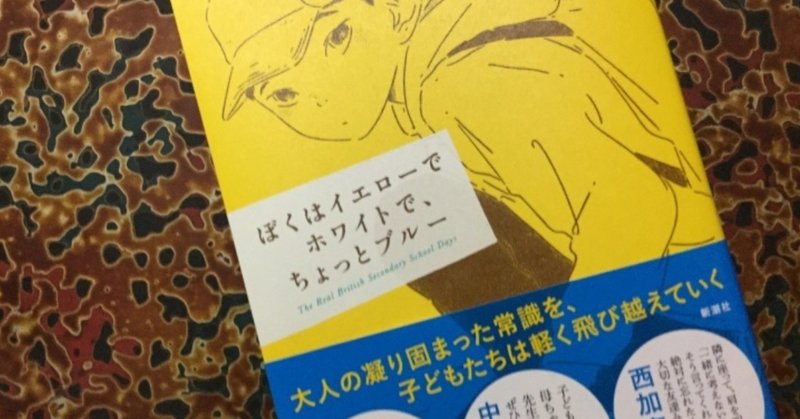
『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』感想
あらすじ
大ファンであるブレイディみかこさんの新刊がこのところ立て続けに出た。岩波書店からは『女たちのテロル』。そして本日紹介したい新潮社からの『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』である。
内容はブレイディさんの息子さんのセカンダリースクール(11歳から16歳まで通う日本の中学校に該当するもの)でのさまざまな体験を綴ったもの。乳幼児期はブレイディさんが働くいわゆる「底辺託児所」に通い、そこで経験豊かなブレイディさんの師匠筋にあたる責任者に見てもらい、小学校は教育熱心な牧歌的カトリックスクールに通っていた優等生の子。ところが、中学校もそのまま優秀なカトリック中学に通うのかと思いきや、なぜか近くの元底辺中学であった学校に通い始め、様々な体験を重ねていく中でなかなかドラマチックな日常が綴られる物語。
ブレイディさんの働いてきた保育所の話などを読めば(『子どもたちの階級闘争』など)、底辺層の子供たちの話などから大変さには思いは至るが、息子さんが通う中等学校はもっと多様で、複雑で、さまざまなレイヤー(層)の子どもたちのあいだで教育が行われていることに、結果として、その先駆性に驚かされる。ある種単純で波風が立たない環境をよしととしてきた、私のような初老期の子どもを持たない者には、その「壁の薄さ」へ向かう力学を強烈に感ずる。社会的アクチュアリティへの対応力の強さだ。
さまざまなレイヤーとエンパシー
そのさまざまに複雑なレイヤー(層)とは何か。例えばEU離脱派と残留派、移民と英国人、様々な階層の移民どうし、階級の上下、貧富の差、高齢者と若者たちなどの分断などなどだ。
そのため、教育にも「シチズン・シップ」の学習に力が入れられている。
英国ではこれらのことについて11歳から学んでいる。特筆に値すると思う。
この学習の中でエンパシーとは何か?という問いも設問される。エンパシーとは他人の経験や感情を想像し、理解しようとする「能力」。だからシンパシーとは違い、意識的に努力して学んでいかねばならない。経験の異質性を解って行こうとする努力。多民族化、アイデンティティが多様化する英国では特に大事な能力になっていくという見立てゆえだろう。
その意味では、愛読者側として知っているエンパシーの能力を磨きに磨いてきたブレイディさんと、相当クオリティの高い共感力をもつ息子さんのエンパシーを磨く修行がお互いに共鳴しているように読める(学校生活において、日本に旅行に来て典型的なオヤジに絡まれることにおいて、人種的な問題について、移民や貧困下にある同級生と接することについてなど)。
いや、よく読むと修行という言葉は違う。息子さんはしなやかに、学校生活にも、教育にも適応している。もちろん、時に悩み、時にブルーになりながらも。
ほかにも思うのは息子さんの世界だけでなく、英国の庶民層が見ている「社会」は外に開かれている世界だな、という印象だ。階級というか、格差が隠蔽されずにオモテに出ているし、性に寛容であるブライトンという土地柄ゆえか、カップルや愛のかたちも多様。
そのような環境の中でブレイディさんの息子さんはさまざまなレイヤーの中で育ち、さまざまなカラーの中で新しい考えが生まれ、こころをひらき、思春期の子として友や周囲の大人を気遣い、自分がコミュニティとなんらかの絡みがあるはずと考える。
アイデンティティの多様化と同朋意識
幾つも印象的なエピソードがあるのだが、中でも中国系の生徒会長が東洋系の自分に同胞意識を持ち、守り接してくれることに戸惑う場面で、ブレイディさんに自分の思いを語る息子さんのことばが印象深い。
ぼくは東洋人の生徒会長が思うほど、自分を東洋人と思ってない。ピンと来ない。仲間意識の感情が強いんだな、って。僕はそういう気持ちが持てない。
僕はどこかに属している気持ちが持てない。悪い部分も、いい部分もない。(P.220ー意訳)
これが排外主義的な態度を持つハンガリー系の友人や貧困地域に住む英国人の友人を持ち、日本で知らないオヤジからガイジン扱いでいわれない批判的な目線を向けられたプレ思春期の子どもの悩みなのだ。何と曇りない大人な悩みなのかと思う。
子どもを社会が育てる
そのほかにも英国の子どもたちが大人たちのドラッグ禍に巻き込まれるさま(ケン・ローチ監督の映画『スウィート・シックステーン』の世界は虚構でない、と思ってしまう)や、そのような問題もあるためか、教室格差などもありつつも、教育機関から離れていると親に罰金が科される制度など、明らかに英国は家庭中心ではなく、「社会が子どもを育てる」土壌が強い文化だなと思う。ゆえにソーシャルワーカーの権力が強く、子供が親から引き離され、里親などに引き渡される傾向もけっこうあると思える。このあたり親子の結びつきが強い日本の文化では違和感が持たれそうだ。ただ、日本でも最近は親の虐待事件が多発しているので、今後は今よりも子どもは社会が守るもの、という風に変わっていくかもしれない。
いずれにしても、英国は移民の包摂や、アイデンティティの多様化が開かれ、オープンな社会になっており、そこでは揺れ幅も大きいかもしれないが、国としてはその分だけさまざまに免疫が強い、オープンゆえに、おそらく今後も世界の動向的にも先頭集団としての力を発揮する国であり続けるのではないかなと思う。ブレイディさんの息子さんが受けている教育、その市民教育への目配りの高さを考えると、そう思われるのだ(ただ逆にそこからこぼれ落ちてしまう子は極めて大変なのかもしれない)。
対比して日本の初等中等教育などでどのような変化があるのか子どもが居ない自分にはわからず、なんとも言えないが、やはり英国に比べてその潮流に乗り遅れているところがあるのではないかと想像する。例えば感情を押し殺すのではなく、感情を正確に相手に伝える教育に力を入れる英国のコミュニケーション教育ひとつとってもそうだろう。
普遍性を獲得しつつある筆力
作品については、ブレイディさんのいままでの作品の中ではもっとも読みやすく、一般性があるのではないかと思う。明るい黄色な表紙と爽やかなイラスト通りに、爽やかなプレ思春期でありつつ、いたいけなまでに大人っぽい少年の成長物語はちょっと懐かしいビルドゥィングス・ロマンの現代版を感じさせる。ブレイディさんの文筆も普遍的に読ませる力量に至っている(偉そうですみません)。
最後に最近のブレイディさんの描写を読んでいると、かつての誰かを思わせるな…とずっと考えていたのだが、思い出した。それは米原万里さんで、「嘘つきアーニャの真っ赤な真実」を読んだ時の感触だ。今回、米原さんのタイトル表題作を読み直したが、流石の力量であった。ただし米原さんの作品のほうが昔の友人と大人になって再会しても、かなり理詰めで向き合って議論的、ある種アグレッシブなのには再読して驚いた。むしろブレイディさんのほうが、持っていたパンクなイメージよりもずっと相手の感情を大事にされているとさえ思える。ただ、お互いのアティチュードはきっと似ていると思う。時代や立場の違いもあるかもしれない。
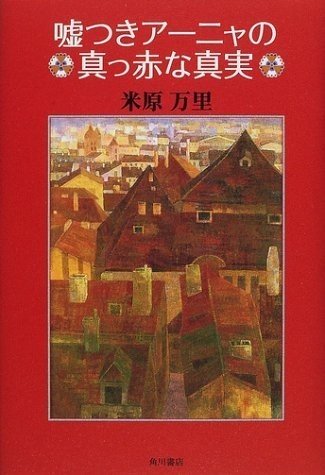
話がずれたけれど、元来ブレイディさんが持つアナーキーな感触、闘士女性たちの憑依(?)する清冽な情熱が沸々湧き上がる鋭利な意識は『女たちのテロル』(岩波書店)のほうにある。こちらにも作家としての筆力的な成長にびっくり。ある意味ではブレイディさんのもう一つの側面がこちらにはあります。また時間があればそちらの感想もかければ幸いです。
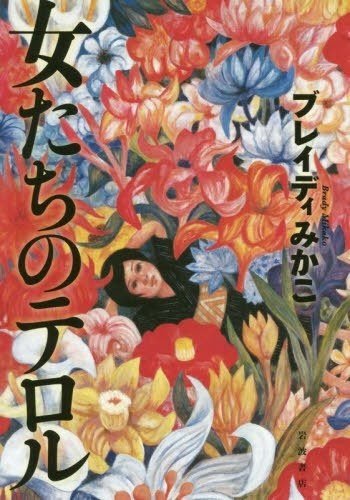
PS.
忘れていました!ぜひ「ぼくはホワイトで~」は中学や高校の学習参考書にして欲しいと思います。それだけの価値ある本だと思います。
よろしければサポートお願いします。サポート費はクリエイターの活動費として活用させていただきます!
