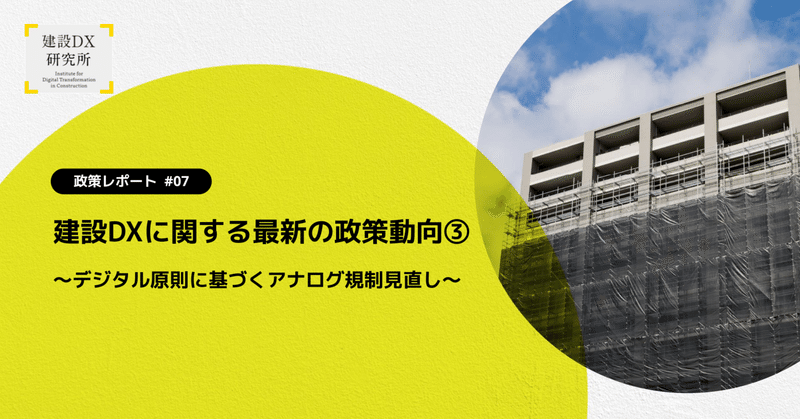
建設DXに関する最新の政策動向③ ~デジタル原則に照らしたアナログ規制見直し~
【はじめに】
前々回の記事で「規制改革実施計画」についてご紹介しました。本計画は、経済社会の仕組みをデジタル時代に合ったものに作り直していくために必要な規制改革の具体的な取組・時期を定めたものです。本計画の具体的な内容は、デジタル庁が所管するデジタル臨時行政改革調査会(通称「デジタル臨調」)と各所管省庁において検討が進められています。
今回の記事では、建築DX推進のために必要となる「 目視規制の見直しの着実な推進」「実地監査規制の見直しの着実な推進」に焦点を当てて、最新の検討状況を紐解いていきます。
【デジタル原則と改革の方向性】
2021年12月に開かれたデジタル臨時行政調査会(デジタル臨調)において、官民の共通の指針となる「デジタル原則」が策定されました。本原則は、「デジタル完結・自動化」「アジャイルガバナンス」「官民連携」「相互運用性確保」「共通基盤利用」の5つからなり、書面提出や対面を義務付ける法令や政省令・通達などを点検し、規制改革を推進していくこととされています。

に基づいて筆者作成
上記の方針を踏まえ、デジタル臨調では、代表的なアナログ規制である「目視」「定期検査・点検」「実地監査」「常駐・専任」「書面掲示」「対面講習」「往訪閲覧・縦覧」の7項目を対象として、1万に上る法律、政省令等から該当する規定を洗い出し、一つひとつデジタル原則への適合性を点検し、見直しに向けた検討を行うことになりました。

に基づいて筆者作成
点検にあたっては、規制の目的を確認した上で、最新技術を利用することで規制目的を達成することができるかどうかを確認していきますが、対象となる規制数が膨大なことから、デジタル臨調では、多数の規制を短期間で効率的に見直しを行うことを目的として、「類型」と「フェーズ」の概念が導入されています。
規制の趣旨・目的が類似した規制「類型」ごとにデジタル技術の活用を検討し、活用が可能な場合には「類型」に属する全ての規制にも適用可能とすることで、迅速な検討が可能とされています。また、類型毎の見直しを行うにあたり、デジタル化の進捗度合いを表す3段階の「フェーズ」を活用することで、現状の見直し状況を把握した上で、当面の目指すべきフェーズを明確化する予定です。

【目視・実地監査規制見直しの概要】
冒頭で触れたとおり、本記事では、建設DXの推進のために避けて通れない目視規制と実施監査規制に焦点を当てて解説していきます。
目視規制と実施監査規制は、異なる項目として整理されているものの、いずれも人が現場に赴く必要があることから、両項目をまとめた上で、「検査・点検・監査」「調査」「巡視・見張」の3つに類型化した上で見直しが進められています。
また、フェーズについては、「現行規制の状態」「情報収集の遠隔化・人による評価」「判断の精緻化・自動化・無人化」の3つとし、類型毎にどのようなデジタル技術の活用余地があるか整理されています。たとえば、巡視・見張では、監視カメラ、ドローン等による遠隔監視の可能性が謳われています。

【目視・実施監査規制のうち代表的な規制の見直し状況】
目視・実施監査規制のうち、建設業界に関係の深い「 特定元方事業者による現場巡視(労働安全衛生法等)」「(建築確認における) 中間・完了検査の目視対応(建築基準法等)」の2つの規制について解説していきます。
① 特定元方事業者による現場巡視
建設業及び造船業は、同じ場所で違う会社の労働者が混在して作業するケースが多いため、特定元方事業者には統括管理が義務づけられており、その中の一つとして一日一回以上の現場巡視が規定されています。
労働安全衛生法 第30条第1項
特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。
(略)
三 作業場所を巡視すること。
労働安全衛生規則 第637条第1項
特定元方事業者は、法第三十条第一項第三号の規定による巡視については、毎作業日に少なくとも一回、これを行なわなければならない。
所管省庁である厚生労働省からは、フェーズ2である情報収集の遠隔化、人による評価の実現のためには、安全衛生水準の低下を招かないことを前提として、「現場に直接赴くことと同等の情報を入手できること」「不安全な状況、危険な作業を現認したとき、労働災害を未然に防ぐための措置を速やかに講ずることができること」の2点が満たされる必要がある旨が示されています。
本規制を代替するデジタル技術としては、「ウェアラブルカメラ等による情報収集の遠隔化」や「定点カメラと画像認識処理等による不安全行動の把握」等が上げられており、業界団体へのヒアリングを通じて、実現の可否について検討が行われており※、2024年6月を目途に見直しが完了する見込みです。
※ 建設業労働災害防止協会内の「ICTを活用した労働災害防止対策のあり方に関する検討委員会 特定元方事業者による遠隔巡視のあり方検討作業部会(WG)」において、有識者、建設事業者、国土交通省を交えて検討が進められています。

安全性確保に必要となる巡視の要件は、現場の規模や作業内容に応じて異なるため、全ての現場に一律の規制ではなく、現場の実態を踏まえて要件を設定することが重要と考えます。特に住宅建築や小規模な設備設置工事の現場では、人手不足が顕著であり、デジタル活用による現場の効率化が図れるよう、現場の実態に応じた適切な要件設定を行っていただくことが重要と考えています。
② (建築確認における) 中間・完了検査の目視対応
建築確認を行う建築物については中間検査(該当する場合のみ)及び完了検査の実施が義務付けられています。本検査は特定行政庁または指定確認検査機関の検査員が現場を訪問し、目視で行うこととされています。
確認審査等に関する指針 第3₋3第2号(完了検査)
申請等に係る建築物等が、建築基準関係規定に適合しているかどうかの検査は、次の各号に定めるところによるものとする。
(中略)
二(一部略)写真及び書類による検査並びに目視、簡易な計測機器等による測定又は建築物の部分の動作確認その他の方法により、申請等に係る建築物等の工事が、施行規則第4条第1項第一に規定する図書のとおり実施されたものであるかどうかを確かめること
確認審査等に関する指針 第4₋3第2号(中間検査)
申請等に係る建築物等について、検査前に施工された工事に係る建築物の部分、建築設備又は工作物の部分及びその敷地が、建築基準関係規定に適合しているかどうかの検査は、次の各号に定めるところによるものとする。
(中略)
二 (一部略)写真及び書類による検査並びに目視、簡易な計測機器等による測定又は建築物の部分の動作確認その他の方法により、検査前に施工された工事に係る建築物の部分等の工事が、施行規則第4条の8第1項第一号に規定する図書のとおり実施されたものであるかどうかを確かめること。
所管省庁である国土交通省では、フェーズ2である情報収集の遠隔化、人による評価の実現については基本的に可能であるとの認識が示されている一方、デジタル技術の利用によって検査員が直接現場で検査するよりも時間を要してしまう懸念が関係事業者から寄せられているとしています。そのため、審査側・申請側のニーズを踏まえつつ、適用できる範囲で効率的な実施手法を検討し、2024年6月を目途に見直しが行われる予定です。
なお、本規制を代替するデジタル技術としては、「Web会議システム」等を用いて、遠隔地にいる確認検査員が建築現場にいる検査側の補助員と映像や音声を繋いで検査することが想定されています。
なお、アンドパッドでは、以前の記事でも紹介した国土交通省の「令和3年度BIMを活用した建築生産・維持管理プロセス円滑化モデル事業」において、ANDPAD HOUSE建築時に中間検査をWeb会議ツールなど複数のツール・デバイスを利用して模擬的に実施しました。国土交通省が懸念するとおり、慣れない環境下では従来よりも時間を要した部分もありますが、手法の確立と一定の習熟さえできれば、作業を大幅に効率化できると考えています。
国土交通省における前向きな検討・推進を期待していきたいところです。

事業報告資料」
【おわりに】
今回は、デジタル臨調で検討されているアナログ規制改革のうち、目視規制と実地監査規制の検討状況と、具体例として特定元方事業者による現場巡視と中間・完了検査の目視対応について解説してきました。
見直し対象とされている規制について、デジタル技術を活用することで代替できれば、建設事業者をはじめとした様々なステークホルダーが恩恵を受けることが予想されます。規制所管省庁には、デジタル技術の活用による現場の効率化が実現できるよう、現場の実態に即した見直し方針を検討していただくことを期待したいと思います。
建設DX研究所としても、建設事業者様からの意見収集や関係省庁・国会議員等への提言も行っていく予定ですので、何かご意見などあれば是非小職までご連絡いただけますと幸いです。
次回は、令和5年度の政府予算のうち建設DX関連予算と注目すべき事業を中心にご紹介する予定ですので、ご期待いただけましたら幸いです。
筆者プロフィール
須田 和宏
建設DX研究所 研究員。
大学卒業後、コンサルティング会社で官公庁向けの経営・業務・ITコンサルティングに従事。同社在籍中にさいたま市のCIO補佐監を6年間兼務。2022年4月より株式会社アンドパッドに入社し、新規事業の推進やガバメント・リレーションズ業務を担当。
