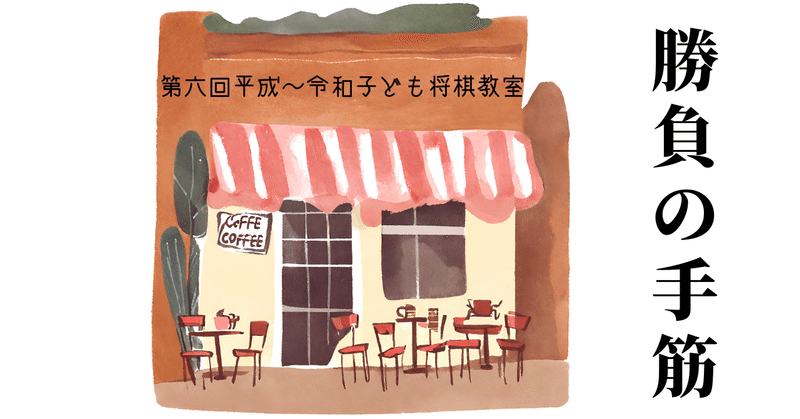
第六回平成~令和子ども将棋教室:子どもに教える勝負の手筋
本題に入る前に先日亡くなられた北海道支部連合会の工藤学さんとお話させていただいたことについて記載します。工藤さんは北海道将棋界の発展にご尽力され、北海道の将棋の普及にも熱い思いを持たれている方でした。さまざまな話の中で、北海道のどこでも将棋を楽しめる環境を作りたいという話が特に印象に残っています。北海道は広大なため、将棋を指す環境が大変な地域も多いとのことでした。近年はインターネット指導や将棋のさまざまな動画など、新しい将棋の普及の形ができています。この問題に関してはさまざまな普及の発展により、工藤さんの思いの方向へ進む流れになるのではないかと思っております。簡単ではございますが、この場をお借りして工藤さんのご冥福をお祈りします。
今回は第六回は子どもに教える勝負の手筋についてです。将棋に限らず、相手がいる競技には勝負の手筋があります。それらの共通点は、相手の気持ちになるということです。とある教室で序盤中盤で悪くなるとそのまま負けてしまう子どもがいました。その子は攻めるのが大好きで、自分の玉を見ずに一心不乱に敵玉を攻めてばかりいました。本人は逆転勝ちもしたいとのことだったので、相手の気持ちを考える練習として「家でお母さんがやってほしそうな事のお手伝いをしよう」と提案しました。これには大きく2つのメリットがあります。
1つは、人のやりたいことを先読みする癖をつけられることです。相手が何をやりたいかを考えて、例えば相手の手を潰すようなことをすると、相手は指したい手を指せなくなってしまいます。また、相手の攻めが分かっているならば、それを見切ることもできます。いわゆる先読みの技術が身につくということです。
もう1つは、家事のお手伝いをするようになることです。将棋教室に通ったら家事を手伝うようになることは、保護者さんの目線では最高なことではないでしょうか。保護者さんの理解を得ることも大切なことです。実際に家事を手伝うようになったその子は教室では勝つようになり、保護者さんも二重に喜んでおられました。
以上、第六回子どもに教える勝負でした。第七回は子どもに使う言葉についてです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
