
松山奇談 八百八狸Ⅵ
第六席
さて、国表では何かと騒がしい事が起りました。
御出入り町人の山内源内はすでに領分を追放され、また、伊豫紙を半分取上げる事に就いても一揆が起こりました。
今はそれも静まって穏やかなようですが、どうもまだスッキリしません。
大道寺矢柄之助という城代家老は、
(悪人は誰か。見破って安泰としたい)
と、思ったので、ある日殿様に会って、
「恐れながら御前、御身体の勝れない時にこの様な事を申し上げるのは、誠に恐れ入りますが、手前近頃、健忘という病に侵されまして、承りし事を忘れがちなって参りました。それ故、大役を勤め兼ねますので、どうか病気養生中という事で御役御免を願いたく存知ます」
「そうか、それはいかんな。願い通り病気養生、御役御免差し許す。緩々養生いたせ」
「有難き仕合せ」
と、御礼を言って下りました。
これを聞いた水野吉右衛門という老臣は、
(はて、近頃領分が騒がしかったのは、ことによると城代家老の大道寺の仕業かもしれんぞ。聞けば健忘だというが、そんな様子は見受けられない。何か魂胆があって御暇を頂いたに違いない。いずれにしても大道寺の様子を見てみよう)
と思い、奥平久兵衛に頼みまして、
「御身体の調子が勝れぬ時に甚だ恐れ入りますが、陽気の加減か近頃耳が遠く成り、御用を聞くことが叶いません。養生中、御役御免を願いたく存じます」
と、御前へ申し上げてもらいました。
すると、御前も、
(近頃、老臣共はよく病気になりおる)
と、思いましたが、仕方がないのでお聞き届になりました。
城代家老の大道寺は、水野吉右衛門が自分を疑っているとは知りません。黒装束で御城下の在所をぶらぶらと歩いて領分の様子を伺っています。
ある日、夜の九つ(午前零時)頃に外手台町で、一軒の家の戸の隙間から明かりが漏れているのを見つけ、
(はて、この夜更けに明かりを付けるとは)
と、戸の隙間から覗いてみますと、それとは知らず、この家の主人と思われる四十格好の男が頻りに提灯の紋を描いており、側には女房がいます。
その提灯の紋がなんと、葵の御紋で御座いましたので、これを見た城代家老は、
(葵の御紋を描いているが、国表では葵の手丸提灯は作れないはず。これは妙だ)
と、再度葵の紋を描いているところを確認し、その夜は不審乍らも帰りました。

翌日も晩になると、邸を出てわざと田の畦道や畠の中を歩き、例の提灯屋の門口へ行き、トントン。
「ここを一寸開けてくれ」
「はい」
と女房が戸を開けてみますと、城代家老が供も連れず唯一人でおります。
「あー、女房や」
「はい」
「気の毒だが表の泥濘(ぬかるみ)に足を入れてしまった」
「はい」
「片足が汚れてしまったので、歩くのに気味が悪くって…。ちょっと足袋を洗ってくれんか」
「お安い御用で御座います。どうぞ中へお入り下さい」
「許せ…。表を通ればよいのに畦道を通ったものだから。とんだお世話をかけるな」
「どういたしまして。お前さん、御城内の旦那様が御出ですよ」
「これは御出でなさいまし、こんなお見苦しい所にようこそ」
「いや、構わん」
といって、足袋を脱ぎ女房に渡します。
「では、これを洗いますね」
「いや、気の毒千万だ」
亭主もお侍なので奥に通しまして、お茶を出してもてなします。
大道寺がお茶を飲みながら、家の中の様子を見ていると、風呂敷包みが見えたので、
「お前の名は何と申す」
「へい、巳之助と申します提灯屋で御座います」
「巳之助か。この中には大層いい提灯が入っているのだろうな」
「ヘイ、それは御誂え物で御座います」
「どれどれ」
と、大道寺が手を伸ばして箱を引き寄せようとしますと、吃驚(きっきょう)した巳之助は手を押えようとしましす。
大道寺は少しも構わず引っぱりまして、風呂敷をほどき、箱の中から取り出した提灯を眺めまして、
「うん、これは良い提灯だ。夕べ出来上がったようなので、見に来たのだ」
といいますと、巳之助は青くなって震えています。
「巳之助、これは誰が誂(あつら)えたのだ」
「へい、誠に恐れ入ります」
「いや、恐れ入る、では分らん。国表では葵の紋の手丸提灯は作れないはず。もし必要なら、江戸表で作ったものを、籠長持ちに入れて送ってもらうようになっているはず。どういう訳で作った。提灯屋が稼業ならば、葵の紋の提灯を国で作る事は禁止されている事は知っているのだろう」
「どうも恐れ入りまして御座います」
「いや、恐れ入る、ばかりでは分らん。これは決して吟味ではない。ただ、儂が尋ねているのだ」
と、いいますが、これではやはり吟味と同じでございます。
「一体全体、これを幾らで作るのだ」
「左様で、一と張り百
「百疋(ひき)で作ります」
「百疋か…高いな。江戸表だと一張り三匁(もん)五分だ。それを一と張り百疋とは破格ではないか。見れば十張りしかない、十張りだと僅かに二両二分にしかならん。それで咎められては詰まらんだろう。ただ、それも承知の上での事だろうが。何者に頼まれた。言え」

「へい、恐れ入ります…」
すると、女房が、
「何かと御勘弁下さいまし」
と、詫びました。
「いや、決して咎めているのではない。唯、頼んだ者を尋ねているのだ」
「これはその…、平松為三郎様が先日お出でに成りまして、『江戸表から送られる際に、籠長持ちの中で十張り程鼠に喰い破られて役に立たなくなった。このままでは係の役人の落ち度になってしまうので、少しでも早く作ってくれ』と、見本を一張り御持ちになりました。そこで私も下手ながら、江戸表の職人が作ったように紋も入れまして御座います」
「うん…。よし分かった。その方はこの提灯を持って、儂(わし)と共に参れ。決して心配致すな。これこれ女房や」
「はい」
「その方も一緒に行ってくれんか。よく戸締りをして盗賊の入らんように致せよ」
「はい、恐れ入ります」
という事で、城代家老は両人を連れて帰りましたが、
(これは調査のよい材料になる)
と、思っての事でございます。
期しくも同じ夜の事でございますが、悪人が滅びる時はこのようなもので、水野吉右衛門は、
(脅かして御用金なぞを何して歩く輩がある)
という噂を聞いたので、そのような者は取り押えてやろうと、近頃、夜分になると葵の紋の付いた提灯を堤まして、御城下で町人などが通る場所をブラブラと歩いていました。
御城下の中頃にある高札の前まで来た時、一人の男が一匹の犬と口を利いています。よく見ますと、一人の仲間(ちゅうげん)が小間物店を開いていて、そこで犬が食べています。汚い話です。
「コー、俺はな、今日は十両儲かった。明日も二十両になるはずだ。もっと旨い物を喰って、お前にも御馳走してやるからな」
「ワンワン」
「畜生、そうかそうか。大金を稼いでお前にも御馳走してやる」

「これ仲間、一緒に来い」
と言われ、突然襟髪を掴まれまして動けない。犬は驚いて逃げて行きます。
「その方、誰の仲間だ。名は何という」
「え‐っと」
といって、振り向いて見ると、黒ずくめで頭巾を被っています。
「これは旦那、驚かしちゃいけねえぜ」
「いや、驚かしはせん。その方、今日は十両になった。明日は二十両になる身だ、と言ってたな」
「へい」
といって、見ますと水野吉右衛門です。
「これは水野様。この頃貴方は耳が悪くになったとお聞きしましたが、よく聞こえましたね」
「左様、時々は聞えるのだ」
「都合のいい事もあったもんだ。私は平松為三郎様の仲間で源平といいます。平松様には長い事御奉公をしておりますが、下女と通じまして、御手打ち寸前に御老母様にお助け頂き、唯今は夫婦になっています。
今度、御老母様が御病気になられまして、妻が手伝いに上がっておりますと、病気も大分良くなったので、世話になった、といって一両下さいました。
それで昨晩、御礼に上がりまして、何気なく庭に入りますと、離れ座敷に十四五人の人が集まって話をしていましたが、何分遠くてはっきりは分りませんでしたが、『若殿をどうする』とかは、処々分かりました。
すると、御主人が私のいるのを見付け、『己は何か聞いたか』というので、『いえ、何も伺っていません』というと、『ここにいたからには何か聞こえたに違いない』といわれますので、『へい、少しは聞えました』というと、突然長いのを引き抜いて私を斬ろうと致しました。その時、赤松金八様が『斬るのは不憫だから』といって助けて下さいまして、『この事は決して人に言うな』といわれ、二十両貰いました。
決して悪事で稼いだものでないので、どうか命だけは御助け下さい」
「そうか。然らば、命は助けてやろう。ただし、儂と一緒に来い」
といって、引っ張っていかれました。
それから徐々に吟味は進みますが、一夜のうちに同様の事が二カ所であるというのは、悪人が滅びる兆候なのでございましょう。
それはさて置き、話は前に遡りますが、あの山内源内の手代の新助は主人を救おうと、江戸表の元老、水野勘解由に代官の横領を訴える為に、松山を出発し、途中、伊勢四日市の茶店でお茶を飲んでいると、三十一ニになる粋な婦人が一人で入って来て、

「御免なさい」
「どうぞお掛けなさいまし」
「あの、済みませんが、盥(たらい)にお水を戴けます」
「はいはい」
と、茶屋の婆さんが水を汲んでくると、婦人は顔を洗い身体を拭いた後、お茶を飲みながら、
「あの、伊豫の松山に行きたいのですが、どのように行けばよろしいのでしょう」
「左様で御座いますか。伊豫といえば四国で御座いますね。船で行くしかありませんね」
「そうですか。何でも大坂から船で行くのだそうですが、どこから船に乗ったものか、皆目分からず、本当に困っています」
と、話してるのを聞きまして、茶を飲んでいた新助が、
(この女は芸人の女房みたいだが、唯一人で松山へ行くのは妙だ。亭主にでも会いに行くのだろうか)
と、思いましたので、
「もしお内儀さん。私がこんな話をすると、人の懐を狙う泥棒じゃぁないかと、思うかも知れませんが、決してそんな者ではありません。今聞けば、お前さんは伊豫の松山に行くと言う事だが…」
「はい、左様で御座います。初めて行くので、行き方が分らず困っております」
「松山はね。大坂から船で三津浜という所へ行くんだ。尤も他にも行く方法は幾らかあるが…」
「はい、有難う御座います。貴方、よく御存知でございますねえ」
「私は松山の者だ」
「あらまあ、左様で御座いますか。貴方、松山の人なら一緒に連れていって下さいな」
といわれましたが、新助は主人の為に江戸へ行かなければならず、また、
(こんな女を連れて、国へは帰れない)
と思いましたが、
(待てよ、このまま江戸に行ったとしても、悪事を暴くのは難しいだろうと、虫が知らせてくる。どうも様子が変だ)
と、思い返しまして、
「お前さんは何で松山に行くんだい」
「はい、他でもありません。私は中村梅三郎という役者の妻で御座います。一昨年、私達は弟子を連れて興行に出ましたが、途中で私は名古屋の自宅に戻りました。それから暫くはお金を送ってくれましたが、近頃では、さっぱり送ってくれません。手紙を出そうにも、何処にいるのか、これもさっぱり分らず、その儘になっています。
それが貴方、この間、弟子の梅吉が帰って来まして、『親方は伊豫の松山でお殿様の妾のおこんさんという御方に大層入れ込みまして、男妾同様になっています』と、言います。
それは役者ですから、御大名様の御妾に惚れられるのはいいのですよ。送ってくれるものさえ送れば、私は嫉妬なんぞは致しません。ただ、送る物も送らないで浮気をされたのでは堪りません。それで、(よしそれなら、松山に行って梅さんとそのお妾を一緒に並べておいて、文句の一つも言ってやろう)と思ったんです。
それに貴方。その妾は殿様を毒殺して、自分が生んだ子を十五万石の跡継ぎにしようと、悪人供と相談していたそうですよ。それで松山に着いたら二人の前で、全部ぶちまけてやろうと思っているんです。
本当に人の亭主を玩具にして、その上殿様を殺して自分の子を跡継ぎにしようなど、呆れるじゃぁありませんか。ねえ、そうでしょう」
と、べらべらと喋り立てているのを聞きながら、新助は腹の中で、
(俺がこれから江戸へ行って、御家老様に悪人供の企みを訴えてやる、と思っていたが、この女の話からすると、妾のおこんの悪事は、俺も女房から聞いたことがある。これは悪人を取り押さえる証拠になるかも知れない。それなら一緒に国へ行こう)
と、思案しました。
「おかみさん、私はその松山で御用達をしている山内源内の手代で新助と申します。私には女房も子供もあって、今は少し理由があって、道後の温泉の花月という女房の親元に預けていますが、お前さんが今話をされた梅三郎さんや妾のおこんさんは出養生ということで、その花月で度々逢引きをしているそうです。私が一緒に行って女房のお梅に頼べば、屹度梅さんに会わせてくれる。そうしようじゃぁないか」
「はい、そうなれば有難いです」
「それじゃ、そうしよう」
と、いうので同道することになりました。

さて、道中は特にお話するようなこともなく、大坂の川口から便船にて三津浜に着きました。そこから松山の城下へは一里(三・九三㌖)といいますが、その実は三十町(三・二七㌖)位しかありません。
三津浜の三桝屋という旅籠に宿を取りますと、そこのご主人が挨拶に出ました。
「これはよくいらしゃいました」
「三枡屋さん、少々お前さんにお願があるのだが」
「はい、何で御座いましょう。大層別嬪をお連れですが、お妾で御座いますか」
「そんな訳ないじゃないか。実はこういう事さ」
と、三枡屋の耳に口を寄せて小声で囁き、
「そういう訳で、花月へやりたいのだが」
「はい畏まりました。それじゃぁ明日、籠を用意しましょう」
「どうか内密にお願いしますよ」
主人が承知して出て行くと、新助はおしずに手紙を渡し、
「さあ、おしずさん、明日この手紙をもって花月へ行けば、私の女房が屹度梅さんに会わせてくれるからね。もしそれに、三日も四日も掛ったなら、知らしておくんなさい」
「色々、御親切に有難うございます」
と、おしずはその晩は三桝屋に泊まりまして、翌日籠に乗って道後の温泉へ行きました。
花月に着き、下女に手紙を渡しますと、奥にいたお梅に届けてくれ、お梅がそれを開きますと、夫からのもので、『中村梅三郎の女房がこれこれこういう理由で梅さんに会いたいというので連れてきたが、都合して会わしてやってくれ。御上に訴える都合もあるので』と、書いています。
何はともあれ、夫からの頼み状なので直ぐにおしずを奥に通しますと、おしずが新助に色々お世話になった事の礼をいいますと、
「いえ、その御挨拶には及びません。幸い今日は梅さんとおこんさんが奥の座敷に来ておりますので、私が都合して会わせてあげますね」
「それはいい具合ですこと、梅さんに会い、いう事だけ言えば、直ぐに三津浜に帰ろうと思っています。あれ、あの通り籠を待たせております」
「それはよう御座います。あの、おこんさんの御座敷へはどんな用があっても、私の以外は入れられません。私のつもりでお入り下さい」
「有難う御座います」
と、悦んで待っていると、奥座敷で手がなり、お梅が座敷へ行きますと、
「あの、すみませんがお酒をくださいな」
「畏まりました」
といって、お梅は元の座敷に来まして、
「さあ、おしずさん早くお行きなさい」
というので、おしずがその座敷の唐紙を開けて入りますと、梅三郎とおこんが差し向えでお酒を飲んでいます。

おこんには見慣れない粋な年増です。梅三郎が、
「おや、お前は…」
「お前はじゃねえゃ。あのぅ、おこんさんというのは貴女ですか。私はその男の女房で、しずと申します。夫が色々とお世話になっている様で、有難う存じます。おい、梅さん」
「何だ。どうして来た」
「用もあれば、来ようじゃぁないか」
「この座敷にはお梅さんの他は入らないように頼んで置いたはずだが、どうやってここに来た」
「梅さん、これはお前さんの女房かい」
「面目ない。女房だ」
「梅さん、こうなったら私も未練な事は言わない。だがよく考えておくれ。あんたは十五万石の御大名様のお妾に可愛がられて幸せだろうが、私は名古屋であんたが金を送らないので食べるのにも困っているんだよ。どうせ芸人の女房だ。亭主が浮気をしようと、ヤキモチも焼けねえで、我慢に我慢をしてきたが、送るものも送らないで、あんたばかりが贅沢をしているのは、いくら何でも冥利(みょうり)が悪いだろう。さあ、三百両出しておくれ。私も一旦愛想をつかされた身だ、未練がましく玉椿の八千代(長くも続くの意)迄も添い遂げようとは思わないや。その金で身体の始末をつけるからさ…。 もし、おこんさん、可愛い亭主だが熨斗(のし)を付けてお前さんにあげるから、三百両をここに並べておくんなさいな。聞けば殿様を押込めるとか、江戸にいる若殿様を毒殺して、あなたの腹から出た要之助さんを跡継ぎにしようとか、しているというじゃないか。梅さん、あんたも一時の栄華に迷って、首を切られないように用心おしな。本当に三つ指ずくめのお部屋様が役者と色をなして、殿様を押込め、十五万石の御身の上を自由にしようなどとは、大層な御腕前だこと」
「しっ…。静かにしろ」
「何だえ。大弊(大祓の時に用いる大串に付けた、ぬさ)を出したら悪いのかへ。人に言われて悪いような事を何故するよ。さあ、三百両並べておくれ。くれないのならば、御城下を叫んで歩くよ」
「まあ待て…。おこんさんすまないが、どうか三百両を女房にやって下さい」
と頼むと、おこんも仕方がなく手を鳴らして、お梅を呼び、
「お前に、無暗に人を入れないよう、頼んで置いたよ、とんだ者を入れてくれたじゃぁないか」
「どなたです。少しも存知ませんが…」
「そう、仕様がない。今、手紙を書くので、それを中澤村の親爺に届けておくんなさい。そうしてすぐ来るように伝えて」
と、手紙を書いて渡しました。
直ぐに中澤村へ届けますと、万太夫は自分の娘からの手紙なので、何事と、見てみますと、
(急に三百両がいるようになったので、直ぐに花月に持って来てほしい) という文面。
兎にも角にも、と仕度をして金を懐に入れますと、花月へ向いました。
「実はお親父ちゃん、すまないがこれこれの訳で、金をおしずさんにやっておくれ」
という事で、普通なら娘の不始末は意見をするところを、何分娘のお陰で代官に出世出来たので、仕方がなく三百両をおしずに渡しました。
「流石は十五万石のお妾様だ。はい、確かに三百両受取りましたよ。おい梅さん、私はねえこのお金さえあれば、立派な亭主をもって遊んで暮らすよ。手切れ金さえ取ればお前さんとは赤の他人さ。とんだお楽しみの処をお邪魔したね。ほな、さようなら」
といって、三百両を懐に入れて座敷を出て行くと、おこんと梅三郎は顔を見合せていましたが、やがて、おこんが、
「梅さん少し待ってておくれ」
といって、父の万太夫を連れて他の座敷に行きますと、一人取り残された梅三郎は、腕を組み、
(先刻、おしずの言ったように、もし悪事が露見したら、どうせ打ち首は逃れられない。それを考えると、お妾に可愛がられてもちっとも有難くねえ。なにかいい方法はないものか)
と、考えていると、
「梅さん、逃げるなら今だよ」 と、入って来たのは女房のおしず、
「手前、まだ帰らなかったか」
「次の間でお前の様子を見ていたんだよ。三百両があれば、これから先は安泰だ。籠も来ているので直ぐにお逃げよ」
「それじゃ逃げよう」
と、仕度もそこそこに、花月の娘に言葉短に礼をいい、街道は追手が掛るので、間道を三ヶ所迂回して、籠で逃げました。
一方、万太夫は道を急ぎ、鍵の手の松並木に先廻りして、悪事を知られたからには生かしておく訳にはいかないと、鉄砲を持ち待ち構えました。
おこんが厠から座敷に戻ってみますと、梅三郎おらず、八方探しても見つかりません。
(ひょっとすると、三百両持って女房と逃げたかもしれない)
と、思いまして、
「まだ遠くへは行くまいから、大急ぎで後を追い駆けて」
といって、宿の籠に乗りました。
陽はもうどっぷりと暮れています。
籠が鍵の手の松並木まで来た時、
(ズドーン)
と、一発の弾丸が籠の中に。

大事な娘を、梅三郎の妻と思って、鉄砲を放ったのは彼の万太夫で御座います。
不憫や、おこんは唯一発の下に落命致して御座います。
悪人への天罰は恐ろしいものです。
万太夫が一発放つと同時に、その鉄砲を横取りして逃げた男がいまして、万太夫が、
「あっ」
と、驚き、
「待て」
と、いったものの、待つはずもなく横っ飛びに逃げてしまいました。
万太夫は、
(仕留めたはずだ)
と、籠の脇に行ってみますと、駕籠かきはとうに逃げていません。
籠の垂を上げて見ますと、
「あっ、これは…」
娘のおこん、言葉もなく唯茫然とするばかりです。
さて、『鉄砲を取ったのは誰か』といいますと、元老の水野吉右衛門の家来、市助で御座います。
市助が直ぐにこの事を主人に報告しました。
吉右衛門が鉄砲を手に取ってみると、『中澤村万六』と掘り付けています。このことから、
(中澤村の代官、万太夫に相違ない)
と思い、直ちにこの事を江戸表の水野勘解由に知らせる為の手紙を書き、市助を遣わしたのでございます。
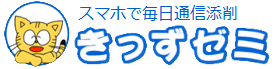
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
