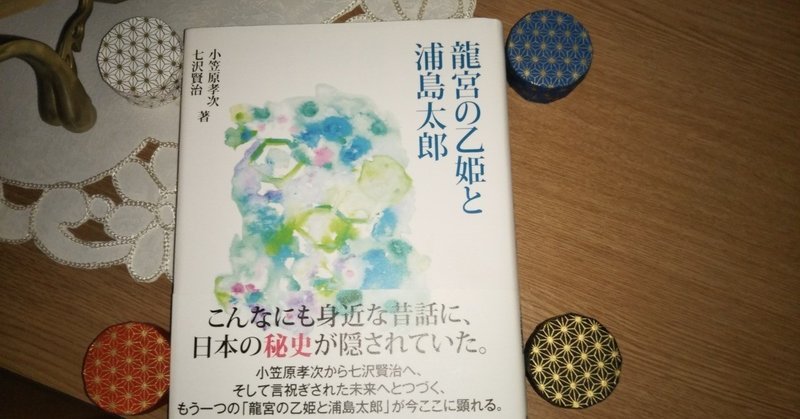
★『龍宮の乙姫と浦島太郎』を紹介します。
山腰明將氏、小笠原孝次氏、七沢賢治氏とバトンタッチされた言霊学の到達点。 龍宮乙姬、浦島太郎、そして玉手箱といった三つのキーワードをテーマに、言霊学的見地から昔話に隠された日本の秘史に関する論述がなされる。詳細は以下をご覧いただきたいが、行間の響きから終始一貫して聞こえるのは、「日本語五十音の珠玉的価値」と、「日本民族の使命の自覚」への促しである。
帯文
こんなにも身近な昔話に、日本の秘史が隠されていた。小笠原孝次から七沢賢治へ、そして言祝ぎされた未来へとつづく、もう一つの「龍宮の乙姫と浦島太郎」が今ここに顕れる。
玉手箱の中身とは一体何だったのか。箱を開けたら、なぜ浦島太郎は白髪の老人になったのか。…つまり、穿った見方をすれば、時間を超えるための訓練によりその解が得られるという、高度な仕掛けが物語に埋め込まれているということである。それを小笠原先生は、文中に言霊が埋め込まれていると表現しているが、現代の作法で文字通り解釈すると、あとは本人の努力次第ということになるだろう。それは、「 浦島を超えてみよ」という公案を解くことでもある。(第二部本文より)
【小笠原孝次氏】 1★「言の葉の誠の道」について
●一言で申せば、「言の葉の誠の道」とは、皇典古事記の内容であります。
元来、申すまでもなく人間の使う言葉というものは、真理(真事)をあらわすものでありますが、しかし言葉を使って真実をあらわす表わし方にも色々と国々によって違いがありまして、ヨーロッパ風の哲学などという方法においては、言葉を道具、あるいは材料として概念というものを組み立てて、その中に真理を捕えようとします。この場合、言葉というものは、結局、概念構成の素材としての役目しか持っておりません。
しかしこの概念というものは、たとえば桶を作るようなものでありまして、真実のまわりに垣根を結びつけて、この中に真理が在るのだぞ、というところまでしか現わす事が出来ないもののように思われます。これと同じ目的のために支那人は文字というものを使っておりまして、幾何学的な象形の中に理を捕えようとしております。
しかし私共の祖先であられる皇祖皇宗の神人達や臣下の仙人達は、天や地や人生についてのすべての真理をあらわすに、西洋的な概念は用いませんでした。また太古にあっては支那的な象形文字さえも使いませんでした。
たとえば古事記の中に支那文字を使って呪文的に書かれてあります天之御中主とか、高御座巣日·神産巣日とか、天照大御神などというような、極めて重大な、しかも簡単明瞭な心理実在をあらわすためには、ウとかアとかワとか、あるいはスというような単音をもってしまいました。
こうした音が宇宙に一つ一つ現われて来ます経過を呪文的に、読者が銘々の思索によっておのずから覚えるように説明してありますのが、古事記の冒頭、天之御中主神以下、第五十番目の火之迦具突智神までの記述であります。
このようにして、宇宙の根本の構成要素たるべき真理の内容とそれを音にして発音するところの人間の性情とがぴたりと一致したところの、最も徹底した明瞭な音が、きっちり五十あります。
この五十音こそ、私共が日常使っております日本語の基になる音でありまして、これを五十神(石上)とも言いますし、またこの五十の要素の完全無欠な組立てを五十鈴宮とも申し、あるいは敷島(磯城島·五十城島)の国とも申します。
この五十の内容の一つ一つには、神代から既に深い哲理と体験が籠められてありまして、永久に動かす事の出来ない意義がもとから定まっておるのですから、この基本の言葉をさえ使って行けば、自然界や人類文化の森羅万象を帰納する場合にも、あるいは演繹する場合にも、いかほど複雑な事柄でも少しも曖昧なところなく、正確に処理する事が出来るのであります。
「言の葉の誠の道」と申すのは、こうした日本語の意義とその使い方のことを言うのでありまして、それを三十一文字の和歌を作る作り方だろうくらいに簡単に考えているようでは、いつまで経っても国語の原則、すなわち国体の本義ということは判ろうはずはありません。
皇典古事記は、この「言の葉の誠の道についての欽定の教科書であるのであります。
2★高御産巣日神と神産巣日神
●生命の樹のことを、日本語では「高木の神」と申します。この神名の元の形を「高御産巣日神」と言いまして、これはここから宇宙のすべての事、すなわち言(事)葉があらわれて参りますところの根本の気(木)のことでありまして、この気が事としてあらわれ尽して、物として纏った状態を「神産巣日神」と申します。
宇宙のすべての事、すなわち言葉は、この高御産巣日と神産巣日の間に生い茂っているのであります。言葉の道では前者をアイウエオであらわし、後者をワヰウヱヲであらわします。これはいわゆる母音と半母音でありまして、この両方の間に生まれた葉、すなわち言葉が、カサタナハマヤラの八行四十個の子音であるのであります。
3★支那と日本に関して
●以上は、ほんの数例に過ぎませんが、こうした例を探し出して調べますと、数限りなく出て参ります。たとえば山海経や楚辞にある太陽と扶桑木の話とか、兎が洪水を治めた話とか、義和と嫦娥の話とか、淮南子にある共工と顓頊の争いの話とか、その他色々途方もない神話的な伝説の断片が幾らでも有るのです。
これらの支那神話に関して、漢学者達の解釈はどんなものであるのか調べた事はありませんが、こうした話の一つ一つを、この宇宙に事があらわれ、それが言葉として生まれ出てその言葉が纏って完全な思想になって行く筋道を説くところの、我が言の葉の誠の道のどこかに当て嵌めて考えて見ますと、「は
はあ、ここのところをそんな工合にいっているのだな」などと、浅学な私共にもよく肯づける事が多々あります。そこで太古の支那思想と我が日本の道とは、実は全くおなじものではなかったろうか、という疑いを深くせざるを得なくなるのであります。
しかしそれにしても遺憾なことは、支那神話はいずれも断片的なことでありまして、宇宙のアルファからオメガまでを一貫して説いているものがありません。それを哲学的に纏めたものに易経がありますが、「易は象なり、範は数なり」でありまして、易の内容は象と数であります。数の道は説いても言の葉の道は説いてありません。支那の太古の聖人や芸術家達は、象形文字や祭祀の方法や神話は説きましたが、言葉は教えなかったようです。
4★帝紀・旧辞
申すまでもなく、我が皇典古事記の内容はその序文に明示されてあります如く、「帝皇の日継及び先代の旧辞」であります。これを簡略して帝紀および本辞(旧辞)とも申します。帝皇の日継という日継ぎは、霊継ぎでありまして、それは、我が皇祖皇宗が言(霊・言霊)すなわち、道を継承して発展させて行かれた経過を述べました現実の歴史のことであります。本辞(旧辞)とは、もとの言葉、または言葉のもとのこと、すなわちその原理原則のこと、そこからすべての日本文明が発祥しましたところの根本的な道(言葉)のことであります。
このように日本の本辞と帝紀とは、国体原理の言わば哲学的内容とその実現過程とでももうすべきものでありまして、両者を分離して考えることの出来ないものであります。
そしてこの両者が不可分に、しかも少しの矛盾もなく発展し運行して行きすところに、我が皇運が世界無比なる所以が存しますもので、この間の消息をはっきりと認識した上でない限り他のいかなる外的な学問の力を籍りても、絶対に我が日本の歴史が釈けるものではありません。
さて、こうした本来の皇運発展の立場に立って日本の古代史を調べて参りますと、それはおおよそ次のような段階に分けて考える事が出来ます。
まず、古事記冒頭に記してあります太初の「天之御中主神」が生りませる事は、人類が仏教のいわゆる梵(梵天王)を自覚した時期を示してあるものと考えられます。この生りませるというナリに他の文字を当てますと、鳴・化・成・熟という色々な意義が出て参りますが、殊にその中の鳴の字を取って考えますと、宇宙に音が鳴り初めたことで、これを人類の自覚の内容として考えますと、宇宙太初の消息を音として、言として、自覚し発声した事を示したものと考えられます。
こうして天之御中主神以下、次々に鳴りませる神の数は合計十七神ありまして、この神々を音(言・事)としてあらわすと、いかなる言葉になりますか。
神名(仮名)であるところの神の名前をその意義と字義とから釈いて参りますと、本当の名すなわち真名があらわれて参ります。
この十七の真名はいわゆる父韻と母音とでありまして、これを仏教的に宇宙の事の因と縁とに考えられます。因縁が結ばれますと果が生じます。この果を生むところを、古事記には次のように記してあります。
ここに天ツ神諸の命を以て、
伊邪那岐命伊邪那美命二柱の神に、
このくりかためな漂へる國を
修理固成せとことよさしたまひき。
この「天ツ神諸の命」と申す命とは御言のことでありまして、十七の因縁、すなわち父母音を結び合わせますと、子音が生まれます。この子音が前述しました「大事忍男神」より「火之迦具土神」までの三十二神でありまして、天之御中主神より通算致しますと合計五十音を得るのであります。
この五十音は、あらゆる宇宙の事を言葉として自覚いたします種子なりますものでありまして、このように考えて参りますと、この岐美二神の創造開始の時を、歴史的に見ますれば日本肇国の時と申すことが出来ます。
ついで伊邪那岐大神は、宇宙の海という創造世界の真中においての禊祓という方法によって、右の五十の言の一つ一つにその位置と時置と処置とを決定致しました。これは宇宙の事の時処位について、どの音を当てて使うかということの決定でありまして、言(事)の位取りを自覚するその自覚体、すなわち理性を天照大御神と申し上げ、その自覚体の姿を文字によって写し出しましたところの言葉の鏡を月読尊と申し上げ、更に流動する時間の変化に応じて言葉をいかに使うか、その使い方を須佐之男尊と申し上げます。
これを「三貴子の出生」と言いますが,この三貴子の出生ということによって、宇宙の事の内容のすべてが、初めて人間の自覚内容すなわち言葉として確実に把握されたのでありました。
この時のことを歴史的に見ますれば、日本立国の時と申すことが出来ましょう。立とは立論、立憲の立であります。日本訓みにしますと断・横刀となります。タツとは龍宮の説明でお話いたしました如く、事の性をはっきり裁断し、それを連ねて新しい物を創造する方針を決定することであります。科学者がしきりに暗中模索しているような、何か知らぬ大自然界の創造の原理という意味での龍宮城ならばいざ知らず、人類が宇宙の事を言として自覚する自覚内容という意味における言葉の全き組織体が浦島説話の龍宮城でありますならば、この龍宮城は、まさに歴史上この三貴子の出生の刹那にその建築が完成されたものと言わねばなりません。
●本辞(道)と帝紀(歴史)がぴったり一つになっている我が日本に生まれた事を、私共はこの上なく幸福な事と思わずにはいられません。
5★儒仏二教の渡来
当時の世界に情勢を見ますに、隣邦支那に老子、孔子が出現して先王の道を復興し、彼等の時代と、そして支那民族とに適合するように学問的あるいは道徳的に説き初めましたのは、既に我が神武朝の頃ほいでありました。
また印度の皇子悉達多が文字の道を説きましたのも、略同じ頃であります。それ以来彼の土において、精密な理論的発展を重ねました儒仏二教は、朝鮮を経て、逐次我が国に渡来し、次第に我が朝野の思想界に浸潤して参りまして、神武建国後五百年、人皇十代崇神天皇の御宇前後に至って、彼我の精神的交通は最高潮に達したものではなかろうかと考えられます。
元来朝廷に仕へ奉る日本の文武百官はこれを神田(御手代)と申しまして
思金ノ神は、
前事を取り持ちて、
まをしたまへ
(古事記)
とあります如くすべて、天皇と人民との間の仲取持(中臣)の役目でありまして、天皇の大御心すなわち御稜威の原理内容を、あるいは風俗習慣に、あるいは道徳法律に、あるいは政治経済に実現し応用して、もって皇運の発展を扶翼し奉るべきものであります。
しかるに、当時印度や支那から渡来しました新奇にして精密な学問思想を真っ先に取り入れて、それに心酔しました者は、この朝廷内部の百官達、今の言葉で申しますれば指導階級の人達であったのであります。それは、我が国本来の道であるところの言の葉の誠の道は、非常に深奥な鋭敏な理性直観を必要といたしまして、下根の者にとっては極めて難解なものであるのに反して、これら印度や支那の思想は、悟性にまず訴えて学べるように、よく理論化されたものであったからでありましょう。
このようにして指導者階級が儒仏二教に凝り初めますと、上の好む所、下これより甚だしでありまして、庶民階級もまた儒仏二教でなければ夜が明けない有様となりました。このようにして二教は遂に澎湃として、やがて我が朝野を風靡し席巻するようになったのであります。
神武維新の後、数百年間のこの日本を理解するためには、近く明治維新以後において起こりました事態がその好個の例を示してくれます。幕末に興りました国学に連れて、勤皇思想による維新の大業は完成されたのでありましたが、この明治の復古思想に対立するものとして、既に維新前後より陸続として輸入されましたのは、欧米のキリスト教思想と自然科学的唯物論思想であります。
民衆は事の当否を問わず常に新奇を好むものでありまして、この民衆の好奇心あるいは好学心のために、維新の大業は、その初め西郷・玉松・大国・副島などの先学者達が意図し計画しました日本的な道義国家建設の方針は、漸次に歪曲を受けまして、あるいは神衹官と太政官の地位の転倒をみましたり、やがては議会が開催されて民意が尊重されるようになって、今日みるところの民主主義、自由主義国家としての日本の姿となったのでありました。
6★同床共殿廃止の背景
方士徐福が、蓬莱の島に不老の仙丹を獲るべく、秦朝の強大な国力を背景として来朝しましたのは、孝霊天皇の二十二年(紀元四四二年)のことと伝えられております。
この年は崇神朝における同床共殿廃止の時を遡ること百二十二年、それは、日本国内において、儒教仏教ないし道家などの思想が漸く盛んになろうとした時代でありまして、国内の民心が漸く帰趨を失い、やがてまさに神鏡が朝廷の実際の祭政機械から秘められようとする間際のことであったのであります。
徐福はこの時不老不死の薬として、まさに秘められんとしつつある国の秘宝を要求に来た事と考えられるのであります。しかもその背後には、秦の国力が控えております事を考え合わせますと、崇神朝における同床共殿の廃止が、この事と無関係なものであるとは考える事が出来なくなります。
当時の支那人は、日本の国体に関しては、今日の日本人など比較にならぬほど深き理解を有していたはずでありましょう。それは支那にあって、先王の道を求めてその淵源を索ねますと、支那に既に絶えて無くなったその道の根源がどこに存するか、おのずから判って参るものであるのです。
ですから始皇帝もひとかたならぬ渇仰と焦燥をもって、それを獲ようと苦心惨憺したのでしょう。崇神朝に近き数世紀の間は、このような意味において東洋の国際関係に非常な微妙な、しかも外的には顕われずとも、内的には非常に深刻な隠れた事情が伏在していた時代であった事が推測出来るのであります。
あるいはこのような目的をもって外国より日本へ渡来した者は、徐福ただ一人のみであると言えぬかも知れません。ですから同床共殿廃止の原因には、対東洋諸国との国際的関係が必ず潜在していたものとも言うことが出来るのであります。
7★言葉と文字
●文字もって道を示した範疇あるいは洪範は言葉の鏡であります。ミカガミすなわち神鏡、甕神です。浦島太郎が玉手箱を開いたと言うことは、洪範の文字を読んだと言うことほどの意味でしょう。読んで、そしてそれに自己の姿を写して見るのです。
しかし洪範は鏡でありますから、そこに写る姿は映像であって、実在するものではありません。写った姿は真如の影でありまして、真実ではありません。
言葉の鏡によって実在を把握するには、もう一度自己に反照しなければなりません。これが真実在としての天照大神と真如の月の影としての月読尊の関係であります。
日本は、先述の如く東海の姫氏国であります。また「女ならでは夜の明けぬ国」という諺も伝わっております。
姫は日女(日霊女)でありまして、すなわち天照大神の御事です。天照大神は女神であられます。「女ならでは」というオンナを御名と書きましたら判り易くなりましょう。御名は音名です、音(言葉)を汝として対象化したもの、すなわち文字のことです。この故に「そもじ」(其文字)と言えば女の代名詞です。
この女が音名(文字)となって現れて来る以前のものが男です。オトコを音子と書きましたら、音の子、すなわち言葉であることが判りましょう。天照大神は女の体で男の魂を持っていられ、高天原における最高の神であられます。
しかるに天孫降臨以後になりますと、歴史の舞台は高天原という理念の世界のみではなく、葦原中国という現実界になりますから、また関係が発展変化して参ります。天照大神は御自身の本質を御鏡にして天孫にお授けになりました。
御鏡は女(音名,洪範)です。天孫は男子をもって正系とする天皇であられます。
すなわち天皇は男の体で女の魂を持たれたお方でいらっしゃいます。男子であられる天皇は、女の魂である生命の道の鏡を、ご自身の倒魂として万世一系に伝えていらっしゃいます。けれども文字の鏡は仏教でいうところの涅槃でありまして、死んだものです。そのままにして置いたなら、永久に寂滅為薬の眠りを続けるだけのものです。天照大神が岩戸隠れになっている状態がすなわちこの寂滅為薬の姿です。
秘め国(神秘国)とは国体の洪範が眠っていて活動しない国のことです。しからば、いかようしたならば秘め国が秘め国でなくなるか、天照大神に岩戸から出て頂いて、日本のみならず世界中を、生命の智慧と愛によって、明るく温かく照らし育んで頂くためにはどうしたらよろしいか。そのためには眠っている御鏡を蘇返えらせればよろしいのです。ヨミガエルは読み返るです。読んで自己に反照し自覚し実行することです
高天原の洪範か現人神によって読み返えらされた、その自覚の具体的な把持者が天皇であらせられます。神の言葉としてのキリストの再生を、キリスト教徒は何と考えていることでありましょうか。この天照大神と天皇との哲学的関係をもって申し上げれば、法身と報身との関係となりましょう。
8★生命の樹と智慧の樹
●生命の樹の道とは事(言 ー高皇産霊)の道です。智慧の樹の果とは物(文字ー神皇産霊)です。生命の樹を隠して置いて、智慧の果だけで生命の道を覚れと命じたエホバの神すなわち西洋文明の創始者は、この上なく意地悪な神です、しかし、その意地悪な事はかえって無限の慈悲でもあるのです。アダムた楽園から追放したエホバの慈悲は、そのままに神鏡の同床共殿を廃された崇神天皇の大御心であられます。
【七沢賢治氏】
9★小笠原先生を偲んで
●さて、本書では、龍宮乙姬、浦島太郎、そして玉手箱といった三つのキーワードをテーマに、言霊学的見地から説明がなされている。つまり、龍宮は「音の飛ぶ宮」、乙姫は 「音秘」、浦島太郎は「秦朝からの使者」といった具合に。結論からいうと、秦の時代に浦島太郎= 徐福が、当時の日本皇室から不老長寿の元の秘宝、すなわち言霊を貰い受けに来たが、接待漬けにされて目的を果たせぬまま、玉手箱を後生大事に故郷に戻ったというのが、物語の裏に隠された史実ではなかろうかということである。
●当然のことながら、小笠原先生は戦前の科学のレベルで本書を書かれている。その中で精一杯の解釈を試みておられるが、それが現代の目から見てどうなのかを究明しなければ、せっかくの本書を現代に生きる人々のために役立てることはできない。先生はそれをよくわかっておられたが故に、その後の検証を私に任せたのだと思う。一見すると本書の解釈を上晝きしているように見えるが、独善的にただそれをしているわけではない。それが今は亡き師との約束であったからである。
●先生は、言霊そのもの、または言霊に纏わる伝承が科学で解明されることを強く望んでいた。逆に、それらが科学によって解明されるまでは、むやみに表に出さないよう釘を刺されていたぐらいである。それを考えると本書はまさに、然るべきタイミングで世に送り出されることになったといえよう。
10★情報と言葉 ●この情報とは一体何であろうか。情報が全ての根元にあるとすれば、この情報の正体を知り、それを自在に扱える人間がこの世を思うがまま操作できるといえないだろうか。だが、それは神事にも近い仕業である。果たして人間にそれができるのだろうかと疑問に思われても仕方ない。しかし、今から二千年以上も前にそれに気づいていた人物がいた。それが秦の始皇帝である。恐らく当時の中国に伝説が残っていたのだろう。それがギリシアから伝わったのか、元からあったのかは分からない。何れにしても始皇帝は、万里の長城を築いたように、設計図としての情報こそが全てを支配することを知っていたフシがある。そして、情報が言葉そのものでできていることを。
●情報とは何か、それを最も単純な姿として捉えれば、今ここで読者も目にしている言葉に他ならない。情報の最小単位とは 言葉であり、逆にいえば、言葉という最小単位から情報は作られていく。情報を支配する者が世界を支配するのであれば、情報の最小単位を掴んだ者が、疑いなくこの世の覇者となるであろう。しかし、その時点で覇者という 言葉は必要ないかもしれない。なぜなら、その時は、単なる空間の覇者ではなく、時空間そのものを創造する存在になっているからである。
だが、言葉ですら最小単位ではないと知ったらどうであろう。たとえば、「あ」や「か」といったそれぞれの一音一音は十分最小単位になりうると考えられるが、厳密にそうではない。更にその最小単位がある。それが言霊である。言葉そのものは当時の中国にもあった。しかし、言霊はなかった。言霊がなければこの世の創造はできないのである。不老不死とは時間を超えることを意味する。言葉は時間の壁を超えられないが、言霊は時間を超え空間を超える。それが物語の中で、浦島太郎の龍宮入りから白髪の老人になるまでのストーリーに表現されたのではないだろうか。
11★日本語五十音という言霊麻邇
●「a . i . u . e . o」という母音が五つの階層を示す。これに「K.S.T. N.H.M.Y.R」という父韻が位相性の概念として加わり、両者から子音が生まれる。それにより音図が完成し、この五十音のマトリクスが、人間が知覚する宇宙を創造していくことになるのである。
12★日本語五十音の珠玉的価値
●すると、日本に住む日本人よりも、むしろ日本を外側から見る立場にある人間の方が、日本の客観的な評価をするには適していることがわかる。しかも日本語を話すことのできない人物であれば尚更である。そのような観点から浦島太郎こと徐福を日本の側から改めて評価すると、現代的には亡命者としての側面も見え隠れする。別の見方をすれば、日本を母国としない亡命者だからこそ、日本人が気づかない日本の宝を、日本人の誰よりも高く評価できたのだろう。
同じく、それを守った当時の日本皇室もそれを知っていたことになる。つまり、日本語五十音の珠玉的価値である。おかしな言い方に聞こえるかもしれないが、その至宝を奪いに来たのが亡命者だったとすれば、それを守ったのも亡命者たる渡来人だったと見ることができるのである。亡命者という一言い方は適切ではないかもしれないが、生粋の日本人ではないという意味を込めて、敢えてそのような表現をさせていただく。
中国が秦の時代、日本は既に弥生時代に入っていた。神武天皇が弥生時代中期に即位して以降は、それ以前とは異なる勢いで大陸の文化も渡来人も入ってきたと考えられる。後の天武天皇のように、大陸から渡ってきた天皇が当時の皇室を守っていたと見てもおかしくない。天武天皇が言霊百神を内に秘めた古事記の編纂を命じたように、徐福を受け入れた時代の日本皇室も、日本語五十音の真価を十分に理解していた。つまり彼らも、元は日本という国を大陸から見ていた亡命者の集団であったと推察されるのである。
すると、浦島の物語には、日本人が気づかなかった言霊の至高の価値を、一つは弥生時代に龍宮を打ち立てた渡来人によって、今一つは宝を持ち帰ろうとした徐福の存在によって、二重に思い知らされる流れが存在することがわかる。
そのような見方からすると、時代は徐福の大分後になるが、日本を「言霊の幸はふ国」と評した山上憶良も、亡命者の一人であったことだろう。史実には、父親と一緒に百済から日本にやって来たとあるが、元の血筋は百済で も漢でもなく、かつての秦朝に繋がっていた可能性がある。秦一族が血族の伝承を聞いて日本に落ち着いたように、憶良も同様の言い伝えを耳にして日本にやって来たのではないか。さすれば、その伝説こそあの浦島伝説に繋がるものであり、人類の至宝たる法の所在を仄めかす暗号を孕んでいたに違いない。
ここまでの流れで読者もお気づきのように、本当の意味で言霊の価値を認めたのは、土着の日本人ではなかったということである。紀元前の昔から、渤海の東に蓬莱の国があることは知られていた。蓬莱の国、それは憶良の言葉を借りるならまさに言霊の幸はふ国であり、徐福が日本を知る遥か以前より道教の口伝に秘された神話の国であった。
しかし、当の日本人は昔も今もそれに気づいていない。何が日本を世界有数の経済大国にしたのか、何が日本人をして数多くのノーベル賞を取らせるのか、そして、日本の何が世界中から集まる観光客から賞賛を得るのか。まさかそれが、秦朝以前の古い時代からあるものとは、誰も思わないのである。
13★近代日中関係
●さて、ここで時代を一気に跨いで近代に目を向けてみよう。特に注目したいのは、日本と中国の関係である。秦の時代の中国人が日本に憧憬を抱き、人類の至宝ともいえる言霊の教えを貰い受けに来たとすると、日本が西欧化の波に呑み込まれた明治期以降、その関係はどのように変化したであろうか。それを知るには、近代において徐福と同じ立場にあった人間が、日本と中国それぞれの国において、どのような役割を果たしてきたのかを見るとわかりやすい。
そこで、今の中国を生み出した原動力ともなった中国人(台湾人)を挙げてみる。蒋介石、孫文、魯迅、郭沫若、胡蘭成。このメンバーの特徴は、全員がかつて日本で日本の教えを学んだということにある。蒋介石は東京振武学校と陸軍に、 魯迅は東北大学、郭沫若は九州大学に在籍した経歴を持つ。また、孫文と胡蘭成は日本への亡命組である。彼らは実際に日本人に触れ、土地に触れ、日本という国のありようを肌で学んだことだろう。
ただ、ここで思い出していただきたいのは、ここで名前を挙げた人物たちが、かつての渡来人のように、日本を外側から見る立場にあったことである。そして、日本で吸収したものを、直接的、間接的に中国に持ち帰ったということ。それが当時の中国に一体どれほどの影響を与えたのか、現代の日本人も中国人もほとんど歴史の1ページ程度にしか考えていないように見えるが、実は今日の中国の成り立ちを考える上で避けては通れない話なのである。
●何も過去の話に終始したいわけではない。秦の時代から近代への歴史が示すものは、龍宮の宝の普遍性である。これまで述べてきた過去の歴史の要約は、むしろ日本人が気づかずに残してきた玉手箱の中身が、いかなるものであるかを証明するようなものである。日本民族はこのことに、もっと自信を持つべきであろう。なぜならこれは、人類が本来の姿を取り戻し、輝ける未来を迎えるために 、いずれなくてはならない存在になるからである。
14★天界という地獄の番人としての龍宮乙姫
●龍宮があった海の世界は、神道の大祓では根の国、底の国と表現されている。根の国とは音(ね) の国でもある。それを隠すのが乙姫の役割であり、そこに行く者が狙った宝を手にすることは未来永劫ない。結局は自らの欲望により、時間というエネルギーを浪費するだけなのである。 それが白髪の老人になった浦島太郎の姿に仮託されたのではなかろうか。そうした見地から、龍宮乙姫は、天界という地獄の番人と見て取れなくもない。
★『龍宮の乙姫と浦島太郎』
★著者:小笠原孝次・七沢賢治
★版元:和器出版(HP 龍宮の乙姫と浦島太郎 – 小笠原孝次 七沢賢治 | 和器出版 (wakishp.com) )
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
