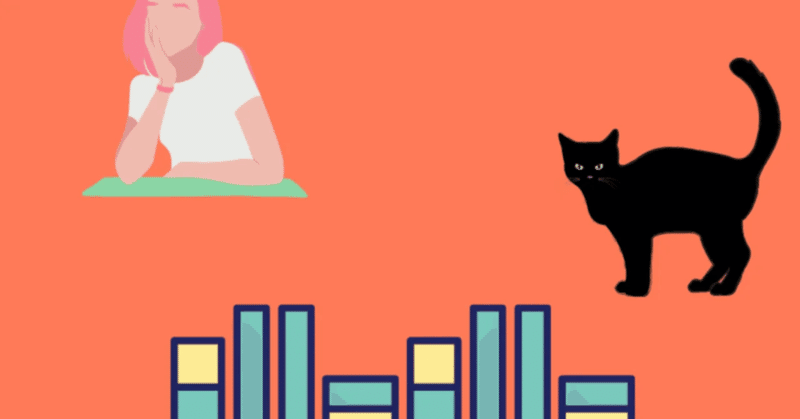
ねこすく ―ねこがきみを救う― 7話(完)
ぬこのいない日々
乾いた頬、割れた唇、隈の浮いた目、重そうに垂れたまぶた。くびをがくりと落とした先にあった水溜りは鏡のように、そんな彼女の顔を映していた。
昨日まで続いた雨がようやくあがった朝、はんなは反射する強い光に顔をしかめ、思わず肩を縮めた。初秋、所々に滴る雫に溶け込んだ冷気がぱちんぱちんと破れ、一気に溢れだしたような寒さが辺りを包んでいた。
彼女はさきほどまで急いでいた。いつものことだが時間ぎりぎりに家を出て、出掛けに家のカギを忘れて戻り、マンションのエレベーターを降りたあたりでスマホを忘れたことに気づいて戻り、ヒールをかつかつと鳴らしながら走っていたのだが、今の彼女はもう、完全に足を止めてしまっていた。
視界の隅に一匹の小さな猫がいた。街路樹の細い枝上に四足をぎゅっとあつめ、小さく丸まった背中をふるわせている。どうやら樹から降りられなくなったようだ。
彼女はおもむろにヒールと営業カバンを投げ捨てた。そして子猫をひとにらみして、ほおってはおけないという決意を示すように、肩をいからせながらずんずんと樹に向かって行った。
猫をたすけなくちゃ
ふと、猫を助けなければという使命感に水を打つよう、冷たい感情が流れ込んできた。ぬこならばどうしただろう、そう思ったのだ。
義理堅く律儀な彼ならば、当然仲間を助けるだろう。しかもまるで風のようにさっそうと、何事もなかったようにやさしく子猫の襟首をくわえて樹から降ろし、名も告げず去っていくに違いない。いや、気高く厳格な彼はひょっとしたら、物陰から見守っているだけかもしれない。子猫が力強く、自分の力で危機を克服するところを見届けようとし、どうしようもなくなったときだけ手をさしのべる。
子猫はいつの間にか自分で飛び降りていた。怪我ひとつ負うことなくきれいな着地を決め、そのままどこかへ去っていった。
「わたしの助けなんていらないんだ」
はんなはそうぽつりとつぶやいて、会社へ遅刻の連絡を入れた。
ぬこがいなくなって
ぬこがはんなのもとからいなくなって半年ほどたっていた。大きな変化といえば、ひとつは彼女の直属の上司がいなくなったことだ。退社する直前、それまで仕事一筋だった彼女が急におだやかに、ゆったりとした雰囲気をもつようなったのがはんなには印象的だった。さらにはんなについて飼い猫のことをたずね、気にかける様子さえ見せた。
人員削減と管理職の更迭、刷新により、会社の労働環境はさらに過酷を極めるようになった。日に12時間労働はざらで、休日出勤も多くなった。はんなはそんな合間をぬって、ぬこを探していた。
年老いた猫が失踪して半年戻らない。それはおそらく、探す探さない以前に、誰もが同様の結末を思い浮かべるのだろう。
ぬこをさがして
「ここでぬこを見たのね」
「ええ、電車の網棚に寝そべってた。他のお客さんがみつけて電車に猫がいるって、田舎だから結構大騒ぎになって、でも後で駅員が来たころにはいなくなってて」
こうちゃんから電車の網棚にねそべっているぬこらしい画像が送られると、はんなはすぐそこへ向かった。こうちゃんは大きくなったおなかをさすりながら、ひさしぶりの再会を喜んだが、はんなはそれもつかの間、仕事のため、すぐにもどらなければいけなかった。
先週の休日には、家出騒ぎでぬこを知った兄弟たちに話を聞いていた。
「人間みたいに、お墓参りするみたいに手をあわせてたけど、すぐどこかに行っちゃった」
兄弟が撮影した画像には、たしかにぬこがつくった土盛りの墓標の前に立つ猫が写っていた。しかし後姿であり、ぬこの特徴的な前足などは確認できなかった。ただ、そのぴんと背筋の伸びた屹立は、どこかあの波際に整列する野良猫たちを想起させた。
ほかにもぬこの目撃情報はいくつかよせられてた。元上司の主任は、TVの野良猫問題の特集で、野良猫を率いるようにその集団の前に立つぬこを見かけたという。また実家の両親からは自分の畑にいたとか、トラクターの座席に丸くなっていたとかいう情報もあった。写真もいくつかあったが、いずれも後姿や体の一部のみで、決定的なものではなかった。
「ごめんね、せっかく来てくれたのに、わたしもちらっと見ただけだから何も」
「ううん、わたし以外にもぬこを知っている人がいて、ぬこのことを考えてくれる人がいるんだなって、それがうれしかった」
それは彼女の本心なのだが、だからこそ無力で、むなしく響く言葉だった。
はんなはこうちゃんと別れて、帰りの新幹線の切符を二席買い、一枚を破り捨てた。乗車して、隣の席に荷物を置こうとしたが、あわてて足元に移した。もしぬこがみたら、自分の席に荷物をおくことを、くどくどと文句を言うだろうと思ったからだ。
ぬこの声、ぬこの記憶
頭の中からかすかにぬこの声が聞こえたような気がした。それが現実のものではないとはんなはわかっていたが、ふと隣の座席に、四足を集めて行儀よく座っているぬこの姿があった。
それは過去のぬこの姿だった。はんなは何度かぬこと新幹線にのっていて、そのときも切符は二枚買っていた。ぬこなら人間の目から隠れることも容易だったが、混雑したときにぬこが不快に思うためだった。
「ぬこ、人間に愛想がつきちゃった?」
ぬこはずっと人間をその冷徹な目で見ており、人間の醜い部分も多く見てきた。失望が根強くその心に巣食っていてもおかしくはなかった。
「それとも、何かを探している?」
新幹線がトンネルに入ると、ぬこの姿は消えた。
ぬこがきえた理由
はんなはひとつの疑問を抱く。ぬこはなぜ今まで、人間に愛想をつかしながらも、助けてくれたのだろう。はんなはこれまで、こうちゃんや少年の兄弟など、ぬこに助けられた人間たちのことを思い返していた。ぬこが人間と猫の間に明確な線を引いているのなら、助けたところで猫には関係ないし、余計な苦労を背負い込むだけだ。
ふと気づくと、ぬこは窓辺のへりに立っていた。体をふるわせて顔をしかめながら、うつろな目に、何かをつぶやいていた。やがて前足がぽろりととれた。後ろ足も順に切断されて、ぬこは悲鳴を上げた。最期に残ったからだから首が刎ね飛ばされ、空中で半回転してはんなの膝上に転がった。ぬこは目を閉じ、ヒゲをふるわせながら、ぐっと歯を食いしばっていた。何かに耐えているかのようだった。
「そうか、ぬこはずっと苦しんでいたんだ」
人間が明日の幸福を望み、さも当然のように享受しながら生きているのとは対象的に、ぬこは明日の苦しみを当然のように受けれていた。それを苦しいと思うようになったのなら、心のどこかに、苦しみを当然と出来ない部分ができたということである。人間と同じく、幸福への期待を抱き、それが裏切られることを恐れるようになった。
ぬこが何に苦しんでいたかはわからない。でもそれを知ろうとする行為は、きっとぬこの本意ではないだろう。はんなは考えることをやめて苦しもうとした。
はんなが体調を崩す
あるとき、会社から帰り、家のドアを空けた瞬間、一筋の閃光がはんなの目の前に走った。細い糸がぷっつり切れたような音がして、そのままベッドに倒れこんだ。何か半身をざっくり鋭利な牛切刀で両断されたような感覚になった。体の中の大事な臓器が、血液の半分がなくなってしまったように力が抜けて、彼女は動くことさえ出来ず、ベッドに倒れこんだ。そのまま朝まで寝込んだ。すべての音がうるさく、近所の野良猫がひとつ鳴き声をあげるたび、汗を流す器官、血を流す器官、涙を流す器官と、順に奪われていくようだった。
両断されて腐っていく半身を野良猫たちが舐め、肉片を噛んでいる。やめさせることも出来ず、ささげることも気が進まなかった。ただ、翌朝になると、まるで夢遊病者のように起き上がり、会社へ行った。会社での仕事ぶりはいつもとかわらなかったが、家に帰れば同じような調子で、休みの日は一日中寝込んでいた。
そうやってはんなが寝込んでいるときである。もうろうとする意識の中で、ふと、はんなの目に猫の顔が見えた。しだいにはっきりとしていく視界に、自分の顔を心配そうに覗き込む、一匹の猫がいた。
猫医者の診察
いや、一人といったほうがいいのだろうか。顔は猫そのものだが、体は成人男性ほどあり、二足で立っている。医者のような白衣を身にまとい、手にはカルテのようなものがあった。
なぜ猫の顔をしているのか、そもそもなぜ自分の部屋に見知らぬ人だか猫がいるのか、意味不明すぎて、はんなはどこか夢見心地で、この猫医者の言葉を聞いていた。
猫医者は聴診器をぴょんと立った耳につけ、はんなの額にあてた。そのまま頬、鼻先、首元にあてると、なにか楽しそうににゃあと声をあげた。
「あ、あのう」
猫医者は返事のかわりに、その肉球をぽんとはんなの額に置いた。
聴診器で診察のようなしぐさをひととおりすると、今度はカバンに入っている注射器やらメスやらを取り出して、にゃあにゃあとはしゃぎながらふりまわした。その様は医者というよりはお医者さんごっこをしている子供に近かった。
やがて猫医者は外からダンボール箱を運んできた。はんなは目を見張った。その中にぬこがいた。体を横たえたまま目を閉じ、ぴくりとも動かなかった。
再会
古傷であった前足や目の治療はひととおりされているようだった。猫医者は置いていったカルテによると、疲労と怪我のため当院でしばらく入院させていたが、怪我は回復ししたが意識が目覚めないため、いったん帰宅をさせるとあった。
はんなの瞳がぬこを映している。ぬこをじっと見ているのに、ぬこではないものを見ているような気がする。それでいて、ぬこの内臓や皮膚、血液や脳まで見えてくるような気もする。
この再会をはんなは驚くほど冷静に受け止めていた。それはいままでずっと供にいたぬこが戻ってくるのは当然という身勝手な考えもあったし、はんなの中にいたぬこの幻想があまりに強く投影されすぎて、現実での存在の有無に大きな意味がなくなったというものもあった。肝心なのは、これでいままでぬこがいた日常に戻る、ということではなく、戻ってきたぬこが、どういう存在に変質しているかであることを、彼女は理解していた。
眠り続けるぬこ
昼に陽光を枕にし、夜に月明かりを毛布とし、ぬこは意識をとざしている。ただ眠っているだけにも見えるし、実は死んでしまっているようにも見える。ぬこはずっと何も話さなかった。だからはんなには、ぬこが何故家を出たのか、何故目を覚まさないのか、知りようもなかった。
「ぬこは人間になりたいの?」
医者の格好した猫人間がその象徴のようはんなの脳裏に残っていた。それは動物に対する人間の空想であり、高いところから見た侮蔑でもある。自身を至上の動物とうぬぼれる人間が抱く猫への幻想、はんなそれをはじめから持っていなかったからこそ、ぬことここまで長くすごせた。
そう、はんなとぬこは実に二十年を越える時間をともにした。人間同士でも、ここまで長い時間をともにすることはあまりないだろう。そう考えたとき、はんなの頭の中に、いままでもやもやと形の定まらなかった感謝の念が、はっきりと存在を示した。長い時間をともにしてくれたこと、長い時間、生きていてくれたこと、ぬこの存在そのもへの敬意と感謝しか残らなかった。
告白
はんなはぬこの前に、スマホと本を置いた。実家から送られてきた祖母の漬物をつまんだ。ベットの上に膝を折り、背筋をのばし、ぬこに対面した。
「わたし、猫を飼っているんです。もう二十年近くも前に出会って、最初は…」
ぬこが見出したはんなの直感のよさ、意図せず真実に近づける力というのを、彼女はぬこが絡めば発揮することができた。それによって、自分とぬこの過去を話すべきだと彼女は思った。自分の覚えている限りのすべてを、ゆっくりと、自分の言葉で。
ただ過去を振り返るといっても、厳密に言えば、たとえば一日分なら、まる一日の時間を費やす必要がある。だからゆっくりと、である。言葉は時間の流れと呼応する。はんなが口を開くと、ぬこの耳がぴくりと動いた。まぶたがぴくぴくとけいれんした。
はんなはずっとぬことの思い出を話し続けた。時間はそれなりにかかった。疲れたらぬこと枕をならべて寝て、忘れていることがあれば、スマホなり日記なり思い出の品をあさったり、思いつく分、時系列もばらばらに、ひとつずつ話していった。
唇を丸めて声を発する。唇をのばしてつぶやく。唇をとじて声を切る。一文字の声が点となり、単語が線となり、文章が風となる。物語が渦となり、半生がひとつの世界となった。はんなはひととおり話して、ふうと息をついた。話したことがぬこと自分の周りに溢れて、おぼれそうになった。普段の友達とおしゃべりする言葉とは違い、一言一言のすべてが、いつまでもこの空間内に固定され、残り続けるような気がした。
つむぐ言葉、紡がれる言葉
はんなは眠ったぬこを抱いて外に出た。深夜、吐く息が白く輝く寒さの中で、はんなは人気のない道を歩いていた。他人のいるところはぬこがいやがるだろうと思ったからだ。
幾千幾万か、言葉をつぐんできた中で、はんなが気をつけていたことがある。それはぬこの返事を求めないことである。彼女の言葉がひとつの流れをつくり、ぬこがその気流に心地よく乗ることである。彼女の言葉はぬこの耳に向かい、胸を通すのではなく、その周囲を漂うのみだった。
都心には珍しくずいぶん冷える夜だった。雪こそ降っていないが、一呼吸するたびに、呼吸で口や鼻の中にさすような痛みを生じさせた。手袋も帽子もしてなかったはんなは、冷える手をこすり、耳を暖めながら歩いていた。
水蒸気が凍りつき、周囲の空間がきらきらとした輝きをまとっている。はんなは自分の言葉が形になったような気がした。誰も聞いていないような言葉でも、こうやってすべてが形となり、誰かが聞いていてくれる、そんな象徴のような気がして、素直に喜んでいた。
突如、夜陰の空気に浮く氷の結晶は不自然な影に覆われる。振り返ると誰かがいた。黒いコートをまとった巨躯の男は両手をひろげて、はんなに近づいて来ていた。
「そうだ、思い出した。最後にぬこに話すこと」
はんなはぬこを守るように抱きしめる力を強くした。不審者の顔はくらがりと目深な帽子によってはっきりとしない。しかしはんなには、恐怖感はそれほどなかった。
過去捏造
「昔、わたしの国語の教科書をかじって、おしっこをかけてダメした…」
「それはわたしではなくハクだ」
ぬこははんなの腕を抜けて、白い息と輝く空気が漂う夜空を跳躍した。まっすぐにのびたぬこの前足は、猫顔の男のコートのチャックを確実にとらえ、自由落下するぬこの体躯とともにチャックをおろし、コートの中身があらわになった。
「ご苦労だった」
肩車をした二匹の猫がコートの中から現れる。上の猫は前足が後ろ足の倍ほども長い。下の猫は体が横に大きく、上の猫の体重をがっしりと支えていた。また、しっぽが異様に長かった。
「わたしにはすこし時間が必要だった。言葉を学び、人間と猫という存在の間で、自分の立ち位置を見定めるために、いままで生涯でえた情報を時間をかけて、精査する必要があった」
「だからずっと眠ってたの?」
「あなたの言葉のすべてが、その助けとなった。ただあまり心配もかけたくなかった」
ぬこはすこし照れくさそうに、肩車の猫のほうに顔をそらして言った。
「人間になりたいのは彼らだ」
前足の長い猫はにっと歯を見せて笑いながら、サラリーマンのようにへこへこと頭を下げた。
猫医者の正体
彼らはぬこを治療した医師のもとにいた猫たちで、普段から医師の診察の真似事をしていた。肩車をした上に白衣やコートをはおり、人間のように二足で立ち、人間のようにふるまうこともあった。彼らは怪我や病気を治療し、病に苦しむ人たちを救う医師に敬意を抱き、自分たちもそうありたいと思っていた。もちろん、まだまだ未熟なところも多いが、いつかは猫の治療をする医者になるのかもしれない。
ぬこはのどに肉球をあてながら、にゃ、にゃ、にゃと声をあげている。声の調子を整えているようだった。はんなにはそれがかいわらしく見えて、思わず喉を撫でた。
「わたしが自我を得てから最期まで、すべての記憶のからわらにはかならずあニャたがいた。ゆえニ、これがわたしの存在意義ニャのだろう。我々の生涯ニ安楽はニャい。人間のようニむやみニ幸福や楽しいといったものをむさぶり喰らうもニョでもニャい。それでもよければ、ともにいくニョもよいだろう」
「なんか難しいこといってるけど、ニャのせいでさまになってない!」
気を抜くと語尾がしまらなくなる。そう、まだ話すことに慣れていなかった。
「ぬこ」
はんなは唇をすぼめた。ぬことはんなの間に浮く氷の結晶が、彼女の言葉に、瞳に、何か輝く存在が重なるようだった。
「いつもありがとう。これからもよろしくね」
ぬこは、いやわたしは思わず鳴いた。わたしのこのか細い声は、誰かにしか届かないような気もしたし、世界を広く覆うような気もした。(完)
最初から
前話
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
