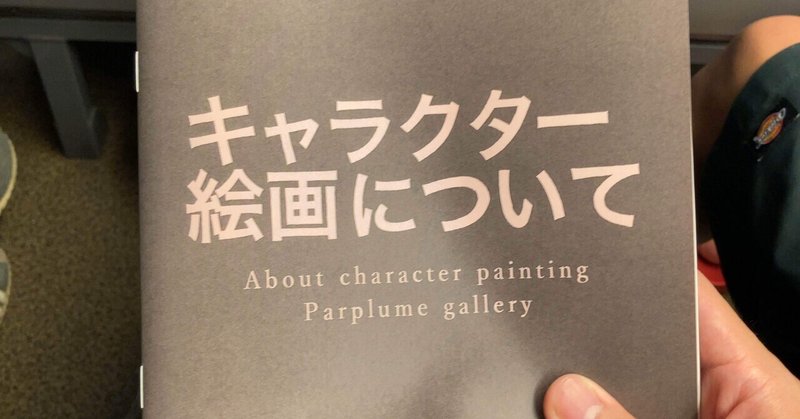
「キャラクター絵画について」について
パープルームギャラリーでの企画展「キャラクター絵画について」を見てきました。
(その日は弾丸アートツアーが敢行され、国立近代美術館ゲルハルト・リヒター展、タカイシイギャラリー梅津庸一個展、六本木アートナイトのドラえもん&カイカイキキギャラリーのドラえもん展、MA2ギャラリー元永定正×岩名泰岳コラボ展、そしてパープルームギャラリーへという、アートファンの濃縮された1日となっていたのであった!そして今帰りの新幹線の中でこれを書いているのである!!)
「キャラクター絵画について」は、昨今アートマーケットや美大芸大でも市民権を得た感のある「キャラクター絵画」と呼ばれている作品とその作家について、絵画的・美術史的・様々な視座から検証を試みるというもの。
この展示を受けて、展覧会の開催前、僕は勝手に「キャラクター絵画」回顧録を書いた。
その辺を読んで頂けたら「キャラクター絵画」のことが僕の視点からですが何となくわかるかもしれません。
さて前置きはこのくらいにして、展示作品について語りたいと思います。
美術作品について語ることに億劫になったり及び腰になったりすること、皆さんあると思います。僕もです。でもせっかく見て感じて考えた事なのだから、例え間違っていたり自信がなかったとしてもそれは一度外に出してみるべきです。そうしなければ、自分が納得できるものには結局出会えないと思うからです。それに、そうすることでしか成立し得ない見えない所でのコミュニケーションが、美術のロマンだと僕はちょっとだけ思うのです。あるいは、そういう態度で臨むことが一人の鑑賞者としての作品に対する礼儀なのではないか?と僕は思っています。

門眞妙さんの作品について
写実的な風景の中に少女が佇んでいる絵画。
こういった図像は、他の作家も扱いのあるもので、Mr.氏の初期作品や、もっと視野を広げれば会田誠氏、狭めれば、2010年頃のpixivイラストに特徴的だった構図、げみ氏から、近年はみなはむ氏まで、多くのイメージが思い出される。(ただ現実の風景の中に少女を置くということが一致しているだけで、各作家で意味合いは勿論全く異なっている。)
しかし、この風景の中に少女を置く、特に女子高生のようなイメージを置く、というやり方については僕自身、個人的には飽き飽きしていた。何故ならば、多くの場合でそれは美人画の亜種のようなものとして描かれており、そもそも少女を美しいと僕はそんなに思わないからだ。少女の聖なるイメージなんて、オタクのフェチズムでしかないと感じていた。さらに言うならば、風景画に単に美しい少女のイメージを入れることで視線を呼び込むという魂胆が、あまりに安易でビジネス視点、享楽主義的に思えて、絵画としての面白さを台無しにしているとさえ思っていた。
そんな見方をしていたから、門眞妙さんの作品もそういった類のモノだろうと、タカを括っていた節があったのだが、実際に作品を目の前にすると、絵画としての細やかな気配りが際立っていた。単にオタクのフェチズムを風景画に拝借したものとはとても言えない、奇妙なリアリズムがそこに立っていた。
構図は風景への視線を遮るように少女が立ち塞がり、しかし、同時に風景の中へとその図像は溶け込んでいる。
制御された色彩のトーンや、輪郭線の僅かな諧調が、それを可能にしている。あるいは、現実の風景と同じ強度で形出しがされた首より下の人体デッサンによるかもしれない。あるいは、風にたなびく少女の髪の毛が、工事現場の揺れる赤旗が、同じ場所で吹いている東北の風を想起させて二つを結びつけているのかもしれない。そう、東北、この風景は門眞妙さん出身の東北の地を描いたもので、そういえば、少女の光を浴びる青白く透き通った肌や、髪の毛やスカートをはためかせる強い風の表現に、日本の東北の風土で育ったキャラクターの輪郭が見えてくる。
パープルームメンバーの聞くところによると、この風景のど真ん中にキャラが直立する構図は、ゲーム画面から着想を得ている可能性があるとのこと。
なるほど、ラノベゲーなどのゲーム画面を想像すると妙に合点がいく。風景の中に少女を佇ませるのでもなく、少女の背景に風景を描くのでも無い、ある特定の場所でイベントが発生しキャラクターが現れて喋っている、そういった場面描写に見えてきた。そう思えば、絵の中の少女は何かセリフを言っているようにも聞こえてくる。
たしかに、画面を占領する少女は、ある特定のキャラクターのように見えるのに、その造形自体には意外にも主眼がいかずに、ほとんど視線が塞がれた風景や、場面として、何かのシーンとしての印象が強いのは奇妙な感覚だった。この奇妙な感覚は、場面風景とキャラクターのレイヤーを滑り込ませて重ね合わせるゲーム画面に由来するものであったのかもしれないということ?そうでなければ、普通は風景を殆ど遮るように半身像をまるで別の層の上に描かないと思う。
しかし、そういったシーンに没入できるのはゲーム画面の中であるからで(裏付けもなくゲーム画面のリアリズム、といった仮定で話を進めています。)、モニターという装置に依存する。そこから離れてペインティングをするならば、今度はキャンバスに依存するハメになる。
ここが問題で、問題と思わなければいいと言う問題とも言えそうだけど、やはりキャラ絵をキャンバスに一度でも描いたことのある人は、キャンバスに本来キャラは描くべきものではないことを身をもって体感しているはずだ。
まず、キャンバスの目が最も邪魔で不快であるし、水平な机の上で描く線と垂直な壁に置いて描く線とでは全く負荷も異なり筆が思うように動かない。そして絵の具は、ペンではなく筆で描く限り根本的には塗りムラから避けられないし、絵の具の質量はキャラ絵の平面性をぶち壊す。さらに大きな問題は、サイズと輪郭線のバランスだ。小さな画面の中での輪郭線は美しくキャラクターのシルエットであり陰影であり得るが、キャンバスに少しでも大きく出力すれば、それはただの黒い塗料になり、絵ではなくただの無駄にデカイ図案になってしまうだろう。
こういった様々な問題は、絵を描く人にしかわからないニッチな問題ではあるけれど、実際にその壁に直面すれば表現を変えざるを得なくなる。そして多くの人がストレスに耐えかねて、デジタルや紙の上での制作、本来キャラクターが住むべき場所へと帰っていく。
しかし、門眞妙さんの作品からは、そのようなキャラ絵をキャンバスに描く上でのメディウムのストレスを感じることはない。
それは様々な方法によってその問題がひとつひとつその痕跡すら残らないほどにクリアにされているからだ。
輪郭線の問題はグラデーションを付けることで回避されているし、キャンバスの目に沈み込むように色彩は細かくコントロールされている。その他にも、おそらく本人にしか知り得ないであろう画家のアイディアや技術が散りばめられているに違いない。(その辺りの話は作家インタビューを収録した展覧会冊子にも記載がありました。)
キャラクターを、そのキャラクターが元々住んでいた場所の状態のまま、キャンバスの上に再現する。
そこには、むしろそこにこそ、オールドスクールのペインティングの技術が濃縮されているような気がして、こういった仕事こそが、本来、正統な洋画と呼べるものなのではないか?という感覚になった。
2010年頃、キャラ絵をキャンバスに描く人が一気に増えた。しかし、キャラクターを本来の姿でそのまま描くというチャレンジは、行われてはいたものの、長続きはしなかった。と、記憶している。ペインタリーな図像を入れたり、表現主義的な動機付けをしたり、キャンバスのフォーマットに合わせる過程でキャラ絵は変形した。
キャラクターを絵画にする、ということを文字通りそのままの意味でやり遂げることは、簡単ではなかったからだ。それはとにかく時間を要するし、何より本当の意味で画家にしかできない仕事だったからだ。
キャンバスの上にキャラを描く、その困難な道の先に何があるのだろうか?
精巧に作られた造形物には魂が宿る?
手垢や情念、そういった余分なものから解放された絵は、本当に伝えたいものをまっすぐ網膜に伝えることが出来るのかもしれない。

川獺すあさんの作品について
ニューペインティングを解体したスタイル、それらが輸入され洋画化されたもの、そういった絵画の皮を入れ物にして、キャラ絵という新たな念を呼び込んだ作品に思えた。
例えばこれがキャラ絵ではなく、単に人物や風景だったとすれば、それは過去において成立してきたもの。モチーフのサイズを変える、パーツを分割する、視点を複数いれて入子状に構成したり、ペインタリーなレイヤー構造そのものを示す、平面の上で出来る遊びを追求した絵画。そういったものは絵としてはそれなりにユニークに見えるかもしれないが、今現在僕はあまり興味は惹かれない。そもそも、絵画はマニアックな趣味であり、絵画について言及した絵画はもっと間口が狭い。それはスキマ産業として生き残っていくが、多くの人の人生には無関係なもの。(T先生がよく話していた言葉。)
しかし、キャラ絵を描くとどうだろう?
子どもから大人までが食い付き、親しみやすさと絵画の不思議とのアンバランスに釘付けになるだろう。つまりこれって単に良い絵ではく、絵画とキャラ、クラスタを交差させる装置になっている。(Zさんの言葉を拝借。)
けれども、僕にはまだ腑に落ちない点がたくさんある。
それは川獺すあさん自身がどれほど絵画に寄り添っているのか?という部分である。
というのも、絵画vsキャラという10年前の古い構図から眺めると、川獺さんの作品は絶妙に当てはまらないところを向いている。
キャラの表象を見てみると、アニメや漫画からの引用という意識は特に見られず、それは原型のわからない一見表現主義的に咀嚼されたものにも思える。しかし、その抑制された手振りからは表現主義的な情念を感じず、絵の具をドライに左官していく感じも見られる。つまり、出典元がハッキリしない。要するに、キャラを愛しているのか、絵画のネタとして利用しているのか、その境目が分からない。これって、もしかすると、10年前のキャラクター絵画からの抜き取り、再現なのではないだろうか?と思ったりする。川獺すあさんの年代から考えても、登場するキャラの表象は少し古く思えるからだ。
絵画からの視点、ペインタリーという側面から眺めても違和感が残る。
ペインタリーであるとは、絵の具の多様な姿を見せ、豊かな絵画を作るという、絵の具教的な信仰に近い考え方だ。例えば薄く絵の具を伸ばしたり、反対にコッテリとハイライトを入れる、あるいは描き残してキャンバス地を見せたり、激しいストロークを上書きしたり、そういった絵の具遊びのことである。
そういった視点から見れば、川獺さんの今回の絵はギリギリ、ペインタリーであると言える。しかしそのテンションが分からない。ペインタリーにすることに楽しみや価値を感じているようには、僕には思えない。かといって、絵画を脱構築することに主眼があるかといえば、そうでもない。
つまり、キャラも絵画も熱量が無い。どちらを愛しているのか分からないし、一体どっちにどれほどの親密さを持っているのかわからない。正体不明で、不穏な空気が漂っている。
ある仮説を立ててみよう。
10年前の僕の経験からも言えることだけれど、キャラ絵を描くことと絵画を描くことは自分の中に分身を二人作ることだった。サブカルに親しい美大生の中では、美大の中で卒業制作をすることと、自宅でペンタブでイラストを描くことは、全く別の創作であった。多くの人が、アンビバレントな板挟みの状態を持っていた。(それは社会で生きることの宿命であり特に絵画に限ったことでは無いけれど。)
美大で一生懸命ウケる作品を作っても、それは卒業するまでの話で、自宅でイラストを描くことの方がその人の人生と寄り添っていることもある。本当の創作活動はそこで行われているのではないか?そう感じることが僕は多くあったし、今もそう思うことがある。
川獺すあさんのドライなペインティングからは、未だにペインタリーなものを崇める美大芸大への最適化と、そんな世界への距離感を感じる。一応適合させてはいるのだけど、それが素晴らしいから模倣をしているわけでない。あくまでも、ペインタリーを偽装したものだ。逆に言えば、それは死体弄りをし過ぎて最早誰も興味を示さなくなったペインタリーな絵画の状況自体を示している。
つまり、ここでは、ペインタリーは最早死んでいるのだが、キャラを使ってあげている、ことによって死体を無理矢理生き返らせる、生きている風に動かす、ということが行われているのだ。
さらに言えば、絵画vsキャラという構図は最早崩れている、むしろキャラが勝利し、絵画は死んでただのガワ、入れ物になっている。そういった悲しい構造が示されているようだ。
キャラクターが主となって、圧倒的にパワーのある側から、あえて使い古された絵画に偽装することで、ペインティングの体を無理矢理呼び覚ます、この構造を近年美大芸大の卒展などでも見るようになってきたと僕は感じる。
キャラクターによる、ペインティングのリビングデッド、その呼び声が聞こえる。

ペロンミさんの作品について
ペロンミさんの今までの作品を拝見すると、懐かしい気持ちになる。
表現主義的な筆触で描かれたキャラ表象をひさしぶりに見た気がする。2010年頃、pixivに潜っていた頃、僕はそういう作品、人たちをお気に入りしていたから。キレイなデジタルイラストでもない、かといって個性や技術がある自分の絵でも無い、二次創作の二次創作のような、原型もわからなくなったキャラをただ生理的に表出する、そういった未分化なエリアに住む人たちがあの頃は確かにいた。そしてその人たちを僕は偏愛していた。
彼らの絵を見ると、クールなオタクにも、賞賛される画家にもなれない、真人間になれない人々の魂の澄んだ歌声を感じ、僕は共鳴して涙が出そうになる。
これは僕の個人的なフェチズムなのだろうか?いや、あの当時はそういう切なさで繋がることが出来ていたはずじゃなかったか?
彼らはどこに行ってしまったのだろうか?
時々僕はpixivを見返した時に思う。作家の消息を必死になってググっても、SNSを辞めていれば全く情報が出てこない。たまにタンブラーやPinterestにリンクされているくらいだ。今もその人が絵を描いているのか、どこにいて何をしているのか、全く僕には知る由がなく、10年以上前に描かれた数枚のデータを眺めるばかりなのである。
ペロンミさんの作品を見ていると懐古厨が発動してしまう。
ただ、かつての表現主義的なキャラ絵とは趣は大分異なっている。
色彩は靄がかかったようなパステルカラーで、淡いピンクやホワイトなど、鮮やかさが抑制されており、不透明なメディウムの粉っぽく乾いた肉体を感じさせる。線描は傷跡のようにも見え、あるいは針金細工で作られた華奢な骨格のようにも見える。(今回生で拝見は出来なかったけど。)
まるで漂白されたミイラのような、、、、こういう表現ばかりで申し訳ないのですが。言い方を変えると、ドライフラワーのように風化している。
白骨化した一輪社さん…?
僕はペロンミさんの絵を見たときにそういうイメージが頭をよぎった。(一輪社さんのことを知らない人はググってください。インターネットには全ての歴史が残されています。ただ顕在化されないだけで。。。。)
今、オタクアートは世界を席巻し、ペインティングはそのフォーマットのみが利用されている。
では、オタクアートにもなれない、かと言って絵画になることもない、あの頃の幼かった僕らの絵はどうなってしまったのか?
それは長年放置され、日光に晒され、色彩が飛んで、体はカラカラになってしまった。肉体は剥製になり、骨だけが残され、かつてのキャラクターの原型は思い出せない。
しかし、そこには美しい天使の羽が生えている。儚い青春の跡を残して、天使がひらひら飛んでいる。
そうか、あの頃のみんなは天使になってしまったのか。見えないけれど、天使になってそこら辺を飛んでいるのかもしれない。
一応、、、隅っこの壁に貼られた履歴書と休学届けについて。
休学届けは日焼けして紙が茶色くパリパリに乾いている。履歴書の方は真新しい紙にペロンミさんの最新の肖像、新鮮な筆跡がのっている。しかし、時が経てば紙は焼けてインクが飛び、紙はボロボロにくずれてしまう。
5年後、10年後、20年、30年後、ペロンミさんはどうなっているんだろう。
ペロンミさんでいるのだろうか?
ペロンミさんの絵を描き続けているのだろうか?
僕には、一見ふざけたこの作品は、ペロンミさんの覚悟を表すものに思えた。
それはキャラクターという虚像に翻弄されずに、キャラ(ペロンミさん)も絵画(ご本人)も自分のものであるという表明だ。
人は変わるし過去を変えられない。
キャラクターだって、そうなのでは無いかと思う。
鑑賞した勢いのまま有る事無い事書いてしまいました。
でもそういうテンションで話す方が面白いよね。面白いですよね…?つまんないかな。。。。けど、マニアックな話と言われればその通りだ。
しかし、マニアックだけれども、作品の印象と無関係かと言われれば、そうではないと思う。
「キャラクター絵画について」の空間に漂っているどこか寂しい雰囲気は、そういった作品の見えない細部から発せられているのではないかと思う。(まぁ、寂しいというのは、僕がそのように感じているというだけの話なんだけど。)
出展作家の皆さん、パープルームの皆さん、ありがとうございました。
みどり寿司おいしかったです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
