
われ思うゆえに猫である
1.
猫と人との関わりは古い。アメリカのさる大学が猫の開発に成功したのが今からちょうど70年前のこと。当時はICチップはおろか磁気テープすら存在していなかったので、エンジニアたちは彼女を置いておくのに倉庫まるまる一棟分のスペースを必要とした。
部屋の壁際を埋め尽くすように整然と並んだ彼女の体は、見た感じ更衣室に備え付けのロッカーに似ていた。もちろん中は真空管(彼女に気まぐれな情緒のひらめきをもたらす)や抵抗器(旺盛な好奇心を発揮するためにはここに蓄えられた電気の力が欠かせない)でいっぱいだ。筐体同士は気だるげに垂れた尾のような、太いコードでつながっていた。
朝目を覚ますとき、猫はいつもエンジニアたちにスイッチを入れてもらった。まず初めに唸りを上げて動き出すのが真空管。それから稼働中の猫を冷やすための無数のファンが、壁の裏の至る所で回り始める。この時点で部屋の中は耳障りな機械音で満たされ、嵐の中の掘っ立て小屋さながらである。天井から吊るされた電球は四方八方に振れまくり、あたりにデタラメな影を描くのが常だった。やがてあらゆるメーターが臨界点を示し、猫を収めた建物全体がバラバラに弾け飛ぼうかという頃になって――おもむろに出力装置から1枚のテープが吐き出される。中身は機械語だ。そのままでは人には読めやしない。
が、朝の第一声はいつも決まっていた。英語で言えばmeow。中国語なら喵。日本語ならニャーゴ。要するに、彼女は自分が猫であることを立派に証明して見せているのだった。
それから時が流れ、人間たちの間には彼女の遠い子孫が普及した。今では電子メールを送るのが猫なら、冷凍食品を温めるのも、将棋を打つのも猫だ。猫なしの暮らしはもはや想像の付きがたいものになりつつある。億のオーダーを超える計算をするのに、今さら誰がそろばんを弾きたがるだろう?
最初の猫はと言えば、今はどこかの博物館に展示されているはずだ。プラグを抜かれ、少なくとも永遠にまどろみから覚めることはないだろう。巷に猫が溢れる今日の世界を彼女が目にすることはない。まして町に野良猫がひしめき、あらん限りの破壊を、損耗を、痛みを振りまいているなどということは――とうに、彼女の知るところではないのだった。
2.
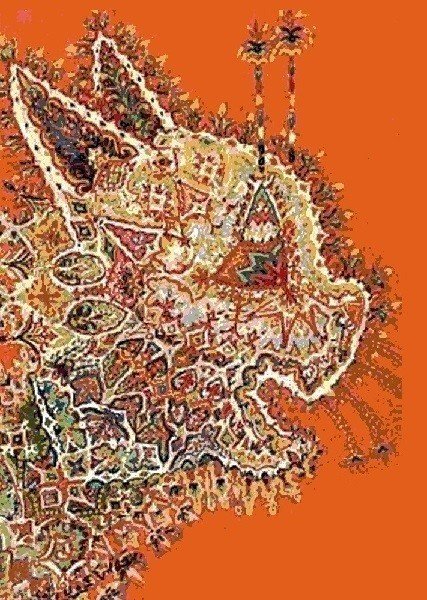
なんでも屋(ハンディ・アンディ)は路地の壁にぴったりと体を寄せ、用心深く角を曲がった。彼はこれから街をさまよう暴走猫を捕まえに行くのだ。すでに警報が行き渡っているためだろう、昼間だというのに一帯には人気がない。彼の耳には道路脇に落ちているゴミの、風にあおられてカサカサと言う音だけが聞こえていた。
不意に何かの気配を感じて、なんでも屋は身構えた。前方を小さな影が横切るのを、間違いなく目にしたように思った。つなぎの腰のホルスターから、そろそろと銀色のスプレー缶を取り出す。缶を前に構えつつ近寄ってみると、なんのことはない、カラスがゴミをつついていた。カラスは急に現れたなんでも屋に驚き、狭い路地を彼方へと飛び去って行く。
「ニャーン」
なんでも屋は安堵のため息をつく代わりに、低い声で猫の鳴きまねをした。別段意味のないつぶやきだが、日々危険に身を晒すことで慢性的にストレスを抱え込んでいた彼は、ある日猫の鳴きまねによって緊張状態をいくらか緩和できることを発見したのだった。始めのうちは仕事の間だけだったのが、今では日常的に口に上るようになり、軽い中毒の様相を呈しつつある。それでも彼には鳴きまねを止めるつもりは、なかった。
猫はどこに行ったのだろう。周囲の路地を見渡すと、先ほどまで猫のいた形跡がそこかしこに見受けられた。道に面した商店のウィンドウがぶち割られていたり、建物の壁に体を擦った焼け焦げの跡があったりするのは皆そうだ。
レジン・バレー。元よりくたびれた雰囲気の漂う、活気に欠ける町だった。だが、街の外れにあった猫工場が倒産してからはそれに輪をかけてひどい。おまけにこうも頻繁に野良猫が姿を見せるようになったとあっては。男は道端に散らばるゴミを蹴とばした。先ほどから道なりに点々と落ちているが、恐らくはこれも猫の落とし物だろう。彼はその後をたどり始める。行けども行けども眼前に広がる景色はごみごみとした、薄暗い、秘密めかした路地ばかり。
「――ここだ」
それから屋根の潰れた二軒の民家の前を通りすぎ、ひしゃげた街灯を跨ぎ越したところで、男はふと足を止めた。――いる。彼は建物の陰から届いてくる、パルスじみた機械音声を読み取った。それによれば今や猫は付近にいるのみならず、こちらへ向かって近づいてきている。バックしているのだ。男は身をこわばらせ、その到来を待ち受ける。
距離にして10メートル先、曲がり角から姿を表したのは、車輪のついた鉄の籠だった。籠の正面には巨大な上顎と、左右のそれぞれで上下二段になった4つの目がついている。その目はオッドアイになっている。即ち右上と左下の目が赤、左上と右下の目が緑だ。籠は食い散らかした餌の重みに車体を軋ませ、一定の周期で機械音声をまき散らしながら、ゆっくりと角を曲がってくる。
それは人工知能によって自動制御されるゴミ収集車だった。それはかつて町一番の綺麗好きだった。それはかつて、不要物を人目につかないよう鉄のベールで覆い隠してくれる便利な使用人だった。だが今やその役割を見失い、本来の順路を外れては一度口に含んだゴミを吐き戻している。なぜか。エンジニアたちはそれを、機器に搭載された猫が仕事への集中を切らしてしまったせいだと考えている。本当のところは誰も知らない。
「ナーオ、ナーオ」
単調な機械音声を垂れ流す猫に向けて、なんでも屋は鳴き声を発した。車両は男の1m手前で停止。威嚇するように長い息を吐き出し、それに合わせて車体がギシギシと軋む。
「ナーオ、ナーオ、ニャーン……うげっ」
猫は背中のハッチを全開にして、なんでも屋の頭上にゴミをぶち撒けた。ぶち撒けられたゴミの中には、とある会社が大規模プロジェクトを立ち上げるにあたって開いた会議の資料があった。その辺のコンビニで売っている菓子パンが食べかけのまま袋に入っていた。勿体なくて取っておかれたチラシがあった。その全てが混ざり合った臭いを胸いっぱいに吸い込んで、男はちょっぴり泣いた。
続けざまに体当たりをしかけてきた猫の体を、労働者は間一髪で脇に転がってかわした。跳ね起きて車の横っ腹に飛びつく。途端に車は猛スピードで元来た方へ向けて走り出した。
振り落とされまいとしがみつく男のもう一方の手には、まだ銀のスプレーが握られていた。ここから銀色の粉を一吹きすれば、世の精密機器はたちどころに煙を吹いて動きを止めてしまうという、ジャック・オブ・オール・トレイズ(J.O.A.T)社の優れものだ。にもかかわらず、男はどうしたものか迷っていた。何せこの銀の粉はたいへんに値が張るのだ。とはいえ今猫の走っている路地の幅はせいぜい車一台分で、このまま手をこまねいていればいずれは靴底のガムみたいにガリガリ壁に擦り付けられるだろう。
男は意を決して動き出した。手近な突起に手をかけ、ついでにタイヤの脇に縛っておかれた人形を踏みつけにして、車体の後方へと身を乗り出す。開いたままになっている開口部にオーバースローでスプレー缶を放り込む。さあ、あとは野となれ山となれ。なお走っている車から飛び降りる際は、無事に済むよう祈りの言葉を忘れないこと。
「ニャーン、ドちくしょう」
信心が薄いせいで祈りの言葉はすぐに出てこなかったが、ともあれ彼は首尾よく仕事を終えて飛び出した。衝突のショックが襲い来たのは次の瞬間だ。彼は幾度となく地面を転がり、その度に身を叩き付けられた。まるで千の手足から蹴られ、殴られるかのような衝撃。つなぎの下に着込んだプラスチック・プレートメイルが音を立てて砕け、痛みを生じる破片となって彼をさいなんだ。「思ってたよりキツい」そんなことを思った男に、続いて火と熱が覆い被さった。
ゴミ収集車はなんでも屋を振り落とした後、数10メートルも走らずに発火した。猫は立ち止まって周囲を見渡した。果たして自分の身に今何が起こっているのか。彼には全く思い当たらなかった。その間火の手は籠に満載された燃料に次々と燃え移り、連鎖爆発を引き起こした。
猫は、自分に接続されている回路の一つ一つが焼き切れていく感覚におののいた。腹に収めたものが残らず毒に替わっていくのを感じて、ようやく自分が今まで口にしてはならない物を口にしていたことに気づいた。それは彼にとって信じがたい出来事だった。
彼はゴミ収集車からの脱出を決断した。すなわち、自分のまるまる全てが収まったマイクロチップを、ボンネットから射出したのだった。
一方で同じ爆発がなんでも屋を夢へ運んだ。夢の中では体に焦げ跡ひとつついておらず、男は元いた路地に立ちつくしている。彼の前には路地を埋め尽くすほどの大きな猫がいて、彼に向けて身を屈めていた。目から鼻から、顔じゅうの穴という穴から火を噴いている。猫が息を吐くたび、燃える和毛が男のすぐそばを飛ばされていったが、彼は身じろぎ一つしなかった。目前でありえない出来事が起こっていると言われればそう信じたかも知れないが、長年の経験から、彼は路地で起こる大抵の出来事に動じなくなっていた。
やがて大猫の陰からもう一頭、その体を回り込むようにして奇怪な生き物が現れた。あばらの浮いて痩せさばらえた一つの胴から、活け花みたいにライオン、ヤギ、ヘビの頭が突き出している。薄汚れた毛並みに、歩くその間もアンバランスに揺れる体。三不獣(キマイラ)だ。獣は男の間近まで近づいてきて、白く濁ったヤギの目で彼を見据えながら、かすれたガラガラ声で唱えた。ハンディ、アンディ、ハンディ・アンディ――
「悪いけど、夢の中で人と話す趣味はないんだ……」
男がそう返事をすると、夢はそこで終わった。目を覚ましたとき日はすでに西に傾いていて、周囲には後片付けの連中が集まってきていた。彼らは車から飛び出した猫の回収と火の後始末に追われて、なんでも屋のことはおかまいなしだ。
男はズキズキ痛む頭に手をやり、唸った。気のせいかもしれないが、なんだか起き上がったら取り返しのつかないことになりそうだ。彼は一旦身を起しかけて、またアスファルトの上に身を横たえた。
彼はまた、自分が破壊したゴミ収集車と、そこに乗っていた猫に思いを馳せた。同じように制御不能状態に陥っていながら、まだ捕獲も駆除もされていない猫が、街には数えきれないほど存在している。ひしめき合っていると言ってもいいくらいだ。恐らくは彼らのそれぞれに意思があり、人の都合など斟酌せず気ままに振る舞っているのだろう。
風に乗って流れてくるゴミの臭いが、たまらないほど不快だった。彼は寝返りを打って臭いのする方に背を向けた。建物の合間から青い空が見える。レジン・バレーの谷底(バレー・フロア)から見る景色だ。男の呼吸は浅く、胸には吐き気がわだかまっている。彼は入り組んだ路地の中で、自分が何か目に見えない巨大な回路の一部であると感じていた。回路は致命的なエラーを内包しながら、それでも何か言い知れない目的に向けて動いていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
