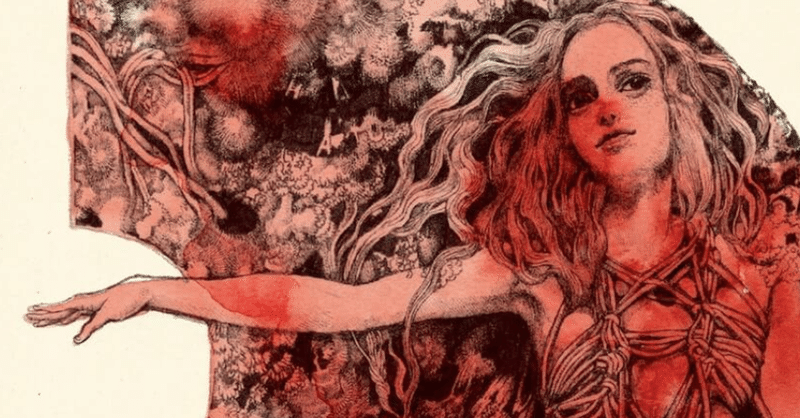
ホラー映画が凄いことになっているぞ
近年のホラー映像作品が尋常でなく盛り上がっているという話。
地方でやらない単館系の映画の話はあとにして、まずは先日公開になった『アクアマン』から。待て。帰るな。後でちゃんとホラー映画の話もします。アクアマンは本国で滅茶苦茶ウケたし、自分もこの前見に行ったが力の抜き方入れ方が上手く面白かった。アメコミ映画が苦手な人が見ても「こういう映像を撮りたい」「ブラックマンタ最高」という作り手の執念が伝わってきて圧倒されるんじゃなかろうか。そんな出来だった。

御本尊ブラックマンタ様
『アクアマン』の監督はジェイムズ・ワン。『死霊館』シリーズで有名な売れっ子ホラー監督だ。『死霊館』のアクロバティックなカメラワークを見た時からアクション映画向きの人だとは思っていたが、まさかアクション初監督作品でここまで凄まじいのが出てくるとは思ってなかった。とは言えこのホラー映画からアメコミ映画への越境、実は前例がたくさんある。
『死霊のはらわた』でデビューを飾ったサム・ライミの監督作は『スパイダーマン』だ。『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』のジェームズ・ガンだってホラーを撮っている。他にザック・スナイダー、ギレルモ・デル・トロ……とまあ例を挙げれば賑やかなもので、実際「ホラー映画の監督は良いヒーロー映画を撮る」というのは以前からよく言われている。自分がそれを実感したのはこの前M・ナイト・シャマラン監督の『ミスター・ガラス』を見てからだったりするのだが……。
ホラー映画の監督は良いヒーロー映画を撮る。大いにうなずけることだと思う。ホラーは現実にはまず起こりえないし、起きてしまったらとてつもなく恐ろしいことを扱うジャンルだ。そしてホラーが撮れるということは、そういう「驚異」の表現が巧みで、さも現実に起きているかのように客に錯覚させられるということである。
同じことがヒーロー映画にも言えるだろう。ヒーロー映画を単なるキャラクターもののアクション映画にせず、彼ら(もちろんブラックマンタのことだ)が周囲に与える驚異を真に迫る表現で、説得力を持って描き出すことができる。きっとそれがホラー映画監督の強みなのだ。
そんなジャンルの垣根を超えて通用する「驚異」にかけてのプロフェッショナルたちが、本気で人のド胆を抜こうとしのぎを削る。そう、ホラー映画界はすごいところだ。この記事ではそういうホラー映画の中でも最前線を行っていると自分が信じてやまない、近年の面白くてインパクト絶大でセンスが良くて邪悪で怖いホラーを紹介していく。アメコミ映画を枕にしたことからもわかるように、ホラー映画に馴染みがない、というか怖い映画が見れない!という人も射程に入れたレビューにするので、ぜひ最後までお付き合い願いたい。
その1.聖なる鹿殺し キリング・オブ・ア・セイクリッド・ディア

心にやましいことがある。すでにしてポスターのイラストにそう書いてある。スティーブンは患者を死なせた医者だ。その患者の息子であるマーティンとは家族ぐるみの付き合いで、彼らはとても仲が良い。仲が良すぎるくらいだ。その理由はマーティンにある。彼の方から積極的に距離を詰めて来るので、スティーブンは受け入れざるを得ないのだ。
マーティンは面構えがいつもふてぶてしく、言動もどこかおかしい。途中で見せてくれるパスタの食べ方など、文句なしに映画史始まって以来最も汚らわしい食べ方だ。なのでスティーブンは徐々に彼のことが疎ましくなっていく。
序盤からずっとスティーブンとマーティンの関係は滅茶苦茶気持ち悪い。人を死なせた者と残された家族との間で、不自然な人間関係が絶ちきることもできずに延々と続く。すると放っておいた傷口から膿が湧くように、やがてどこからともなく一家に呪いが降りかかる。スティーブンの息子、ボブの足が動かなくなるのだ。続いて姉のキムまでもが。
二人の子供が萎えた足で床を這い回り、さながら地獄絵図の様相を呈する一家。スティーブンは呪いを解く方法を追い求める……と、ここまでが中盤過ぎまでのあらすじ。映画の公開は2017年。日本だと一年遅れの2018年3月に公開された。この2018年というのをよく覚えておいてもらいたいのだが、この年はホラー映画のとんでもない当たり年だった。さておき今は『聖なる鹿殺し』の話を。
先程も書いた通り序盤はスティーブンとマーティンの神経戦だが、呪いの全貌が明らかになってからは画面のパワーが凄まじい。特殊効果やショックシーンは一切なし。蛇のように這いずるキムとボブ、頭に血が登りっぱなしのスティーブン、ふてぶてしい上にふてぶてしいマーティン……彼ら役者の演技力だけが底知れない恐怖と謎を感じさせるリング上のデスマッチだ。
それでいて作品には目に見えずとも確実に存在する呪いの禍々しさがみなぎっている。これこそまさに先に書いた「驚異」の顕れというもので、見かけの派手さはなくとも受け手の頭の中では大変なことが起きているという好例だろう。そういう意味ではホラーファンはもちろん、一般的なイメージのホラー映画が苦手な人にもお薦めしたい作品だ。
『聖なる鹿殺し』は特定ジャンルの枠に収まらない映画だが、そうでなくともこの記事では『この映画はホラーの中でも◯◯のジャンルの映画だ』という安易な分類はしたくないと思っている。見る前に謎があった方が映画は楽しいし、本当に心に残る映画というのはジャンルのお約束のようなものをたいていはすっ飛ばしているからだ。例えるならそういう映画はスタート地点からすでに宗谷岬であり、そこからさらにオホーツク方面へ泳ぎだしていくようなものだ。例えになってないが……。
そういえばヨルゴス・ランティモス監督の最新作『女王陛下のお気に入り』は今年度のアカデミー作品賞にノミネートされた。現在公開中だ。シアターナウ!
その2.霊的ボリシェヴィキ

2018年2月に全国の小規模劇場で公開された邦画作品。監督は言わずと知れた『リング』の脚本家高橋洋。近年のJホラー映画の面目躍如と位置付けたくなる作品だ。この映画はそれほどまでに怖い!
恐るべき目的のために工場に集められた7人のゲストたち。彼ら彼女らは一人一人が恐怖体験の持ち主だ。そして工場の壁にかけられているのはレーニンとスターリンの肖像画。彼らはさも当然のように歌い始める。ボリシェヴィキの党歌を!しょっぱなから何が何やらわからん!
というわけで作品の強みはハッタリが謎めいた雰囲気を生み、タメの中から生じる恐怖がまた次なるハッタリを生む正(負?)のフィードバックにある。歌が一段落したゲストたちは互いの恐怖体験を語り合うのだが、この怪談話が抜群に良い。ある死刑囚の逸話、震災の被災地を歩く夢、自分が『何か』と入れ替わった話……。
オムニバス形式の連作ではない。あくまで集まった男女が画面の前で怪談話を語るだけ。イメージ映像もほんのちょっとだ。それが最大限に高まった場の緊張の中では堪らなく怖い。そうでなくとも薄気味悪い話ばかりだ。都市伝説風の話あり、ネットの匿名掲示板発の怪談風の話あり。手を変え品を変え、近年のホラーブームを俯瞰したような趣さえある。
個人的に大好きなのが、霊能者の語る「自分だけに見える不吉な何か」の話。長きに渡ってずっと同じものが、見たくもないのに見えてしまっている。それが何かは、本人にも観客にもわからない。ものすごく微妙なニュアンスを持って話は終わる。そしてまた次の話が始まる。『霊的ボリシェヴィキ』はその不安定な積み重ねだ。
ホラー初級者へのオススメ度は中くらいだ。それはもう怖いが、終始やけくそみたいな妙なテンションの高さがある上、これ見よがしなショックシーンがない。怖がるのもそうだが、怪談話の持つ語り口の巧みさを面白がる目線で見てもらいたい。
さて、次に紹介する『ヘレディタリー/継承』と『ザ・ホーンティング・オブ・ヒルハウス』は、記事を書くきっかけになった作品だ。前者は長編映画、後者はドラマという違いはあるものの、二作ともが「家庭」、引いてはその源となる「血縁」を扱い、それらを病的なほど暗い視点から描いている。
それだけに両者にはダブって見える箇所が多い。見ている間その点が気になって話に集中できないのは非常にもったいないので、自分としては始めに『ヘレディタリー/継承』、次に尺の長い分描写も濃密な『ホーンティング・オブ・ヒルハウス』という順で見ることをお薦めする。公開順は逆なのだが、この記事でも上記の順で扱うことにしたい。
その3.ヘレディタリー/継承

『ヘレディタリー/継承』は最終兵器だ。
日本公開前から本国アメリカから「怖い」「超怖い」という嬉しい悲鳴(誤用)が届き、自分のような末端ホラーファンも首を長くして公開を待ちわびていた。そして2018年11月ついに公開。またしても2018年だ!早速見に行ったがその徹底した重苦しさ、人が何人死のうと衰えないテンション、禍々しいシナリオに打ちのめされた。
物語は一軒のミニチュアの家から始まる。言葉のアヤでも何でもなく、ミニチュアの家がアップになり 、そこへ主役であるグラハム家の面々が入ってくるのである。彼らは玄関前に車を回し、母アニーは自室でまたミニチュアハウスを作り……という風に、何事もなかったかのように日常を送り始める。こうして強烈な違和感とともに物語は幕を開ける。
一家は先日亡くなった祖母の葬儀に向かい、そこでアニーはどうしても打ち解けられなかった母への複雑な思いを語る。息子のピーターは落ち着いたものだが、13歳の妹チャーリーはそうもいかない。葬儀のあいだ「コッ」「コッ」と舌を鳴らして遊んでいる。チャーリーはおばあちゃん子なのだ。
我々が「そう、おばあちゃんが死んじゃったのね」などとノンキしてられる時間はそこからあまり長くない。葬儀の後、一家の父であるスティーブには「義母を埋めた墓が荒らされていた」という報せが入ってくる。極めつけはアニーがカウンセリング先でする家族の話で、彼女の兄は「母が自分の中に何かを入れた」と言って自殺したというのだ。
これはどう考えてもおばあちゃんに何かある。アニーは家の中を徘徊する人影を目にするし、チャーリーは操られるかのように奇怪な行動を繰り返す。人形の首を千切り、歩きだした先には燃え盛る火の中に座り込む老人がいる。チャーリーには別の世界が見えている。そしてその中心にはブラックホールのごとく死んだおばあちゃんが鎮座しているのだ。
さて、ここまで語ったあらすじは未だほんの触りに過ぎない。この後には驚天動地の展開が続くのだが、映画の終わりまでの間にはとにかく物凄い数の要素が詰め込まれているので、見終わってすぐだと何がなんだかわからないかもしれない。ミニチュアアート、血筋、そして移ろいゆく家族のあり方……全てが渾然一体となったラストシーンを見たとき、自分は「これを作った人は頭がおかしいんだな」「なるほどね」と清々しい気持ちになったものだ。
また付け加えておくと、この映画は怖い。というか怖いを越えて邪悪な映画である。緊張感というよりは殺気が横溢しており、見ている間ずっと柄杓で毒を浴びせられているような感覚がある。よくもまあ全国規模で劇場にかけられたものだという感じで、後の世まで語られるカルト映画となろう。自分としては祝福せざるを得ない。
その4.ホーンティング・オブ・ヒルハウス

『ヘレディタリー』も怖いが、こちらも負けず劣らず怖い。
『ホーンティング・オブ・ヒルハウス』はNetflix限定配信のドラマだ。タイトルにホラー映画と書いておいてドラマとは何だ、という向きもあるかもしれないが、むしろ今作を語らずして近作ホラーの何を語るんだという気持ちがある。だったら記事のタイトルを変えろ。
クレイン家はスティーブン、テオドラ、シャーリー、ルーク、ネルの5人兄弟だ。スティーブンは作家で、幼い頃自分達が住んでいた家のことを本に書いた。そこは幽霊屋敷だった。昼夜を問わず首折れ女や時計修理人の霊、頭を天井に擦り付けて歩く長身の男が徘徊する。彼らはかつて母親を置き去りにそこから逃げてきたのだ。
以来家族仲は良くない。ルークは薬物に溺れ頻繁に盗みを働くし、感じやすいネルは精神のバランスを崩している。兄弟は過去を捨て去ろうとするかのように幽霊屋敷の存在を否定するが、父親のヒューはそうではないし、何かにつけ屋敷のことを引き合いに出すので彼らから疎んじられている。とにかく彼らは笑ってしまうくらい仲が悪いのだが、それは屋敷の存在が彼らの生き方に影を落としているためである。
ネルがシャーリーに電話をかけたことをきっかけに、兄弟は再び連絡を取り合うようになる。彼らは屋敷で過ごした日々に思いを馳せるが、回想の中のクレイン一家は郊外で暮らす幸せな家庭といった風情だ。だがそれもほんの短い間のこと。決して開かないが向こう側に誰かのいる扉や、ルークの前にしか姿を現さない少女アビゲイルが現れ、彼らの記憶は次第に狂気の色を強めていく。そして現在の彼らの前には、家庭の残骸とでもいうべき険悪な人間関係ばかりが残っているのだ。ちなみに初登場でスティーブン宅に現れたルークはカメラをパクっていった。
すでに言い疲れた感があるが、この作品も掛け値なしに怖い。それも突然目の前にお化けが現れてびっくり、という物わかりの良い怖さではない。(そういうシーンがないでもないが)次第に逃げ場を失い、絶望の中で追い詰められていく。そういう窒息しそうな恐怖がこの作品にはある。それは登場人物たちにしてみても同じことで、彼らがどれだけ過去を否定しようとしたところでいずれは屋敷へ帰っていく運命なのである。
ちなみにこの作品には原作がある。シャーリィ・ジャクスン『山荘奇譚』『たたり』ないしは『丘の屋敷』がそうだ。古典だが今日の目で見ても新鮮さの衰えない傑作怪奇小説で、雰囲気の盛り上げ方やキャラクターの心理描写にかけては現代の最新鋭ホラー映画に全く引けを取らない。
『ホーンティング~』はこの原作にアレンジを加え、大幅に設定を変えている。例えばネル、テオドラ、ルークという名の登場人物は原作にもいるが、彼らは兄弟でも何でもないし、幽霊屋敷へはむしろ心霊現象を記録する目的で訪れている。前述のように端々で『ヘレディタリー/継承』と符合が見られる本作だが、両作品が同時期に出てきたのは全くの偶然だった。それでいて二作とも恐ろしいほどにレベルが高いのだから、やはり2018年という年はものすごいホラーの当たり年だったと言うほかない。
食わせものども『ゲット・アウト』『サスペリア』
最後に比較的ストレートさは薄いが、上記のほかにホラー新時代の息吹を感じさせた作品を紹介したい。
『ゲット・アウト』

日本公開2017年9月。彼女の帰省について行った片田舎で、黒人男性が100点満点中40点くらいの機能不全に陥ったポリティカルコレクトネスに晒され続ける。扱っているテーマは直球で人種差別であり、白人に混じって日系人が加害者側にいるあたりも抜群の切れ味を感じさせる。恐怖描写の盛り上げも上手い。周囲から受ける一つ一つは耐えられる程度の不快感が、やがて耐えがたいまでの不信の念へと繋がっていく。その書き込みが丁寧だ。
さて、この作品ジャンルとしてはホラーなんだけれど困ったことにギャグが面白い。主人公の友達が物語に特に関わりのないところで延々とコントをするのだが、これが本当にしょうもないことばかり言っており、劇場のウケもなかなか良かったことをこれを機に書き留めておきたい。
リメイク版『サスペリア』

日本公開2019年1月。かの有名な70年代のオカルトホラーのリメイクにして、ヘレディタリーに次ぐ「頭のおかしい人が撮ったんだな」映画第2弾。スージーが入団した舞踏団は、現代に生きる魔女たちの隠れ蓑であった。当時のドイツ社会の描写やジェンダーの要素があり、よそのレビューを見るとその点にばかり触れている感想が目につくが、自分としてはやはりちょっと出力のリミッターが外れているオカルト要素の強さを取り上げたいのである。
何度かあるダンスシーンの人が人に見えない撮り方が滅茶苦茶カッコよく、まさに「取り憑かれたよう」という形容がしっくりくる。魔女が使う鉤爪を始め小道具の造形も凝っていてホラーファンとしては至れり尽くせりなのだが、反面魔女がスージーの夢に現れる描写はスージーの部屋の壁に色セロファンを通したみたいな色とりどりの光が現れるという珍妙な演出でずっこけてしまう。これはもうあまり映画が格調高くなりすぎないように気を使ったウケ狙いとしか思えないのだが、それにしても意味不明で好きだ。
上映時間は3時間近い。映画は静かに始まり、非常に重たい足取りでクライマックスへと行軍していく。そして来たるラストシーンが素晴らしい。端的に言って地獄の底から来たラ・ラ・ランドみたいだし、自分は見終わった後非常にスッキリした。どちらかと言えば恐怖よりオカルトに軸があり、怖いシーンはあっても全体の印象がホラーでないのでこの節にまとめてしまったが、自分はリメイク版『サスペリア』を気に入っている。しかしそんじょそこらのカルト映画より余程ゲテモノの域にあるこの映画も『ヘレディタリー/継承』と同じく全国規模での上映となったのだから、まことホラーファンにとっては良い時代が来たものだ。またこういう映画を劇場で見たいものである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
