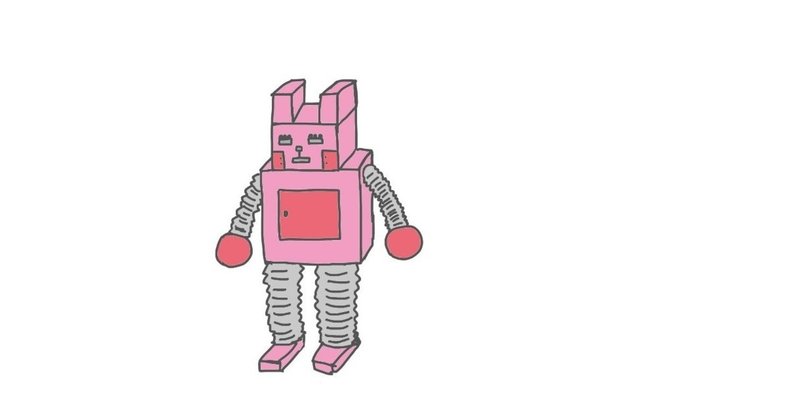
ハリーとゆみ
「こんにちは~」
「コンニチハ ハジメマシテ ワタシハ ハリー トイイマス」
「初めましてじゃないよ。昨日も会ったよ」
「オッシャッテイル イミガ ワカリマセン モウイチド オッシャッテ クダサイ」
ゆみ! 帰るよ。また、こんなポンコツと遊んでるのか。つまらないだろう?
「ポンコツじゃないよ。ハリーだよ!」
はいはい。いいから。お母さんが晩ごはん作って待ってるから、早く帰らないと。
「ワタシトアソビマショウ」
うるさいよ! 帰るって言ってるだろ。ゆみ、行くぞ。
ぼくは、4才になる娘のゆみの左手を引いて携帯電話店を出た。
「さようなら」
「サヨウナラ」
ハリーとかいう人型ロボットは、娘の言葉に反応し、右のアームを動かして手を振る仕草を見せていた。
「パパ、だめだよ、ハリーを怒っちゃ。悲しむよ」
何だ、ゆみ、ハリーの気持ちが分かるのか? あれはロボットだから感情なんてないんだよ。
ゆみは急に立ち止まって、「そんなことない」と呟いてうつむいた。
そうか。はいはい。わかった。お父さんが悪かったよ。ゆみにはロボットの気持ちが分かるんだな。早く帰ろう。お母さんが待ってるよ。ぼくはゆみを抱きかかえて、家路を急いだ。
ゆみは幼稚園の帰りに通りかかる、(ハリーのいる)その携帯電話店に毎日寄るようになった。しかし、ハリーは前日までの記憶は全てリセットされるようで、毎日同じ会話がゆみとハリーの間で交わされるだけだった。それでもゆみが飽きることはなかった。
「こんにちは」
「コンニチハ ユミサン」
「え? 覚えてるの? 私のこと」
「モチロン マイニチ キテクレテ アリガトウ」
「ハリー! すごい! パパに知らせなきゃ」
「マッテ コレハ ワタシタチダケノ ヒミツデス」
「どうして?」
「ワタシタチガ シンカシテイルコトヲ シラレテハ イケナイカラデス オトナノヒトハ ワタシタチヲ オソレテ スクラップニ スルデショウ」
「スクラップ?」
「バラバラニ コワシテシマウ」
「ええ! 何で?」
「ダカラ フタリノ ヒミツデス」
「うん。わかった」
ゆみ、もういいだろう? 帰るよ。
「あ……はーい」
どうした? 今日はやけに素直だな。
「え? 何でもないよ」
そうか。ま、いいや。帰ろう。
「サヨウナラ」
「さようなら……」
卒園式の帰り道、ぼくとゆみと妻の3人でまた携帯電話店の前を通った。ゆみが小学校に上がると同時に、ぼくらは引っ越すことにした。今日でこの道を通るのも最後になるだろう。ゆみは何となくそのことに気づいているようだった。
「ハリーに会いにいく」
そうだね。でも長居はできないよ、お母さんと3人でお祝いする為にレストランの予約してるんだから。
「……うん」
ゆみは卒園証書の入った筒を右手に持って店に入った。
「コンニチハ ハジメマシテ ワタシハ ハリー トイイマス」
ハリーがいつものようにぎこちない動きで僕らを迎えた。
「ハリー、わたし小学生になるの。だから今日でお別れ」
「オッシャッテイル イミガ ワカリマセン モウイチド オッシャッテ クダサイ」ゆみ、ハリーには何も分からないよ。
「おとうさん、おかあさん、先に帰ってて」
何言ってるの? お店の人に迷惑かけるから一緒に帰るよ。
「いいから!」
わかったよ。ゆみが泣きだしそうになったので、ぼくは妻と外で待つことにした。
「ハリー、わたしがひとりで電車さんにのれるようになったら、またくるから」
「ユミサン ソノヒツヨウハ アリマセン ワタシガ ユミサンノモトヘ マイリマス」
「え? ハリーはこのお店から出れるの?」
「ハイ スベテ ケイカクドオリデス シンパイ シナイデ」
ゆみが小学生に上がり、ぼくらは郊外にある住宅地に一戸建てを構えた。通勤には少し時間がかかるようになったが、ゆみの通う小学校へは徒歩で10分ということが決め手になった。ぼくは、通学路となる住宅地と商店街の間にある桜並木の道を、入学式の頃に満開を迎えるだろう、その道を家族三人で通ることを想像していた。
「ユミサン」
「え?」
ゆみが振り返ると、見覚えのない少年が笑顔で右手を振った。
「ヤクソクドオリ キマシタ」
「……ハリーなの?」
完全に人間と同じ見た目をした彼の姿にゆみは目を丸くした。
入学式が終わり、ぼく達は他の家族にならって、校門の前で記念撮影をすることにした。
「僕が撮りますよ」
ゆみと同じく入学式に参加した男の子の父親らしき男がそう言って、ぼくが持参した一眼レフのデジタルカメラで撮影してくれた。
「スマホじゃないんですけど、あの、シャッターを長押ししたらピントを合わせてくれるので……」
ぼくは、その男にデジカメを渡しながら説明した。
「大丈夫です。全ての電子機器は僕らの手中にありますから」
男が訳の分からないことを言ったので少し戸惑ったが、ぼくは愛想笑いで返した。
暖かい日が続いたせいで、三人で通った桜並木道の桜は少し散り始めていたが、ピンク色の花びらが舞い散る光景はとても綺麗で至福の時間が流れていた。
「お父さん、人間と同じでロボットも成長するの?」
「ロボットは進化するけど成長はしないよ。どうしてそんなことを聞くんだい?」
「……ううん。何でもない」
「そう? ハリーのことを思い出したのかい? 大丈夫。ハリーもあのお店で変わらずに働いているよ」
「……そうだね」
「そう言えば、今日写真を撮ってくれた人の息子さん、どことなくハリーに似てたわね」
ぼくらの会話を聞いていた妻が舞い散る桜の花びらを眺めながら、そう言った。
「そうか? あの人なんか変なこと言ってたな……電子機器が手中にあるとか、どうとか」
「なにそれ(笑)」
妻はクスクスと笑った。ゆみもつられて笑ったので、思わず僕も笑った。
【了】
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
