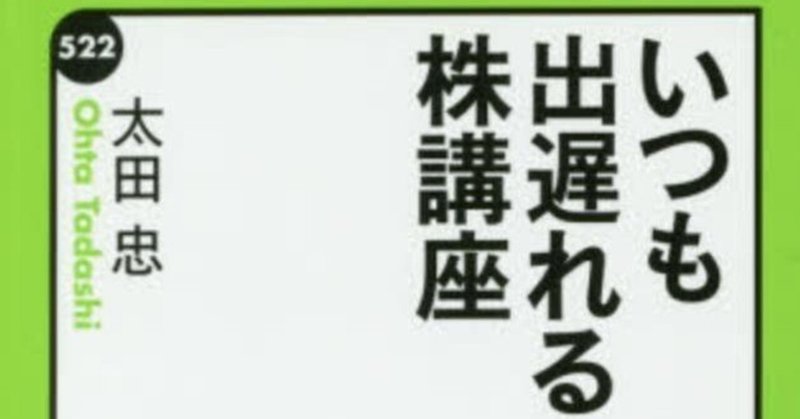
「いつも出遅れる人の株講座」太田忠著(中公新書ラクレ)
今年一年は株と金融の勉強に捧げるぞ!と決意しました。
まず第一弾がこれ。石橋を叩いて渡らぬ極度のリスクオフ、臆病マンの私にとってピッタリじゃないか、と思い読んでみた。2015年刊行でチョイ古いですが。
金融リテラシー低い人向けに書いてますよ、と入門書の体裁で中々透徹した市場観が見れる。
第1章 株式市場は「非日常」の世界である
第2章 大半の投資家が犯す間違いとは
第3章 株式市場に「何を求めるか」を明確に
第4章 それでも飛び込む人の準備体操
第5章 投資に最適な期間とは?
第6章 上昇相場の投資戦略
第7章 下落相場の投資戦略
第8章 偉大な先人からの20の金言
1章において筆者が力説するのは、株式市場の怖さ(ボラティリティの高さ)、予見不可能性、信用取引の深刻なリスクなど。
2章では、銘柄保有の考え方など。含み損の株は早く売りナンピン買いはするな、むしろ含み益のある株を買い増すべき、など。
4章では市場の見方や銘柄探しのコツ、リスク管理のための逆指値の提案など。
5章で触れられている長期トレード、スイングトレード、短期トレードの区別は、株式投資やる人は絶対に認識すべきこと。投資家の話をまとめた類書を見ていても、長期の人とデイトレでは、投資に対するアプローチが全然違う。
7章にて、空売りやインバース、つなぎ売りによるリスクヘッジの活用法に触れて終わる。
8章は、断章的な相場格言での学び。
まず株式というのは、その本質上、急騰もしやすいし急落もしやすい、ボラティリティ(価格変動性)の高いものだ、ということが力説されている。そういった株式観ゆえ、急落相場の逃げ方、ヘッジ方法、そもそも踏み込むべきなのか、踏み込むとしたらどういった利点のためか、ということから説き起こしている。
ゆえにダウントレンドに入った時にどう対処するかについて、小冊の中でもかなり分量を割いている。過去の急落相場のエピソード、そういった場合に生じる投資家心理などはかなり参考になる(気がする)。
複利運用なんだから一時的に大きく儲けることよりも、長期のリスク管理能力が一番大切!という主張は、そうなんだろうなと素直に思う。
時たま株の本にある「株式市場は最終的に適正価格に収斂する」とかいう根拠不明な、市場原理主義的な前提(思い込み?)に立っていないところはかなり好感を持てた。
むしろ「なんなら半分くらいデタラメだから、それ覚悟してきてね」という厳しさが、むしろ親身ではないか。
それと規制強化≒株下落、規制緩和≒株上昇、という構図に触れているのも、ハッとした。規制強化の具体例としては、消費者金融業界。上限金利と過払い返還で大手がバタバタと倒産または吸収合併された。他方、郵政民営化で銀行や証券会社は大喜びした。この点は自論とは異なる部分があるのだが、市場ではほぼ自動的にそう見られている、ということは大きな学び。
この手の本は本人にとって有益かどうかだけの話なので、評価とか大して意味はないが、あえて5つ星で評価するなら4以上。新書のこの分量で、これ以上の詰め込みは難しいと思う。サラッと書いているようで、よくよく読んでみると随分含蓄のあることだったりして、密度は高い。
頂けるなら音楽ストリーミングサービスの費用に充てたいと思います。
