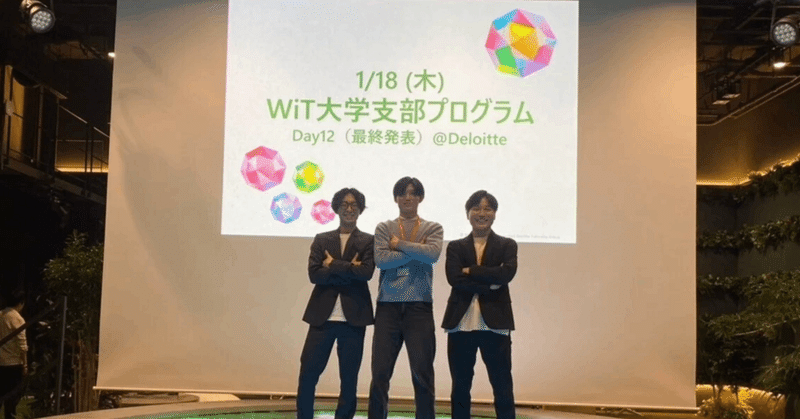
テクノロジーの仕事を選択する女子学生を増やすには?[WIT チームB]
このnoteは、エリックゼミ×デロイト トーマツ グループ「Women in Tech」との1年間に渡るプログラムにて、自分たちグループBが構想した内容をまとめたものです。全部で3編に分かれていて、この記事はその1つ目になります。
①背景の捉え方
私たちは今回のお題である「テクノロジーの仕事を選択する女子学生を増やすには?」に対して、女子学生と女子大学の現状を分析し、私たちの経験に基づいた「目指したい社会」から課題解決について考えました。
はじめに女子学生の現状です。問題を、様々な無意識バイアスや漠然としたキャリアへの不安からテクノロジー職を志向する女子学生が少ないことと捉えました。テクノロジー領域における女性活躍人材やロールモデルなどの少なさから、無意識に「女性はテクノロジー職に就職しない」、「女性がテクノロジー領域ではたらくことは難しそう」という価値観が生まれているのではないかと考えたためです。
次にその原因を考え、「テクノロジーへの認知や興味付けの機会はある一方で、『テクノロジー職でこれをやりたい』と感じ、思い描けるような感動の機会が足りない」と仮説を立てました。
ニュースやイベントなどでテクノロジーの魅力を発信することはできているが、実際にテクノロジーを使うことでどのくらい自身の可能性が広がるかを知る機会は少ない。テクノロジーを志向するには「テクノロジーってすごい」では終わらずに、「私はテクノロジーで〇〇をしたい」と想像できる機会が必要です。
その後、解決の方向性として「大学のスマートキャンパス化推進プロジェクト」を考えました。企業との協業を通じた密度の濃いテクノロジー体験により心が揺さぶられ、「テクノロジーで〇〇をやりたい」と感じ、想像し、それをキャリアとする学生を増やしたいと考えました。

②解決の方向性
解決の方向性の設定は「ターゲットとそれを取り巻く環境の持つ課題」と「我々の実現したい社会」の2つの側面から考えました。
はじめに、ターゲットの課題は先ほど述べたとおりですが、ターゲットを取り巻く環境である女子大学の現状の課題に焦点を当てました。
女子大学に焦点を当てた理由としては、3つあります。ターゲットである女子大生に直接アプローチできる点と、我々の所属する青山学院大学の歴史。そして女子大学の抱える課題があります。
青山学院大学は1874年に、麻布に開校した女子小学校から始まりました。そのためどの大学よりも女子教育に歴史があります。歴史ある学校の学生である我々であるからこそ、シナジーを感じ、あまり触れられていない女子大学の現状や課題に寄り添えるのではないかと考えました。そのうえで調査を進めると女子大学は今大きな課題を抱えています。
③女子大の現状
女子大学の現状はグラフの通り、生徒数の減少により経営難が続いています。実際に学校数も25年で98校から73校と減少しています。これは共学との差別化ができていないことや女子大学ならではの魅力が不足していることで、学生の共学志向が進んでいることが原因です。

この課題と、先ほど述べた女子大生の課題である「テクノロジーに対するバイアスやキャリアに対する不安」を同時に解決したい。
事業を通じて「テクノロジーでこれがやりたい」を追いかける、発見する姿をみて、「このプロジェクトを行うこの女子大はどこよりも魅力的だ、私も入学したい」と魅力を感じ、志願者や入学者数が増えるという好循環を起こすことで、経営難の課題を解決し、より意義のある事業構想になると考えています。

④私たちが目指したい社会
このように、「やりたいことを見つけること」を中心に事業を考える背景としては、我々の「目指したい世界」があります。
それは「『これでよい』ではなく『これがよい』があふれる社会の創造」です。
私たちは進路やキャリアの意思決定において後悔をした経験があります。
周りの声や自身のバイアスによって本当に自分のやりたいことを妥協した選択をしました。現在も後悔しています。
我々がしたいことは、それを防ぎ、人々がこれが良いと「自分のやりたいこと」を見つけ、人生を謳歌できるような意思決定の実現をサポートすることです。
それを今回は女子学生が「テクノロジー」を通して「私はこれが良い/やりたい」というような意思決定をサポートをします。

⑤構想内容
私たちは、女子大学スマートキャンパス化推進プロジェクトを提供します。また、その企画設計から運営、実行までも一気通貫で支援していきます。具体的な提供の方法として、ハンズオン型開発の体験講義を想定しております。様々な企業と連携しながら、最先端のテクノロジー技術を実際に女子学生がエマージングテックを活用してスマートキャンパス化を推進していきます。

⑥プロジェクトの流れ
実際プロジェクトの流れは以下を想定しております。

期間
期間としては、一つの講義の期間が約6ヶ月ということで、6ヶ月間と置いておいております。6ヶ月ごとにひとつのプロジェクトを構想・実行していくことで、女子学生のテクノロジーに対する楽しさや熱を生み出していきます。
流れ
大きな流れとして4つあります。
まずはじめに、テーマの設定をします。具体的にどのようなスマートキャンパス化を実装するかという内容に関しては、弊社メンバーと女子学生、提携企業と議論した上で設定していきます。
その次に、実際に講義であったり開発をスタートします。ここで最先端の技術を活用している企業からサポートを受けながらシステム開発であったりプログラミングを学びつつ、スマートキャンパス化をスタートしていきます。
開発に伴って、定期的なメンタリングも実施していきます。具体的な内容としては、進捗のサポートはもちろん、中間ピッチや運用テスト提供企業との社員交流イベントなどを通して、メンタリングを想定しています。
その後最終的にピッチを実施します。成果物をピッチとしてまとめた上で、SNSやオンラインメディアを通して社会に発信をしていきます。
この施策で大切にしている点
私たちは、女子学生のテクノロジーに対する ”楽しさ” や ”熱” を生み出すことを一番の目的においています。では、どういうタイミングでテクノロジーに対する ”楽しさ” や ”熱” が生み出されるか。私たちのチームでは、以下の2つの要素が重要なのではないかと結論づけました。
①テクノロジーがある場合とない場合で、どのくらい変化があるのか。その変化の前後を身をもって体験していること。
②その変化を自分自身が生み出すということ。
これら二つの条件を満たすには、このようなハンズオン型の開発体験プロジェクトが最も良い手段なのではないかと考え、このプロジェクトを構想しました。

⑦テーマ例
具体的なスマートキャンパス化のテーマは、基本的に学生主体で構想を進めていくのですが、弊チームから具体例として二つ用意しました。
テーマ例❶テクノロジーによる食堂改革
一つ目は、テクノロジーによる食堂改革です。テクノロジーを活用することで、学食の注文から決済までクラウド上で完結する体験を提供するだけでなく、安全性や健康面における体験も向上することで、より豊かな食生活を実現することができます。

具体的にやることとしては以下の4つです。
①モバイル決済システムの開発
今までは、一つの学食を受け取るまでに、20分ぐらいかかることもありました。券売機の列に並んで、紙で食券を買って、その上でまた受け渡し口の行列に並んで…という面倒なことをしていました。しかし、モバイル決済システムの開発によって、その手間がなくなっていつでもどこでも注文可能になります。
②調理ロボットのプログラミング開発
食事を提供するロボットを導入するのですが、そのロボットのプログラミング開発をします。これによりヒューマンエラーによる事故を未然に防いだり、人手不足を解消することができます。
また、モバイル決済システムとの連携を通して食事を準備するので、必要以上に食事を作る必要がなくなり、結果として食糧廃棄も減らしていくことができます。
③混雑予想システムの開発
これによってどのくらいの時間にどのくらいの食事が必要かというところがわかるので、学生も指定時刻に受け取ることができるようになります。結果として待ち時間がゼロになり、休み時間を有効活用できるようになります。
④人工肉の開発
食制限がある人とも同じ食事を楽しめるので、食事がより楽しくなったり、ヘルシーで美味しい料理を楽しむことができるようになったりします。
テーマ例❷メタバースによる保健室改革
二つ目は、メタバースを活用した保健室の改革です。特に健康面に関して、女性ならではの悩みは様々あり、その中には人に相談しづらいものも多くあります。メタバース空間の開発によって、このような悩みを専門家に相談しやすいような環境を作っていくのがこのテーマです。

具体的な内容としては大きく3つあります。
①メタバース空間の設計
女子学生目線から、相談のしやすい空間を設計します。その際、保健室のような相談ができる空間のみならず、以下の画像のような学生同士が相談できるような空間も作成します。

これによって、先生には相談しづらいが、学生になら話せる悩みを解決することができます。
②メタバース空間の開発
①をもとに、メタバース空間を開発していきます。
③メタバース空間の提供
開発で終わるのではなく、構築した環境を実際に医者や専門家の方が使えるように、使い方のレクチャーをしていきます。
⑧女子大学へのメリット
女子大学スマートキャンパス化推進プロジェクトを実施することによって、女子大学と提携企業それぞれに対してメリットがあります。

女子大学はこのプロジェクトを導入することで、話題性を得るだけでなく、テクノロジー業界における女性人財を輩出することができます。これらよって、女子大学の認知が増すだけでなく、その女子大学のOGがテクノロジー業界で活躍することが期待できるので、結果として女子大学のリブランディングを実現します。
⑨提携企業へのメリット
提携企業がこのプロジェクトを通して、技術提供をしていただき、女子学生へのタッチポイントを得ることができます。

まず、技術提供をしていただくことによって、話題性を得ることができるのはもちろん、対外的に技術力のアピールをすることができます。また、女子学生と関わる機会が増えることで、女子学生のインサイトを深く知ることができ、結果として女性人材の採用活動をより進めていくことができたり、採用した先に女性が活躍しやすいような環境の構築につながったりします。これらによって、企業の社会的価値が向上することが、提携企業の得られるメリットです。
⑩ビジネスモデル
私たちはビジネスモデルを「提供する価値の流れ」と「お金の流れ」の2つに分けて考えました。
提供する価値の流れ

まず「提供する価値の流れ」です。
「誰が」「誰に」「何を」「どのように」価値提供するかというものを表しています。まず、私たち(弊社チーム)とIT企業がアライアンスを組みスマートキャンパスPJをマネジメントしていきます。特に提携企業は技術提供をメインとし、私たちは講義の企画や運営をメインとします。そしてこのプロジェクトを通して、女子大生と女子大学に対して情熱を生み出す機会や大学のリブランディングの推進による経営支援等の価値を提供します。
お金の流れ

続いて「お金の流れ」です。
私たちのキャッシュポイントは大きく2つあります。1つ目は女子大学からのコンサルティングフィーです。スマートキャンパスPJの企画設計、運営、実行などを通したプロジェクト予算として1,000万円/1PJをいただく予定です。
2つ目は提携企業からのスポンサー料です。スマートキャンパスPJを通して女子大生とのタッチポイントや世の中の話題性、技術力のアピールなどを提供する代わりに、100万円/1PJをいただく予定です。
⑪マーケット

続いてマーケットについてです。
まず市場規模を、TAM(全国の教育機関へのコンサルティング事業)、SAM(全国の大学へのコンサルティング事業)、SOM(全国の女子大学へのコンサルティング事業)と設定しました。具体的な数値としては「学校数×プロジェクト単価」として計算しました。その中でもまず私たちは「SOM(全国の女子大学へのコンサルティング事業)」をターゲットとして7億3,000万円の市場を狙います。
⑫KPI
続いてKPIについてです。
私たちはKPIを「中長期的なKPI」と「FSに向けたKPI」の2つに分けて考えました。
中長期的なKPI

まず「中長期的なKPI」についてです。
項目としては「女子大学との提携」と「テクノロジー企業とのアライアンス」の2つの観点からKPIを設定しました。見込み顧客からアポ取り、商談実施そして受注するまでの数値を設定しました。7年目には「30の女子大学」「15のテクノロジー企業」と提携している推定でいます。
FSに向けたKPI

次に「FSに向けたKPI」についてです。
項目としては「女子大学との提携」と「テクノロジー企業とのアライアンス」、「社内体制」の3つの観点からKPIを設定しました。「女子大学との提携」においては、営業候補先の大学リストアップや候補先の在学生へのアンケート調査、講義の座組み調整(時間割,参加人数等)などを考えています。「テクノロジー企業とのアライアンス」については、営業候補先企業のリストアップや学生の開発範囲の調整などを考えています。「社内体制」においては、講師委託先の確保や運営マニュアルの作成などを考えています。
⑬収支計画

続いて収支計画についてです。
前で設定したKPIをもとに収支計画を立てました。1年目は1,300万、5年目には1.1億円、そして7年目には3.1億円の売上を目標としています。7年目には30の女子大学、15のテクノロジー企業と提携している想定で算出しています。
⑭ロードマップ

最後にロードマップについてです。
私たちは3つのフェーズで事業をグロースしていきたいと考えています。まず最初は実績づくりです。特に初年度に関しては、必ず1校の女子大学、3つの企業からの受注を獲得しプロジェクトをやりきりたいと考えてます。利益を抑えつつもしっかりと企業との連携をとって運営していきます。続いて仕組み化、型化のフェーズです。ここでは実績をもとに運営の仕組みをしっかり進め、プロジェクト内におけるコンテンツや活用するテックのバラエティを拡充していきたいと考えています。。最後にブランドポジションを確立するフェーズです。プロジェクトワークの他に弊社のコーポレート機能をしっかり強化しつつ会社としてのブランディングに力を入れていきます。そしてアライアンス企業を拡充する上で、これまで関わった女子大生とのデータをもとにプロモーションを進めていきたいと考えています。
そしてこのプロジェクトを通して、「女子大生」と「女子大学」の抱える課題を解決し私たちの目指す社会である【「これでよい」ではなく「これがよい」があふれる社会の創造】を実現します。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
