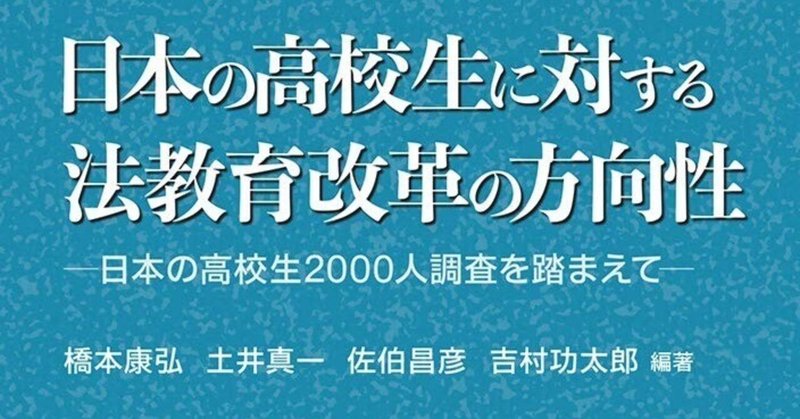
【ブックレビュー】『日本の高校生に対する法教育改革の方向性』
橋本康弘他『日本の高校生に対する法教育改革の方向性 ―日本の高校生2000人調査を踏まえて―』風間書房、2020年
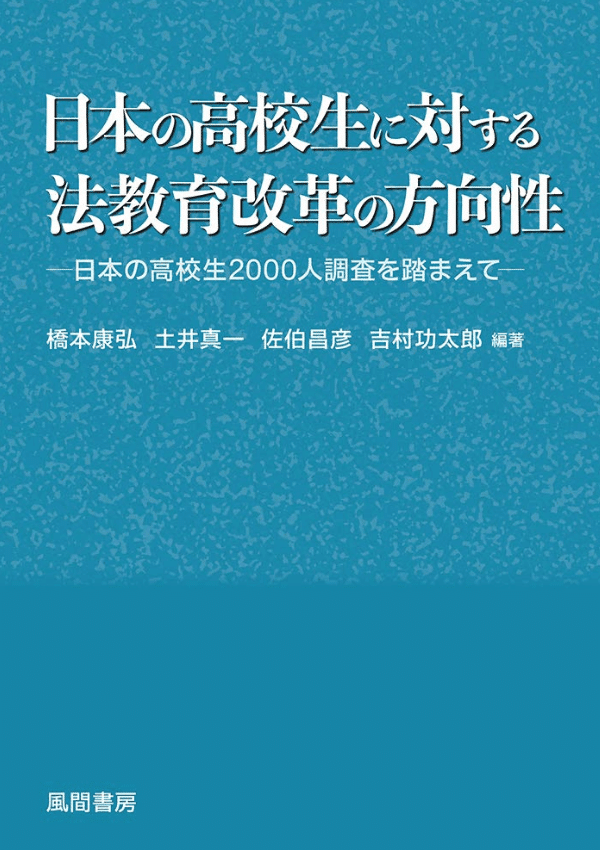
高校生2000人を対象としたアンケート調査から、高校生の「法知識」と「法意見」の現状と課題を認識し、課題を解決するための教育プログラムを開発する…という作業を第2章第2節までで行っているのだが、その作業に関わっていない第三者が問題設定そのものを批判する第2章第3節が面白い。第2章第2節までは、第2章第3節を楽しむための壮大な前振りだと考えるのが良いだろう。
第1章:高校生の法知識・法意見に関する質問紙調査
第1章「日本の高校生はどのような法知識・法意見・法意識を有しているのか?」では、高校生約2000人を対象としたアンケート調査をもとに、高校生の法知識・法意見の現状を把握するとともに、法知識・法意見を左右する要因を推測する。
法知識と法意見について「黙秘権」に関わる例を挙げると、法知識とは「QK:日本国憲法では、被疑者や被告人は、取り調べや裁判のときに、自分が犯した罪をすべて正直に言わないといけないと定められている」という問いに対する答えとして表され(※正解はNo)、法意見とは「QB:被疑者・被告人は真実を明らかにするために知っていることを正直に話すべきだと思う」という問いに対する答えとして表される。
アンケート調査では回答者の属性(性別・家の蔵書数・公民系科目の履修歴等)を問う項目も含まれており、回答者の属性と法知識の相関関係や、法知識と法意見の相関関係が分析されている。
第1章の結論として、法知識と法意見の関連について、憲法が黙秘権を保障していることを理解しているにもかかわらず「被疑者・被告人は知っていることを正直に話すべきだ」という意見を持つこと(QKにNoと答えつつ、QBにYesと答える)ことは“論理的矛盾”であり、矛盾の原因を探るとともに矛盾を解消する(正しい法知識と整合するような法意見を持たせる)教育プログラムを開発することが必要だという指摘される。
第2章第1~2節:「黙秘権」に関する法知識と法意見の矛盾を解消するための教育プログラム
第2章第1~2節では、「黙秘権に関する法知識と法意見の論理的矛盾をどうすれば解消できるか」という問題設定のもと、2コマ(ないし4コマ)の教育プログラムを開発し、それを2つの高校で実施した結果を分析するものである。 ※2つの高校に共通するプログラムとして2コマ分の授業案が用意され、片方の高校ではその前後に付加的な授業案が1コマずつ追加された。
2校に共通する2コマ分の授業案は、1時間目に「黙秘権が認められるに至った歴史的経緯」として過去に自白を引き出すために拷問が行われていたことなどを学習し、2時間目に「黙秘権がないとどうなるか」を考えるために虚偽の自白によって誤った有罪判決が出されてしまった事例などを扱うという構成だ。
授業前アンケートにおいてはもちろん、授業後アンケートにおいてさえ(特に高学力校の)生徒が「黙秘権を法律上の権利として認めることは適切/被疑者は取り調べにおいて知っていることを正直に話すべき」と答える割合が高かったことである(高学力校においては66.8%)。この“論理的矛盾”を解く鍵となる生徒の発言のうち、2つを以下に引用する。
文章によってとらえ方が違ってくるが、裁判全体としては真実を明らかにすべきであるが、被疑者自身が真実を明らかにするために正直に話をしなければいけないということはない。話さない権利もあるはずだ。
自白の強要をされたときに、黙秘権がないと黙っていてはいけないことになってしまう。無実であったときとかの場合に、誤ったことにつながりかねないので、黙秘権は認めておく必要があると思う。
(一方で)話をしないことには真実は明らかにならない。心持ちとして、正直に話すべきであるということは持っておいた方が良い。
ここまで生徒がヒントを出してくれているのに著者らが気づかないのが不思議であるが、「法制度としては黙秘権を保障する必要があるが、個人の行動規範としては黙秘権の行使にはなるべく自制的であるべきだ」という立場は論理的に矛盾している訳ではない。…という話を説得的に論じてくれているのが、このあとに続く第2章第3節だ。
第2章第3節:刑訴法学者笠倉宏紀による刑訴法教育への提言
第2章第3節は、アンケート調査や教育プログラム開発に関わっていない中立的な第三者として、慶應大学の刑訴法学教授である笠倉宏紀氏が上述の問題設定上の誤りを指摘するものだ。
本教育プログラムは「黙秘権の法的保障が必要である」という法制度に対する意見と「被疑者は知っていることを話すべきだ」という個人の行動規範に対する意見が同居することを“論理的矛盾”だと評価し、法的判断が「道徳」に引きずられる「誤り」を犯したものだとされているが、そもそも「法」と「道徳」は別次元の問題だし、「法」の世界から「道徳」を排除することが正しい法理解に資するとは言えない。また、それ以前に、本教育プログラムはそうした「法」と「道徳」の複雑な関係に言及した形跡すらない。
法の世界には一般道徳と矛盾するかに見える規範が数多くあるが、黙秘権の保障はその典型例である。だが、そもそも「黙秘権を保障すべきである」という意見は普遍的なものではなく、例えば功利主義の提唱者として知られるジェレミー・ベンサムは黙秘権不要論を展開したし、中国の刑法は被疑者に対して取り調べにおける真実供述義務を定めつつ、別途拷問による自白強要を禁止している。また、黙秘権を強力に保障する日本の刑事司法においてさえ、警察庁によるサンプリング調査で「罪の意識」から自白をした者が4割強と少なくない割合を占めることが明らかにされている(黙秘権があることが必ず告知されるにもかかわらず)。日本の刑事司法は少なからずこうした道徳的義務感に助けられているのであり、もしこうした自発的自白さえも無くなってしまったら、無実の人が「無実である」と確定されるのが遅れたり、検察側が有罪を確信する前に「あっさり起訴」して裁判所の判断に任せるようになって間違った起訴が増加したりする可能性がある。「権利として黙秘権が認められていることを知りつつ、あえてそれを行使せずに自白する」という被疑者の道徳的判断が、かえって無実の人を守っているのである。
法教育においては、表面的な法知識に基づいて素朴な道徳観を“断罪”するのではなく、法と道徳の関係性を含む刑事法の本質的争点に基づいて素朴な道徳観を“相対化”する実践が求められる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
