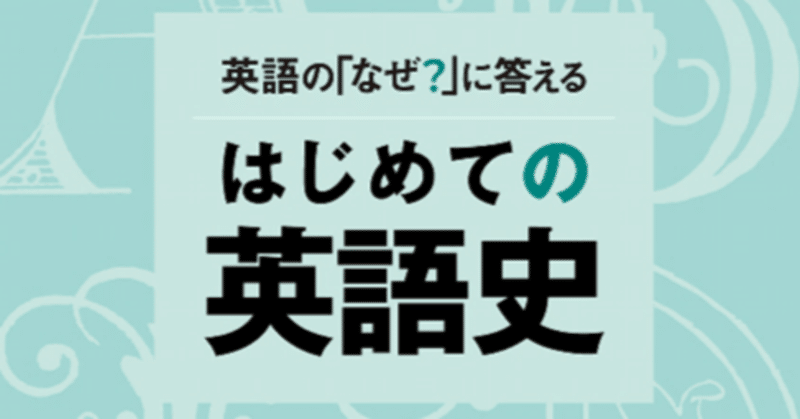
【ブックレビュー】『英語の「なぜ?」に答える はじめての英語史』
堀田隆一『英語の「なぜ?」に答える はじめての英語史』研究社、2016年

なぜ不定冠詞ではaとanが区別されているのだろう、なぜ3単現の-sなどというものがあるのだろう、なぜ仮定法では現在のことなのに過去形で表現するのだろう、なぜアメリカ英語とイギリス英語は異なっているのだろう、次々と疑問が湧いてくるはずだが、このような疑問にあまりこだわりすぎると語学学習上能率が悪いので、そのうちに問うことを止めてしまう。たいていそういうものだと吞み込んで、やりすごすよりほかない。しかし、一般に疑問は素朴であればあるほど本質的であり、その答えを知ろうと努力することは、英語のみならず日本語を含めた言語というものを理解するうえで、一見遠回りのように見えて、実は近道なのである。
冒頭の一節があまりに強烈で、折に触れて読み返したいと思わされる。中高における英語は数学と並んでとりわけ実用主義の強い圧力に晒されていて、「なぜ不規則動詞なんてものがあるんだろう?規則的な変化だけでは言語としてうまくいかないのだろうか?」なんてじっくり考えていたら瞬く間に置いていかれ、そのうち与えられる英文を満足に読みこなすことすらできなくなって、次第に興味をなくしてしまう。だから、素朴な疑問はなるべくはなるべく圧殺すること、知的好奇心に蓋をすることが求められる。もちろん、ひとたび「習得」できればそれによって世界が広がって知的好奇心を満たしてくれる様々なものに出会えるのだけど、「面白くなるまでが長い」というのは学習者にとってはストレスでしかない。
本書は、そうした事情で学び始めの頃に圧殺してきた素朴な疑問に応えてくれる。もっとも、この本の強みは一問一答的な理由付けを超えて、言語としての体系や歴史といった「物語」が感じられるように英語史の説明を厚くしているところにあるという(p.ⅳ)。そこで、本の趣旨を反映して第1章で取り上げられる英語史の概略を説明したあと、歴史的背景と絡める形で「素朴な疑問」の例を2つ取り上げたい。
いかにして英語は現在の姿になったのか? ——英語史入門
英語史の世界の通史として、過去に存在した英語は便宜上、古英語(449年~1100年頃)、中英語(1100年頃~1500年頃)、近代英語(1500年頃~1900年頃)、現代英語(1900年頃~)にわけられる。もっとも、それぞれの境界は明確に定まるものではないし、話し言葉と書き言葉が別々に変化していることと、とりわけ話し言葉の変化がグラジュアルであることには注意したい。
449年はアングロ・サクソン人がブリテン島を攻略したとされる年で、この象徴的な出来事をもって英語史の開始とするのが慣例だ。以降600年ほどアングロ・サクソン人の王朝が続くが、1066年にノルマン征服が起こり、フランスの一族であるノルマン人のウィリアム一世に王権を奪われる。その後400年ほどは中英語期と呼ばれ、フランス語からの借用語が増えるとともに、「二流の言語」に位置づけられた英語は自由気ままにドラスティックな変化を遂げた。その後に続く1500年以降の近代英語期は、ルネッサンスを経て近代に移り変わる時代で、シェイクスピアをはじめとする優れた英文学者が多く輩出された時代と重なる。1900年以降の現代英語期は、イギリスからアメリカに覇権が移行するとともに、英語が世界共通語としての地位を獲得した時代だ。
なぜdebt, doubtには発音しない〈b〉があるのか?
debtに〈b〉がねじ込まれたのは、近代英語期のことだ。debt(債務)はラテン語のdebtiumがフランス語経由で英語に借用されたものだが、フランス語から借用されたときにはすでに〈b〉が落ちてdetteという綴りになっていた。当然〈b〉の発音もない。ところが、ルネサンス期に借用元のフランス語でラテン語化したdebteが改めて用いられるようになり、おそらくそれに影響されて英語も〈b〉をねじ込んだdebtに綴りが変化した。doubtの〈b〉も同様の経緯で導入された。いわば、ラテン語にかぶれた学者(書かれていないが、おそらく神学者)の見栄である。
ポイントは、綴りに〈b〉がねじ込まれたにも関わらず、発音は〈b〉を取り戻さなかったという点にある。書き言葉としてのdebtに〈b〉をねじ込むことに成功した学者たちは、庶民の発音までもを改革しえた訳ではなかった。庶民は相変わらず中英語以来の「崩れた発音」を使い続けたのである。書き言葉と話し言葉が別々に変化することの一例だ。
一方で、「書かれているのだから発音しよう」という発想のもとで〈b〉を発音する動きも一部にはあったようだ。このような考え方は綴字発音と呼ばれ、現代英語ではoftenにおける〈t〉の発音に代表される。 ※〈t〉を発音する人の割合は米英で1/4にものぼるという(!)。
なぜ不規則動詞があるのか?
swim-swam-swumやgive-gave-givenのような不規則動詞は、高頻度語が多いため相当数あると思われがちだが、現在はよく使われるものでは70個程度しかない。古英語期には270個ほどあったものが、規則動詞化したり廃語となったりしたことで激減したのだ。例えば、help(助ける)の場合は、古英語ではhelpan-healp-holpenと活用していたものが、現代英語では規則動詞となった。
不規則動詞の中でもとりわけ変なものとしてgo-went-goneがある。goとgoneの繋がりはまだ許せるが、wentは明らかに異質だ(初歩的な語であるためみな許してしまっているが…)。wentはwend(向ける、向かう)という別の語の過去形であり、このように活用の一部に語源を異にする形態が入り込むことを補充法と呼ぶ。他には、good-wellやbe動詞などで見られる。
過去に多くの不規則動詞が存在していたことを踏まえると、「なぜ不規則動詞があるのか?」という問いは、「なぜ不規則動詞が生まれたのか?」という問いではなく、「なぜ一部の不規則動詞はいまだに規則動詞化していないのか?」という問いに還元されるべきだと言える。この問いに対する答えとして、「高頻度語は古い形を残す」という一般的な法則を指摘することができる。高頻度語は、子どもが最初に聞いて学習する単語であるから、過去形に-edを付すといった規則を習得する前に不規則形のまま丸暗記され、記憶の引き出しに格納されてしまうのだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
