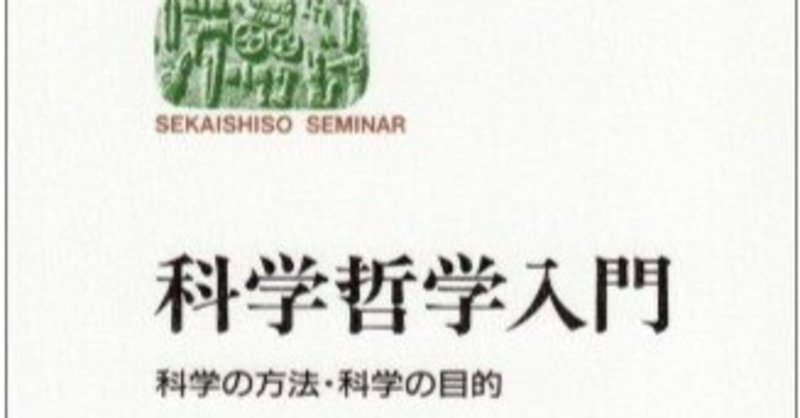
【ブックレビュー】『科学哲学入門』

教科書のようでいて、ときどき著者の見解が詳しく述べられる微妙な位置づけの入門書。科学哲学に興味を持って教養課程時代にそれなりに学んできた学生が、専門課程の序盤にこの本で歴史上の科学哲学者の実績を大雑把に把握して、その後専門分野を絞っていくイメージか。
一般的には(教養課程レベルの理解では)、科学哲学はベーコン&デカルト、論理実証主義&境界問題、ポパーの反証主義、クーンのパラダイム論あたりを"点で理解"されることが多いのではないか。
もうちょっと踏み込んでいる本書では、そのような素朴理解を打破するものとして以下のような内容に触れている。
・帰納主義はハーシェル、ヒューエル、ミルといった19世紀イギリスの科学哲学者によって厳密に定式化されており、「不完全な推論として棄却された」と片付けられるほど単純な代物ではない。帰納法の根幹にある「将来は過去に類似する」という仮定は確かに恣意的な仮定であるのかもしれないが、一方で演繹法ですら「推論規則」というある意味で恣意的な仮定を置いているのであり、仮定の恣意性をもって帰納法を不当だとみなすことはできない。
・19世紀の統計学の発展に伴って、「科学的知識の確率・統計的性質」を取り入れた科学哲学が発展した。「ある事象が観察されたとき、その背景に〜という条件が存在した可能性は○○%である」という"確率の逆算法"は、帰納的推論と結びつく形で新たな科学の基盤を為した(所謂ベイズ統計学である)。確率論的帰納法を発展させた科学哲学者としてラプラスやジェヴォンズが紹介されている。
・「科学的知識の確率・統計的性質」の認識は、演繹法にも影響した。演繹法は、法則と初期条件が与えられれば常に単一の結果を導くが、法則が確率的なものである場合は単一の結果を導くことができない。確率論的演繹法は、演繹的推論によって確率的な(単一でない)結果を導く。(AB型とO型の間にできは子は50%の確率でA型、のような)
・ポパーは帰納法を厳しく批判し、「反証主義」を提示した。個別的事象は一般法則を正当化できないが、反証することは可能であり、科学理論を「反証テスト」にかけることでより良い理論を選択できるとした。ところが、「科学的知識の確率・統計的性質」を考慮すると、個別的事象で一般法則を反証することも困難になる(AB型とO型の親がB型の子ばかり何人設けようと、遺伝法則は統計的手続き無しに反証されない)。
・また、ポパーは「過去に反証されていない理論は、少なくとも既に反証された理論よりは確からしい」としているが、「過去に誤らなかった理論はこれからも誤らないだろう」という信念は、「将来は過去に類似する」という帰納の原理とどう違うのだろうか。著者にしてみれば、反証主義が帰納主義より優れた科学哲学的立場だとは到底言えない。
・第4章で触れられる「何をもって科学的説明を加えたと言えるか」という問いも、科学哲学における重要なテーマだ。事象の原因を特定することであるとする因果説と、複数の事象に共通する法則を抽出することであるとする統合説があり、ミルは両者の調停を試みた。また、因果説は統計学と結びつくと「統計的説明」となる。「説明項が被説明項が生じる確率に違いをもたらしたか否か」が重要であるとしたウェス・サモンの主張は、現代の我々が大学で親しんでいる統計的因果説明の考え方そのものだろう。
・そもそも「説明」という行為には、理解不能なものを理解可能なものに置き換えるという行為だ。トゥルーミンは、そのときの人々(科学者)にとって理解可能なものを「自然的秩序の理想」と呼び、変化し得るものだとした。だとすれば、科学的説明は我々の直観と切り離して考えることは出来ないのだろう。
・第5章では、「観察の理論負荷性」について述べられている。我々が採用する理論は誤りである可能性があるとして、観察結果それ自体は確かなものと考えられるだろうか。「観察に理論負荷性がある」というのは、観察という行為も観察者が採用している理論に依拠する以上、観察結果も不確かであるという主張だ。著者は、理論と観察に関する科学史上の事例を取り上げつつ、「観察の理論負荷性」を否定する。
【コメント】しかし、「このような事例で、観察結果が理論に依存していたと言えるだろうか?」と直観に訴えるばかりで、論理的に明晰な議論がなされている訳ではない。一方で、『客観的知識』において「観察の理論負荷性」を肯定していたポパーも、「感覚器官がある種の理論を採用している以上、観察が理論に依拠するのは当然だ」とこちらも直観に訴えるような議論だ。互いに立証責任を押し付けあっているような印象があった。
・第6章はベイズの定理とベイズ主義の話。「発見の論理」は「正当化の論理」と区別されることが多いが、ベイズ主義は両者を区別しない。「当初考えていたある仮説の確からしさ」を事前確率と呼び、観測された事象によって事前確率を更新するのがベイズ主義の基本的な発想だ。更新された事前確率は「事後確率」と呼ばれ、それが新たな事前確率になる。ポイントは「真の(客観的)確からしさ」を観念しないことで、自分が持っている情報から合理的に導き出される主観確率を認める。事前確率には恣意性が入り込む余地があるが、事象の観測を充分に繰り返せば事後確率は収束する。もっとも、結論として得られるのが「事後確率:現在持っている情報から合理的に導かれる仮説の確からしさ」だから、有意水準を定めて帰無仮説を棄却したりしなかったりする(つまりYes/Noの二値で結論を下す)古典統計に慣れているとエッセンスをつかみづらい。
・第7章ではクーンのパラダイム論を批判している。『科学革命の構造』は、批判者からクーンを庇おうとしたマスターマンでさえ「パラダイムという言葉が異なる21の意味で使われている」と指摘せざるを得ないほど理論的に杜撰だった。クーンもそうした批判を受けて理論を精緻化させていったが、今度は逆に従来の科学哲学とほとんど見分けがつかないものになってしまう(例えば、良き科学理論の条件として正確さ/整合性/適用範囲の広さ/単純性/実り豊かさを挙げたことなど)。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
