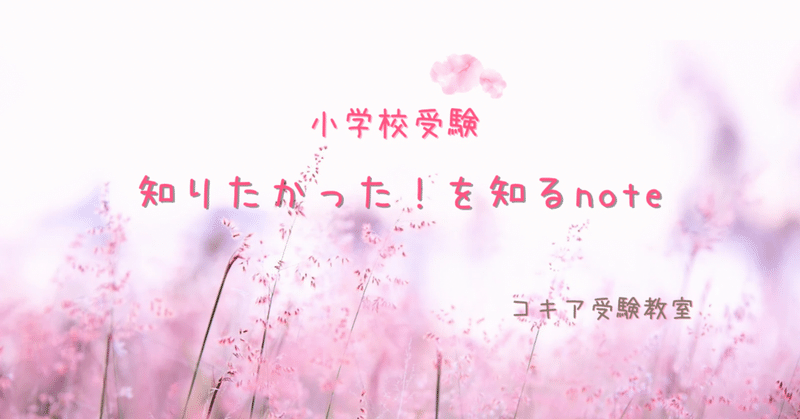
小学校受験 「ちゃんと」がちゃんと伝わっているか
こんにちは。コキア受験教室の桜井です。
昨日、我が子が取り組んでいる国語の問題集で、このような文章が掲載されていました。
「ちゃんとする」ことについては、もっと難しいことがあります。それは、人によってその内容が違っている場合です。
丸つけをしながらこの文章を読んでいて、ふと思い出したことがあります。
我が子の受験生時代、長子のハサミ切りが、どうしても上達しないことを巧緻性の先生に相談したことがありました。そのときに、確か「どれだけ丁寧に、綺麗にって伝えても伝わらないんですよ…」というようなことをお話したところ、「本人は丁寧に、綺麗にやっているつもりなんじゃないの?」と言われたんです。
それで、私も「あ、私の教え方が違ってたかも」と急にハッとしました。
それからは、「どうやったら、この子のハサミが、真っ直ぐ立った状態で画用紙に描かれた黒い線の中心をブレることなく切り進んでくれるか」ということをかなり懸命に研究しました。
◆背もたれに、もたれていないか。(手の可動範囲が狭まる)
◆足の裏は、床にピッタリついているか。(ブラブラしていると手がブレる)
◆脇は軽くしめているか。(手の可動範囲を広げる)
◆ハサミは、立てているか。
◆画用紙を持つ手の位置は変ではないか。
◆画用紙をピンと持てているか。
◆切り進む時、ハサミを閉じ切っていないか。
◆黒線の中央を切るとは、「黒線を右と左で半分こする」ということだと本人は理解しているか。
◆切るスピードが早すぎないか。
◆切るリズムは一定か。
私が集めただけでも、ハサミ切りにはこれだけのポイントがありました。
大人には、「丁寧に、綺麗に切って」と言うと、その認識はある程度一致しています。でも、完成形を知らない子どもは、もしかしたら「これの何が悪いの?」「どうやったら出来るのか分からないのに」と思っているかも知れません。
その不一致を減らすためには、どうするか。
それは、上記のポイントのように「より具体的に説明する」か親が一緒にやって「見本を見せてあげる」ということが必要になってきます。
ペーパーも同じです。
「なんで分からないの!」と思う親の横で、子どもは「どうしたら解けるのか分からない」と思っているのかも知れません。それなのに、親が同じ解き方に拘って教えていては、その不一致が解消に至るのはなかなか難しい。
そういうとき、親がやるべきことは「分かるまで何度も同じ説明してあげる」のではなく、「アプローチを変えること」です。もちろん、都度違うアプローチをしていては混乱するだけですので、そういう意味ではなく、子どもは親の説明を実践する努力をする一方で、親としても子どもが理解する方法を "探る" 努力が必要になりますよ、ということです。
集団塾だと、先生も一人一人に合う解き方を探るわけにはいかないので、どうしても引っかかってしまうお子様は出てきます。そして、そういうときに相談して他の解き方を一緒に探ってくれる先生だと良いのですが、必ずしもそういう先生ばかりではありません。それは、先生としての能力的な話でもありますが、抱えている生徒数だったり、塾としての方針であったり、そういう理由も考えられます。
ですから、ご自宅で勉強するときは、まず塾で教えてもらった方法で教える。でも、それがどうしても理解できないなら、親の方で他のアプローチを試してみましょう。もしかしたら、言い方ひとつでスッと腑に落ちるかも知れません。勉強とは、そんなものです。
もし策を出し切り、他のアプローチが思いつかなくなりましたら、ぜひコキアにも相談してみてくださいね。
テキストベースでのご相談は、LINEで24時間いつでも無料で受け付けておりますし、お子様への直接の指導をご希望であれば、4・5月は個別レッスンを特別に実施しております。また、KOKIA membership labでは、月に1回無料でお子様の個別レッスンを受講可能です。なにか突破口が見つかるかも知れません。
いずれにしましても、まだまだ今の時期に苦手分野を諦めるのは早すぎますので、是非しっかりと苦手分野の底上げをしていただけたらと思います!
☆学習についてのご相談は、LINEでお気軽にどうぞ(無料です)☆
☆当教室の主催する講座については、アメブロでご確認ください☆
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
