
【短編小説】十四時二十七分の停留所
※有料設定になっていますが、投げ銭方式なので全文無料で読めます。
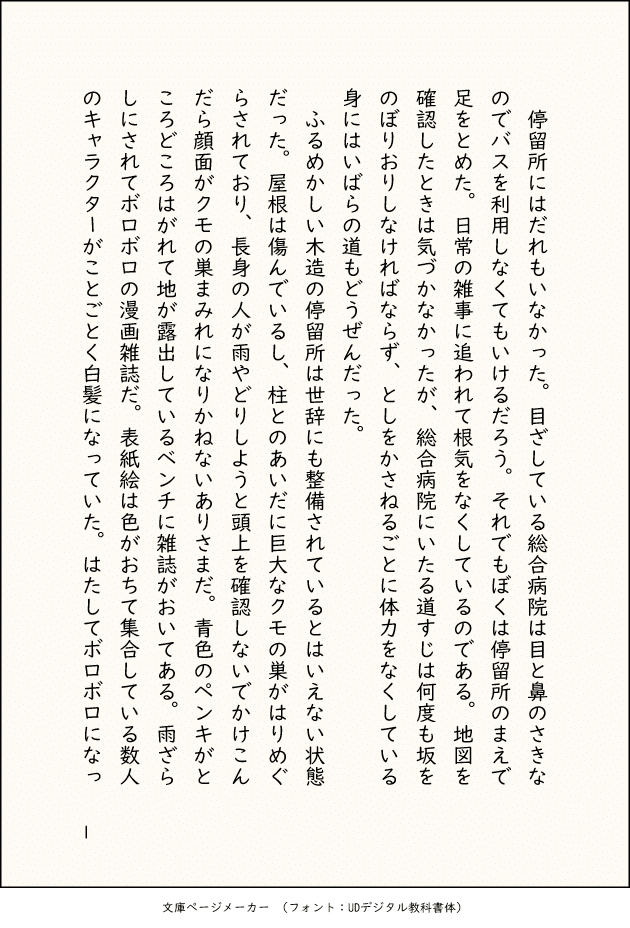
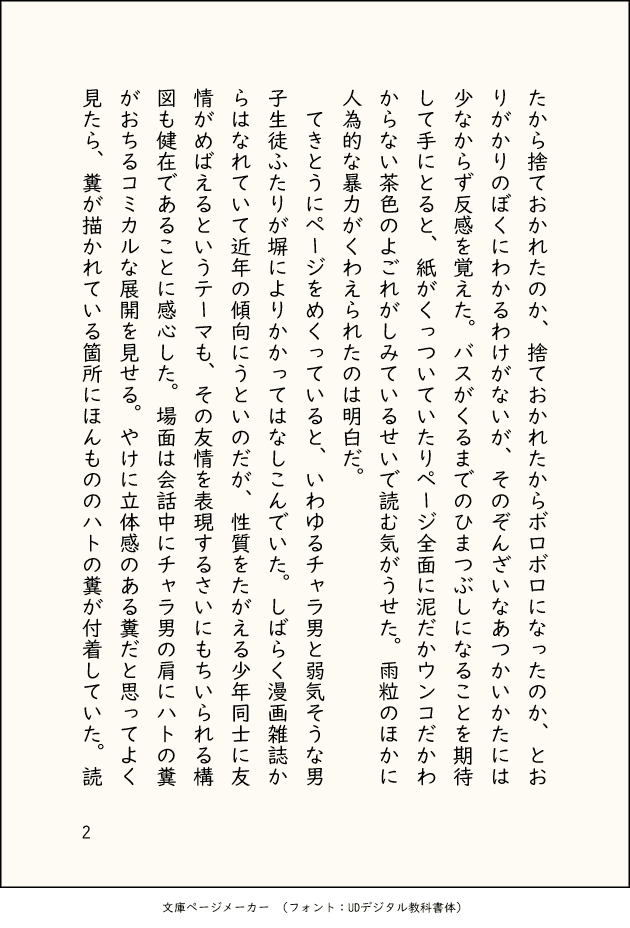
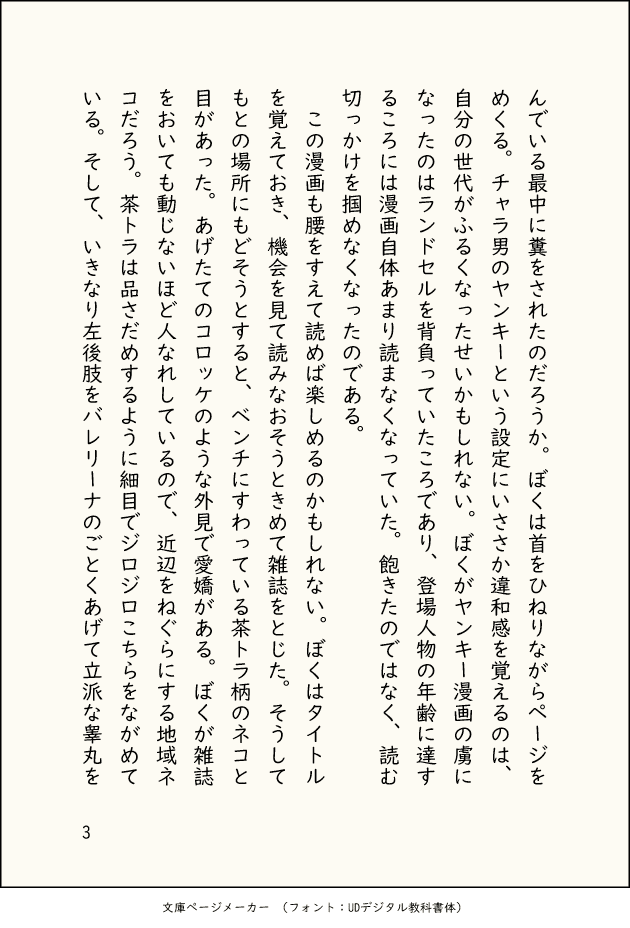
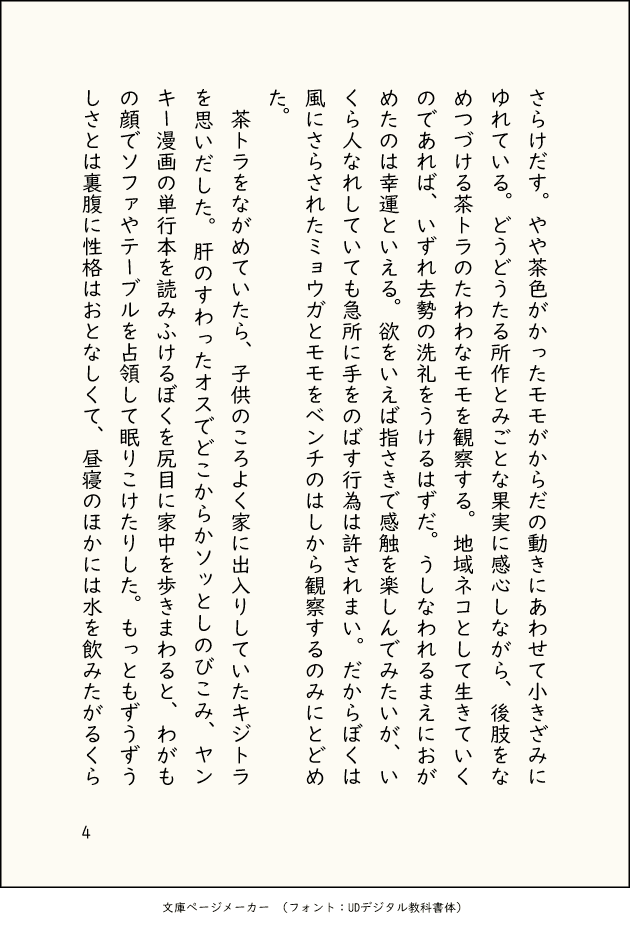
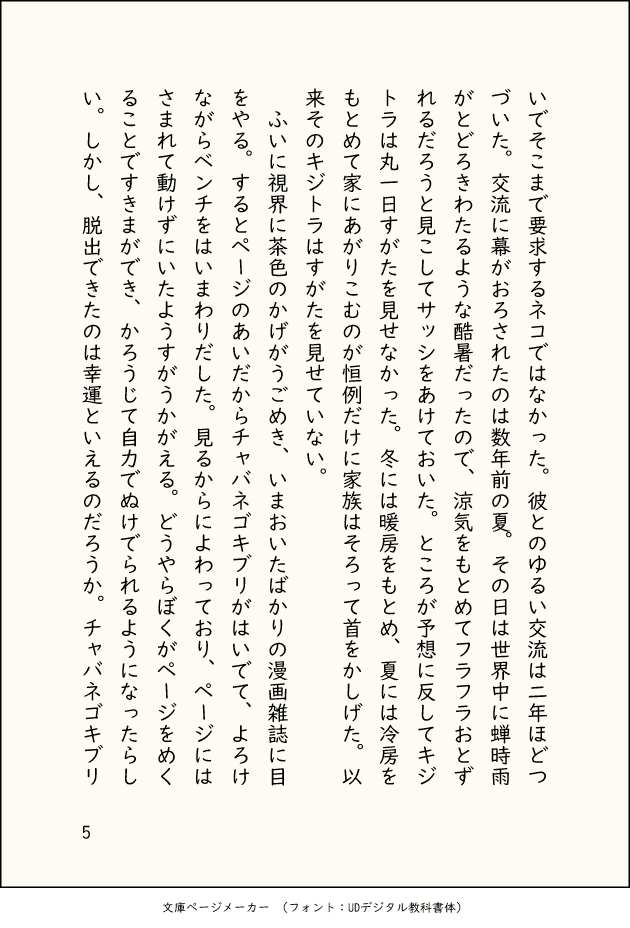
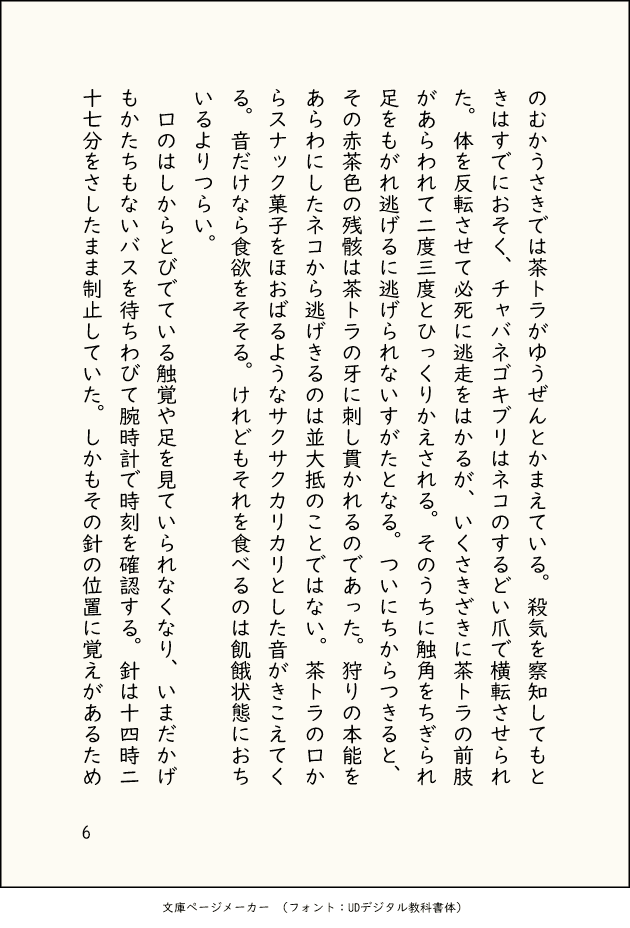
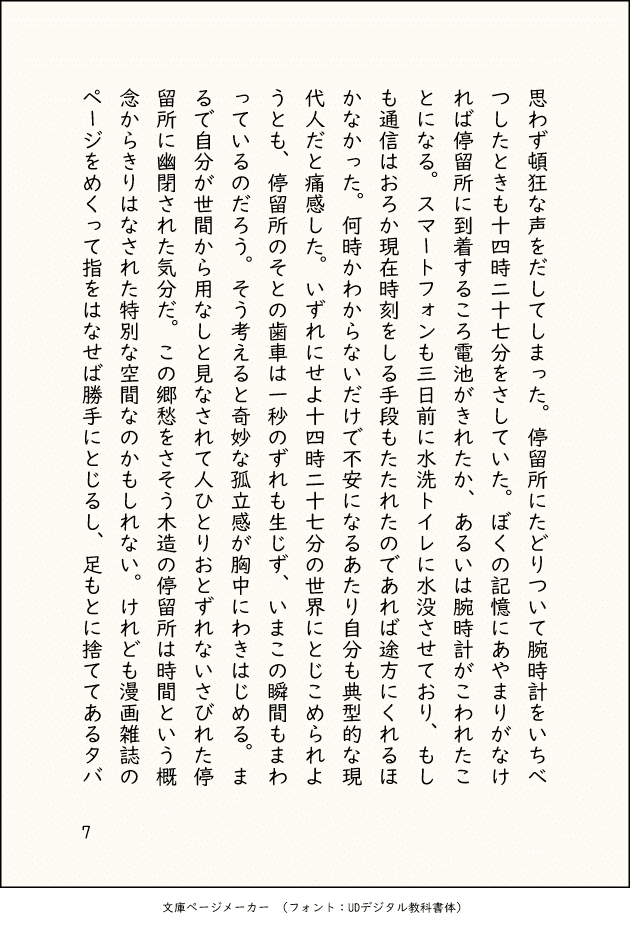
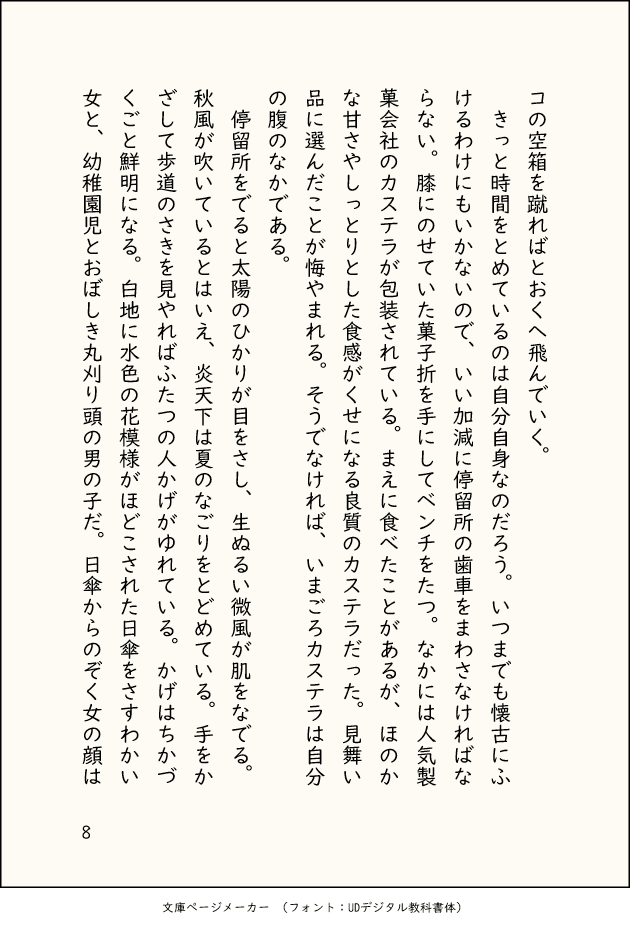
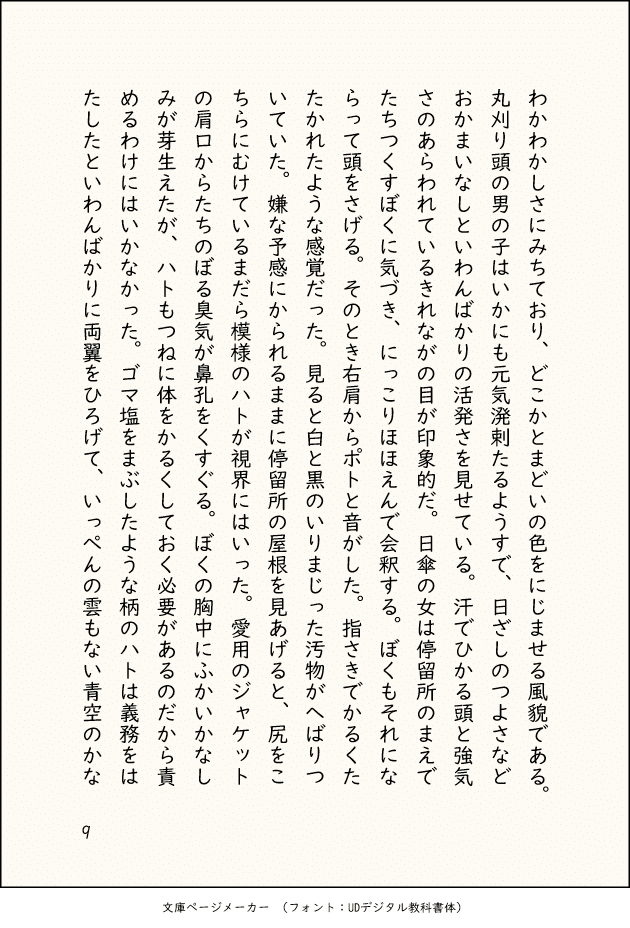
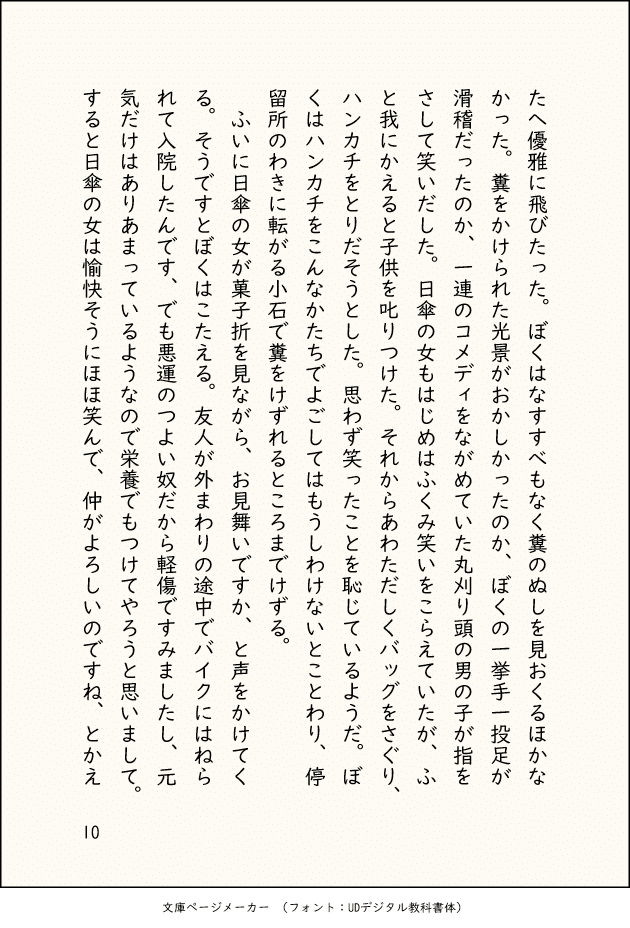
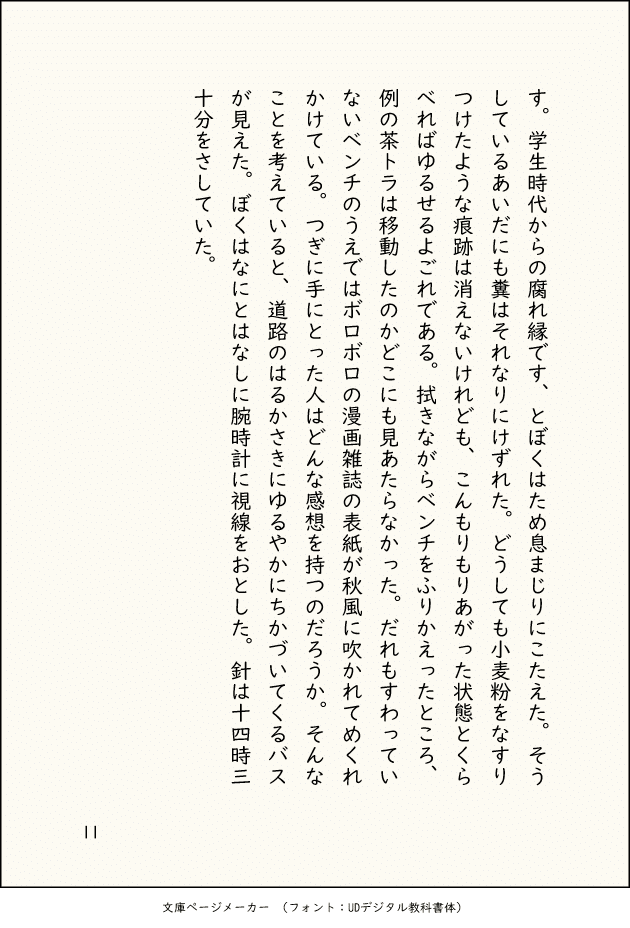
停留所にはだれもいなかった。目ざしている総合病院は目と鼻のさきなのでバスを利用しなくてもいけるだろう。それでもぼくは停留所のまえで足をとめた。日常の雑事に追われて根気をなくしているのである。地図を確認したときは気づかなかったが、総合病院にいたる道すじは何度も坂をのぼりおりしなければならず、としをかさねるごとに体力をなくしている身にはいばらの道もどうぜんだった。
ふるめかしい木造の停留所は世辞にも整備されているとはいえない状態だった。屋根は傷んでいるし、柱とのあいだに巨大なクモの巣がはりめぐらされており、長身の人が雨やどりしようと頭上を確認しないでかけこんだら顔面がクモの巣まみれになりかねないありさまだ。青色のペンキがところどころはがれて地が露出しているベンチに雑誌がおいてある。雨ざらしにされてボロボロの漫画雑誌だ。表紙絵は色がおちて集合している数人のキャラクターがことごとく白髪になっていた。はたしてボロボロになったから捨ておかれたのか、捨ておかれたからボロボロになったのか、とおりがかりのぼくにわかるわけがないが、そのぞんざいなあつかいかたには少なからず反感を覚えた。バスがくるまでのひまつぶしになることを期待して手にとると、紙がくっついていたりページ全面に泥だかウンコだかわからない茶色のよごれがしみているせいで読む気がうせた。雨粒のほかに人為的な暴力がくわえられたのは明白だ。
てきとうにページをめくっていると、いわゆるチャラ男と弱気そうな男子生徒ふたりが塀によりかかってはなしこんでいた。しばらく漫画雑誌からはなれていて近年の傾向にうといのだが、性質をたがえる少年同士に友情がめばえるというテーマも、その友情を表現するさいにもちいられる構図も健在であることに感心した。場面は会話中にチャラ男の肩にハトの糞がおちるコミカルな展開を見せる。やけに立体感のある糞だと思ってよく見たら、糞が描かれている箇所にほんもののハトの糞が付着していた。読んでいる最中に糞をされたのだろうか。ぼくは首をひねりながらページをめくる。チャラ男のヤンキーという設定にいささか違和感を覚えるのは、自分の世代がふるくなったせいかもしれない。ぼくがヤンキー漫画の虜になったのはランドセルを背負っていたころであり、登場人物の年齢に達するころには漫画自体あまり読まなくなっていた。飽きたのではなく、読む切っかけを掴めなくなったのである。
この漫画も腰をすえて読めば楽しめるのかもしれない。ぼくはタイトルを覚えておき、機会を見て読みなおそうときめて雑誌をとじた。そうしてもとの場所にもどそうとすると、ベンチにすわっている茶トラ柄のネコと目があった。あげたてのコロッケのような外見で愛嬌がある。ぼくが雑誌をおいても動じないほど人なれしているので、近辺をねぐらにする地域ネコだろう。茶トラは品さだめするように細目でジロジロこちらをながめている。そして、いきなり左後肢をバレリーナのごとくあげて立派な睾丸をさらけだす。やや茶色がかったモモがからだの動きにあわせて小きざみにゆれている。どうどうたる所作とみごとな果実に感心しながら、後肢をなめつづける茶トラのたわわなモモを観察する。地域ネコとして生きていくのであれば、いずれ去勢の洗礼をうけるはずだ。うしなわれるまえにおがめたのは幸運といえる。欲をいえば指さきで感触を楽しんでみたいが、いくら人なれしていても急所に手をのばす行為は許されまい。だからぼくは風にさらされたミョウガとモモをベンチのはしから観察するのみにとどめた。
茶トラをながめていたら、子供のころよく家に出入りしていたキジトラを思いだした。肝のすわったオスでどこからかソッとしのびこみ、ヤンキー漫画の単行本を読みふけるぼくを尻目に家中を歩きまわると、わがもの顔でソファやテーブルを占領して眠りこけたりした。もっともずうずうしさとは裏腹に性格はおとなしくて、昼寝のほかには水を飲みたがるくらいでそこまで要求するネコではなかった。彼とのゆるい交流は二年ほどつづいた。交流に幕がおろされたのは数年前の夏。その日は世界中に蝉時雨がとどろきわたるような酷暑だったので、涼気をもとめてフラフラおとずれるだろうと見こしてサッシをあけておいた。ところが予想に反してキジトラは丸一日すがたを見せなかった。冬には暖房をもとめ、夏には冷房をもとめて家にあがりこむのが恒例だけに家族はそろって首をかしげた。以来そのキジトラはすがたを見せていない。
ふいに視界に茶色のかげがうごめき、いまおいたばかりの漫画雑誌に目をやる。するとページのあいだからチャバネゴキブリがはいでて、よろけながらベンチをはいまわりだした。見るからによわっており、ページにはさまれて動けずにいたようすがうかがえる。どうやらぼくがページをめくることですきまができ、かろうじて自力でぬけでられるようになったらしい。しかし、脱出できたのは幸運といえるのだろうか。チャバネゴキブリのむかうさきでは茶トラがゆうぜんとかまえている。殺気を察知してもときはすでにおそく、チャバネゴキブリはネコのするどい爪で横転させられた。体を反転させて必死に逃走をはかるが、いくさきざきに茶トラの前肢があらわれて二度三度とひっくりかえされる。そのうちに触角をちぎられ足をもがれ逃げるに逃げられないすがたとなる。ついにちからつきると、その赤茶色の残骸は茶トラの牙に刺し貫かれるのであった。狩りの本能をあらわにしたネコから逃げきるのは並大抵のことではない。茶トラの口からスナック菓子をほおばるようなサクサクカリカリとした音がきこえてくる。音だけなら食欲をそそる。けれどもそれを食べるのは飢餓状態におちいるよりつらい。
口のはしからとびでている触覚や足を見ていられなくなり、いまだかげもかたちもないバスを待ちわびて腕時計で時刻を確認する。針は十四時二十七分をさしたまま制止していた。しかもその針の位置に覚えがあるため思わず頓狂な声をだしてしまった。停留所にたどりついて腕時計をいちべつしたときも十四時二十七分をさしていた。ぼくの記憶にあやまりがなければ停留所に到着するころ電池がきれたか、あるいは腕時計がこわれたことになる。スマートフォンも三日前に水洗トイレに水没させており、もしも通信はおろか現在時刻をしる手段もたたれたのであれば途方にくれるほかなかった。何時かわからないだけで不安になるあたり自分も典型的な現代人だと痛感した。いずれにせよ十四時二十七分の世界にとじこめられようとも、停留所のそとの歯車は一秒のずれも生じず、いまこの瞬間もまわっているのだろう。そう考えると奇妙な孤立感が胸中にわきはじめる。まるで自分が世間から用なしと見なされて人ひとりおとずれないさびれた停留所に幽閉された気分だ。この郷愁をさそう木造の停留所は時間という概念からきりはなされた特別な空間なのかもしれない。けれども漫画雑誌のページをめくって指をはなせば勝手にとじるし、足もとに捨ててあるタバコの空箱を蹴ればとおくへ飛んでいく。
きっと時間をとめているのは自分自身なのだろう。いつまでも懐古にふけるわけにもいかないので、いい加減に停留所の歯車をまわさなければならない。膝にのせていた菓子折を手にしてベンチをたつ。なかには人気製菓会社のカステラが包装されている。まえに食べたことがあるが、ほのかな甘さやしっとりとした食感がくせになる良質のカステラだった。見舞い品に選んだことが悔やまれる。そうでなければ、いまごろカステラは自分の腹のなかである。
停留所をでると太陽のひかりが目をさし、生ぬるい微風が肌をなでる。秋風が吹いているとはいえ、炎天下は夏のなごりをとどめている。手をかざして歩道のさきを見やればふたつの人かげがゆれている。かげはちかづくごと鮮明になる。白地に水色の花模様がほどこされた日傘をさすわかい女と、幼稚園児とおぼしき丸刈り頭の男の子だ。日傘からのぞく女の顔はわかわかしさにみちており、どこかとまどいの色をにじませる風貌である。丸刈り頭の男の子はいかにも元気溌剌たるようすで、日ざしのつよさなどおかまいなしといわんばかりの活発さを見せている。汗でひかる頭と強気さのあらわれているきれながの目が印象的だ。日傘の女は停留所のまえでたちつくすぼくに気づき、にっこりほほえんで会釈する。ぼくもそれにならって頭をさげる。そのとき右肩からポトと音がした。指さきでかるくたたかれたような感覚だった。見ると白と黒のいりまじった汚物がへばりついていた。嫌な予感にかられるままに停留所の屋根を見あげると、尻をこちらにむけているまだら模様のハトが視界にはいった。愛用のジャケットの肩口からたちのぼる臭気が鼻孔をくすぐる。ぼくの胸中にふかいかなしみが芽生えたが、ハトもつねに体をかるくしておく必要があるのだから責めるわけにはいかなかった。ゴマ塩をまぶしたような柄のハトは義務をはたしたといわんばかりに両翼をひろげて、いっぺんの雲もない青空のかなたへ優雅に飛びたった。ぼくはなすすべもなく糞のぬしを見おくるほかなかった。糞をかけられた光景がおかしかったのか、ぼくの一挙手一投足が滑稽だったのか、一連のコメディをながめていた丸刈り頭の男の子が指をさして笑いだした。日傘の女もはじめはふくみ笑いをこらえていたが、ふと我にかえると子供を叱りつけた。それからあわただしくバッグをさぐり、ハンカチをとりだそうとした。思わず笑ったことを恥じているようだ。ぼくはハンカチをこんなかたちでよごしてはもうしわけないとことわり、停留所のわきに転がる小石で糞をけずれるところまでけずる。
ふいに日傘の女が菓子折を見ながら、お見舞いですか、と声をかけてくる。そうですとぼくはこたえる。友人が外まわりの途中でバイクにはねられて入院したんです、でも悪運のつよい奴だから軽傷ですみましたし、元気だけはありあまっているようなので栄養でもつけてやろうと思いまして。すると日傘の女は愉快そうにほほ笑んで、仲がよろしいのですね、とかえす。学生時代からの腐れ縁です、とぼくはため息まじりにこたえた。そうしているあいだにも糞はそれなりにけずれた。どうしても小麦粉をなすりつけたような痕跡は消えないけれども、こんもりもりあがった状態とくらべればゆるせるよごれである。拭きながらベンチをふりかえったところ、例の茶トラは移動したのかどこにも見あたらなかった。だれもすわっていないベンチのうえではボロボロの漫画雑誌の表紙が秋風に吹かれてめくれかけている。つぎに手にとった人はどんな感想を持つのだろうか。そんなことを考えていると、道路のはるかさきにゆるやかにちかづいてくるバスが見えた。ぼくはなにとはなしに腕時計に視線をおとした。針は十四時三十分をさしていた。
※2015年脱稿・2017年改稿
ここから先は
¥ 100
お読みいただき、ありがとうございます。 今後も小説を始め、さまざまな読みものを公開します。もしもお気に召したらサポートしてくださると大変助かります。サポートとはいわゆる投げ銭で、アカウントをお持ちでなくてもできます。
