
【短編小説】救われた日 ~雪と記憶~
※有料設定になっていますが、投げ銭方式なので全文無料で読めます。
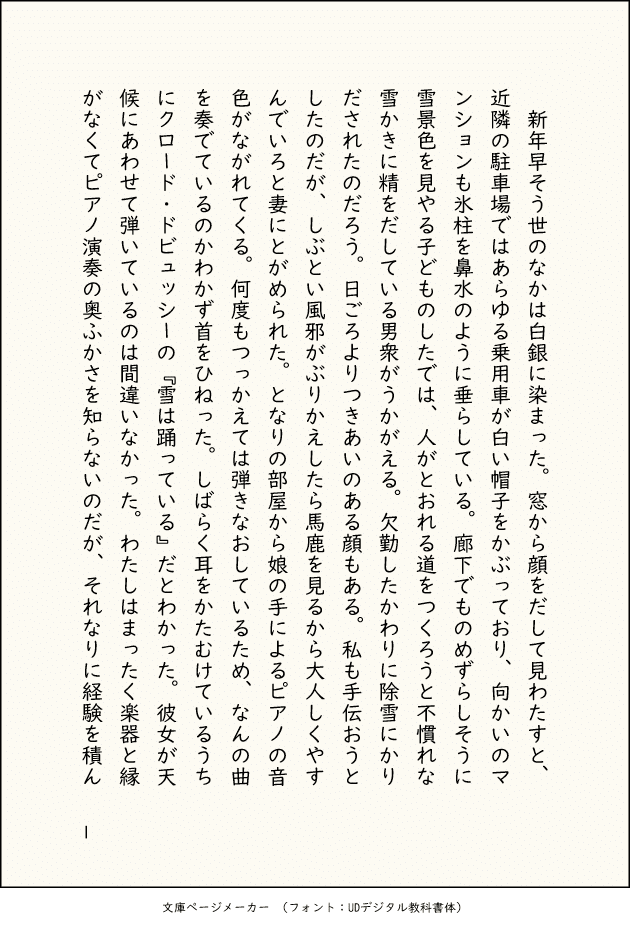


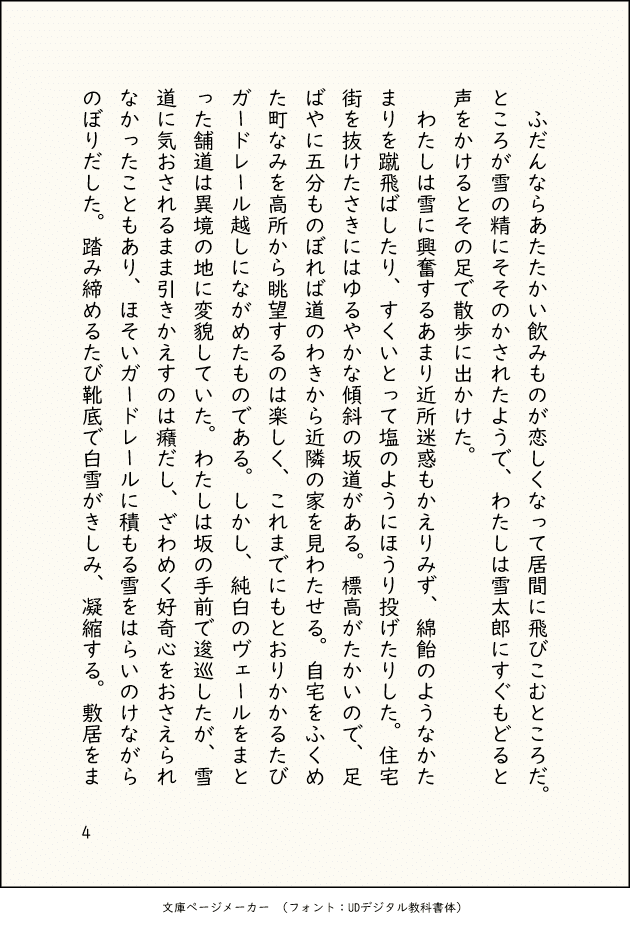
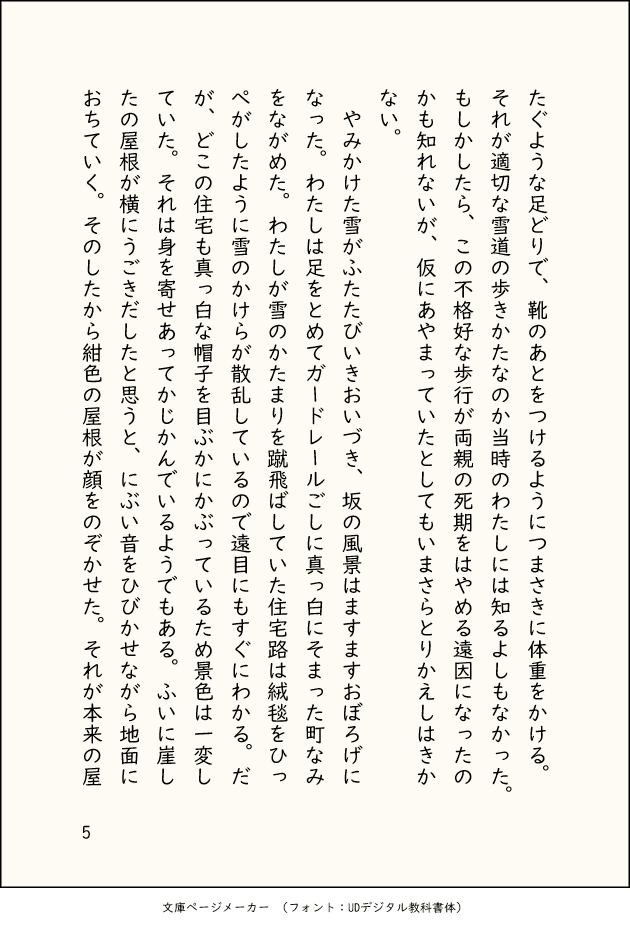
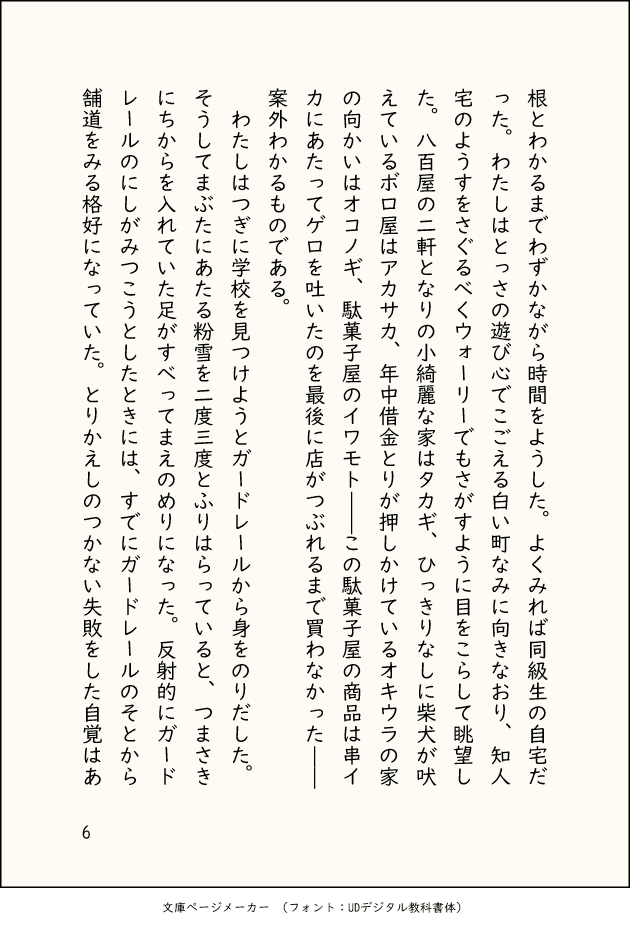
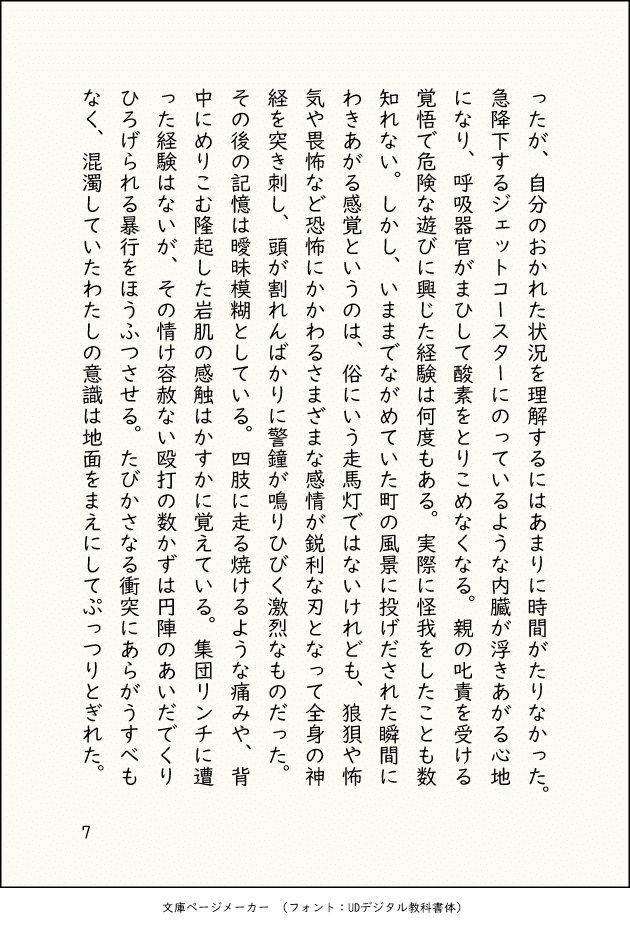
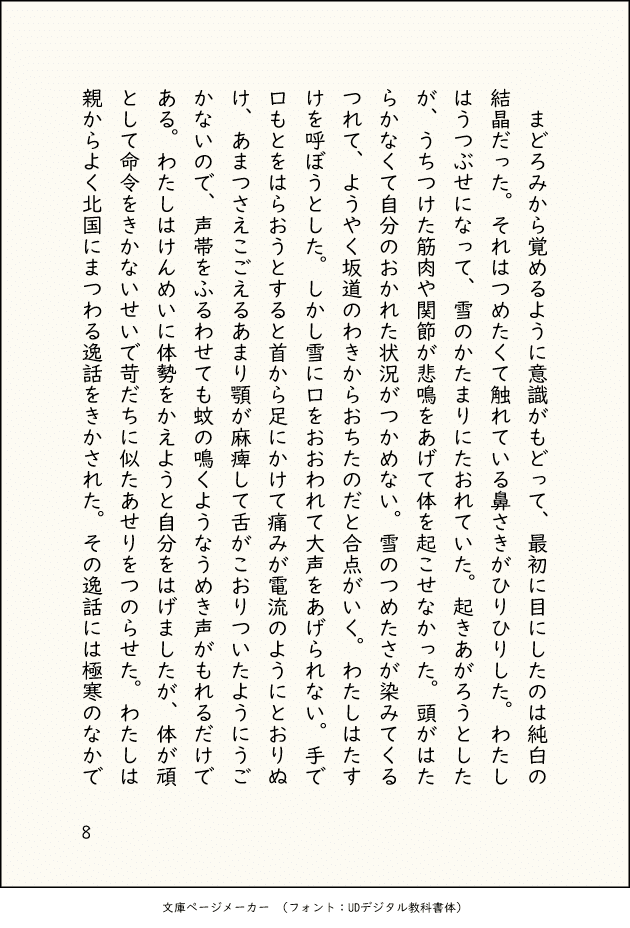

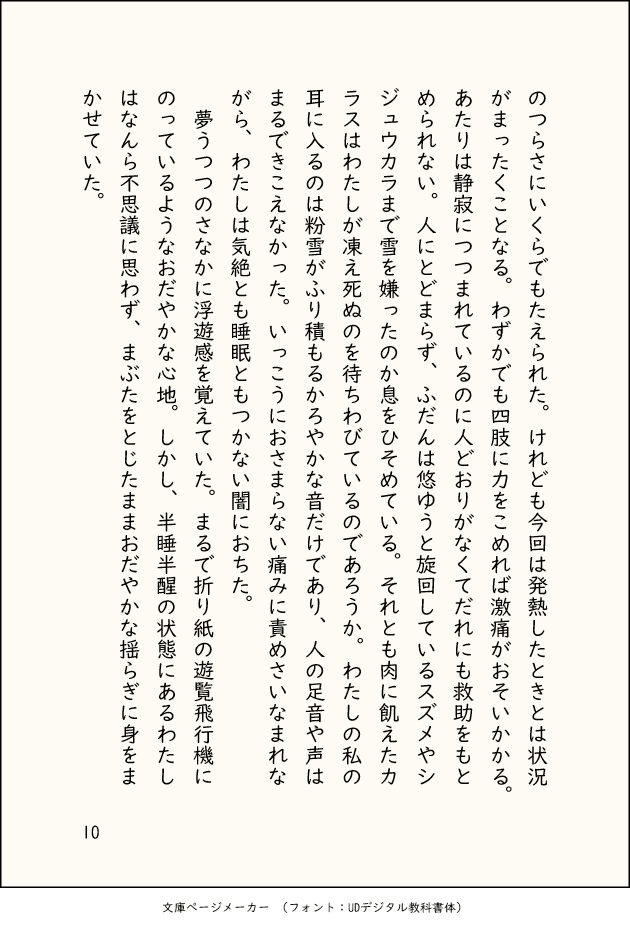
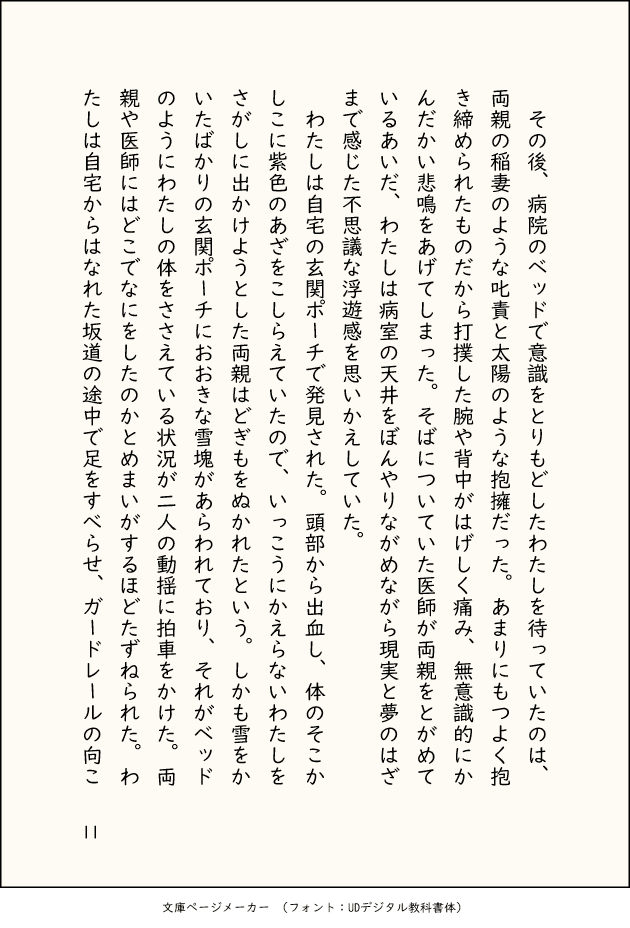

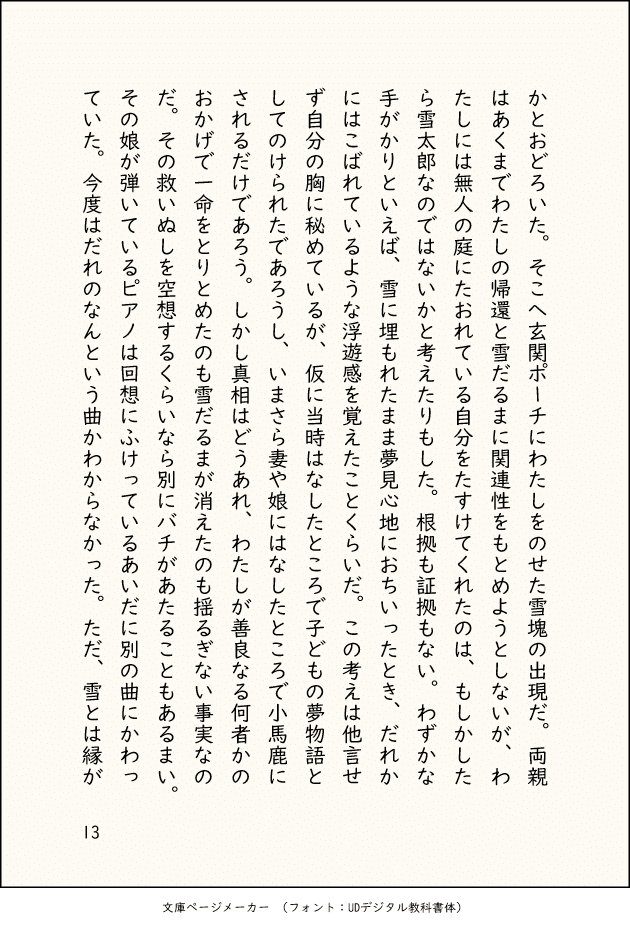
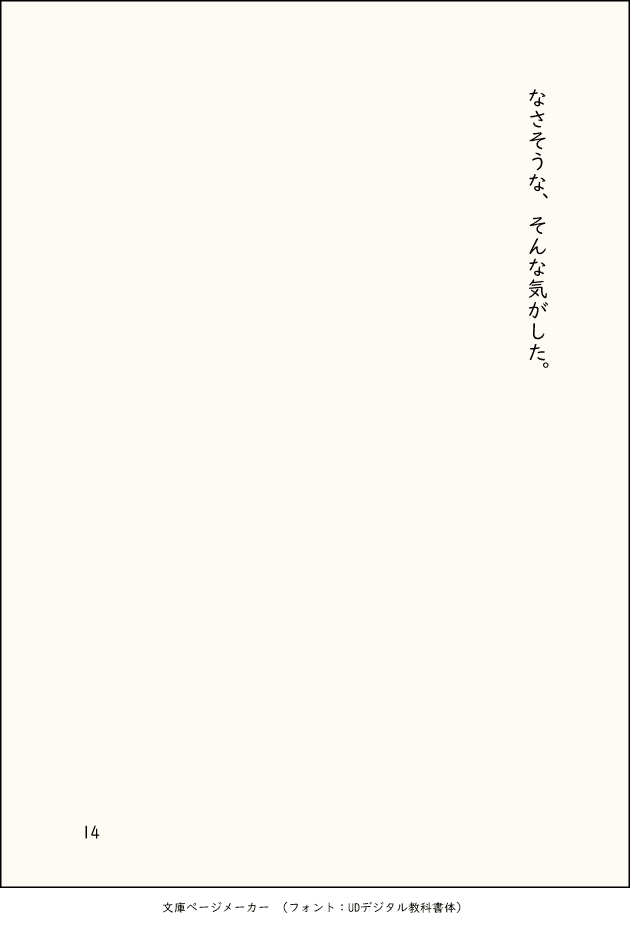
新年早そう世のなかは白銀に染まった。窓から顔をだして見わたすと、近隣の駐車場ではあらゆる乗用車が白い帽子をかぶっており、向かいのマンションも氷柱を鼻水のように垂らしている。廊下でものめずらしそうに雪景色を見やる子どものしたでは、人がとおれる道をつくろうと不慣れな雪かきに精をだしている男衆がうかがえる。欠勤したかわりに除雪にかりだされたのだろう。日ごろよりつきあいのある顔もある。私も手伝おうとしたのだが、しぶとい風邪がぶりかえしたら馬鹿を見るから大人しくやすんでいろと妻にとがめられた。となりの部屋から娘の手によるピアノの音色がながれてくる。何度もつっかえては弾きなおしているため、なんの曲を奏でているのかわかず首をひねった。しばらく耳をかたむけているうちにクロード・ドビュッシーの『雪は踊っている』だとわかった。彼女が天候にあわせて弾いているのは間違いなかった。わたしはまったく楽器と縁がなくてピアノ演奏の奥ふかさを知らないのだが、それなりに経験を積んでいる娘が手こずるのだから、きっとむずかしい曲なのだと一人で納得する。
昨今では雪が積もるのはめずらしいことだ。私が子どものころは大雪に見舞われることもおおく、小寒をすぎてからはよく雪道に足あとをつけながら登校していた。それだけに雪にまつわる思い出は豊富なのだ。雪合戦をやりすぎて肺炎をわずらったこともあるし、雪の絨毯がしかれた肥溜めにおちたこともある。年輪をかさねたいまだから過去の失態を笑いばなしの種にできるが、数えきれないほど命にかかわる災難に遭ってきたので、両親にはおまえのせいで二十年は寿命がちぢんだと耳にたこができるほどなげかれた。けれども両親の嘆きは比喩でも冗談でもなかった。実際に二人とも七十路をまえにして他界したのである。もしも彼らの薄命に一枚噛んでいるとしたら親不孝者としての十字架をせおわなければならない。特にもっとも無鉄砲な時分に巻き起こした騒動は両親の寿命をおおいに消耗させたのではないだろうか。いっこうにやまない粉雪をながめたまま、わたしはおぼろげになりつつある記憶の箱をまさぐってみる。
当時のわたしは膝が埋まるほど積もった雪に興奮をかくせず、庭に飛びだすなり雪をころがしはじめた。計画性に欠け、しかも生来の不器用とくれば綺麗にまるめられるわけがなく、完成した雪だるまは全体のバランスがくずれているばかりか、レモンのような珍妙なかたちの頭部が心持ち右がわにずれていて不格好きわまりなかった。のっぺらぼうのままにはしておけないので、顔面にVサインを突っこみ目をつくる。バケツの帽子もほうきの腕もない質素な雪だるま。そのできばえは不細工なものではあるが、正真正銘の自作品だからわたしは満足した。せっかくつくった雪だるまなのだから雪太郎と名づけた。生まれたばかりなのに図体のおおきい雪太郎。庭におりてきた母が「こんなおおきい雪だるまよくつくったね」と感心するようすを見て、わたしは意気揚ようと胸をはった。
ふだんならあたたかい飲みものが恋しくなって居間に飛びこむところだ。ところが雪の精にそそのかされたようで、わたしは雪太郎にすぐもどると声をかけるとその足で散歩に出かけた。
わたしは雪に興奮するあまり近所迷惑もかえりみず、綿飴のようなかたまりを蹴飛ばしたり、すくいとって塩のようにほうり投げたりした。住宅街を抜けたさきにはゆるやかな傾斜の坂道がある。標高がたかいので、足ばやに五分ものぼれば道のわきから近隣の家を見わたせる。自宅をふくめた町なみを高所から眺望するのは楽しく、これまでにもとおりかかるたびガードレール越しにながめたものである。しかし、純白のヴェールをまとった舗道は異境の地に変貌していた。わたしは坂の手前で逡巡したが、雪道に気おされるまま引きかえすのは癪だし、ざわめく好奇心をおさえられなかったこともあり、ほそいガードレールに積もる雪をはらいのけながらのぼりだした。踏み締めるたび靴底で白雪がきしみ、凝縮する。敷居をまたぐような足どりで、靴のあとをつけるようにつまさきに体重をかける。それが適切な雪道の歩きかたなのか当時のわたしには知るよしもなかった。もしかしたら、この不格好な歩行が両親の死期をはやめる遠因になったのかも知れないが、仮にあやまっていたとしてもいまさらとりかえしはきかない。
やみかけた雪がふたたびいきおいづき、坂の風景はますますおぼろげになった。わたしは足をとめてガードレールごしに真っ白にそまった町なみをながめた。わたしが雪のかたまりを蹴飛ばしていた住宅路は絨毯をひっぺがしたように雪のかけらが散乱しているので遠目にもすぐにわかる。だが、どこの住宅も真っ白な帽子を目ぶかにかぶっているため景色は一変していた。それは身を寄せあってかじかんでいるようでもある。ふいに崖したの屋根が横にうごきだしたと思うと、にぶい音をひびかせながら地面におちていく。そのしたから紺色の屋根が顔をのぞかせた。それが本来の屋根とわかるまでわずかながら時間をようした。よくみれば同級生の自宅だった。わたしはとっさの遊び心でこごえる白い町なみに向きなおり、知人宅のようすをさぐるべくウォーリーでもさがすように目をこらして眺望した。八百屋の二軒となりの小綺麗な家はタカギ、ひっきりなしに柴犬が吠えているボロ屋はアカサカ、年中借金とりが押しかけているオキウラの家の向かいはオコノギ、駄菓子屋のイワモト——この駄菓子屋の商品は串イカにあたってゲロを吐いたのを最後に店がつぶれるまで買わなかった——案外わかるものである。
わたしはつぎに学校を見つけようとガードレールから身をのりだした。そうしてまぶたにあたる粉雪を二度三度とふりはらっていると、つまさきにちからを入れていた足がすべってまえのめりになった。反射的にガードレールのにしがみつこうとしたときには、すでにガードレールのそとから舗道をみる格好になっていた。とりかえしのつかない失敗をした自覚はあったが、自分のおかれた状況を理解するにはあまりに時間がたりなかった。急降下するジェットコースターにのっているような内臓が浮きあがる心地になり、呼吸器官がまひして酸素をとりこめなくなる。親の叱責を受ける覚悟で危険な遊びに興じた経験は何度もある。実際に怪我をしたことも数知れない。しかし、いままでながめていた町の風景に投げだされた瞬間にわきあがる感覚というのは、俗にいう走馬灯ではないけれども、狼狽や怖気や畏怖など恐怖にかかわるさまざまな感情が鋭利な刃となって全身の神経を突き刺し、頭が割れんばかりに警鐘が鳴りひびく激烈なものだった。その後の記憶は曖昧模糊としている。四肢に走る焼けるような痛みや、背中にめりこむ隆起した岩肌の感触はかすかに覚えている。集団リンチに遭った経験はないが、その情け容赦ない殴打の数かずは円陣のあいだでくりひろげられる暴行をほうふつさせる。たびかさなる衝突にあらがうすべもなく、混濁していたわたしの意識は地面をまえにしてぷっつりとぎれた。
まどろみから覚めるように意識がもどって、最初に目にしたのは純白の結晶だった。それはつめたくて触れている鼻さきがひりひりした。わたしはうつぶせになって、雪のかたまりにたおれていた。起きあがろうとしたが、うちつけた筋肉や関節が悲鳴をあげて体を起こせなかった。頭がはたらかなくて自分のおかれた状況がつかめない。雪のつめたさが染みてくるつれて、ようやく坂道のわきからおちたのだと合点がいく。わたしはたすけを呼ぼうとした。しかし雪に口をおおわれて大声をあげられない。手で口もとをはらおうとすると首から足にかけて痛みが電流のようにとおりぬけ、あまつさえこごえるあまり顎が麻痺して舌がこおりついたようにうごかないので、声帯をふるわせても蚊の鳴くようなうめき声がもれるだけである。わたしはけんめいに体勢をかえようと自分をはげましたが、体が頑として命令をきかないせいで苛だちに似たあせりをつのらせた。わたしは親からよく北国にまつわる逸話をきかされた。その逸話には極寒のなかで眠りにおちることは死を意味するという教訓がこめられていた。はなしの趣旨は別にあるのだが、なぜか当時のわたしには凍死のくだりがきわだっておそろしく、幽霊にとりつかれたかのごとくいいしれぬ不安におそわれがちになった。こうしたいきさつがあるだけに、身うごきがとれないまま体温をうばわれていく状況はわたしの恐怖心をあおった。しかもせっかくとりもどした意識がふたたびとおのこうとしていたので、せきたてられるように声にならない声をはきだして睡魔を追いはらった。けれども睡魔はいやらしくつきまとい、あの手この手でわたしを夢見心地にしようとする。いつしかわたしはインフルエンザにかかった前年の冬を回想していた。あのときも起きあがれないのが歯がゆくて、布団のなかでうらみがましくうめきつづけていた。夜なかに目を覚ましたわたしはさびしさにたえかね、うごかない体を引きずりながら母のいる居間を目ざした。特別な手あてはのぞんでいない。そばにいてくれるだけで充分なのだ。そのためなら高熱のつらさにいくらでもたえられた。けれども今回は発熱したときとは状況がまったくことなる。わずかでも四肢に力をこめれば激痛がおそいかかる。あたりは静寂につつまれているのに人どおりがなくてだれにも救助をもとめられない。人にとどまらず、ふだんは悠ゆうと旋回しているスズメやシジュウカラまで雪を嫌ったのか息をひそめている。それとも肉に飢えたカラスはわたしが凍え死ぬのを待ちわびているのであろうか。わたしの私の耳に入るのは粉雪がふり積もるかろやかな音だけであり、人の足音や声はまるできこえなかった。いっこうにおさまらない痛みに責めさいなまれながら、わたしは気絶とも睡眠ともつかない闇におちた。
夢うつつのさなかに浮遊感を覚えていた。まるで折り紙の遊覧飛行機にのっているようなおだやかな心地。しかし、半睡半醒の状態にあるわたしはなんら不思議に思わず、まぶたをとじたままおだやかな揺らぎに身をまかせていた。
その後、病院のベッドで意識をとりもどしたわたしを待っていたのは、両親の稲妻のような叱責と太陽のような抱擁だった。あまりにもつよく抱き締められたものだから打撲した腕や背中がはげしく痛み、無意識的にかんだかい悲鳴をあげてしまった。そばについていた医師が両親をとがめているあいだ、わたしは病室の天井をぼんやりながめながら現実と夢のはざまで感じた不思議な浮遊感を思いかえしていた。
わたしは自宅の玄関ポーチで発見された。頭部から出血し、体のそこかしこに紫色のあざをこしらえていたので、いっこうにかえらないわたしをさがしに出かけようとした両親はどぎもをぬかれたという。しかも雪をかいたばかりの玄関ポーチにおおきな雪塊があらわれており、それがベッドのようにわたしの体をささえている状況が二人の動揺に拍車をかけた。両親や医師にはどこでなにをしたのかとめまいがするほどたずねられた。わたしは自宅からはなれた坂道の途中で足をすべらせ、ガードレールの向こうがわに転落するまでのいきさつをはなした。彼らがしんじるには時間をようした。右足の半月板損傷や左足首捻挫にくわえ、数ヶ所に打撲傷をおった子どもが歩けるわけはない。そうなると、何者かの手だすけにより九死に一生をえたことになる。わたしが転落した場所は空家になってひさしい一軒家の庭だった。発見される見こみは非常にうすく、凍死しなかったのはまさに奇跡といえる。そのため救いぬしには返礼してしかるべきだといって親たちは奔走した。けれども無人の庭をおとずれる酔狂な人物をつきとめるのは骨が折れた。結局すったもんだのあげく、事故はとおりがかりの善人による無私無欲の救済としてかたづけられた。
しかし、わたしには思いあたるふしがあった。それは出かけるまえに庭でつくったおおきな雪だるまである。母のはなしによると、わたしが町にくりだしたあと庭の雪だるまも消えたのだという。くずれたり溶けたりした痕跡もないので、てっきり母はわたしが庭のそとにころがしていったのかとおどろいた。そこへ玄関ポーチにわたしをのせた雪塊の出現だ。両親はあくまでわたしの帰還と雪だるまに関連性をもとめようとしないが、わたしには無人の庭にたおれている自分をたすけてくれたのは、もしかしたら雪太郎なのではないかと考えたりもした。根拠も証拠もない。わずかな手がかりといえば、雪に埋もれたまま夢見心地におちいったとき、だれかにはこばれているような浮遊感を覚えたことくらいだ。この考えは他言せず自分の胸に秘めているが、仮に当時はなしたところで子どもの夢物語としてのけられたであろうし、いまさら妻や娘にはなしたところで小馬鹿にされるだけであろう。しかし真相はどうあれ、わたしが善良なる何者かのおかげで一命をとりとめたのも雪だるまが消えたのも揺るぎない事実なのだ。その救いぬしを空想するくらいなら別にバチがあたることもあるまい。その娘が弾いているピアノは回想にふけっているあいだに別の曲にかわっていた。今度はだれのなんという曲かわからなかった。ただ、雪とは縁がなさそうな、そんな気がした。
※2013年脱稿・2016年改稿。
ここから先は
¥ 100
お読みいただき、ありがとうございます。 今後も小説を始め、さまざまな読みものを公開します。もしもお気に召したらサポートしてくださると大変助かります。サポートとはいわゆる投げ銭で、アカウントをお持ちでなくてもできます。
