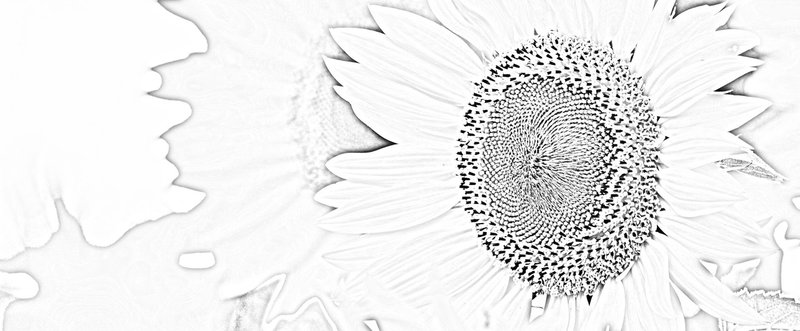
【短編小説】ヒマワリの季節に ~雪と記憶~
※有料設定になっていますが、投げ銭方式なので全文無料で読めます。
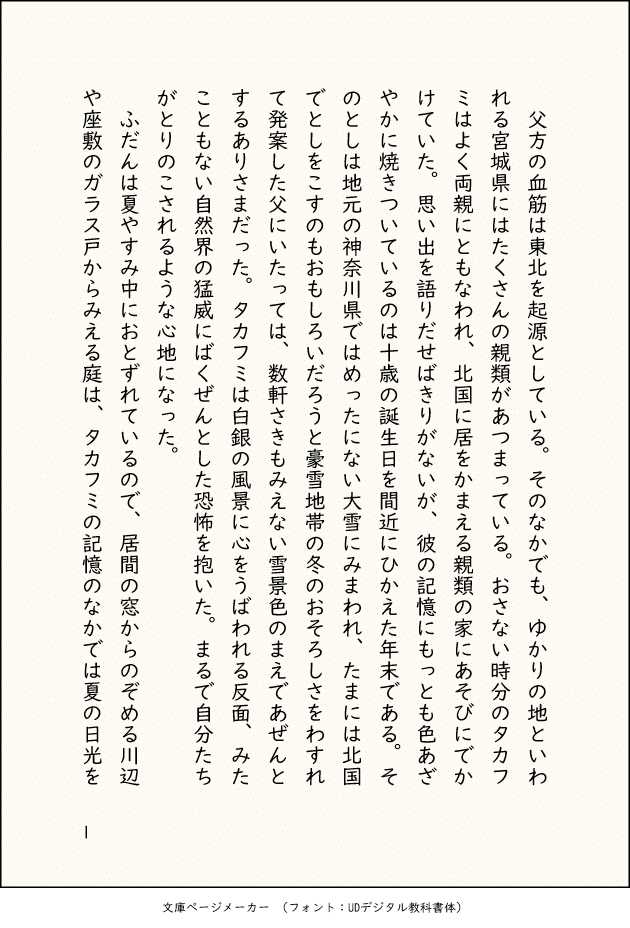
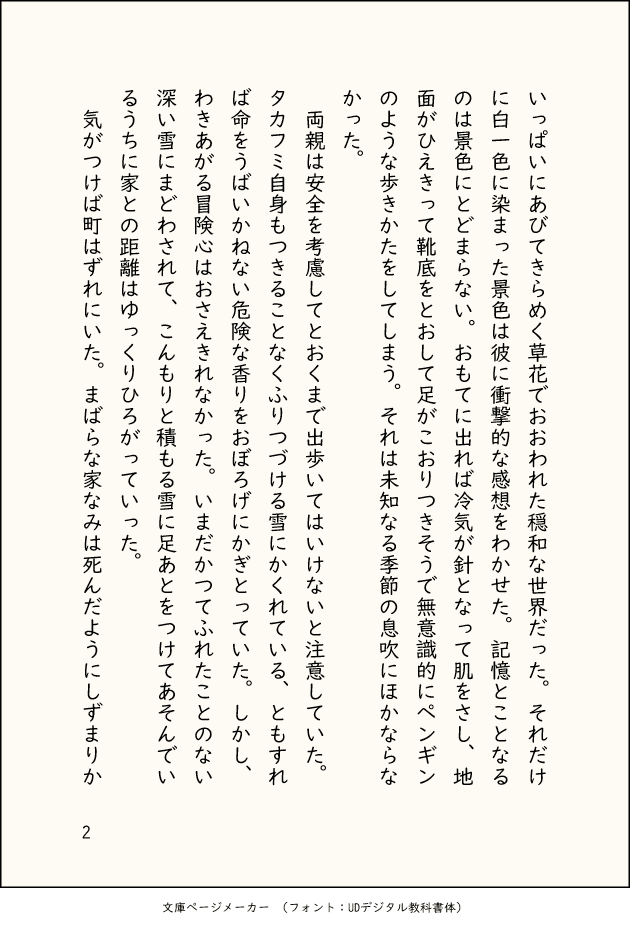


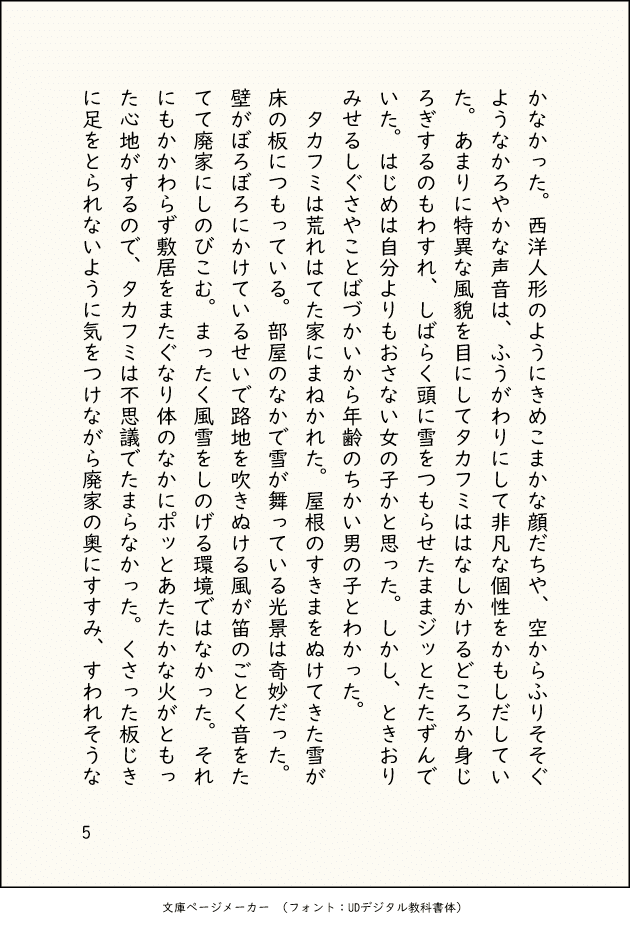
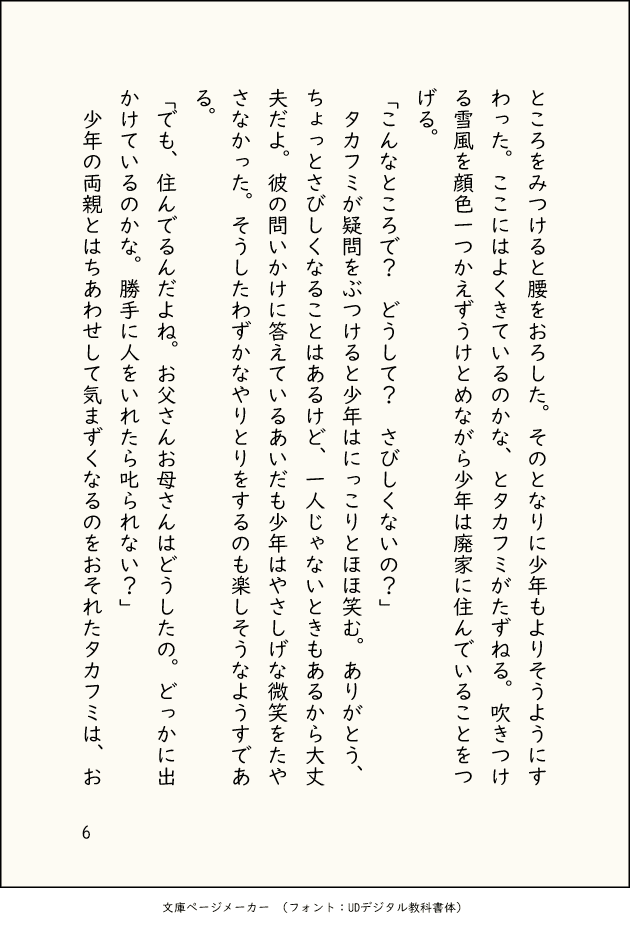
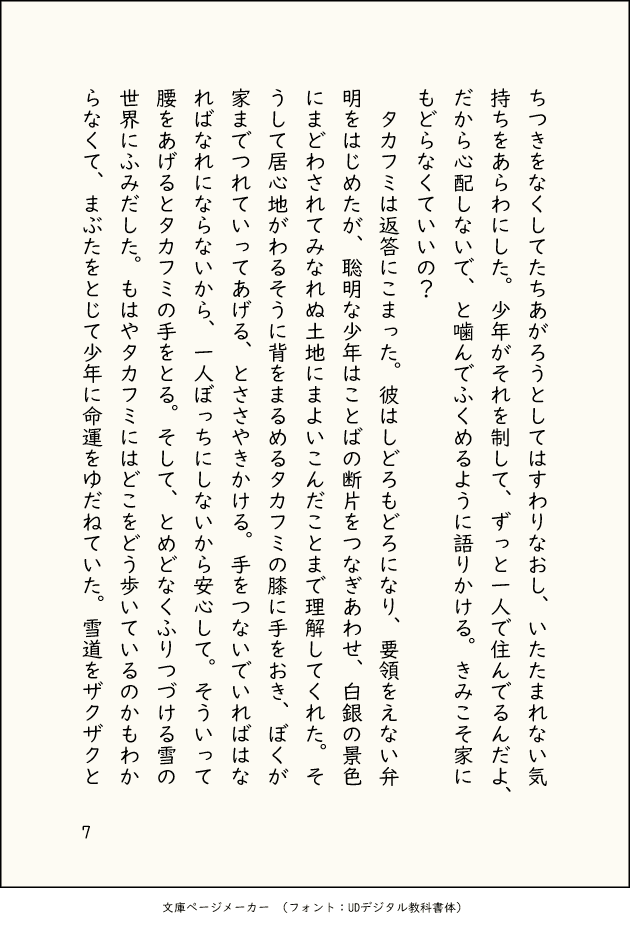

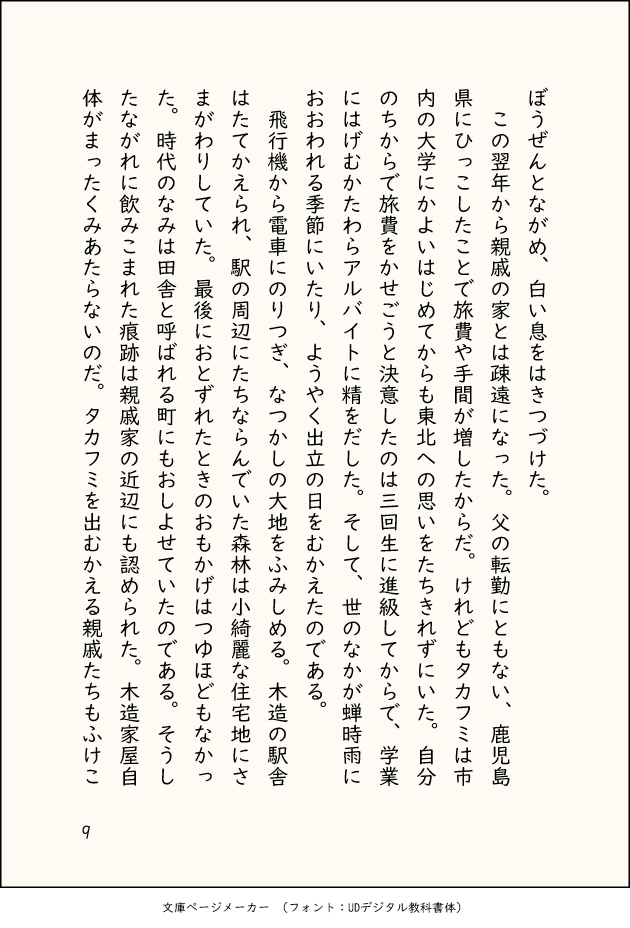
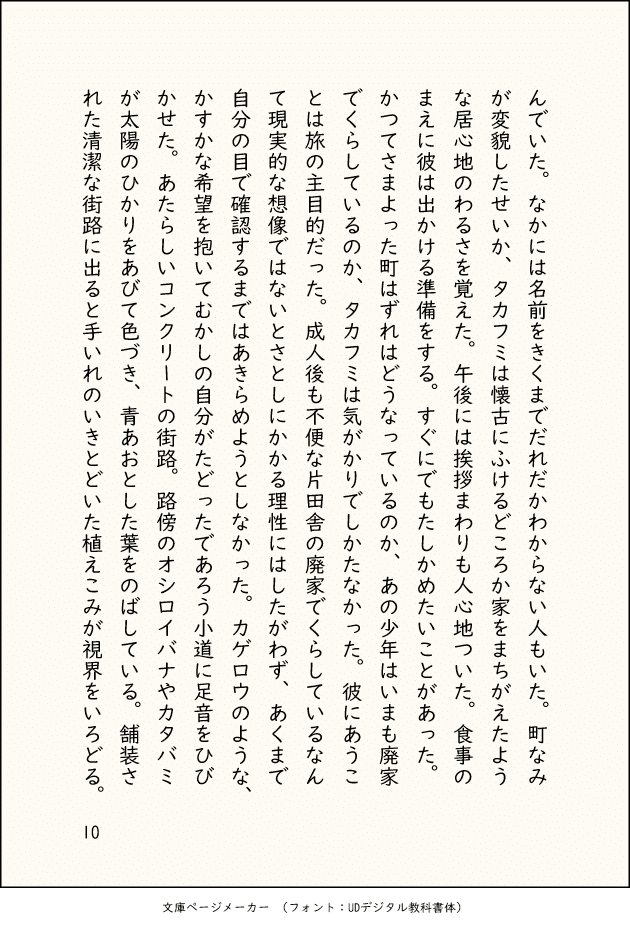
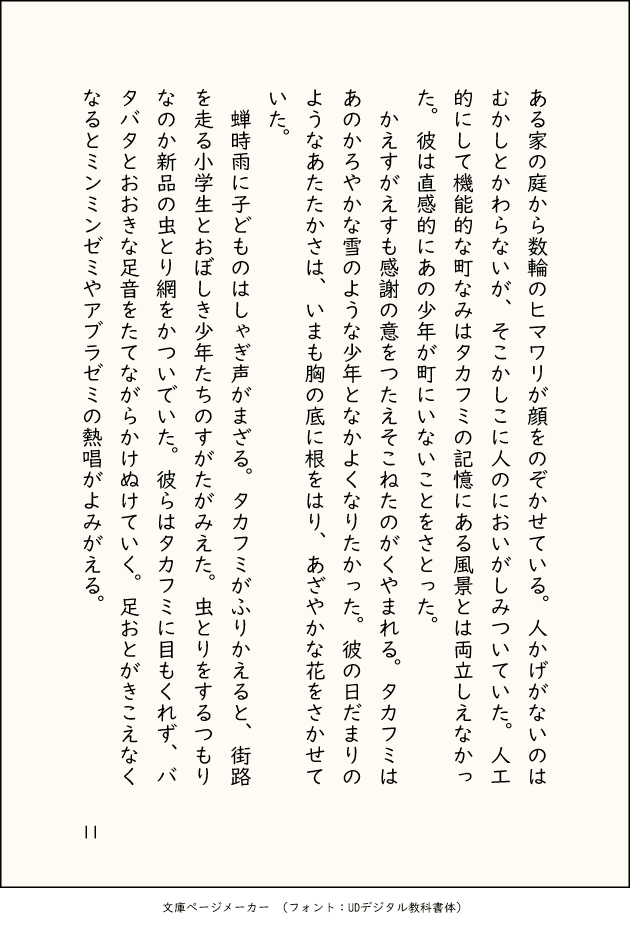
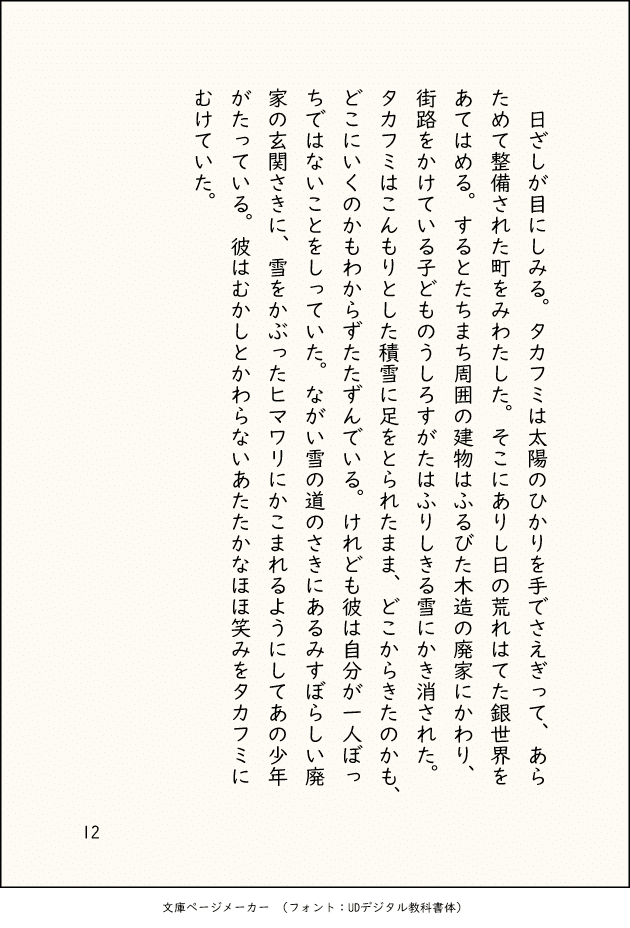
父方の血筋は東北を起源としている。そのなかでも、ゆかりの地といわれる宮城県にはたくさんの親類があつまっている。おさない時分のタカフミはよく両親にともなわれ、北国に居をかまえる親類の家にあそびにでかけていた。思い出を語りだせばきりがないが、彼の記憶にもっとも色あざやかに焼きついているのは十歳の誕生日を間近にひかえた年末である。そのとしは地元の神奈川県ではめったにない大雪にみまわれ、たまには北国でとしをこすのもおもしろいだろうと豪雪地帯の冬のおそろしさをわすれて発案した父にいたっては、数軒さきもみえない雪景色のまえであぜんとするありさまだった。タカフミは白銀の風景に心をうばわれる反面、みたこともない自然界の猛威にばくぜんとした恐怖を抱いた。まるで自分たちがとりのこされるような心地になった。
ふだんは夏やすみ中におとずれているので、居間の窓からのぞめる川辺や座敷のガラス戸からみえる庭は、タカフミの記憶のなかでは夏の日光をいっぱいにあびてきらめく草花でおおわれた穏和な世界だった。それだけに白一色に染まった景色は彼に衝撃的な感想をわかせた。記憶とことなるのは景色にとどまらない。おもてに出れば冷気が針となって肌をさし、地面がひえきって靴底をとおして足がこおりつきそうで無意識的にペンギンのような歩きかたをしてしまう。それは未知なる季節の息吹にほかならなかった。
両親は安全を考慮してとおくまで出歩いてはいけないと注意していた。タカフミ自身もつきることなくふりつづける雪にかくれている、ともすれば命をうばいかねない危険な香りをおぼろげにかぎとっていた。しかし、わきあがる冒険心はおさえきれなかった。いまだかつてふれたことのない深い雪にまどわされて、こんもりと積もる雪に足あとをつけてあそんでいるうちに家との距離はゆっくりひろがっていった。
気がつけば町はずれにいた。まばらな家なみは死んだようにしずまりかえっている。そこは夏の日光に焼かれる季節も人もおとずれない辺境にして、好奇心を刺激されながらも不気味なたたずまいに恐れをなしていた地域にちがいなかった。綺麗な雪景色にまどわされたとはいえ、禁断の地に足をふみいれたことを理解した以上、いつまでもすくみあがっているわけにいかない。親の警告が脳裏をよぎると不安はますますふくらみ、ついにタカフミは探検をきりあげてはやくかえろうときびすをかえした。ところがふりかえった彼を待ちかまえていたのは、自分がクモの巣にかかったバッタであることを思いしらされる非情な現実であった。舞いおちる白雪はいっそう激しくなり、タカフミがひきかえそうとしたときには雪面の足あとをあらかたうめていたのである。
孤島にとりのこされたような孤独感にさいなまれたタカフミが周囲の人家をみてまわると、ほとんどがもぬけのからだとわかった。なかには倒壊寸前の木造家屋もある。最近は町の人口が減るばかりで廃屋が増えていると父からきいたのを思いだし、なおさら心ぼそくなる。手足から体温がぬけ出ていくのを感じる。どこにむかえばかえれるのか見当もつかなかったので、むやみにうろつくのもためらわれた。ときおり木の枝から雪のかたまりがおちておおきな音をたてる。近くにおちると地響きすらした。通行人のあらわれない路地で、彼は目に涙をためながらたちつくす。
しんしんとふる雪の音にすきとおった声がまざる。その声がわりしていない子どもの声をタカフミの耳はききのがさなかった。それは自分を呼んでいるようだった。彼はワラをつかむ思いで声のぬしをさがした。
屋根がくずれおちていたり垣根がこわれていたりする廃家がのきをならべるなか、ひときわ崩落がすすんでいる木造家屋の戸口にちいさな人かげを発見すると、ころびそうになりながら駆け寄る。こわれた玄関さきにたっていたのは小柄な子どもだった。ダッフルコートのようなふっくらした防寒着をきているのにタカフミよりひとまわりほそく、背丈も肩口までしかなかった。西洋人形のようにきめこまかな顔だちや、空からふりそそぐようなかろやかな声音は、ふうがわりにして非凡な個性をかもしだしていた。あまりに特異な風貌を目にしてタカフミははなしかけるどころか身じろぎするのもわすれ、しばらく頭に雪をつもらせたままジッとたたずんでいた。はじめは自分よりもおさない女の子かと思った。しかし、ときおりみせるしぐさやことばづかいから年齢のちかい男の子とわかった。
タカフミは荒れはてた家にまねかれた。屋根のすきまをぬけてきた雪が床の板につもっている。部屋のなかで雪が舞っている光景は奇妙だった。壁がぼろぼろにかけているせいで路地を吹きぬける風が笛のごとく音をたてて廃家にしのびこむ。まったく風雪をしのげる環境ではなかった。それにもかかわらず敷居をまたぐなり体のなかにポッとあたたかな火がともった心地がするので、タカフミは不思議でたまらなかった。くさった板じきに足をとられないように気をつけながら廃家の奥にすすみ、すわれそうなところをみつけると腰をおろした。そのとなりに少年もよりそうようにすわった。ここにはよくきているのかな、とタカフミがたずねる。吹きつける雪風を顔色一つかえずうけとめながら少年は廃家に住んでいることをつげる。
「こんなところで? どうして? さびしくないの?」
タカフミが疑問をぶつけると少年はにっこりとほほ笑む。ありがとう、ちょっとさびしくなることはあるけど、一人じゃないときもあるから大丈夫だよ。彼の問いかけに答えているあいだも少年はやさしげな微笑をたやさなかった。そうしたわずかなやりとりをするのも楽しそうなようすである。
「でも、住んでるんだよね。お父さんお母さんはどうしたの。どっかに出かけているのかな。勝手に人をいれたら叱られない?」
少年の両親とはちあわせして気まずくなるのをおそれたタカフミは、おちつきをなくしてたちあがろうとしてはすわりなおし、いたたまれない気持ちをあらわにした。少年がそれを制して、ずっと一人で住んでるんだよ、だから心配しないで、と噛んでふくめるように語りかける。きみこそ家にもどらなくていいの?
タカフミは返答にこまった。彼はしどろもどろになり、要領をえない弁明をはじめたが、聡明な少年はことばの断片をつなぎあわせ、白銀の景色にまどわされてみなれぬ土地にまよいこんだことまで理解してくれた。そうして居心地がわるそうに背をまるめるタカフミの膝に手をおき、ぼくが家までつれていってあげる、とささやきかける。手をつないでいればはなればなれにならないから、一人ぼっちにしないから安心して。そういって腰をあげるとタカフミの手をとる。そして、とめどなくふりつづける雪の世界にふみだした。もはやタカフミにはどこをどう歩いているのかもわからなくて、まぶたをとじて少年に命運をゆだねていた。雪道をザクザクと音をたてて歩いていく少年の歩調にはまよいがいっさいなかった。
疲労と寒気で足があがらなくなる頃、ふいに少年がたちどまる。ここまでくればもう大丈夫だよ、と声をかけてくる。まぶたをあけるとみなれた町なみが視界に入った。窓からもれるあかりに気づいたとたん、タカフミの胸はおどりだした。生きてかえれたというよろこびが血液とともに体のすみずみをかけめぐり、感きわまって両目から大粒の涙をこぼしだした。約束どおり家までつれてきてくれた少年に感謝しようとしても、しゃくりあげるばかりでことばにならなかった。それでもタカフミの気持ちはつうじたのか、ふたたびあのあたたかな手が彼の雪まみれの頭をやさしくなでた。そのぬくもりは彼にさらなる安堵をもたらした。懸命に喉から声をしぼりだしながら視線をあげる。しかし、雪化粧した風景に人のすがたはなかった。周囲には餅のような雪塊がところせましとつみかさなっており、タカフミだけがポツンとたちつくしていた。彼は自分一人ぶんの足あとをぼうぜんとながめ、白い息をはきつづけた。
この翌年から親戚の家とは疎遠になった。父の転勤にともない、鹿児島県にひっこしたことで旅費や手間が増したからだ。けれどもタカフミは市内の大学にかよいはじめてからも東北への思いをたちきれずにいた。自分のちからで旅費をかせごうと決意したのは三回生に進級してからで、学業にはげむかたわらアルバイトに精をだした。そして、世のなかが蝉時雨におおわれる季節にいたり、ようやく出立の日をむかえたのである。
飛行機から電車にのりつぎ、なつかしの大地をふみしめる。木造の駅舎はたてかえられ、駅の周辺にたちならんでいた森林は小綺麗な住宅地にさまがわりしていた。最後におとずれたときのおもかげはつゆほどもなかった。時代のなみは田舎と呼ばれる町にもおしよせていたのである。そうしたながれに飲みこまれた痕跡は親戚家の近辺にも認められた。木造家屋自体がまったくみあたらないのだ。タカフミを出むかえる親戚たちもふけこんでいた。なかには名前をきくまでだれだかわからない人もいた。町なみが変貌したせいか、タカフミは懐古にふけるどころか家をまちがえたような居心地のわるさを覚えた。午後には挨拶まわりも人心地ついた。食事のまえに彼は出かける準備をする。すぐにでもたしかめたいことがあった。かつてさまよった町はずれはどうなっているのか、あの少年はいまも廃家でくらしているのか、タカフミは気がかりでしかたなかった。彼にあうことは旅の主目的だった。成人後も不便な片田舎の廃家でくらしているなんて現実的な想像ではないとさとしにかかる理性にはしたがわず、あくまで自分の目で確認するまではあきらめようとしなかった。カゲロウのような、かすかな希望を抱いてむかしの自分がたどったであろう小道に足音をひびかせた。あたらしいコンクリートの街路。路傍のオシロイバナやカタバミが太陽のひかりをあびて色づき、青あおとした葉をのばしている。舗装された清潔な街路に出ると手いれのいきとどいた植えこみが視界をいろどる。ある家の庭から数輪のヒマワリが顔をのぞかせている。人かげがないのはむかしとかわらないが、そこかしこに人のにおいがしみついていた。人工的にして機能的な町なみはタカフミの記憶にある風景とは両立しえなかった。彼は直感的にあの少年が町にいないことをさとった。
かえすがえすも感謝の意をつたえそこねたのがくやまれる。タカフミはあのかろやかな雪のような少年となかよくなりたかった。彼の日だまりのようなあたたかさは、いまも胸の底に根をはり、あざやかな花をさかせていた。
蝉時雨に子どものはしゃぎ声がまざる。タカフミがふりかえると、街路を走る小学生とおぼしき少年たちのすがたがみえた。虫とりをするつもりなのか新品の虫とり網をかついでいた。彼らはタカフミに目もくれず、バタバタとおおきな足音をたてながらかけぬけていく。足おとがきこえなくなるとミンミンゼミやアブラゼミの熱唱がよみがえる。
日ざしが目にしみる。タカフミは太陽のひかりを手でさえぎって、あらためて整備された町をみわたした。そこにありし日の荒れはてた銀世界をあてはめる。するとたちまち周囲の建物はふるびた木造の廃家にかわり、街路をかけている子どものうしろすがたはふりしきる雪にかき消された。タカフミはこんもりとした積雪に足をとられたまま、どこからきたのかも、どこにいくのかもわからずたたずんでいる。けれども彼は自分が一人ぼっちではないことをしっていた。ながい雪の道のさきにあるみすぼらしい廃家の玄関さきに、雪をかぶったヒマワリにかこまれるようにしてあの少年がたっている。彼はむかしとかわらないあたたかなほほ笑みをタカフミにむけていた。
※2012年脱稿・2016年改稿
ここから先は
¥ 100
お読みいただき、ありがとうございます。 今後も小説を始め、さまざまな読みものを公開します。もしもお気に召したらサポートしてくださると大変助かります。サポートとはいわゆる投げ銭で、アカウントをお持ちでなくてもできます。
